酒甕窯巡りの第3弾は、沖縄県八重瀬町にある『琉球南蛮ようざん窯』です。国道507号線を南に下りちょうど国道331号線と交わる場所、南側の緑地帯にあります。近くには『汗水節の碑』があります。


『ようざん窯』は穴窯(薪窯)で、一度火入れがされると一週間は火を絶やさないようです。

その間、窯は開けることもできず、ただひたすら温度計と炎をにらみ合いながら、燃え盛る炎を操り、窯の陶器を焼き締めていきます。

焼き上げた後、そこからまた約10日ほどかけて徐々に熱を冷ましていき、焼き上がりは窯を開けるまではわからないようです。

こちらは工房で焼く前の嘉瓶(ユシビン)や酒甕(サキガーミ)が見られます。


ようざん窯の灰かぶりの技法は何回か灰をかけて焼くようです。

『ようざん窯』の特徴である『灰かぶり』は、通常は、釉薬(ガラス質)などを塗り色づけしますが、ここでは一切使用せず、灰をかけて、溶けてこのような光沢を生み出しています。

窯の中で舞う、灰が生み出す 神秘の世界のようですねぇ。

ようざん窯の『灰かぶり酒甕』、是非欲しい逸品ですねぇ。
ブログランキングに登録中です。ポチッとお願いします。

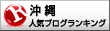 沖縄 ブログランキングへ
沖縄 ブログランキングへ
 にほんブログ村
にほんブログ村



『ようざん窯』は穴窯(薪窯)で、一度火入れがされると一週間は火を絶やさないようです。


その間、窯は開けることもできず、ただひたすら温度計と炎をにらみ合いながら、燃え盛る炎を操り、窯の陶器を焼き締めていきます。


焼き上げた後、そこからまた約10日ほどかけて徐々に熱を冷ましていき、焼き上がりは窯を開けるまではわからないようです。


こちらは工房で焼く前の嘉瓶(ユシビン)や酒甕(サキガーミ)が見られます。



ようざん窯の灰かぶりの技法は何回か灰をかけて焼くようです。


『ようざん窯』の特徴である『灰かぶり』は、通常は、釉薬(ガラス質)などを塗り色づけしますが、ここでは一切使用せず、灰をかけて、溶けてこのような光沢を生み出しています。


窯の中で舞う、灰が生み出す 神秘の世界のようですねぇ。


ようざん窯の『灰かぶり酒甕』、是非欲しい逸品ですねぇ。

ブログランキングに登録中です。ポチッとお願いします。











