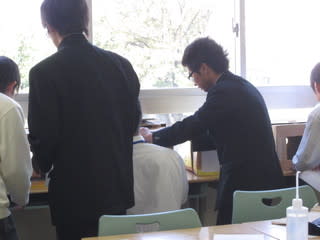10月21日(金)
明日は小学6年生向けの中学オープンスクールが行われます。
理科部は、アイスクリームを作ることになりました。
小学生にもよく分かるように、準備をしたいと思います。

机の上には、すべての器具が見やすいように並べました。
机の上にあるものは、作り方の冊子、洗面器、ステンレス製のボール、ヘラ、泡立て器、ゴム手袋、スプーンです。

来てくれた人たちに分かりやすいようにそれぞれの材料をどのように入れるのかをわかるように、
机に紙を貼りました。

砂糖を測る場所です。

生クリームを測る場所です。

脱脂粉乳を測る場所です。

黒板は、小学生用に少しにぎやかにしました。

また、アイスクーム作りの手順が見ただけで分かるように紙も貼りました。
あとは、司会の仕方をみんなで考えて、今日は解散しました。
明日は小学6年生向けの中学オープンスクールが行われます。
理科部は、アイスクリームを作ることになりました。
小学生にもよく分かるように、準備をしたいと思います。

机の上には、すべての器具が見やすいように並べました。
机の上にあるものは、作り方の冊子、洗面器、ステンレス製のボール、ヘラ、泡立て器、ゴム手袋、スプーンです。

来てくれた人たちに分かりやすいようにそれぞれの材料をどのように入れるのかをわかるように、
机に紙を貼りました。

砂糖を測る場所です。

生クリームを測る場所です。

脱脂粉乳を測る場所です。

黒板は、小学生用に少しにぎやかにしました。

また、アイスクーム作りの手順が見ただけで分かるように紙も貼りました。
あとは、司会の仕方をみんなで考えて、今日は解散しました。