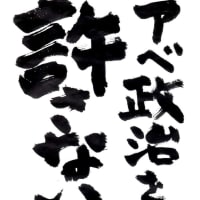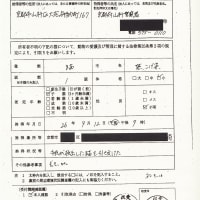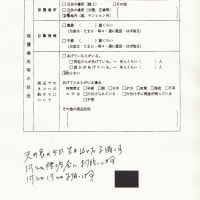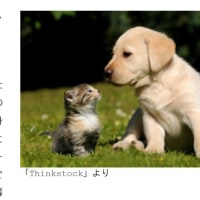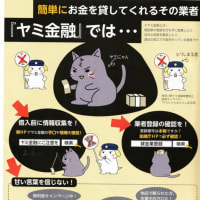2013年5月5日、auのニュースサイト EZニュースフラッシュ増刊号
「潜入! ウワサの現場」で記事
「『記者クラブの闇』を外国特派員が暴露する講演に潜入!」
を企画、取材、執筆しました。
国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団」が今年1月30日に公表した、世界各国の報道の自由度ランキングによると、日本は世界179か国中、53位だった。アフリカのガーナ(30位)、ボツワナ(40位)、ニジェール(43位)や、アジアの台湾(47位)、韓国(50位)といった国々よりも、日本は低い。その最大の要因は、情報アクセスを独占する差別システム“記者クラブ”が存続しているため、と同団体は指摘している。
そうした中、「外国特派員が見る今の日本」と題するシンポジウムが4月27日、都内の茗荷谷であった。主催は日本マスコミ文化情報労組会議など。
開催の告知文には「なぜ日本のメディアは国民が知りたい事実を伝えず、『権力者の代弁』ばかりをたれ流すような報道に終始するのか。当局の発表をそのまま報じる『記者クラブメディア』の限界。(略)外国特派員から見た今の日本の『ジャーナリズムの欠落』という問題について気鋭のジャーナリストに語っていただきます」とある。
講演者は、ニューヨーク・タイムズ東京支局長のマーティン・ファクラー氏、インディペンデント紙記者のデイヴィッド・マクニール氏など。現地へ向かった。
会場はメディア関係者など140人が参加。同シンポで特筆すべきは、両氏がこれまでに経験した記者クラブの弊害を物語るエピソードを語ったときだった。このとき会場は爆笑に包まれた。話の内容はこうだ。
マクニール氏は、インディペンデント紙以外で、上智大の非常勤講師でジャーナリズムを教えている。だが、生徒たちに記者クラブの弊害を説明しても、なかなかピンとこないので、次のエピソードを紹介するようにしているという。
それは07年のこと。皇太子がモンゴルに行くことになり、記者会見を行うことになった。会見時間は30分。質問内容は、事前に宮内庁とやり取りをして、役所の意に沿ったものだった。こうして予定調和の質疑が始まり、25分で終わった。そこで宮内庁の役人が、「あと5分残っていますから、他に質問ありますか?」と言った。
このときマクニール氏は、「すごいチャンスだ」と思い、すぐに手を挙げた。実は宮内庁に事前に言ってもはじかれる、本当に聞きたいことがあったのだ。
「ある出版物によると、雅子様は離婚したがっている、と書いてあました。その真偽をたしかめようとしたのです」(同氏)
しかし、宮内庁の役人は、オロオロして、横目でマクニール氏をチラッと見るだけで、無視した。そして、日本の記者クラブのメンバーのほうを助けを求めるような目でジーと見つめた。こうして、5秒、10秒…20秒近くが経った。
すると、もう一人の外国メディアの記者も手を挙げた。会見場は緊張感に包まれた。
そこで、TBSの女性記者が、まるで学校の教室の子どものように、そっと手を挙げた。すると、その役人は「じゃあ、レディファーストにしましょうか」と言って指名し、その記者は、当たり障りのない、つまらない質問をして会見は終わったのだという。
「要するに、彼女の仕事は、宮内庁に立ち向かって質問をするのではなくて、宮内庁に協力して聞くこと。僕と彼女は、同じ記者職ですが、仲間ではないですね。彼女の仲間は、宮内庁なのです」(同氏)
また、ニューヨーク・タイムズのファクラー氏が、「記者クラブ制度が本当におかしい」と感じたのは、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)の記者で日銀担当をしていたときのこと。当時の日銀総裁は福井俊彦氏だった。ファクラー氏は、福井総裁の記者会見に出席したかった。そこで日銀に電話すると、「記者クラブに聞いて下さい」という。そこで記者クラブに聞くと、幹事の日本経済新聞の記者が「ダメだ」というので、「なぜダメなのか?」と食い下がったところ、「じゃあ、参加してもいいけど、質問してはダメ」と言われた。
「WSJという世界の金融紙が日銀総裁の会見に出席できない、または質問はダメだ…。これは中国よりひどい話ですよ。北朝鮮並み。日銀は『我々に責任はない。記者クラブが勝手にやっている事』と責任逃れをし、記者クラブは、他の記者を差別する…。本当、不思議ですね」
また、会場参加者が質問用紙に記入して休憩中に用紙を回収する形の、質疑のコーナーでは、会場から「日本のメディアにジャーナリズムは存在しない、といわれるが、日本のメディアで働いている人は、ジャーナリストというよりは、サラリーマンなんじゃないか?」「日本のマスメディアで働く人には、非常にエリート主義があって、それがジャーナリスト精神を腐らせているのではないか?」といった声が出た。
これについて、ファクラー氏は、20年前、東京大で2年間、留学生として勉強していた時のエピソードを語った。同級生がちょうど就職活動の時期で、当時はバブル期だったので、東大生は引く手あまただった。そのとき、どこに就職するか迷っている学生が「いやぁ、東京海上にするか、トヨタにするか、官僚になるか、朝日新聞にするか…」と悩んでいたという。
「その学生は、ジャーナリズムがいいとか、車の営業がしたい、とか、そういう気持ちは全くなかった。大学を選ぶのと一緒で、会社の知名度を優先して、全然仕事の中身を見ていなかった。そういうふうに職業を選んでいいのかな、と正直思いました」(ファクラー氏)
さらに、もう一つエピソードを語った。現在、ニューヨーク・タイムズ東京支局は朝日新聞本社内にある。両社は東京とニューヨークで安く貸し合う提携をしているのだという。こうして朝日新聞社内にいるファクラー氏は、毎年、就職活動の時期になると、数百人の学生が、全く同じ黒いスーツで、まるでペンギンの大群のように歩く姿を見て驚くのだという。
「自分が雇う側だったら、周りと違う服を着ている人を、まず雇います。ジャーナリストは、反発精神がないとダメですよね。怒りとか、これはいけない、という正義感がないといけない。ジャーナリストは、世の中を変えたいから、この仕事をするんですよ。みんなで黒いスーツで歩くタイプは、違うと思う」(同氏)
また、質疑では、記者クラブメディアの現役社員たちから「じゃあ、私はどうすればいいんですか?」という趣旨の質問も複数出た。司会の林香里氏(東大教授、ジャーナリズム専門)は、この質問文を読み上げた後、「『そんなの自分で考えろ』という回答でも結構ですので、お願いします」と何度も述べていたが、両氏は、現役社員たちを慮ってか、そうは言わず、「構造的な問題なので、自分一人で変えようとしても難しい」という趣旨の発言をしていた。
こういう記者クラブの仕組みの中から、マスメディアの報道は生まれている。情報を得る側は、そのことを理解して記者クラブメディアに接する必要があるのではないか。(佐々木奎一)
写真は、インディペンデント紙のデイヴィッド・マクニール氏。