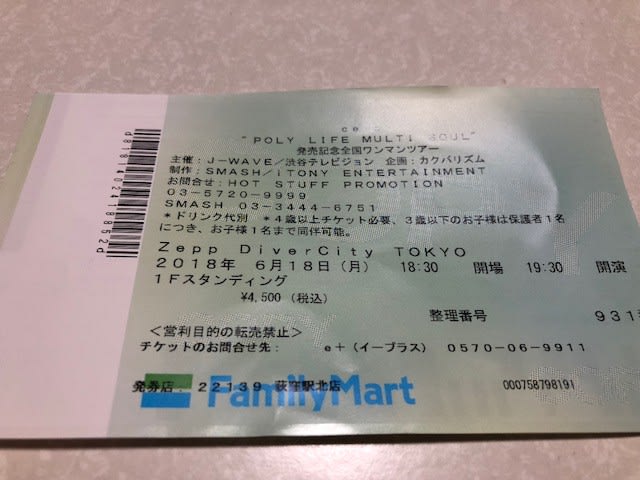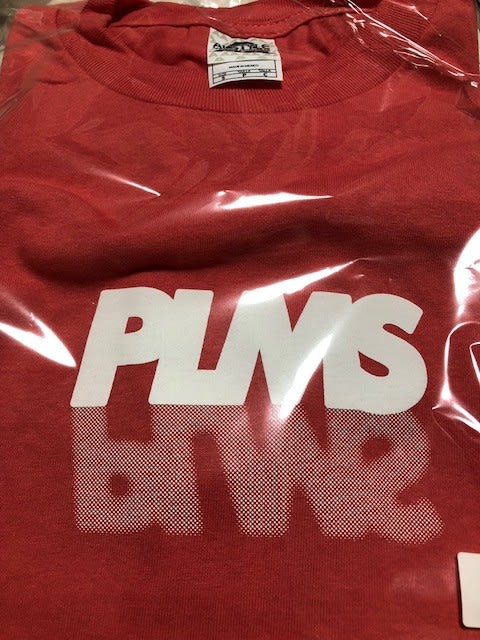暑い、暑すぎる!!(さいたま名物「十万石饅頭」のノリで)
あまりの暑さにぐったりして更新が滞っておりました。
我が家の観葉植物ボディくん↑(インドボダイジュ)も、この熱気でぐったりしています、悲しい。
もう一人のモンちゃん(モンステラ)はすこぶる元気なんだけどな、どうしてこうなった。
こう暑いと、夏の曲とか聴きたくなりますよね。ビールも飲みたくなりますよね。
夏の曲を聴きながらビールを飲みたくなりますよね。
というわけで本日は夏の曲特集、すべて日本語の曲どす。
なつやすみ(終)/ザ・なつやすみバンド
夏と言えば彼ら。以前もこのブログで紹介しました。
これは1stの1曲目、毎年夏になると聴きたくなる。途中の笛、マンドリンが好きです。
今年の秋頃に新譜を出すとのこと、またライブに行きたいな。
Summer Soul/cero
東京のシティポップは俺たちだ、cero。
PV見てて思うんだけど、ハー本当にオシャレ!荒内さんが運転する姿が格好いい。
こういう音楽聴いてたらモテそうだよな~と思って聴いてたけど全然モテませんでした、完。
サマージャム ‘95/スチャダラパー
20年過ぎても色あせない名曲。最近誰かがカバーしてましたね。
心地よいビートに乗って語られる、夏の日常的な歌詞。ANIのおちゃらけが好き。
「"この曲好き"なんて言われちゃう感じね(笑)」とか「そーなるってことはもーあれだ、熱めのお茶だ」とか。
そこはかとなく嬉しそうに言うのがまたかわいらしい。
ワイルドサマー/ビートでゴーゴー/Flipper’s Guitar
彼らの中でも1、2位を争うふざけた曲。
マッチョマンに対する熱い風評被害、気持ちはわからんでもない。
昼の海辺ではしゃぎながら聴きたい。
甲州街道はもう夏なのさ/Lantern Parade
ソロの人、根暗な七尾旅人って感じ。根暗かつセンチメンタル、好き。
何度も「もう夏なのさ」と言っておきつつもフルート、シンセがどこか涼しげな雰囲気。
夜にぼんやり散歩している時に聴くと心地よい。
Sunset/AIR
元spiral life、AIRことくるまたにいさん。一時期オーストラリアに行ってて、その頃に出したものだったと思う。
彼の夏ソングは「夏の色を探しに」もあるんだけど、こっちの方が好き。
ダサさと格好よさが7:4くらい、絶妙なバランスで曲を作る人だと思う。
クレイジーサマー/キリンジ
「スウィートソウルEP」に収録されているヤスの曲。シンプルで気だるく、美しいメロディ。
キリンジはベタに季節を感じさせる曲が少ない気がする。
浜辺で夕焼けを見ながら聴きたい、ラムコークとか飲みつつ。
あの夏へ/久石譲
日本語…?
それは置いといて、映画「千と千尋の神隠し」のメインテーマです。
これ聴くとすごく胸が締め付けられるような気がする。やっぱり夏に聴きたい曲。
関係ないけどいつかジブリを映画館で再上映してくれないかな、千と千尋は10回くらい観に行きたい。
そんなわけで暑すぎるから記事も短め。もう何もやる気が起きません。毎年この時期になると、夏休みの宿題をヒイヒイ言いながら9月1日にやっていたのを思い出します。今年もだらだらしているうちに過ぎていってしまうんだろうな。でもこうやってぼんやりしている時間も人生には必要なのだよな、と自分に言い聞かせつつ、時にはセンチメンタルにもなりつつ。
余談ですけど、夏が切ないのはどうしてなんでしょうね。人の一生を四季に例えると、夏が青年期ということになるんでしょう。でもそんな夏も気づけばあっという間に終わってしまう。そう考えると「人の一生が刹那的」ということを、どこかで感じさせるからなのかな。まあそんなこと考えても仕方ないから、今夜は熱の余韻に浸りながらビアでも飲もうか。