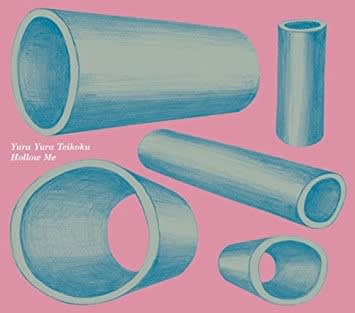「いまにして思えばいつもファンショーがそこにいたような気がする。」
今年最後の更新になりそうです。
本日はポール・オースターの『鍵のかかった部屋』、白水Uブックスで柴田元幸の翻訳です。これは昨年読んで衝撃を受けました。こんなに面白い本があるのか、と。もともと海外小説を好んで読む方ではないのですが、この人の作品はハードカバーのもの以外たいてい読んでいます。同じアメリカの作家だとスティーブン・ミルハウザーも。こちらも幻想的で面白い物語が多いです。
余談ですけど白水Uブックスは面白い本が多いですね、高いけど(笑)アントニオ・タブッキもそうだし、カフカも白水Uブックスの池内紀訳が好きです。装丁もシンプルで美しい。
ちょっと誤解を生むかもしれないですが、この人の物語を読んでいるとすごく「村上春樹的ななにか」を感じます。今回紹介する『鍵のかかった部屋』の「他人の原稿が爆発的なヒット作となる」というストーリーは『1Q84』に出てくる「空気さなぎ」に似ているし、友達の母親と懇ろになるのは『ノルウェイの森』の玲子さんと寝るシーンのようだし...ちょっと強引かもしれませんが。もちろんパクリとかそういうのを言いたいわけじゃなくて、両者ともなにか普遍的なテーマを扱いながら、非常に注意深く―あるいは用心深くと言ってもいいかもしれませんが―書いているような印象を受けるのです。
ポール・オースターという作家は、暴力的な喪失を描くのが好きなのかもしれません。初期の作品である『ガラスの街』も『幽霊たち』も、奇妙な「剥奪」に満ちた話が出てきます。それは時間であったり、言語であったり、最終的には生命であったり。また『偶然の音楽』は賭けに負けて人権を奪われるし、『オラクル・ナイト』ではもっと直接的に盗まれる話が出てきます。そういえば村上春樹の長編『ねじまき鳥クロニクル』でも、妻は他人に寝取られるし、誰かが家に侵入して荒らしまわっていったっけ。話のもっていき方はとても面白いし、すごく先が気になるんだけど、読むとなんだか微妙に傷つく気がします。人によっては、こころに余裕がある時に読む方がいいかもしれません。
基本的にはニューヨークを舞台とした、知的で洗練された雰囲気が漂っています。随所にちりばめられている比喩、ウィットに富んだ言い回し、入れ子構造のように挿入される興味深い逸話たち。でも物語の背後には、暴力的なものが地下水脈のようにひっそりと流れている。そんな気がします。さりげなく残酷な話が描かれることも多く、ひやりとする気持ちになります。
さてこの物語について。
旧友のファンショーの妻から連絡が来るところから始まります。以前に川上弘美の『真鶴』を紹介した時にも書きましたが、私は物語の書き出しをすごく重視する派です。時々振り返って書き出しだけ読むことがあります、何度も。
書き出しというのは、CDで言うところの1曲目だし、作家にとって非常に大事な部分ですよね。書き出しでぐっとくる小説と言えば漱石の『吾輩は猫である』や『それから』、カフカの『変身』やガルシア=マルケス『百年の孤独』が挙げられるでしょうか。
この小説に話を戻すと、若干のネタバレになっちゃうかもしれませんが、この作品も冒頭の部分が非常に示唆的な意味を持っているように思います。読み終わった後、すぐにでも読み返したくなるような。これから手に取ろうとする方は、少し意識して読み始めると面白いかもしれません。
おそらく2、3時間ほどあれば読めると思うので、ここでは漠然とした印象を。話の中身については、ぜひ本編を読んでいただければと思います。
さてこの話は友人ファンショーが自分の「分身」のような存在として出てきます。幼少期、常に主人公の一歩先にいたファンショーは、早くして独立した人格を持ち、主人公の憧れの存在でした。大人になった彼は美しい妻と結婚し、自分が持ちえなかった文学的な才知に満ちている。まるで自分が手に入れたかったものをすべて持っている、そういう存在として出現します。
だけど話は少しずつ、妙な方向に向かっていくことになります。主人公は失踪したファンショーの代理人となり、本を出版する、ファンショーの元妻と結婚し、あまつさえ彼の伝記を書くことになる。そうして主人公の人生は幾重にも入り組んだ迷路に引き込まれていき、あるとき突然に、もう後戻りのできない場所に立っていることに気づく。そういった話の持っていき方が、実に上手いと思います。
そういえば最初に「この作家は剥奪が多い」と話しました。ではこの『鍵のかかった部屋』では何が剥奪されているというのか。それは恐らく「自分とは何か」「自分はどういう存在か」「自分はどうしたいのか」を考える行為だと思います。大きな流れに飲みこまれるようにして進んでいく物語。そして話が進むにつれて主人公の輪郭はずいぶんぼやぼやとしたものになっていく。しかし話の終盤になってようやく、主人公は立ち止まって考えられるようになる。
でも私たちの人生も、そういうことって多いんじゃないかと思うのです。「自分とは何か」「自分はどうしたいのか」そういったことは、しばしば自分でもわからないうちに考えられなくなってしまいます。気付けば「しなくてはならない」「こうあらねばならない」といった、思考のこりのようなものが頭に重くのしかかっていることは、決して他人事ではないはずです。この本は、そういった状態の恐ろしさを暗に示唆しているのではないか。そんな風にも読めるかなと思います。個人的な読み方がずいぶん入っているかもしれませんけど。
年の瀬ですから、今年自分が何を為したか、何を為さなかったか、そういったものを振り返るにはいい機会だと思います。でも結局は人生の限られた時間で、何が出来て何が出来なかったかなんて、そんなに重要ではないのかもしれません。「自分はどうやって生きたいんだろう?」決してすぐに答えの出る問題ではないし、考えるのは苦しいし孤独な行為です。しかし、そういったことをときどき考えてうんうんうなされるのも、案外悪いものではないのかなと思います。自分なんかすぐ楽な方に流れたがるので、こういう本を読んで目を覚ます行為が、長い目で見たときにどこかで自分を救ってくれているようにも感じるのです。