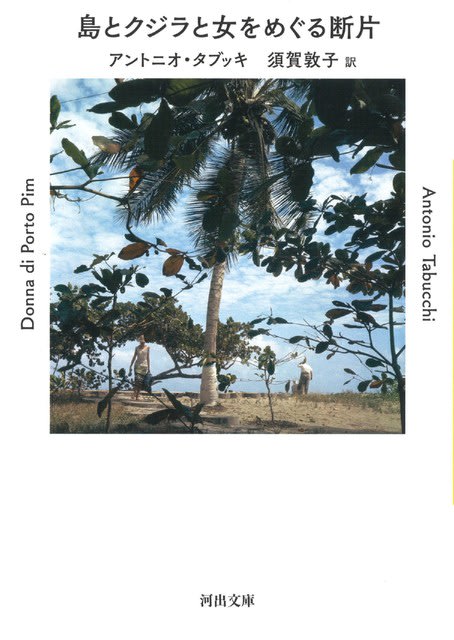サボります。
しょうがないとはいえ、ここしばらく同僚が休んでいるのを見ていいな~~~と思っています。
抜き差しならない事情だとはわかっているんです。
しかしそのぶん些末な仕事が降りかかってきたり、代わりに応対しなくてはなかなかったりと、疲弊しています。
お互い様であること、頭では理解しているつもりです。いつ自分がそうなってもおかしくないんです。
しかし感情が納得していない。俺だけ頑張っている、割を食っている、ついそんな気持ちが浮上してきます。本当はそんなことないのにね。だってその同僚の方はサボってブログ書いたりしてないから。なんなら普段は私よりも頑張っていると思います。
そう、今回は自分の感情を静めるためにブログを書いています。
「俺だけ被害を被っている」と感じている状態は、精神分析で「P-Sポジション」と言われます。オーストリア出身の精神分析家メラニー・クラインが提唱した概念です。フェレンツィの弟子にあたるユダヤ人で、のちにイギリスに移り、アナ・フロイトとケンカします。
このPとかSというのは、ParanoidとSchizoidの頭文字でして。
Paranoidは偏執的、被害妄想的なことですね。
誰かに狙われている、人から嫌われている、という思考が優勢な状態です。
SchizoidはKing Crimsonの名曲”21st century schizoid man”でおなじみ、精神病や統合失調症のことです。
人が恐ろしくなり、引きこもってしまう状態です。
こころが未成熟な赤ちゃんや子どもは、容易にP-Sポジションになります。
もちろん赤ちゃんが「俺はFBIから狙われている!!」と妄信することはありませんが、空腹や眠気などの不快を感じ続けると、ものすごく強い不安、圧倒的な恐怖を強く抱くことになります。それが大人の抱っこ、授乳、おむつ交換などで和らいでいくのですね。つまりP-Sポジションにとって、まず優先されるのは「適切なケア」と言えるかもしれません。
P-Sポジションに陥るのは赤ちゃんだけではありません。
小学生のときを思い出してほしいのですが、親に怒られて「自分はいらない子なんだ」「生まれてこない方がよかった」と思う、友達とケンカして「○○ちゃんとは絶交!」と関係を断ち切ろうとする。そういったことが、みなさんもあったことかと思います。このへんのことは、ヘッセの小説を読むとよいかもしれません。彼は少年の気持ちを描写する天才ですので。
大人になっても、P-Sポジションがこころから消えることはありません。
誰かがひそひそ話しているのを見聞きして「自分のことを言われているのではないか」と勘繰ったり、ちょっとミスをして「使えないやつだと思われたに違いない…!」と思い込んだり。
P-Sポジションでは、そういった極端な思考、決断に至ってしまいがちです。苦しいですね。
こころに余裕がないと、大人でも気持ちがP-Sポジションに傾いてしまい、むくむくとネガティブな思考が渦巻きます。そんなときは立ち止まって「いかん、俺はいまP-Sポジションに陥っている!!」と考え直し、こころにゆとりを取り戻すことが重要です。
ここまでお読みの読者はお気づきだと思いますが、こうして私がサボっていることは、こころにゆとりを取り戻すための必要な営みなのです。さきほど「適切なケア」が大事と述べましたが、ブログを書くこともある種のケアだと言えるでしょう。
もうすぐ5月の大型連休ですが、差し当たり大きな予定はありません。
TOEICの勉強もしなくてはな~図書館こもって勉強するか。
山にも行きたいところです。ふたたび高尾陣馬縦走チャレンジをしたい。
安易に酒を飲まず、もっと丁寧に自分へのケアをしていきたいところですね、人とも会いたいな。
仕事について。
必ずしも嫌じゃないというか、楽しい瞬間もあるのです。
ただ、仕事が自分の人生のほとんどを占めている感じが嫌だなあ。
もっとさ、近所をぶらぶら歩いて花を愛でたり暖かい風を感じたりしたいんだよね。
ベンチに座って行き交う人を眺めたり、遠くから聞こえてくる物音に耳を澄ませたりしたい。
自転車で少し遠くに行って、普段飲まないようなものを自販機で買って飲みたい。
自分とは違う世界を持っている、誰かに思いを馳せたりしたい。
たぶんちょっと疲れているんです。
最近は人間同士の調整をしたり、着地点を探ったり、政治的な業務を多くやっているからですね。
今日は早く寝たい。でも早く寝ると翌日の仕事が待ち構えている。
悩ましいところです。
そういえばこの前『ハムレット』を読みました。
ジョン・エヴァレット・ミレーの絵画でも、オフィーリアが亡くなる場面が描かれていますね。
シェイクスピアはこれまで『リア王』と『マクベス』と読みましたが、大学生の頃だったのでもうあまり憶えていません。いつかまた読み返したいな。次は何を読もうかしらん。
『ハムレット』は主人公の気持ちの波がすごかったです。周囲を欺くために狂気を演じるところはもちろん、明晰なときとの差が大きく、ついていくのに精いっぱいなうちに読み終わりました。それこそP-Sポジション的なこころの状態のようにすら感じられました。そうしてそのまま、彼も破滅していきました。
それはそうと。
シェイクスピアの作品のほとんどは、下敷きになる物語があったようで。
この『ハムレット』も、北欧の伝承をもとに書かれたもののようです。
そう考えると、かの偉大なシェイクスピアですら、無から作品を生み出していったわけではないのですよね。
その事実に、ちょっと勇気づけられもします。
人間が本当にいい仕事をできる時期って、限られているんだなあ。
私自身、その時間を無駄にしてはならないなあ、とも思います。
そんなわけでストレスがひとまず落ち着いたところで今日は筆をおきます。
みなさま、よき大型連休をお過ごしください。私も久しぶりの4連休で心がときめいています。
しょうがないとはいえ、ここしばらく同僚が休んでいるのを見ていいな~~~と思っています。
抜き差しならない事情だとはわかっているんです。
しかしそのぶん些末な仕事が降りかかってきたり、代わりに応対しなくてはなかなかったりと、疲弊しています。
お互い様であること、頭では理解しているつもりです。いつ自分がそうなってもおかしくないんです。
しかし感情が納得していない。俺だけ頑張っている、割を食っている、ついそんな気持ちが浮上してきます。本当はそんなことないのにね。だってその同僚の方はサボってブログ書いたりしてないから。なんなら普段は私よりも頑張っていると思います。
そう、今回は自分の感情を静めるためにブログを書いています。
「俺だけ被害を被っている」と感じている状態は、精神分析で「P-Sポジション」と言われます。オーストリア出身の精神分析家メラニー・クラインが提唱した概念です。フェレンツィの弟子にあたるユダヤ人で、のちにイギリスに移り、アナ・フロイトとケンカします。
このPとかSというのは、ParanoidとSchizoidの頭文字でして。
Paranoidは偏執的、被害妄想的なことですね。
誰かに狙われている、人から嫌われている、という思考が優勢な状態です。
SchizoidはKing Crimsonの名曲”21st century schizoid man”でおなじみ、精神病や統合失調症のことです。
人が恐ろしくなり、引きこもってしまう状態です。
こころが未成熟な赤ちゃんや子どもは、容易にP-Sポジションになります。
もちろん赤ちゃんが「俺はFBIから狙われている!!」と妄信することはありませんが、空腹や眠気などの不快を感じ続けると、ものすごく強い不安、圧倒的な恐怖を強く抱くことになります。それが大人の抱っこ、授乳、おむつ交換などで和らいでいくのですね。つまりP-Sポジションにとって、まず優先されるのは「適切なケア」と言えるかもしれません。
P-Sポジションに陥るのは赤ちゃんだけではありません。
小学生のときを思い出してほしいのですが、親に怒られて「自分はいらない子なんだ」「生まれてこない方がよかった」と思う、友達とケンカして「○○ちゃんとは絶交!」と関係を断ち切ろうとする。そういったことが、みなさんもあったことかと思います。このへんのことは、ヘッセの小説を読むとよいかもしれません。彼は少年の気持ちを描写する天才ですので。
大人になっても、P-Sポジションがこころから消えることはありません。
誰かがひそひそ話しているのを見聞きして「自分のことを言われているのではないか」と勘繰ったり、ちょっとミスをして「使えないやつだと思われたに違いない…!」と思い込んだり。
P-Sポジションでは、そういった極端な思考、決断に至ってしまいがちです。苦しいですね。
こころに余裕がないと、大人でも気持ちがP-Sポジションに傾いてしまい、むくむくとネガティブな思考が渦巻きます。そんなときは立ち止まって「いかん、俺はいまP-Sポジションに陥っている!!」と考え直し、こころにゆとりを取り戻すことが重要です。
ここまでお読みの読者はお気づきだと思いますが、こうして私がサボっていることは、こころにゆとりを取り戻すための必要な営みなのです。さきほど「適切なケア」が大事と述べましたが、ブログを書くこともある種のケアだと言えるでしょう。
もうすぐ5月の大型連休ですが、差し当たり大きな予定はありません。
TOEICの勉強もしなくてはな~図書館こもって勉強するか。
山にも行きたいところです。ふたたび高尾陣馬縦走チャレンジをしたい。
安易に酒を飲まず、もっと丁寧に自分へのケアをしていきたいところですね、人とも会いたいな。
仕事について。
必ずしも嫌じゃないというか、楽しい瞬間もあるのです。
ただ、仕事が自分の人生のほとんどを占めている感じが嫌だなあ。
もっとさ、近所をぶらぶら歩いて花を愛でたり暖かい風を感じたりしたいんだよね。
ベンチに座って行き交う人を眺めたり、遠くから聞こえてくる物音に耳を澄ませたりしたい。
自転車で少し遠くに行って、普段飲まないようなものを自販機で買って飲みたい。
自分とは違う世界を持っている、誰かに思いを馳せたりしたい。
たぶんちょっと疲れているんです。
最近は人間同士の調整をしたり、着地点を探ったり、政治的な業務を多くやっているからですね。
今日は早く寝たい。でも早く寝ると翌日の仕事が待ち構えている。
悩ましいところです。
そういえばこの前『ハムレット』を読みました。
ジョン・エヴァレット・ミレーの絵画でも、オフィーリアが亡くなる場面が描かれていますね。
シェイクスピアはこれまで『リア王』と『マクベス』と読みましたが、大学生の頃だったのでもうあまり憶えていません。いつかまた読み返したいな。次は何を読もうかしらん。
『ハムレット』は主人公の気持ちの波がすごかったです。周囲を欺くために狂気を演じるところはもちろん、明晰なときとの差が大きく、ついていくのに精いっぱいなうちに読み終わりました。それこそP-Sポジション的なこころの状態のようにすら感じられました。そうしてそのまま、彼も破滅していきました。
それはそうと。
シェイクスピアの作品のほとんどは、下敷きになる物語があったようで。
この『ハムレット』も、北欧の伝承をもとに書かれたもののようです。
そう考えると、かの偉大なシェイクスピアですら、無から作品を生み出していったわけではないのですよね。
その事実に、ちょっと勇気づけられもします。
人間が本当にいい仕事をできる時期って、限られているんだなあ。
私自身、その時間を無駄にしてはならないなあ、とも思います。
そんなわけでストレスがひとまず落ち着いたところで今日は筆をおきます。
みなさま、よき大型連休をお過ごしください。私も久しぶりの4連休で心がときめいています。