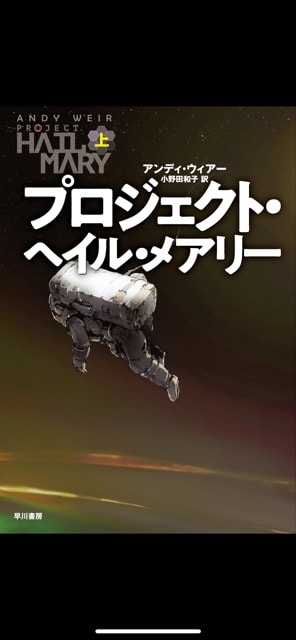
やる気が起きないのでブログを書きます。
おい、ブログ書く気はあるのかよ!って思ったあなた、その通りです。
ブログを書く気持ちはあるんです。
むしろそれしかないと言った方が正しいかもしれません。
年末年始にかけて、久しぶりに英語の論文をちゃんと読みました。
英語を読んでいて思うのは、意外と基礎的な単語の意味理解がむつかしいということ。
たとえばengageやrespect、languageなど。
このようにやさしそうに見える単語こそ、意味の幅が広くて訳す時に困ります。
いっそspontaneously(自然発生的)やadministration(管理部門)みたいな硬いことばの方が、意味の幅が少なくて助かるのです。
日本語でもそうですよね。
「たすかる」には命拾いしたりsafe、役に立ったりusefulする、幅広いニュアンスがあります。
しかし「援助」と表現するとhelpに限定されます。
意外と優しい顔をしているやつらの方が、あなどれません。
あとは接続詞やカンマ。こいつらがまた複雑で。
こいつらを多用する文章に税金をかけてほしいくらいです。
いったい何を並列したり、何を対比させたりしているか。
ここを見失うと一気に意味がわからなくなりますね。言葉は奥深いなあ。
論文を読んでいて思ったのは「頭いいって人から思われて~!!」という欲望がオノレのなかにあること。
そういう気持ちがある時点で、頭がよくないんだよな。
本当に頭がいい方は、「人から頭がいいと思われたい」など考えないと思うので、たぶん。
自分の年になってまで「人から頭いいって思われたい!」気持ちがあるのはダサいですね。
それに自分の頭が良くないことは、長年の勉強を経てある程度わかってきたつもりです。
勉強自体は好きなんですけどね、とほほ。
最近読んで面白かった本のコーナー
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』アンディ・ウィアー
昨年末にKindleで買いました。以前映画化された『火星の人』の作者ですね。
科学的なことはよくわからないのですが、目の前にある問題に対してどのように解決をしていくか、トライアンドエラーのなかで何を見出すか。そのプロセスの描写の一つひとつが見事で、物語のテンポもよく、のめり込むように読んでしまいました。
問題を解決したい気持ち。それは人間の本質的な欲望なのかなと感じます。赤ちゃんでも、四角いブロックを穴にうまく入れられると嬉しそうにしますよね、両手をぱちぱち叩き合わせますよね。小学生も算数が解けると嬉しいし、ゼルダが楽しいです。大人になってもひとつのプロジェクトが落ち着くと安堵します、もちろんゼルダも楽しいです。らせん階段を上るように、深さは違えども似たような場所をぐるぐると回っているのかもしれません。
とてもよいSFでした。そしてSFが好きでなくてもじゅうぶん愉しめると思います。
『ぼくがぼくであること』山中 恒
岩波から出ている児童文学です。
初版が昭和なので多少ステレオタイプ的な描写もあるのですが、とても面白かったです。
この物語のよい点は、とにかく一筋縄ではいかないところ。あんまり言うとネタバレになりますが、物語が着地しそうなところでもう一展開あったり、こちらの予想を上回ることが起きたり…。
また喧嘩のシーンの迫力がすごくて。島尾敏雄の『死の棘』を彷彿とさせるところがありました。もちろん、児童文学なのでこちらの方が表現はマイルドです。
『知ってるつもり 無知の科学』スティーブン・スローマン、フィリップ・ファーンバック
Twitterで本の有益な情報を呟き続けている「本ノ猪さん」のツイートで、この本を知りました。
この場を借りてお礼申し上げます、いつもありがとうございます。
筆者の2人は心理学者です。人間の認知バイアスのことや、「ファスナーの仕組み」の説明を求められると無知に気づくメカニズム、いかにものを知らないままで生きているか、専門知の分担について。
平易な文章で幅広く説明されていてすっと読めるのですが、ふと思い返したときにどんなことが書かれていたか思い出せず、あらためて自身の無知に自覚的になれるよい本でした。また読み返そうと思います。
さて。
今年の目標は「失敗を恐れない」です。
自分がものをよくわかっていないこと、頭がじゅうぶん良くないことを抱えつつ。
じゃあ何がわかっているのか、どこまでわかっているのかを何かしらで形に出来たらいいなと思っています。
ああ、でも今日はもうブログを書く気持ちしかありません。
しかも書き終わってしまったので、全部なくなってしまいました、おしまいです。
どうもありがとうございました。
おい、ブログ書く気はあるのかよ!って思ったあなた、その通りです。
ブログを書く気持ちはあるんです。
むしろそれしかないと言った方が正しいかもしれません。
年末年始にかけて、久しぶりに英語の論文をちゃんと読みました。
英語を読んでいて思うのは、意外と基礎的な単語の意味理解がむつかしいということ。
たとえばengageやrespect、languageなど。
このようにやさしそうに見える単語こそ、意味の幅が広くて訳す時に困ります。
いっそspontaneously(自然発生的)やadministration(管理部門)みたいな硬いことばの方が、意味の幅が少なくて助かるのです。
日本語でもそうですよね。
「たすかる」には命拾いしたりsafe、役に立ったりusefulする、幅広いニュアンスがあります。
しかし「援助」と表現するとhelpに限定されます。
意外と優しい顔をしているやつらの方が、あなどれません。
あとは接続詞やカンマ。こいつらがまた複雑で。
こいつらを多用する文章に税金をかけてほしいくらいです。
いったい何を並列したり、何を対比させたりしているか。
ここを見失うと一気に意味がわからなくなりますね。言葉は奥深いなあ。
論文を読んでいて思ったのは「頭いいって人から思われて~!!」という欲望がオノレのなかにあること。
そういう気持ちがある時点で、頭がよくないんだよな。
本当に頭がいい方は、「人から頭がいいと思われたい」など考えないと思うので、たぶん。
自分の年になってまで「人から頭いいって思われたい!」気持ちがあるのはダサいですね。
それに自分の頭が良くないことは、長年の勉強を経てある程度わかってきたつもりです。
勉強自体は好きなんですけどね、とほほ。
最近読んで面白かった本のコーナー
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』アンディ・ウィアー
昨年末にKindleで買いました。以前映画化された『火星の人』の作者ですね。
科学的なことはよくわからないのですが、目の前にある問題に対してどのように解決をしていくか、トライアンドエラーのなかで何を見出すか。そのプロセスの描写の一つひとつが見事で、物語のテンポもよく、のめり込むように読んでしまいました。
問題を解決したい気持ち。それは人間の本質的な欲望なのかなと感じます。赤ちゃんでも、四角いブロックを穴にうまく入れられると嬉しそうにしますよね、両手をぱちぱち叩き合わせますよね。小学生も算数が解けると嬉しいし、ゼルダが楽しいです。大人になってもひとつのプロジェクトが落ち着くと安堵します、もちろんゼルダも楽しいです。らせん階段を上るように、深さは違えども似たような場所をぐるぐると回っているのかもしれません。
とてもよいSFでした。そしてSFが好きでなくてもじゅうぶん愉しめると思います。
『ぼくがぼくであること』山中 恒
岩波から出ている児童文学です。
初版が昭和なので多少ステレオタイプ的な描写もあるのですが、とても面白かったです。
この物語のよい点は、とにかく一筋縄ではいかないところ。あんまり言うとネタバレになりますが、物語が着地しそうなところでもう一展開あったり、こちらの予想を上回ることが起きたり…。
また喧嘩のシーンの迫力がすごくて。島尾敏雄の『死の棘』を彷彿とさせるところがありました。もちろん、児童文学なのでこちらの方が表現はマイルドです。
『知ってるつもり 無知の科学』スティーブン・スローマン、フィリップ・ファーンバック
Twitterで本の有益な情報を呟き続けている「本ノ猪さん」のツイートで、この本を知りました。
この場を借りてお礼申し上げます、いつもありがとうございます。
筆者の2人は心理学者です。人間の認知バイアスのことや、「ファスナーの仕組み」の説明を求められると無知に気づくメカニズム、いかにものを知らないままで生きているか、専門知の分担について。
平易な文章で幅広く説明されていてすっと読めるのですが、ふと思い返したときにどんなことが書かれていたか思い出せず、あらためて自身の無知に自覚的になれるよい本でした。また読み返そうと思います。
さて。
今年の目標は「失敗を恐れない」です。
自分がものをよくわかっていないこと、頭がじゅうぶん良くないことを抱えつつ。
じゃあ何がわかっているのか、どこまでわかっているのかを何かしらで形に出来たらいいなと思っています。
ああ、でも今日はもうブログを書く気持ちしかありません。
しかも書き終わってしまったので、全部なくなってしまいました、おしまいです。
どうもありがとうございました。











