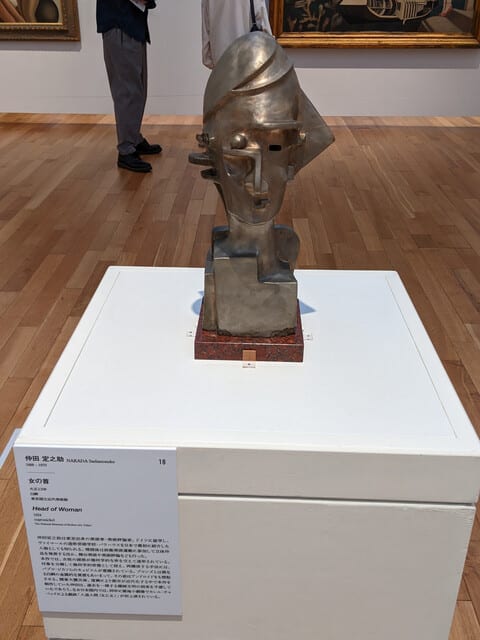
こは如何にせんとあきれたるに、洞の奥に声ありて、「はやく捉へて伴來れ」と呼るほどに、其かたちさまざまにおそろしき妖邪五六十人出来り、三人をとらへて魔王の前につれ行きたり。おそるおそる頭を上て是を見るに、眼は電のごとく、こゑは雷の如く、左右の牙するどく現れ、鉤の如き爪を鳴らして摑み吃んとす。 時に外面より按内して、「熊山君特處士來れり」と罵て、二箇の恠物入来り、何事にや物語り終り、三蔵が二人の従者を引裂てことごとく喰ひ、東方既に明なんとする時、あまたの妖怪何所ともなくかきけして見えずなりぬ。
三蔵は旅に出たとたんに妖怪に襲われた。そんな馬鹿なと思う人は書生ぐらいだ。三蔵なんかお外にでたら一瞬でやられてしまうに決まっているのである、――これは、学者なんか文弱にきまっている、武装もせずに世の中渡るのは無理で、、みたいな理屈であり、わたくしはこのようなものを、とりあえず今日の處は、「ぶっちゃけ論」と言っておきたい。しかし、学問や批評というのは、ぶっちゃけと絵空事の間にすごく具体物、その具体物の反映と派生物などなどがあることに注目するものだ。特に批評は、学者と妖怪の間を取り持つ「発見」をする役割だったはずだ。それは学問への扉であり出口をつくることである。妖怪に寄り添うことではない。
評論家や学者が、発見ではなく、外部的自分が「ぶっちゃけ論」をやってあげます、みたいなことを言う人になってしまった理由は一体何なのであろうか。たぶん有名媒体とかがまだ機能しているからであろうが、それにしても象牙の塔でもそういう人が多いので困惑のいたりである。ドグマにとらわれていない自分は「ぶっちゃけ」お前に××と言えるぜ、という云い方って、私が目撃してきた、ある種のいじめ主犯者の言い分なのである。そのドグマはかなりの確率で学校的なものを指している。田舎の学校を出たわたしにいわせると、ほとんどの連中にとっては学校なんかもともと権威ではない。連中は学校をバカにしているのではないのだ、いじめの時の方便なのである。対して、学校が輪切りの頂点にある進学校出身者におけるマジョリティとは一応学校を権威とみる風な姿勢をみせている。で、上の権威とも思っていない人間たちにくらべて、内なる自分が反学校のマイノリティである。彼らの上のような「いじめッ子」化は、かつて学生運動に入る勇気がなくて自分を責めていたタイプが就職してからなんかガンバルとかと同じで、卒業後にマイノリティだと自分が思っているものになるというパターンではなかろうか。学校世界で自分の周りに反抗的になれないような人間がまたおなじような過ちを犯しているとおもわないところが変であるが、意識的であるがゆえに思えないのであろう。ブルデューは、ハビトゥスとは「無意識」なんだ単に習慣ではないんだと言うが、そこまで人間は素朴であろうか。
つまりこの「ぶっちゃけ論」は、通俗化したブルデューみたいなものだ。ブルデューの原点には、フランクフルト学派が妙に上流階級のようにみえた経験がある。だからなのかわからないが、彼の研究が持つ、読者のルサンチマンを吸い込むブラックホールみたいな性格は顕著だとわたくしは思う。結果、おそらくブルデューのように、読者はルサンチマンを吸い込まれて正義派の紳士になる。最近は学会とかでもハラスメント的な発言はやめましょうみたいな宣言があったりするが、それで世の中うまくゆほど甘くはなく、その威嚇的な言論が抑圧していたのであろう、あきらかにお☆子なタイプが台頭してきている。威嚇に対しては威嚇はやめよと言えるが、頭がお菓×いのはやめてくれとはいえないのだ。しかし、このタイプは、えせブルデューが庶民的で紳士なので、幇間的な態度でいけば仲良くなれ、且つ威張れると思ってしまったタイプなのではないだろうか。――もっとも、こういう状況にいらいらしすぎると、彼らに対してはどこか階級的暴力をしてしまう可能性がある。ついに、プチブルジョアに対する貴族的な何かが暴力として生成する時代になってしまった。
うえの「ぶっちゃけルサンチマン」の起源はどこらあたりにあるのか。まったくわからないが、――彼らと同世代であるわたしの経験を記しておこう。学費値上げ反対闘争はむかしからあり、大学に入っておれもやるのかなあと想像していたところ、行われていたのは、一部の過激なセクトとは距離をとった、学食うどん・カレー値上げ反対運動で、どうみても十分やすいのに要求を呑まされた食堂のおばちゃん達がかわいそうであった。で、結果、おされな資本主義のまわしものみたいな食堂がとってかわり、値段は爆上がりし、それに慣れた腐敗学生の巣窟になってしまったのである。あのあたりから、運動が「調子こいた腐敗大衆」に抑圧されたマイノリティ(つまり自分である)擁護に変わっていった気がする。転向というのはいろいろな現実を背景に起こるものである。
緩やかに言い直して、現代の啓蒙主義的なひとたちと呼ぶが、そこに大正教養主義とか日本の大学の頑迷性をみてもしかたがない。八〇年代からゼロ年代をよく考えなきゃいけないのである。
大学の研究者は案外、大学や、へたすると大学院の段階で対象の面白さに目覚める「遅い」タイプが多い。上のひとたちの世代はとくにそうだ。受験戦争の延長の側面があるのである。しかし、大学に入った頃にすでに文学や思想にくるって10年ぐらいみたいな年季の入ったわたくしのようなタイプは、入学した頃はすでに面倒くさいかんじになっている。しかしマジョリティが文学青年ではないので、大学はあまり大切にしてくれない予感があった。特に大学院ではそれを感じた。わたくしは、先生達に恵まれたから生きのびたが、みんながそうであったとは限らないと思う。



















