三回前の話の続き。
前にも引用した「日活の社史と現勢」(昭和5年)という古い本の巻末に千恵蔵が書いた文章があったことを思い出し、引っ張り出してみた。
題名は「若者の団結『千恵蔵映画』を素描す」。日本活動写真会社提携千恵蔵映画サガノ撮影所盟主という肩書で、片岡千恵蔵とあり、なんと!書き出しがこうなっている。
私が映画に関係したのは関東大震災直後遊んでいた時、懇意に願っていた本荘子爵の紹介により小笠原プロダクションで『三色すみれ』の主役を演じたのが最初で、其後松居松翁氏から城戸四郎氏を経て野村芳亭氏に紹介され、松竹の蒲田に入ることになっていたのが、野村氏の下加茂行で立ち消えたので再び恩師片岡仁左衛門氏の下で舞台を踏むことになった。従って、私の映画界入りは一時中絶したけれど決して斯界に対する希望を捨てたのではなく、殊に、歌舞伎に対する心の動揺を感じていた際とて、依然その機会の来る事をひそかに待望していたのである。
最初の2行に千恵蔵自身が書いているではないか、小笠原プロの『三色すみれ』が映画デビュー作だと。紹介者の本荘子爵の名前も出ている。それに本荘には本文では「ほんそう」とルビかふってある。
これで判明。「日本映画俳優全集 男優編」(1979年キネマ旬報社)の片岡千恵蔵の項目を書いた滝沢一は千恵蔵のこの文章を参考にしたことが確かになった。
が、この本荘子爵という人物が依然としてナゾである。苗字は分るが、名前は何というのだろう? 誰だか分らないじゃないか。
この事典が発行された時点では、片岡千恵蔵はまだ生きていのだから、本人に確かめるべきであったし、もし本人が憶えていないのなら、執筆者が調べなければならない。
執筆者の滝沢一(1914~1993)の名前の「一」は、「おさむ」と読むそうで、通称は「ピンさん」。京都の映画人について多くの著作を遺した映画評論家で、彼の「映画歳時記」という本は私の愛読書の一つだが、滝沢ピンさん、こうした人名事典の記載は正確を期すべきだと思いますが、どうでしょうか。が、滝沢ピンさんの書いた項目などずっとマシなほうで、他の映画評論家の文章にはやっつけ仕事でひどいものが多いし、誤りも目立つ。注意が必要だ。岸松雄氏の書いたものは文章は主観的で面白いが、やや正確さに欠ける。
さて、本荘子爵だが、インターネットという便利なものがあるので(誤りの拡大普及で問題も多いが)、調べてみた。
すると、「麻雀概史 日本への伝播」というページに本荘子爵という名が出て来るではないか。そうか、千恵蔵は麻雀(マージャン)が大好きだったので、そのつながりなのかもしれない。千恵蔵の言っている「懇意に願っていた本荘子爵」の「懇意」とは、麻雀仲間のことなんじゃないか。
日本で麻雀が普及し始めたのは大正10年代だったそうだ。普及者の一人に中国で麻雀を習い覚えて帰国した空閑緑(くがみどり)という人がいて、この人が、
「大正13年の夏、四谷に東京麻雀会の看板を掲げ、無報酬で家庭麻雀の出張教授を行うなど、活発な活動を行った。この空閑緑の無料教授を受けた人が、丹後宮津の旧藩主・本荘子爵家等の華族などであったことなどから上流家庭に麻雀熱が広がったと云われる」
「丹後宮津の旧藩主・本荘子爵」とあるではないか。千恵蔵(当時は千栄蔵で20歳)が本荘子爵に紹介されて小笠原プロへ行ったのは関東大震災後の大正12年9月以降。同年2月に名題になってからも千恵蔵は東京の歌舞伎界で良い役がつかず、無聊をかこっていたらしいから、震災前後のある時期に麻雀を覚えたことは十分考えられる。
でも待てよ。本荘子爵というのは一人ではないかもしれない。そこで、またインターネットで「華族 近代日本の名家」というページを覗いてみると、あった! 一人しかいない。
本荘
子爵
武家
本荘宗武
丹後宮津藩7万石
5代将軍徳川綱吉の生母(桂昌院)の家系
姓名・本荘宗武である。なんと読むのだろう。「ほんそうむねたけ」か?
今度はウィキペディアのお世話になる。
松平 宗武(まつだいら むねたけ、本庄 宗武/本荘 宗武)
丹後宮津藩の第7代(最後の)藩主。本庄松平家10代。
弘化3年(1846年)6月9日、第6代藩主・松平宗秀の五男として生まれる。
(中略)
明治2年(1869年)6月19日、版籍奉還により宮津知藩事に任じられ、明治4年(1871年)7月15日の廃藩置県で知藩事職を免職された。明治6年(1873年)からは開拓使として北海道の農業開拓に従事したが、父が死去すると宮津に戻り、以後は籠神社の宮司として働く一方で、俳句の世界をたしなんだといわれる。
明治17年(1884年)、子爵に列した。
明治26年(1893年)4月28日に死去。享年48。
あれっ! 明治26年に死んじゃっている。この人じゃない!
子爵を継いだ息子のほうだ。名前は、本荘宗義。
検索するとお墓が出て来た。
「貴族院議員従三位勲四等子爵本荘宗義墓」
お墓は足立区東伊興、竹ノ塚近くの法受寺にある。
貴族院議員をやっていたのは明治39年~44年。それ以外に何も分らない。
千恵蔵が懇意にしていた本荘子爵は大正12年頃に生きていた人だが、この本荘宗義は明治一ケタ生まれだとして、大正12年だと50歳くらいだから、この人に間違いない。
そこでまた「麻雀概史」のページから、
「大正12年、関東大震災が発生した。銀座にあったカフェー・プランタンが新宿区牛込神楽坂で仮営業した。店主・松山省三は著名な画家であり、妻の松井潤子も女優という関係で画家・俳優はもとより多くの文人墨客が出入りし、当時ようやく日本に伝来した麻雀が楽しまれた。この店へ洋行帰りの市川猿之助と平岡権八郎が上海で買った麻雀牌を店に持ち込んだ。最初は松山省三・松井潤子夫妻を初め、佐々木茂索、広津和郎、片岡鉄兵などがうろ覚えでやっていたが、やがて後に牌聖と謳われる林茂光を初め、前島吾郎、古川緑波、川崎備寛、長尾克など、多くの文人、画家、芸能人が集まり、麻雀を楽しんだ南部修太郎「麻雀を語る」)。麻雀時代の夜明けを告げる光景であり、これを世にプランタン時代と称する。後年、このとき指導を受けたメンバーが日本麻雀界の指導者となる」
もしかすると、カフェー・プランタンで千恵蔵は麻雀をやったことがあったのかもしれない。そしてこの本荘子爵というのも麻雀概史に名前が残るほどの麻雀狂だったから、プランタンに出入りしていた可能性があり、そこで二人は雀卓を囲んだ、なんてことも想像できる。
もう一つ分ったことは、本荘家のお屋敷は、市ヶ谷近くの曙橋にあったということ。
震災後移転したプランタンがあった神楽坂の近くではないか。ということは、この本庄子爵が神楽坂のプランタンへ通って、麻雀をやっていたことも十分あり得るのではなかろうか。そこには小笠原プロの関係者である古川緑波や松井潤子(松井千枝子の妹で小笠原プロの『金色夜叉』に姉妹揃って出演したようだ)もいて麻雀をやっていたらしいから、彼らも千恵蔵に小笠原プロ入りを勧めたのかもしれない。千恵蔵の映画デビュー作『三色すみれ』には古川緑波も出演しているが、二人はその前に雀友だった、なんて。
それと、かの松井潤子がプランタン店主の松山省三と結婚していたということはホントなのだろうか? 「日本映画俳優全集 女優編」(キネマ旬報社)によると、そんなことはまったく書いていない。彼女は1906年12月生まれだというから、大正12年(1923年)だとまだ17歳ではないか。松竹に入って清純派の人気女優となり、28歳で巨人軍の水原茂と結婚したとばかり思っていたが……。
前にも引用した「日活の社史と現勢」(昭和5年)という古い本の巻末に千恵蔵が書いた文章があったことを思い出し、引っ張り出してみた。
題名は「若者の団結『千恵蔵映画』を素描す」。日本活動写真会社提携千恵蔵映画サガノ撮影所盟主という肩書で、片岡千恵蔵とあり、なんと!書き出しがこうなっている。
私が映画に関係したのは関東大震災直後遊んでいた時、懇意に願っていた本荘子爵の紹介により小笠原プロダクションで『三色すみれ』の主役を演じたのが最初で、其後松居松翁氏から城戸四郎氏を経て野村芳亭氏に紹介され、松竹の蒲田に入ることになっていたのが、野村氏の下加茂行で立ち消えたので再び恩師片岡仁左衛門氏の下で舞台を踏むことになった。従って、私の映画界入りは一時中絶したけれど決して斯界に対する希望を捨てたのではなく、殊に、歌舞伎に対する心の動揺を感じていた際とて、依然その機会の来る事をひそかに待望していたのである。
最初の2行に千恵蔵自身が書いているではないか、小笠原プロの『三色すみれ』が映画デビュー作だと。紹介者の本荘子爵の名前も出ている。それに本荘には本文では「ほんそう」とルビかふってある。
これで判明。「日本映画俳優全集 男優編」(1979年キネマ旬報社)の片岡千恵蔵の項目を書いた滝沢一は千恵蔵のこの文章を参考にしたことが確かになった。
が、この本荘子爵という人物が依然としてナゾである。苗字は分るが、名前は何というのだろう? 誰だか分らないじゃないか。
この事典が発行された時点では、片岡千恵蔵はまだ生きていのだから、本人に確かめるべきであったし、もし本人が憶えていないのなら、執筆者が調べなければならない。
執筆者の滝沢一(1914~1993)の名前の「一」は、「おさむ」と読むそうで、通称は「ピンさん」。京都の映画人について多くの著作を遺した映画評論家で、彼の「映画歳時記」という本は私の愛読書の一つだが、滝沢ピンさん、こうした人名事典の記載は正確を期すべきだと思いますが、どうでしょうか。が、滝沢ピンさんの書いた項目などずっとマシなほうで、他の映画評論家の文章にはやっつけ仕事でひどいものが多いし、誤りも目立つ。注意が必要だ。岸松雄氏の書いたものは文章は主観的で面白いが、やや正確さに欠ける。
さて、本荘子爵だが、インターネットという便利なものがあるので(誤りの拡大普及で問題も多いが)、調べてみた。
すると、「麻雀概史 日本への伝播」というページに本荘子爵という名が出て来るではないか。そうか、千恵蔵は麻雀(マージャン)が大好きだったので、そのつながりなのかもしれない。千恵蔵の言っている「懇意に願っていた本荘子爵」の「懇意」とは、麻雀仲間のことなんじゃないか。
日本で麻雀が普及し始めたのは大正10年代だったそうだ。普及者の一人に中国で麻雀を習い覚えて帰国した空閑緑(くがみどり)という人がいて、この人が、
「大正13年の夏、四谷に東京麻雀会の看板を掲げ、無報酬で家庭麻雀の出張教授を行うなど、活発な活動を行った。この空閑緑の無料教授を受けた人が、丹後宮津の旧藩主・本荘子爵家等の華族などであったことなどから上流家庭に麻雀熱が広がったと云われる」
「丹後宮津の旧藩主・本荘子爵」とあるではないか。千恵蔵(当時は千栄蔵で20歳)が本荘子爵に紹介されて小笠原プロへ行ったのは関東大震災後の大正12年9月以降。同年2月に名題になってからも千恵蔵は東京の歌舞伎界で良い役がつかず、無聊をかこっていたらしいから、震災前後のある時期に麻雀を覚えたことは十分考えられる。
でも待てよ。本荘子爵というのは一人ではないかもしれない。そこで、またインターネットで「華族 近代日本の名家」というページを覗いてみると、あった! 一人しかいない。
本荘
子爵
武家
本荘宗武
丹後宮津藩7万石
5代将軍徳川綱吉の生母(桂昌院)の家系
姓名・本荘宗武である。なんと読むのだろう。「ほんそうむねたけ」か?
今度はウィキペディアのお世話になる。
松平 宗武(まつだいら むねたけ、本庄 宗武/本荘 宗武)
丹後宮津藩の第7代(最後の)藩主。本庄松平家10代。
弘化3年(1846年)6月9日、第6代藩主・松平宗秀の五男として生まれる。
(中略)
明治2年(1869年)6月19日、版籍奉還により宮津知藩事に任じられ、明治4年(1871年)7月15日の廃藩置県で知藩事職を免職された。明治6年(1873年)からは開拓使として北海道の農業開拓に従事したが、父が死去すると宮津に戻り、以後は籠神社の宮司として働く一方で、俳句の世界をたしなんだといわれる。
明治17年(1884年)、子爵に列した。
明治26年(1893年)4月28日に死去。享年48。
あれっ! 明治26年に死んじゃっている。この人じゃない!
子爵を継いだ息子のほうだ。名前は、本荘宗義。
検索するとお墓が出て来た。
「貴族院議員従三位勲四等子爵本荘宗義墓」
お墓は足立区東伊興、竹ノ塚近くの法受寺にある。
貴族院議員をやっていたのは明治39年~44年。それ以外に何も分らない。
千恵蔵が懇意にしていた本荘子爵は大正12年頃に生きていた人だが、この本荘宗義は明治一ケタ生まれだとして、大正12年だと50歳くらいだから、この人に間違いない。
そこでまた「麻雀概史」のページから、
「大正12年、関東大震災が発生した。銀座にあったカフェー・プランタンが新宿区牛込神楽坂で仮営業した。店主・松山省三は著名な画家であり、妻の松井潤子も女優という関係で画家・俳優はもとより多くの文人墨客が出入りし、当時ようやく日本に伝来した麻雀が楽しまれた。この店へ洋行帰りの市川猿之助と平岡権八郎が上海で買った麻雀牌を店に持ち込んだ。最初は松山省三・松井潤子夫妻を初め、佐々木茂索、広津和郎、片岡鉄兵などがうろ覚えでやっていたが、やがて後に牌聖と謳われる林茂光を初め、前島吾郎、古川緑波、川崎備寛、長尾克など、多くの文人、画家、芸能人が集まり、麻雀を楽しんだ南部修太郎「麻雀を語る」)。麻雀時代の夜明けを告げる光景であり、これを世にプランタン時代と称する。後年、このとき指導を受けたメンバーが日本麻雀界の指導者となる」
もしかすると、カフェー・プランタンで千恵蔵は麻雀をやったことがあったのかもしれない。そしてこの本荘子爵というのも麻雀概史に名前が残るほどの麻雀狂だったから、プランタンに出入りしていた可能性があり、そこで二人は雀卓を囲んだ、なんてことも想像できる。
もう一つ分ったことは、本荘家のお屋敷は、市ヶ谷近くの曙橋にあったということ。
震災後移転したプランタンがあった神楽坂の近くではないか。ということは、この本庄子爵が神楽坂のプランタンへ通って、麻雀をやっていたことも十分あり得るのではなかろうか。そこには小笠原プロの関係者である古川緑波や松井潤子(松井千枝子の妹で小笠原プロの『金色夜叉』に姉妹揃って出演したようだ)もいて麻雀をやっていたらしいから、彼らも千恵蔵に小笠原プロ入りを勧めたのかもしれない。千恵蔵の映画デビュー作『三色すみれ』には古川緑波も出演しているが、二人はその前に雀友だった、なんて。
それと、かの松井潤子がプランタン店主の松山省三と結婚していたということはホントなのだろうか? 「日本映画俳優全集 女優編」(キネマ旬報社)によると、そんなことはまったく書いていない。彼女は1906年12月生まれだというから、大正12年(1923年)だとまだ17歳ではないか。松竹に入って清純派の人気女優となり、28歳で巨人軍の水原茂と結婚したとばかり思っていたが……。










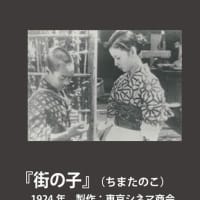



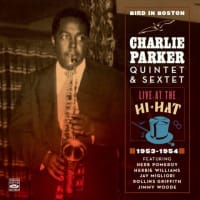
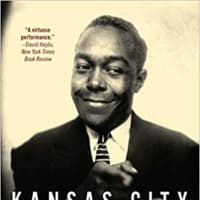

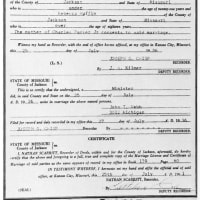



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます