仕事で出かけた水戸の帰りに、
かねてから行きたかった鹿島鉄道線(旧関東鉄道鉾田線)の廃線跡を訪れた。
特に鉄道に興味があるわけではないが、
この私鉄線だけは特別な思い入れがある。
東京で育った両親が、戦時中疎開していた先が鹿島鉄道線の沿線だったため、
子供の頃両親に連れられて、よくこの電車に乗った。
電車・・・いや、ディーゼルで走るから、電車とは言わないのだろう。
鹿島鉄道線は自分にとっては鉾田線としての記憶しかないので、
これからは鉾田線と書く事にしよう。
鉾田線は、常磐線の石岡駅から出発して約30キロ。
終点の鉾田駅までの単線の私鉄だった。
上野から1時間とは思えない程長閑な田園地帯を、
1輛編成(混雑時は2輛)のディーゼルカーがいなたく走る様子は、
子供心に強烈に刷り込まれたのか、
今でもはっきりと思い出す事ができる。
▼現役時代の様子
鉄の匂い / 鹿島鉄道 平成15年5月19日
父親の故郷は石岡から約15分の常陸小川という駅から、
バスで30分位のところだった。
また母親の故郷は終点鉾田駅から、
やはり同じくバスで30分くらいのところだった。
なので、この2つの駅は思い出深いが、
特に鉾田駅は、別の路線にアクセスする駅ではなく、
地図で見ても線路がそこでプツッリ終わっている終着駅だったので、
線路が必ずどこかへ繋がっている東京の駅しかしらない自分には、
地の果てへ来てしまったような気がして、それだけで物珍しかった。
昨日アップした船のレストラン アリューシャンに失望しつつ、
国道51号を南下して鉾田駅を目指す。
鉾田町へ入ると、記憶の片隅に残る景色が断片的に現れる様になり、
まぶたに残る鉾田駅の駅舎が徐々に近づいているのに、
すこし興奮している自分がいた。

しかしいざ鉾田駅に着いてみると、
もうそこに駅舎はなく、
駅舎の跡地に真新しい砂利が敷き詰められているだけだった。
いくらいなたい田園風景が広がる土地でも、
やはり東京の近郊だということを痛切に感じる。
鉾田駅は降車用と乗車用のホームが単線の両側にある駅だったが、
かろうじてこのホームと線路は残っていて、
そして構内には3輛だけ車輛も残っている。
また当時から駅前にあった、売店と食堂と休憩所をかねた建物も残っていた。

鉄道廃止後、路線に沿ってバスが運行しているので、
バスが発着する駅前のロータリーはそのままの雰囲気だった。
ほぼ記憶の通りの鉾田駅だったが、やはり駅舎がないのはとても寂しい。
とりあえず残っているホームを見ておこうと線路伝いに近づくと、
石造りのホームに挟まれた線路の丁度真ん中あたりが、
油ですごく真っ黒く湿っていた。

ディーゼルカーの構造はわからないが、
駅に停車している間に車輛から垂れた油の跡だと思う。
鼻をつく強烈な油の臭をかいだとたんに、
幼少の頃の記憶が一気に吹き出してきた。
> 鹿島鉄道線 #02 田舎の思ひ出(後編)
★ 廃線跡の記録 2 ★
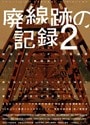

KLO@廃墟徒然草による鹿島鉄道線のリポート掲載。
その他、鉄道ファンとはひと味違う、
ワンダーJAPANならではの廃線跡の記録が満載。
かねてから行きたかった鹿島鉄道線(旧関東鉄道鉾田線)の廃線跡を訪れた。
特に鉄道に興味があるわけではないが、
この私鉄線だけは特別な思い入れがある。
東京で育った両親が、戦時中疎開していた先が鹿島鉄道線の沿線だったため、
子供の頃両親に連れられて、よくこの電車に乗った。
電車・・・いや、ディーゼルで走るから、電車とは言わないのだろう。
鹿島鉄道線は自分にとっては鉾田線としての記憶しかないので、
これからは鉾田線と書く事にしよう。
鉾田線は、常磐線の石岡駅から出発して約30キロ。
終点の鉾田駅までの単線の私鉄だった。
上野から1時間とは思えない程長閑な田園地帯を、
1輛編成(混雑時は2輛)のディーゼルカーがいなたく走る様子は、
子供心に強烈に刷り込まれたのか、
今でもはっきりと思い出す事ができる。
▼現役時代の様子
鉄の匂い / 鹿島鉄道 平成15年5月19日
父親の故郷は石岡から約15分の常陸小川という駅から、
バスで30分位のところだった。
また母親の故郷は終点鉾田駅から、
やはり同じくバスで30分くらいのところだった。
なので、この2つの駅は思い出深いが、
特に鉾田駅は、別の路線にアクセスする駅ではなく、
地図で見ても線路がそこでプツッリ終わっている終着駅だったので、
線路が必ずどこかへ繋がっている東京の駅しかしらない自分には、
地の果てへ来てしまったような気がして、それだけで物珍しかった。
昨日アップした船のレストラン アリューシャンに失望しつつ、
国道51号を南下して鉾田駅を目指す。
鉾田町へ入ると、記憶の片隅に残る景色が断片的に現れる様になり、
まぶたに残る鉾田駅の駅舎が徐々に近づいているのに、
すこし興奮している自分がいた。

しかしいざ鉾田駅に着いてみると、
もうそこに駅舎はなく、
駅舎の跡地に真新しい砂利が敷き詰められているだけだった。
いくらいなたい田園風景が広がる土地でも、
やはり東京の近郊だということを痛切に感じる。
鉾田駅は降車用と乗車用のホームが単線の両側にある駅だったが、
かろうじてこのホームと線路は残っていて、
そして構内には3輛だけ車輛も残っている。
また当時から駅前にあった、売店と食堂と休憩所をかねた建物も残っていた。

鉄道廃止後、路線に沿ってバスが運行しているので、
バスが発着する駅前のロータリーはそのままの雰囲気だった。
ほぼ記憶の通りの鉾田駅だったが、やはり駅舎がないのはとても寂しい。
とりあえず残っているホームを見ておこうと線路伝いに近づくと、
石造りのホームに挟まれた線路の丁度真ん中あたりが、
油ですごく真っ黒く湿っていた。

ディーゼルカーの構造はわからないが、
駅に停車している間に車輛から垂れた油の跡だと思う。
鼻をつく強烈な油の臭をかいだとたんに、
幼少の頃の記憶が一気に吹き出してきた。
> 鹿島鉄道線 #02 田舎の思ひ出(後編)
★ 廃線跡の記録 2 ★
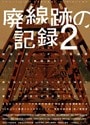

KLO@廃墟徒然草による鹿島鉄道線のリポート掲載。
その他、鉄道ファンとはひと味違う、
ワンダーJAPANならではの廃線跡の記録が満載。








































