リーダシップについて、直近の 新国立競技場設計に関する問題が露呈されたばかりですが、
ちょうどタイミングよく、いつものH氏からの配信記事にその本質がいつまでたっても変わらないとの
痛切な指摘がありましたので、ご紹介させていただきたいと思いました。
先の大戦の6つの例を引き、ことごとく敗戦の決着を見た“失敗の本質”(戸部良一、野中郁次郎他、
中央公論社、1998.3 15版)に見る日本の組織、意識構造に基づく自己革新能力の欠如並びに
概念の創造欠如が、今また繰り返されているのです。 過去の決定的な失敗を反省することを避けたがる
穏便気質に加えて、現状の部分最適解を求める傾向が今また、散見されるというのです。
記事は、戦後70年が、丁度平成の失われた20年に重なるとして、その対比も加えた評価の視点に立った
警鐘を発しています。 それでは前置きが長くなりましたが、以下にコピペします。
記事内容とは関係ありませんが、今頃のクロコスミアです。
 (2015.7.19)
(2015.7.19)
****************************
「『太平洋戦争の肉声』 日本型リーダーの致命的な欠陥」
船橋 洋一(ジャーナリスト) (文藝春秋 2015年8月号 p162-177)
【要旨】今年2015年は第二次世界大戦終戦から70年という節目の年に当たる。本記事の筆者、
元朝日新聞記者のジャーナリスト、船橋洋一氏は、この70年という節目が、ちょうど年号が平成に
なってからの「失われた20年」の果てに位置することを指摘。その20年に日本が経験したさまざまな
失敗(=敗戦)と、先の大戦における敗戦の原因を重ねてみることができると主張する。戦前と戦後は
コインの裏表にすぎず、いずれにおいても、日本特有の組織やリーダーシップの欠陥が敗戦を招いたのだ
という。本記事では、『太平洋戦争の肉声』シリーズ(文藝春秋刊)に集められている、将官や
兵士として戦争にかかわった日本人の体験談をもとに、ガダルカナル撤退、インパール作戦、レイテ島と特攻などの具体的な戦局で日本はどういう過ちを犯したのかを、その要因とともに検証している。
------------------------------------------------------------
戦後70年は平成の「失われた20年」のトンネルの果てに位置するが故に、そこでの「敗戦」が先の
戦争の「敗戦」と重なって見える。
平成の幕開けとともに、日本は敗戦に次ぐ敗戦を重ねた。バブルが破裂し、銀行の不良債権問題が
泥沼化し、国家債務が膨張した。デフレが深まり、人口が減少に向かい、原発がメルトダウン事故を
起こした。これらの困難にぶつかるたびに、私たちは改めて日本の組織文化の弱さと欠陥を思い知らされた。
「失われた20年」の「敗戦」の本質が、先の大戦のそれと驚くほど似通っていることをどう考えれば
よいのか。たとえば、次のようなことだ。異論や反論は、既定路線への疑問と挑戦と見なされ、
排除される。議論も会議も手順も儀式化され、目的と手段をクリティカルに問うことは嫌われ、
先例を踏襲し、プロセスを無事こなしていくことが奨励される。中でも、従来の路線や政策を止め
なければならない「損切り」は、組織としての失敗を認めることになるため、なかなか決断できない。
組織の「縦割り」「たこつぼ」が個々の組織をムラ社会として固定化させる。そこでは、内部の秩序の
安定と人間関係の維持が何よりも重視されるため、組織を超えたステークホールダーを巻き込んだ
全体最適解の探求より先に、個々の組織の中での部分最適解を求めることに関心が集中してしまう。
戦前、戦後に関わりなく、日本の組織は、危機的状況を招来する事象や出来事の事実認定と原因究明を
真摯に、そして独立の立場から検証しない。個人としても組織としても、社会的、組織的に不都合な
真実をぼかそうとする重力が働くからである。
真実をとらえないことには、教訓を引き出せない。そして、教訓を学ぶことができないと、備えが
できない。再び危機が起こった場合、適切な対応ができない。その繰り返しである。それは、最も大切な
備えが反省する心だからである。戦略と統治の両面で、組織の学習能力を高める必要がある。
それには「反省力」が欠かせない。
戦後70年、私たちにいま一度、求められているのは、この「反省力」にほかならない。真摯に歴史に
向き合い、検証し、教訓を学び続ける「反省力」である。
1942年8月5日、大本営は、オーストラリアが米軍の対日反攻作戦の拠点となるのを防ぐため、
米豪を遮断することを目的とし、ガダルカナル島に飛行場を完成させた。ところが、その二日後、
米海兵隊が対岸のツラギ島を急襲し、日本側の海軍守備隊が全滅、ガダルカナルの飛行場も米軍に占領された。
大本営は飛行場奪回のため、次から次へと戦力の逐次投入を行っては、そのたびに壊滅的な打撃を受け、
戦力を消耗した。その揚げ句、制海権を奪われ、投入した陸軍部隊は深刻な飢餓に見舞われた。
年末までに日本軍は31,358名の兵力を投入、2万千余名が戦死した。その3分の2以上が戦闘ではなく
栄養失調やマラリアなどの病気が原因だった。
ガダルカナルは、その後、戦力を逐次投入する愚の代名詞となった。福島原発事故の際、政府と
東電の統合対策本部に詰めた外務省の幹部を取材したことがある。彼は、本店側が事故現場からの資材・
人員の要求に対して何事も受け身で、決断に手間取り、決めても小出しにする様をテレビ会議で見て、
「これはガダルカナルだな」と思ったと述懐した。ガダルカナルはこんな風に日本の国民の意識の基層を
成している。
小出しの逐次投入症候群は、「最悪のシナリオ」を考えたくない心理的抵抗からも来ている。
米国の連邦緊急事態管理庁(FEMA)は、危機の際の物動作戦は「Go Early, Go Fast, Go Big」の三つを
要諦としているが、日本にもっとも欠けている動作がこのうちのGo Bigである。「最悪のシナリオ」を
想定するのを忌避する心理に、Go Bigの発想は生まれにくい。
太平洋戦争は陸海軍が戦略を共有できず、海軍が戦線を拡大し、陸軍がそれに引きずられる形で
突き進んだ。戦闘においても、陸軍と海軍の航空隊はそれぞれ別個に航空戦を戦い、それぞれ別々に
陣地を構築して地上戦を戦った。
敗戦後、陸軍と海軍は敗戦の原因を相手のせいにした。天皇、陸軍、海軍の三者の不一致は、
この時期の日本の最大のガバナンス上の欠陥だった。
その背景には、全体を見て、全体をつかみ、全体を動かすことが苦手な日本の細切れガバナンスの
体質がある。ここでは、個々の組織の部分最適解が全組織の全体最適解を凌駕してしまう力学が執拗に
働くのだ。
1944年10月17日、米軍はフィリピン中部のレイテ島への上陸作戦を開始した。レイテ作戦に従軍した
神子清(伍長)は米国人の戦闘の仕方に戸惑いと、そして戦慄を覚えた。米国が15回戦を戦い抜く体力と
その消耗度合いの配分を管理するタフ・ビジネスを旨としているとすれば、日本は「この一撃」に
総てを託す気力頼みだった。
同じフィリピン戦線で従軍した山本七平は、日本人は「現実的解決を心理的解決に置き換えようとする」
特徴があると指摘したことがある。心理的解決という「精神的一撃論」である。戦争末期、この
「精神的一撃論」が何度も顔を出すことになる。その行き着く果てが特攻だった。
特攻隊員の「死所は一つ」の運命共同体に抱かれて死途につく、その使命感と連帯感と、家族への
愛と責任感と、そしてある種の諦観。若い彼らの清逸な無私の姿勢は今なお、人々の心を激しく揺さぶる。
しかし、無策と無謀の果てに、日本の軍部が「現実的解決を心理的解決に置き換えようとする」べく、
彼らを玉砕の華として神話化し、使い棄てた、冷厳たる事実を記憶しておかなくてはならない。
彼らは「英雄」でもなければ、「犬死に」でもない。むろんテロリストではない。
歴史家の保阪正康は、生き残ったかつての特攻隊員の上官が唱える「美化論」には「戦争という
メカニズムのなかでの人為的政策の犠牲者という視点がみごとなまでに欠落している」と書いた。
「むしろ志願であるとして軍上層部は責任のがれを図るが、現実には『命令』という状態」が実相に
近かった、というのである。
「日本はなぜ、あのような戦争を始め、あのようにしか終わらせることができなかったのか」。
この疑問に凝縮した形で答えようとするならば、リーダーシップが足りなかったからである、としか
言いようがない。リスクに正面から取り組み、ガバナンスを効かし、全体を見て、全体を動かすには、
リーダーシップが欠かせない。
そして、危機において、リーダーシップは往々にして勇気と同義語になる。恐らく戦前の政治リーダー
シップにおいて最も欠けていたのは、この勇気だっただろう。
戦後、吉田茂の指示によって外務省の中堅職員がまとめ上げた日本外交の反省の書『日本外交の過誤』
(作業ペーパー)は、「終戦外交」に関して、その末尾にこう記した。「当時の廟堂に智者はあったかも
知れないが、勇者の無かったことを歎ぜざるを得ない」
コメント: 筆者の指摘する日本型組織の欠陥は、新国立競技場問題をはじめ、現在起きている多くの
社会問題に当てはめることができる。部分最適解が全体最適解を凌駕したり、精神論に逃げたり、
既定路線を見直せなかったりするのは、日本人が場当たり的に「手っ取り早さ」に飛びつくというクセを
もっているからではないか。現状を「点」ではなく、過去と未来につながる「線」、さらにはさまざまな
視点を含む「面」で捉えられるリーダーシップが絶対的に必要。そしてそのためには、過去の失敗
のみならず成功についても、その要因を冷静に分析できる真の「反省力」が不可欠なのだと思う。 Copyright:株式会社情報工場
*************************
先ごろ衆院を通過した 『安保関連法案』 が、どうぞ “部分最適解” でないことを望んでいます・・。












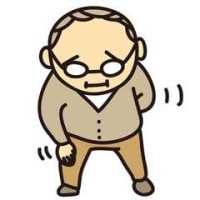














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます