
「空海と密教美術展」@東京国立博物館
空海の幼名は(真魚)まおちゃん。そういうわけで、朝一で開館直前に東博に行くと表慶館の前にいきなり行列ができていた。あ、なんだこりゃ、と思ったが、行列の始まりは表慶館の前だった。ほどなく平成館入り口に誘導されたので事なきを得たが、ぞくぞくやってくる観客で館内はそれなりに混雑していた。
展示場レイアウトを見るといちばん最後が「仏像曼荼羅」となっていたので、いきなり最後の出口に逆行、すると目の前にゾウに乗った池麺帝釈天が現れた。この帝釈天はけっこう好き。帝釈天の前には先客がひとりいるくらいで、その瞬間だけ東寺の講堂と同じくらいの静寂を体感できた。ここでは仏像をぐるりと回り込んで見ることができる。講堂ではなかなか見えないゾウの尻、割と四角いゾウの尻の真ん中からゆらりと垂れさがった長い尻尾。帝釈天の腕には市役所のおじさんみたいな黒い腕ぬき。この帝釈天の顔は傷んだために後に造りかえられたものだと何かに書いてあった。まさかの整形池麺だったのか?
今回は東寺の《立体曼陀羅》21体のうち8体の国宝が出張してきている。それらが講堂と同じ立ち位置に並べられて、曼荼羅の雰囲気を体感することができる。帝釈天の隣には大威徳明王が水牛に乗っている。いちばん右には梵天がガチョウに乗っている。ゾウやウシならわかるが、4羽の小さなガチョウの乗っちゃうってのはいかがなものか、そうこうするうちにだんだん人が増えてきたので移動。
京都・醍醐寺の大威徳明王はまんまるおめめのかわいい水牛に、これでもかっていうほど怒った顔で乗っている明王。もう、ウシくんが不憫で不憫で。
東寺以外にも、醍醐寺の如意輪観音、五大明王、仁和寺の阿弥陀如来、神護寺の虚空蔵菩薩なども来ている。曼荼羅では、高野山・金剛峯寺の血曼荼羅、神護寺の高尾曼荼羅、東寺の西院曼荼羅などがあって、西院曼荼羅は鮮やかでよく見える。高尾曼荼羅は最古の曼荼羅とかいうありがたいものだが、まっ黒けでなんだかもうよくわからない。
《崔子玉座右銘断簡》
「人の短をいうこと無かれ 己の長をとくこと無かれ」
空海の幼名は(真魚)まおちゃん。そういうわけで、朝一で開館直前に東博に行くと表慶館の前にいきなり行列ができていた。あ、なんだこりゃ、と思ったが、行列の始まりは表慶館の前だった。ほどなく平成館入り口に誘導されたので事なきを得たが、ぞくぞくやってくる観客で館内はそれなりに混雑していた。
展示場レイアウトを見るといちばん最後が「仏像曼荼羅」となっていたので、いきなり最後の出口に逆行、すると目の前にゾウに乗った池麺帝釈天が現れた。この帝釈天はけっこう好き。帝釈天の前には先客がひとりいるくらいで、その瞬間だけ東寺の講堂と同じくらいの静寂を体感できた。ここでは仏像をぐるりと回り込んで見ることができる。講堂ではなかなか見えないゾウの尻、割と四角いゾウの尻の真ん中からゆらりと垂れさがった長い尻尾。帝釈天の腕には市役所のおじさんみたいな黒い腕ぬき。この帝釈天の顔は傷んだために後に造りかえられたものだと何かに書いてあった。まさかの整形池麺だったのか?
今回は東寺の《立体曼陀羅》21体のうち8体の国宝が出張してきている。それらが講堂と同じ立ち位置に並べられて、曼荼羅の雰囲気を体感することができる。帝釈天の隣には大威徳明王が水牛に乗っている。いちばん右には梵天がガチョウに乗っている。ゾウやウシならわかるが、4羽の小さなガチョウの乗っちゃうってのはいかがなものか、そうこうするうちにだんだん人が増えてきたので移動。
京都・醍醐寺の大威徳明王はまんまるおめめのかわいい水牛に、これでもかっていうほど怒った顔で乗っている明王。もう、ウシくんが不憫で不憫で。
東寺以外にも、醍醐寺の如意輪観音、五大明王、仁和寺の阿弥陀如来、神護寺の虚空蔵菩薩なども来ている。曼荼羅では、高野山・金剛峯寺の血曼荼羅、神護寺の高尾曼荼羅、東寺の西院曼荼羅などがあって、西院曼荼羅は鮮やかでよく見える。高尾曼荼羅は最古の曼荼羅とかいうありがたいものだが、まっ黒けでなんだかもうよくわからない。
《崔子玉座右銘断簡》
「人の短をいうこと無かれ 己の長をとくこと無かれ」




















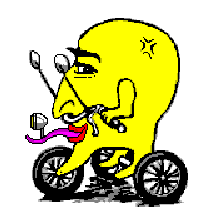




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます