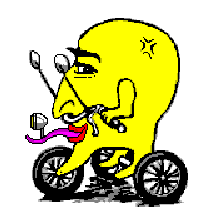「猫まみれ ようこそ猫の迷宮へ」@笠間日動美術館
震災後、ひさびさの笠間。狭い道路のあちこちが継ぎはぎだらけ、マンホールがちょっと盛り上がっていてクルマが跳ねる。そのたびにドライブレコーダーがピピッと鳴って録画を始めてしまう。美術館は入り口付近の敷石がずれていたりする程度で、大きな被害はなかったようだ。入り口の彫刻がひとつ倒れたが損傷には至らなかったとのこと。
「猫まみれ」という踏んだり蹴ったりニャ~ゴなタイトルの展覧会。猫好きの「招き猫亭」夫妻が40年に渡って蒐集した猫作品を展示。どうやらこれは山形美術館の企画であるらしい。浮世絵時代の擬人化された猫から現代に至るまでのさまざまな平面、立体の猫たち。リアルな猫もいれば奇々怪々な猫もいる。これのどこが猫やねんという猫もいる。せんとくん作者の藪内佐斗司のブロンズや木彫りの猫、顔つきがややせんとくんだったり、首だけ離れていて紐で胴体と結びつけるという変わった作風。前から好きな猫絵の歌川広重 《浅草田甫西の町詣》、高橋弘明 《ジャパニーズ・ボブテイル》、小林清親 《猫と提灯》もあった。これは猫好きには見逃せない。「猫まみれ」の「猫」のロゴが面白い。
震災後、ひさびさの笠間。狭い道路のあちこちが継ぎはぎだらけ、マンホールがちょっと盛り上がっていてクルマが跳ねる。そのたびにドライブレコーダーがピピッと鳴って録画を始めてしまう。美術館は入り口付近の敷石がずれていたりする程度で、大きな被害はなかったようだ。入り口の彫刻がひとつ倒れたが損傷には至らなかったとのこと。
「猫まみれ」という踏んだり蹴ったりニャ~ゴなタイトルの展覧会。猫好きの「招き猫亭」夫妻が40年に渡って蒐集した猫作品を展示。どうやらこれは山形美術館の企画であるらしい。浮世絵時代の擬人化された猫から現代に至るまでのさまざまな平面、立体の猫たち。リアルな猫もいれば奇々怪々な猫もいる。これのどこが猫やねんという猫もいる。せんとくん作者の藪内佐斗司のブロンズや木彫りの猫、顔つきがややせんとくんだったり、首だけ離れていて紐で胴体と結びつけるという変わった作風。前から好きな猫絵の歌川広重 《浅草田甫西の町詣》、高橋弘明 《ジャパニーズ・ボブテイル》、小林清親 《猫と提灯》もあった。これは猫好きには見逃せない。「猫まみれ」の「猫」のロゴが面白い。