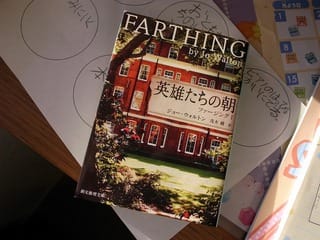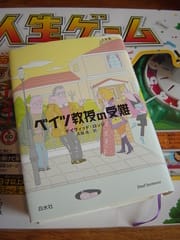ジョー・ウォルトン「英雄たちの朝(ファージングⅠ)」
1949年、イギリス南部に広大な敷地を持つ貴族の館。週末、そこで身内だけのパーティが催された。集まった者たちは保守党の要人そしてその妻たち。彼らは館の名に因んだファージング・セットと呼ばれる政治派閥の面々である。館で生まれ育ち、周囲の反対を押し切ってユダヤ人実業家と結婚したルーシーも夫とともにこのパーティに招かれていた。その夜、下院議員が殺害される。死体に何かのメッセージなのかユダヤ人のワッペンが残されていた。駆けつけたスコットランド・ヤードの刑事カーマイケルは、この事件に何か陰謀めいた臭いを感じる。そして第2の事件が・・・・。ここまでだと、伝統的な館、密室殺人事件です。が、この話がちょっと違うのが、1949年のイギリスが我々の知っているイギリスとは違うということ。先の戦争は連合国側の勝利で終わってはおらず、ルドルフ・ヘスの来英を期とし講和が成立。ヒトラーはいまだ健在で東部戦線はいつ果てるとも無く続いている状況。大陸のユダヤ人の絶滅作戦も進行中という時代なのです。
3部構成の最初の巻ということなので全体の評価は未知数ですが、ちょっと今後に期待できる読み応えでした。館での貴族の生活描写も興味深いですし、ナースリー・ティーという子供たちのための午後のお茶の時間があるということも初めて知りました。(アッパークラスの夕食は子供といっしょには行わないことが多かったために、このお茶の時間が子供たちの夕食を兼ねてたんですって・・) 館の図書館でルーシーの夫が読みふける本がジェローム・K・ジェロームの「ボートの三人男」というのもご愛嬌。それにしてもイギリス人には同性愛者が多いのかなあ・・。この作品に限らず多いですよね。
この巻の結末が暗示する全体主義と独裁への傾斜は「1984」への流れなのでしょうか。作中オーウェルの「1984」は「1974」と改変されて登場しています。
早く次巻の発売を・・。