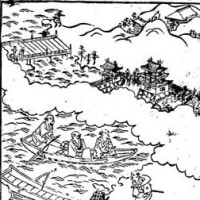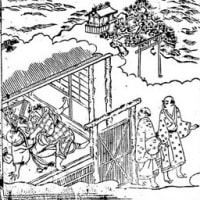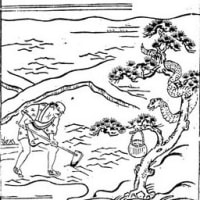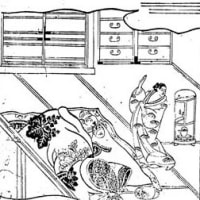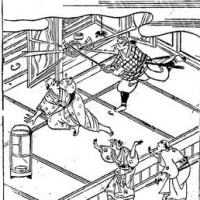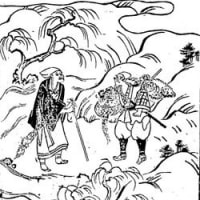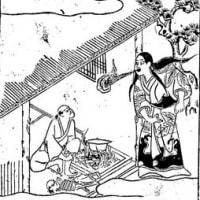ご訪問ありがとうございます→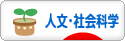 ←ポチっと押してください
←ポチっと押してください
日本国憲法第36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
刑法第9条
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第11条
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
日本国憲法第36条では、拷問と残虐な刑罰を禁止していますが、最高裁の判例により、死刑は残虐な刑罰ではないとされています。
また、刑法第11条では、死刑の方法を、絞首刑と定めています。つまり、電気イスや、薬殺、銃殺などは認められていません。
ご参考までに、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第178条第2項によって、土・日曜日および祝日と年末年始に、死刑は執行されないことになっていますから、他の誰よりも、土・日曜日を安息に過ごし、年末年始や祝日を心底祝っているのは、死刑囚かもしれませんね。
さて、「目には目を、歯には歯を」という言葉はご存知でしょう。
他人の目を潰した者は、刑罰として目を潰されるという、古代メソポタミアの、復讐法として名高いハンムラビ法典の原則ですが、現代の考え方では、死刑以外の、人体への苦痛や損壊を伴う刑罰が、まさに残虐な刑罰にあたり、ゆえにハンムラビ法典は、野蛮な法典と評価されています。
余談ですが、ハンムラビ法典は、「目を潰した者」への刑罰が「目を潰される」に止まり、それ以上の刑罰を恣意的に加えられることはないという、近代法の原則にもなっている「罪刑法定主義」の先駆けであるという、「野蛮」とは正反対の評価もあります。
さて、昔はどこの国でも、放火をした者が、火炙りの刑に処せられるのはあたりまえでしたが、これは、死刑執行に際し、必要最低限以上の苦痛を与えていることになります。
また日本でも凶悪犯は、市中引き回しの上斬首された罪人の首は、晒しものにされたものですが、これは、死刑を執行した後に死体を損壊・放置していることになります。
当然、現代では、いずれも残虐だとして、認められていません。
なぜこうした残虐な刑罰がいけないのか、それは、余計な苦痛を与えたり、死者への敬意を持たない点が非人道的だからです。
では、誰に対して非人道的なのか、それは死刑囚に対してです。
こうして「死刑囚の人権」は、手厚く保護されています。
ただ翻って考えると、江戸時代でも、俗に「十両盗めば首が飛ぶ」と言われていたとおり、殺人などの凶悪犯でなくとも、死刑になることはありました。
しかしその場合でも、凄腕の執行人(有名なところでは、首斬り浅右衛門)が、一瞬で首を斬り落とし、罪人の苦痛は最小限に抑えられています。
つまり、他人の身体へ大きな危害を加えていない罪人には、「人道的な」死刑が執行されていたわけです。
しかし凶悪事件の被害者は、裁判を受けることもなく、予告もされず、苦しんだ揚句、無念にも命を奪われているのです。
「犯人を同じ目に遭わせてやれ」というのは、遺族のみならず、民衆の、犯人が被害者に与えた苦痛を等しく受けることで、罪と罰の平衡を保ち、ひいては秩序を維持しようとする、ごく自然な要求です。
少なくとも、いつ、どのようにして刑が執行されたのかわからないのでは、遺族には、「終わったんだ」という、心の区切りができません。・・・ここ数年、法務大臣は、死刑の執行を発表するようになりましたが。
死刑囚への苦痛が非人道的だと言うのならば、被害者や遺族の心を救済しないのは、もっと非人道的です。
また刑法の目的のひとつに、罰を意識させることで、犯罪を抑止する、というのがあります。
昔の人は、磔刑や晒し首を見て、「罪を犯せばああなるんだ」と、強く自戒の念を持ったことでしょうし、火刑になる放火犯を眼前にすれば、放火魔に対しての抑止効果になります。
これは、若いお母さんが子供に対して、「悪いことをしたら、お巡りさんに連れて行かれるよ」と言って、子供の素行を正しく指導しようとすることと、本質的に何ら変わりがありません。
生首や火炙りはともかくとしても、刑務所暮らしや刑務作業、死刑を公開すれば、「悪いことをしたら、ああなるんだ」という、犯罪への抑止力は、より一層増すのではないでしょうか。
「人が死ぬのを見世物にするつもりか」「前近代的な、怒りに任せた刑罰の加重だ」というご意見もおありでしょう。
しかし私が言っているのは、刑の執行状況を見せ、以って犯罪の抑止力にするという、まさに刑法の目的に適った意味であり、刑法第9条に、罰金刑や懲役刑と同列に死刑が規定されている以上、死刑だけを除外する理由はありません。
逆に、死刑だけを別扱いにするのなら、そもそも刑法で死刑という刑罰を定めていること自体が、おかしな話だ、ということになります。
それは裁判員裁判で、裁判員に、死刑という量刑を選択させる意義まで失いさせかねません。
ただ、翻って我が身で考えれば、私が裁判員になった裁判で、被告の死刑判決が確定し、その死に様を見せられたら、私は正気を保てるかどうか、自信はありません。
さて、ここからは法を離れて心情的な話になりますが・・・
人間の、心理の奥底には、死に対する本源的な興味があります。
また、罰の実行、すなわち正義の実現を望む気持ちもあります。
さらに、知る権利というのもあります。
マリー・アントワネットがギロチンにかけられた時、コンコルド広場は、数万人の群集で埋め尽くされました。
民衆は、自分たちを苦しめた張本人に相応の罰が与えられることを望み、それが確実に執行されるところを見届ける権利を行使し、そして正義が実行された時には快哉を叫び、ルイ王朝の実質的な終焉、すなわち「正義と公平」が実現されたことを確認しました。
パリ市民がそれだけ集まったぐらいですから、もし当時、メディアが今ほど発達していたら、処刑の様子はフランス全土に、いや、全世界に生中継され、YouTubeやツイッターのサーバはパンクしてしまったことでしょう。
余談ですが、フランスでは1981年(つい30年前です)まで、死刑執行の正式な手段はギロチンでした。
人が死ぬのを見世物にするのには抵抗がある、という人も、死刑ではなく、例えば鞭打ち刑だったら、「よし、悪党が懲らしめられるところを見てやろう」といった気持ちになるでしょう。
つまり、犯罪者が罰を受けるのを公開すること自体は、何ら差し支えないのです。
そして前述のとおり、その罰の中には、刑法によって死刑が含まれている、というだけの話です。
もちろん、人の死を見たくない人が見なくて済む権利は、厳として保障されなければなりません。
日本国憲法第36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
刑法第9条
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第11条
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
日本国憲法第36条では、拷問と残虐な刑罰を禁止していますが、最高裁の判例により、死刑は残虐な刑罰ではないとされています。
また、刑法第11条では、死刑の方法を、絞首刑と定めています。つまり、電気イスや、薬殺、銃殺などは認められていません。
ご参考までに、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第178条第2項によって、土・日曜日および祝日と年末年始に、死刑は執行されないことになっていますから、他の誰よりも、土・日曜日を安息に過ごし、年末年始や祝日を心底祝っているのは、死刑囚かもしれませんね。
さて、「目には目を、歯には歯を」という言葉はご存知でしょう。
他人の目を潰した者は、刑罰として目を潰されるという、古代メソポタミアの、復讐法として名高いハンムラビ法典の原則ですが、現代の考え方では、死刑以外の、人体への苦痛や損壊を伴う刑罰が、まさに残虐な刑罰にあたり、ゆえにハンムラビ法典は、野蛮な法典と評価されています。
余談ですが、ハンムラビ法典は、「目を潰した者」への刑罰が「目を潰される」に止まり、それ以上の刑罰を恣意的に加えられることはないという、近代法の原則にもなっている「罪刑法定主義」の先駆けであるという、「野蛮」とは正反対の評価もあります。
さて、昔はどこの国でも、放火をした者が、火炙りの刑に処せられるのはあたりまえでしたが、これは、死刑執行に際し、必要最低限以上の苦痛を与えていることになります。
また日本でも凶悪犯は、市中引き回しの上斬首された罪人の首は、晒しものにされたものですが、これは、死刑を執行した後に死体を損壊・放置していることになります。
当然、現代では、いずれも残虐だとして、認められていません。
なぜこうした残虐な刑罰がいけないのか、それは、余計な苦痛を与えたり、死者への敬意を持たない点が非人道的だからです。
では、誰に対して非人道的なのか、それは死刑囚に対してです。
こうして「死刑囚の人権」は、手厚く保護されています。
ただ翻って考えると、江戸時代でも、俗に「十両盗めば首が飛ぶ」と言われていたとおり、殺人などの凶悪犯でなくとも、死刑になることはありました。
しかしその場合でも、凄腕の執行人(有名なところでは、首斬り浅右衛門)が、一瞬で首を斬り落とし、罪人の苦痛は最小限に抑えられています。
つまり、他人の身体へ大きな危害を加えていない罪人には、「人道的な」死刑が執行されていたわけです。
しかし凶悪事件の被害者は、裁判を受けることもなく、予告もされず、苦しんだ揚句、無念にも命を奪われているのです。
「犯人を同じ目に遭わせてやれ」というのは、遺族のみならず、民衆の、犯人が被害者に与えた苦痛を等しく受けることで、罪と罰の平衡を保ち、ひいては秩序を維持しようとする、ごく自然な要求です。
少なくとも、いつ、どのようにして刑が執行されたのかわからないのでは、遺族には、「終わったんだ」という、心の区切りができません。・・・ここ数年、法務大臣は、死刑の執行を発表するようになりましたが。
死刑囚への苦痛が非人道的だと言うのならば、被害者や遺族の心を救済しないのは、もっと非人道的です。
また刑法の目的のひとつに、罰を意識させることで、犯罪を抑止する、というのがあります。
昔の人は、磔刑や晒し首を見て、「罪を犯せばああなるんだ」と、強く自戒の念を持ったことでしょうし、火刑になる放火犯を眼前にすれば、放火魔に対しての抑止効果になります。
これは、若いお母さんが子供に対して、「悪いことをしたら、お巡りさんに連れて行かれるよ」と言って、子供の素行を正しく指導しようとすることと、本質的に何ら変わりがありません。
生首や火炙りはともかくとしても、刑務所暮らしや刑務作業、死刑を公開すれば、「悪いことをしたら、ああなるんだ」という、犯罪への抑止力は、より一層増すのではないでしょうか。
「人が死ぬのを見世物にするつもりか」「前近代的な、怒りに任せた刑罰の加重だ」というご意見もおありでしょう。
しかし私が言っているのは、刑の執行状況を見せ、以って犯罪の抑止力にするという、まさに刑法の目的に適った意味であり、刑法第9条に、罰金刑や懲役刑と同列に死刑が規定されている以上、死刑だけを除外する理由はありません。
逆に、死刑だけを別扱いにするのなら、そもそも刑法で死刑という刑罰を定めていること自体が、おかしな話だ、ということになります。
それは裁判員裁判で、裁判員に、死刑という量刑を選択させる意義まで失いさせかねません。
ただ、翻って我が身で考えれば、私が裁判員になった裁判で、被告の死刑判決が確定し、その死に様を見せられたら、私は正気を保てるかどうか、自信はありません。
**************************
さて、ここからは法を離れて心情的な話になりますが・・・
人間の、心理の奥底には、死に対する本源的な興味があります。
また、罰の実行、すなわち正義の実現を望む気持ちもあります。
さらに、知る権利というのもあります。
マリー・アントワネットがギロチンにかけられた時、コンコルド広場は、数万人の群集で埋め尽くされました。
民衆は、自分たちを苦しめた張本人に相応の罰が与えられることを望み、それが確実に執行されるところを見届ける権利を行使し、そして正義が実行された時には快哉を叫び、ルイ王朝の実質的な終焉、すなわち「正義と公平」が実現されたことを確認しました。
パリ市民がそれだけ集まったぐらいですから、もし当時、メディアが今ほど発達していたら、処刑の様子はフランス全土に、いや、全世界に生中継され、YouTubeやツイッターのサーバはパンクしてしまったことでしょう。
余談ですが、フランスでは1981年(つい30年前です)まで、死刑執行の正式な手段はギロチンでした。
人が死ぬのを見世物にするのには抵抗がある、という人も、死刑ではなく、例えば鞭打ち刑だったら、「よし、悪党が懲らしめられるところを見てやろう」といった気持ちになるでしょう。
つまり、犯罪者が罰を受けるのを公開すること自体は、何ら差し支えないのです。
そして前述のとおり、その罰の中には、刑法によって死刑が含まれている、というだけの話です。
もちろん、人の死を見たくない人が見なくて済む権利は、厳として保障されなければなりません。