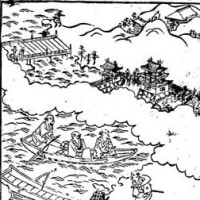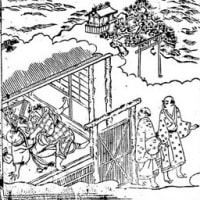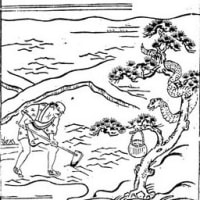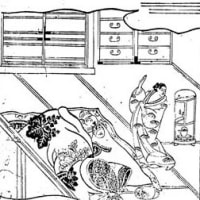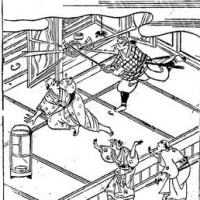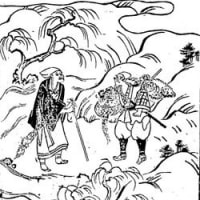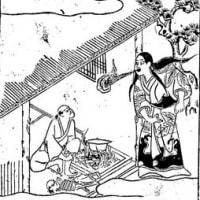前野良沢は、言わずと知れた「解体新書」編纂者の一人です。
教科書では、「解体新書」の翻訳者は杉田玄白と教わりますが、オランダ語の実力は前野良沢が随一であり、共著として知られる中川淳庵が続き、杉田玄白の語学力は取るに足らず、実質的な翻訳者は前野良沢であり、杉田玄白は、極端な話、前野良沢が訳したものを書き記したに過ぎない、というのが、最近の研究による、日本史の新たな「常識」となっています。
さて、秋の日長、ご覧のような講演会に出かけてまいりました。
大分県立先哲史料館では、現在、中津藩医である前野良沢に関する展示を行っており、この日は、大分大学の鳥井教授から、前野良沢や解体新書についての講演があり、講演後は、学芸員による展示品の解説があり、どちらも非常に興味深く、有意義な午後でした。
内容については、いちいち説明してもきりがありませんので、省略するとして、展示品を観覧するにあたり、私にとって、大変うれしいことがありました。
私は、歴史好き、特に文化史が好きで、わけても江戸文化に大変興味を持ち、それが高じて、十返舎一九や山東京伝などの戯作や、鳥山石燕(妖怪画)を、原文で読みたいと思うようになり、昨年来、古文書解読の勉強を進めてきました。・・・ナントカの手習いで。
それが今回、展示品の中には、解体新書翻訳の苦労話をまとめた、杉田玄白の「蘭学事始」もあり、もちろん古文字で書かれているのですが、展示してあるその書物が、ほぼ読めたのです。
1年前の私には考えられなかったことで、勉強の成果が実戦で確認でき、非常にうれしかったとともに、書物を通じて杉田玄白の書斎にお邪魔しているような錯覚さえあり、ひとときのエアー江戸訪問を堪能しました。
・・・作者の書いたものを直接読み、時空を超えて江戸の雰囲気に浸って悦に入る、それがしたくて古文書の勉強を始めたようなものですから、今回の成果はひとしおです。
「蘭学事始」も、わざわざ古文書で読まなくたって、現代の活字本はいくらでも出版されているのですが、それでは、「江戸の空気」に触れることは不可能でしょう。
しかし、残念ながら私に読めるのは、印刷された書物のように、楷書に近い字体が精いっぱいで、草書で書かれた書簡などは、半分も読めませんでした。
まあいずれ、「半分も」が「半分は」になり、「半分以上」「大半は」になればいいのですが・・・学成り難し。
ご訪問ありがとうございます→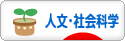 ←ポチっと押してください
←ポチっと押してください