チャールズ・ディケンズ【クリスマス・キャロル】第五章「大団円」(最終)(英語原文朗読+和英対照表)
さて、【クリスマス・キャロル】の最終章です。三人の精霊の訪問を受けて、スクルージはどのように変わったのか。ユーモアを交えながら、ディケンズは彼の変貌ぶりを語ります。
ショートストーリーに定評のある山川方夫がクリスマスを題材に短編を書いています。前後二回に分けて転記します。
メリイ・クリスマス
山川方夫
(前半)
ある秋の夜。むし暑く、寝苦しいまま、彼はアパートの手すりにもたれて、目の下にひろがる都会の夜を、ぼんやりと眺めていた。彼の部屋は、都心に近い高層アパートの、それも最上階にあった。
月の美しい夜ふけで、空は月のまわりだけ穴をあけたように明るく澄み、淡い煙に似た薄い雲が、ときどきそのまんまるな月の前を流れていた。しばらく風に吹かれてから、彼が部屋に戻ろうとしたとき、ふと、背後にごく小さな――まったく、ごく微《かす》かな、しかし明瞭な女の忍び笑いが聞こえた。びっくりして彼は振りかえった。背後には、高い夜空に突き出したアパートの手すりと月光のほか、なにひとつあるわけがなかったのだ。
しばらくのあいだ、彼は口をポカンとあけ、自分が精神錯乱におちいったのだ、とくりかえし思いつづけた。月光に青白く光る手すりの金棒に腰をかけて、豆つぶほどの一人の女が、脚を組み、手を唇にあてて笑っている。小さな、しかしあきらかに若い女性だけのもつ愛らしい澄んだ忍び笑いが、そこから、彼の耳にとどいてくる。
蟋蟀《こおろぎ》や、鈴虫やの見まちがいではなかった。彼は自分の耳を疑い、目を疑い、顔を近づけてしげしげとその若い女性のミニアチュアのような生物を観察した。それは、大きささえ無視して考えれば、まったく人間の若い女性、それもかくべつ美しく魅力的な女性と、かわるところがなかった。
漆黒のやわらかな髪が肩まで垂れ、まるで月の光を凝固したような色のスーツは、胸のこんもりした双つの丘のしたで花籠のように緊《しま》って、腰から腿にかけてのカーヴをひときわ魅惑的にしている。真白な肌。小さな紅い唇。形よくのびた脚のさきには、服とおなじ銀色の小さなハイヒールが、キラキラと光を弾いている。……しかし、その身長は、わずか5センチにみたない。
睫毛《まつげ》の深いせいか、その目は大きく見え、そして女は――どうみても完全な女性だった――笑っていた。愛らしく。無邪気に。彼の心に沁みるように。
思わず、彼は手をさしのばした。開いた彼の掌は汗ばみ、彼女にとっては、それはレスリングの選手の汗にぬれたマットみたいなものだっただろう。が、躊躇《ちゅうちょ》なく彼女はひらりとその巨大な掌のくぼみに降り、(マッチ棒二、三本ほどの重さだった)彼を見上げながらニッコリと笑いかけた。
「……私を好き?」
話しかけているのは、声ではなかった。それは彼女の目なのだった。
「いい? あなたも目で話すの。お祈りと同じだわ。声なんか出しちゃ駄目よ。だって、私、吹き飛ばされちゃうかもしれないもの」
「……わかった。目で話そう」
それが、彼が彼女に逢い、目で言葉をかわしはじめた最初だった。……いつのまにか、彼はたとえそれが夢であり、自分の狂気がつくりあげた幻影であるとしても、彼女といるその時間を失うのが惜しくなりはじめた。彼女が、どこからどうやってこの高層アパートの最上階に来たのか、彼女の正体はなにか、そんなことはどうでもいいと思った。問題は、いまげんに彼女がぼくの目に見えているという事実だ。せっかくやってきたこの可愛らしい、貴重な、すばらしいお客を失いたくない。ただそれだけで彼は夢中だった。
「……ねむいわ。どこか眠るところない?」
やがて、彼女はいった。彼は、そっと両手でかこうようにして彼女を自分の机の上に運び、その抽斗《ひきだ》しの一つに、柔らかな絹ハンカチと綿とで彼女のベッドをつくった。
「おやすみ」
未練な自分の気持ちをそこにしまいこむみたいに、彼はそっと抽斗しを押してやった。彼女はベッドの上で大きな欠伸《あくび》をしながら、机の中にかくれた。
彼は、自分がふたたび彼女を見ることができるとは、つまり明日もこの錯乱がつづいていることは、信じられなかった。だが、彼はその抽斗しを閉めるとき、通風のごく細い隙間をのこすのを忘れなかった。
眠りこけている妻のとなりのベッドに横になると、彼は、しばらくは煙草《たばこ》をふかしつづけた。ばかげた幻覚だと思った。が、奇妙に幸福な気分ものこっていた。……ふと、妻の寝息がうるさく耳についた。休息中の巨大な機関車のような眠っている妻をながめ、そのときはじめて彼は、結婚してまる三年、妻への自分の愛が、いまでは一つの義務に似た負担になっていることをはっきりと感じとった。
翌日の出勤まえ、念のため昨夜の抽斗しをひらいて、彼はあやうく声をあげるところだった。小さな彼女は、ちゃんとそこにいたのだ。
「もうお出かけ?」
眩《まぶ》しげに目をひらくと、いたずらっぽく彼女は笑いかけた。「安心してらっしゃい。私、あなたに無断で消えちゃったりはしないわ。ほんとよ、当分ここにいるわ」
そのときとなりの部屋から妻がいった。
「早くしないと遅れるわよ。大丈夫なの?」
まるで雷鳴のように、無数のバケツを土間にほうり出したみたいに、その声は彼の全身にひびいた。……ふつうの声音だったのだが。
それから、彼と身長5センチの彼女との交際がはじまった。彼は毎日いそいで会社から帰ると、抽斗しの鍵をあける。(ただの夢ではなかったとわかったとき、彼は彼女の部屋を鍵のかかる抽斗しへと移した。鍵穴は通風孔によかった。)そして、いつもなにから伝えようかと惑いながら、彼女との「目で」のお話をはじめる。
どうやら、彼は気が狂ったのではなかった。小さな彼女は幸運の女神なのか、会社での勤務も評判がよく、彼の位置も課長補佐にあがった。ただ、彼はだれにも――もちろん、妻にさえも――この小さな彼女のことはいわなかった。彼女は、彼の、彼だけの大切な秘密だった。
彼女との話はたのしかった。おそらく、彼女はちがう星の生物に違いなかった。彼は、彼女から、月が四つある星の話や、それらの星たちの上での奇妙な習慣、彼女の星では実現されているタイム・マシン、宇宙旅行用のロケットの話など、彼には想像もつかない別世界の話を聞くのだった。その中にはロボットの話もあったし、意のままのものを出現させたり、時間、空間を無視して、自分を好きなところに、好きな形で存在させうる星の生物たちの話も、自分たちの手で作りあげたエネルギーで全滅した星、宇宙間の戦いの話もあった。また、いまごろ旧式の空飛ぶ円盤におどろいている星や、その存在を信じないという、彼女にいわせれば「知能の遅れた生物」の支配する星での出来ごとなどもあった。
彼女の衣裳は、そのときの光によって変化するのだった。月夜には月光の色に、太陽の照る昼は、きらめく黄金色に、朝は昧爽《まいそう》のバラ色に、夕暮はあたたかい茜《あかね》色に、そして雨の夜は、正確にその濡れた闇の色に。彼女は、まるで空気だけで充分だというみたいに、なにも食べなかった。いつもニコニコと蠱惑《こわく》的にやさしかった。彼が目ざめたときに目ざめ、彼が眠るときに眠り、彼が見ていないときは、まるでどこにも存在しないもののように、彼女も彼を見ない。……
彼の生活は、この5センチたらずの彼女をめぐってまわった。毎日、彼は飽きもせず彼女の話を聞き、彼女に見惚れつづけた。彼女はしだいに彼には欠くべからざるもの――恋人に近いものになっていった。彼は彼女を愛し、彼女といっしょに話しあっているときが、彼にとっての最高の幸福な時間だった。彼は、ほとんど妻をかまいつけないようになった。












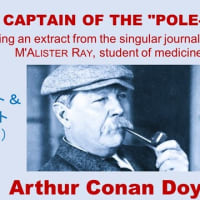



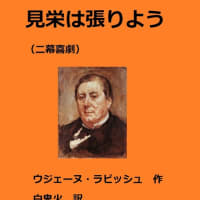







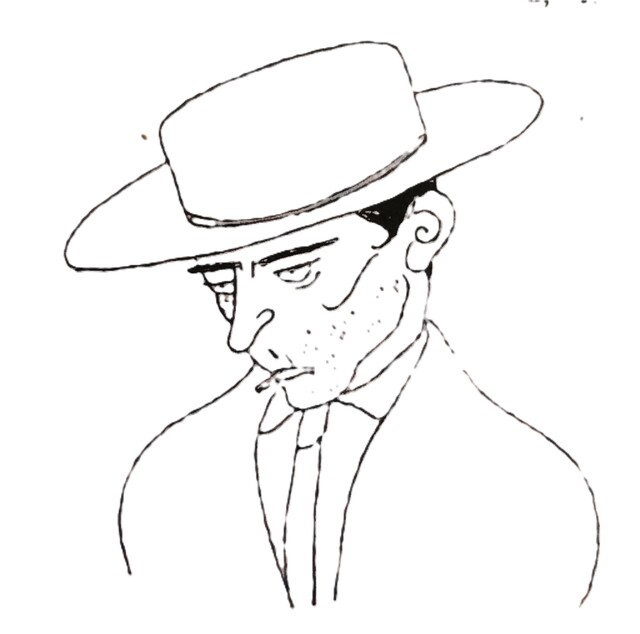

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます