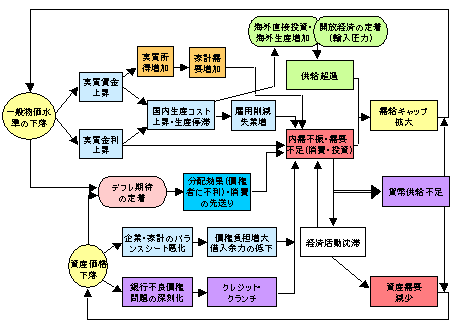土佐のくじらです。
2020年に開催される夏期オリンピックの開催地が、東京に決定いたしました。
本当におめでとうございます。
しかし、喜んでばかりではいられません。
これで、財務官僚が主導する、消費税増税論議が本格化するはずだからです。
なぜなら、アベノミクス+東京オリンピック効果で、景気が大幅に回復するのが確実だからです。
景気が回復するから、増税しても大丈夫・・・という論理で、財務官僚側は、増税を肯定化し、論調強めてくるはずです。
増税が肯定化されるから、増税論議を活発化させるのではありません。
役人は、好景気が嫌だから、増税するのです。
皆様、ここを間違わないでください。
彼らは賢いので、増税しても税収が増えないことは百も承知です。
日本を好景気にしたくないからこそ、増税するのです。
実はここが、増税論議の本丸なのです。
好景気になれば、一般的日本人の給料が上がり、生活レベルは上がります。
ここが、ほぼ固定給の公務員には耐えられないのです。
バブル景気時がそうでした。
周囲の人々の給料が、月100万円などになり、大体30万円以下で暮らす公務員は、相対的な貧者になったのです。
彼らは、過去のバブル経済期に、相当の屈辱を味わったはずです。
彼らは、絶対に日本の再バブル化を、あの手この手を駆使して、潰しにかかるはずです。
良いですか?
好景気潰しのための、消費増税なのです。
そして、天下り先確保のための消費増税なのです。
最終的には、公務員の給与体制を、景気連動性にする以外は、日本は増税体質から抜け出すことはありません。
なぜなら、国家の大きな経済政策を創っているのは、財務官僚だからです。
増税は確実に、不景気になります。
不景気は確実に、日本国民を貧乏にします。
日本人が貧乏になれば、国家が衰退します。
国民を富まさないで、国家が富むことなどありません。
世界史を見れば、税金の高い国は滅んでいます。
そして現在、経済の調子の良い国は、税金の安い国ばかりです。
東京オリンピック開催決定で、消費増税に関するマスメディアなどの、増税やむなし論が活発化するはずです。
それは、好景気になるのが確実だからです。
これである意味で、役人は追い込まれたと言えます。
増税しか、近い将来の好景気を、潰す材料がないからです。
皆様、向こう(財務官僚)は、背水の陣です。
窮鼠猫を咬む・・・状態です。
必死で仕掛けて来るでしょう。
しかし日本は、これ以上増税してはいけません。
民主主義社会では、一般市民の見識こそ全てです。
民主主義国家日本の国民として、役人の生活レベル保持のための消費増税をは、何としても阻止しましょう。
それがひいては、ご自身の老後のためであり、子孫に迷惑をかけないことになるのです。