このたびの仮処分をご担当された坂本弁護士より、結果についてのご所見をいただきました。
鮫川村仮設焼却操業差止仮処分決定について
弁護士 坂本博之
1 鮫川村仮設焼却施設操業差止仮処分事件(福島地方裁判所郡山支部平成26年(ヨ)第14号)は、同施設の建設地の所有者の一人が債権者となり、国を債務者(仮処分事件では、通常の裁判での「原告」「被告」に相当する者を、「債権者」「債務者」という)として、平成26年7月に申し立てたものである。
この申立は、債権者の土地所有権に基づく、妨害排除請求権という性質を有するものである。
福島地裁郡山支部は、平成27年8月31日、この仮処分事件の決定を出した。申立から約13か月後、結審から約2か月後に出された決定であった。
2 土地所有権に基づく妨害排除請求権において、原告ないし債権者が、その土地の所有権があることを主張立証した場合、被告ないし債務者が、その土地の利用権原(この「権原」という言葉は、法律用語で、その物を利用する権利がのことを言う。「権限」の誤りではないのでご注意いただきたい)があることを主張・立証しなければならない。
本件では、債権者が問題となった土地の所有者であることは争いがないので、債務者である国が、その利用権原を有することを主張・立証しなければならない。そして、本件では、問題となった土地は共有地であり、18名の共有者がいた。国の主張は、その共有者の過半数との間で土地賃貸借契約を締結しており、その賃貸借契約は管理行為に該当するから、適法な権原を有している、というものであった。
一方、問題の土地は農地(牧草地)であり、農地を非農地化して賃貸するものであるから、処分行為に該当する、というのが債権者の主張であった。
なお、民法上、共有物の利用形態には、処分行為、管理行為、保存行為の3種類がある、とされる。それぞれ、共有者全員の同意を必要とする行為、共有者の共有持ち分の過半数で行うことができる行為、共有者のうちの一人でもできる行為、ということである。
3 裁判所の決定は、国の賃貸借契約は管理行為であり、国は適法な利用権原を有している、というものであった。その理由は、
①賃貸借契約が締結された当時、本件土地は牧場として利用することが事実上不可能な状態にあった、
②賃貸借契約の期間は、民法602条2号所定の短期賃貸借契約の期間を超えるものではない、
③本件施設は仮設のものであり、契約が終了したときに容易に撤去することができる、
④本件施設の建設用地は、本件土地全体のほんの一部でしかない、
というものである。またこの決定は、
⑤本件施設の操業等により、本件土地が放射性物質によって汚染され、あるいはその具体的な危険性が生じているなどとは認めがたい、
ということも述べている。
しかし、この決定は、判断の枠組みをそもそも誤っているし、管理行為であるという判断をした理由として挙げた上記の理由の何れについても、誤った考えをしている。
4 まず、判断枠組みの誤りについて指摘する。既に述べたように、本件は、土地所有権に基づく妨害排除請求権に基づく申立であり、土地の利用権原があること(=本件では、国の賃貸借契約が管理行為であること)についての主張立証責任は国にある。上記⑤の点は、そもそも、国の方が、管理行為であることを根拠づける理由の一つとして、本件施設からは、周囲に放射性物質を放出しておらず、本件土地が放射性物質に汚染されていない、という主張を行ったものである。これに対して、債権者は、本件施設から放射性物質が放出されていないとは言えないことについて、専門家の意見書等を踏まえて主張を行い、債務者の主張が誤っていることを指摘した。
従って、本件では、少なくとも、国の上記主張が十分に立証されていないことが明確になったはずである。そこで、裁判所は、国が管理行為の根拠として挙げた、本件施設から周囲に放射性物質を放出していないこと等について、認めるに足りる証拠はない,という判断をしなければならなかったはずである。
この点、本件が、人格権に基づく操業差止仮処分であったのであれば、債権者の方に、本件施設から放射性物質が放出されること、周辺住民の生命健康に具体的危険性が及ぶこと等について主張立証責任があるということになるのかもしれない。裁判所は、本件を人格権に基づく仮処分と混同して、混乱の上、誤った判断を行ったものと言わざるを得ない。
裁判所は、要件事実論(法律上の請求が認められるために必要な事実)と主張立証責任論を基本として、判決や決定を組み立てるのが基本である。本件決定は、このような基本を見失った、どうしようもない決定である。
5 次に、この決定が、管理行為であるという判断をしたいくつかの理由について、その誤りを指摘する。
第一に、本件賃貸借契約当時、本件土地が農地として利用することが事実上不可能な状態にあったという点である。しかし、このような理屈は、一時的に農地としての利用が困難であったとしても、将来農地として再び使用する可能性があり、しかも債権者にそのような意思がある場合に、農地としての利用をより困難にするような利用の仕方をすることを、容易に認めてしまうことになる。例えば、この理屈に従えば、農地に産業廃棄物をわざと少しだけ不法投棄し、農地としての利用を一時的にできなくしてしまえば、その土地を産業廃棄物の一時保管場所として利用することができる、ということになる。
第二に、本件賃貸借が短期賃貸借の期間を超えるものではないとの点である。この点、この決定は、他方で、本件施設には、焼却によって生じた焼却灰の仮保管場所も含まれるところ、債務者は、その焼却灰の保管期間がいつまで続くのか不明であると主張していたものである。従って、債務者の主張を前提とする限り、賃貸借契約の期間が短期賃貸借の期間を超えないという証拠がない、ということにならざるを得ない。この点に関する裁判所の判断は明らかな誤りである。
また、裁判所は、農地法は、農地の一時転用の場合であっても、農地の共有者全員の同意を必要としているという点について、民法上の共有物の規制と農地法に基づく農地に関する規制は目的が異なる旨述べ、農地法上の一時転用であるからと言って、処分行為に該当しないという判断が左右されるものではない、などとも述べている。しかし、農地法は、民法の特別法なのであるから、特別法上、共有者全員の同意を必要とするとされている行為は、民法上の共有物に関する規定の特別法ともなっているものと解されなければならないはずである。この決定は、一般法と特別法の関係に関する解釈を誤っているし、法令の間の統一的な解釈という、法令の解釈に関する大原則を蔑ろにしている者との誹りを免れない。
第三に、賃貸借契約が終了した場合の原状回復が容易であるとの点である。しかし、裁判所が、原状回復が容易であるという認定をした根拠として挙げているのは、主に施設の構造に関する認定である。これは、建物を撤去して更地の宅地にする場合のやり方を述べているに過ぎない。本件土地は農地であり、宅地ではないのであるから、単に構造物を撤去するだけではなく、それをどのようにして農地として回復するのかという指摘がなされなければならない。そして、債務者はそのような主張立証は行っていない。従って、本件は、裁判所としては、農地としての原状回復が容易であるとの主張立証はないという判断を行う必要があったものである。
第四に、本件賃貸借契約の対象が本件土地全体の一部であるとの点についてである。しかし、本件賃貸借契約の対象は、3108㎡であり、約1000坪に近い面積であり、必ずしも狭小な面積ではない。本件農地がいくつもの筆に分かれており、本件土地がそれらの筆の中の一筆全体であったならば、本件決定のようなことが言えたかどうか、疑問である。たまたま、本件土地が一筆で非常に広い面積(21万5179㎡)もあったから、筆が滑ってこのようなことを言ってしまったものと評価すべきであろう。
6 以上の通り、本件決定は、判断の大枠においても、個々の判断内容においても、誤っているものであり、極めて不当な決定というべきである。
なお、本件決定は、「当裁判所の判断」の箇所は、わずか7頁程度しかない。結審の時、裁判官は「裁判所としても、この事件については、慎重な判断をしたい」などと述べていた。しかし、ふたを開けてみると、非常にあっさりとした、しかも、極めて不当且つ杜撰な内容であった。国が進めている、福島県内の特定廃棄物(放射性物質汚染特措法上、指定廃棄物と対策地域内廃棄物をまとめてこのようにいう)の焼却処理に関して、水を差すような決定を書くわけにはいかないという政治的な判断が働いたものであろうと思われる。
裁判所は、このような決定を出して国を助けるたびに、自らの権威を落としていくのだということに、そろそろ気づいてもいいのではなかろうか。
(マーカー・色文字はブログ管理人)
特に最後の部分に強く共感します。
裁判所はどこを向いて仕事をしているのか、私達市民もしっかり監視していかなければと思います。















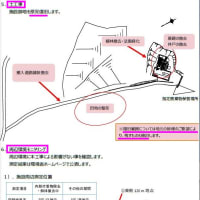
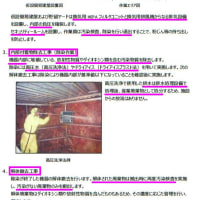
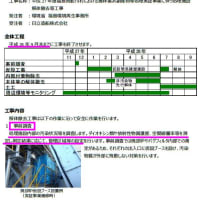







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます