
◆サッカー・第19回FIFAワールドカップ南アフリカ大会 第20日(2010年7月2日)
・準々決勝
オランダ 2(0-1)1 ブラジル (@ポート・エリザベス/ネルソン・マンデラ・ベイ・スタジアム)
得点者:オランダ)53分&63分 ウェスレイ・スナイデル
ブラジル)10分 ロビーニョ
ウルグアイ 1(0-1)1 ガーナ (@ヨハネスブルグ/サッカー・シティ・スタジアム)
(延長0-0、0-0:PK戦4-2)
得点者:ウルグアイ)55分 ディエゴ・フォルラン
ガーナ)45分+2 スレイ・ムンタリ
国際サッカー連盟の今大会の関連ページ
日本サッカー協会の今大会の関連ページ
出場32チームの最終登録メンバー(各国23名)
〔写真はGetty imagesより〕
* * * * *
同じ退場劇だけど、どえらい違いですね
準々決勝の最初の試合であったオランダvsブラジル戦は予想外の展開でしたね。前半だけ見るとブラジルが優位に試合を運んでいたので、堅守速攻のスタイルのブラジルがこのまま逃げ切るのかと思いました。しかし、後半はブラジルの守備が崩壊して逆転されます。ビハインドを背負ってからのブラジルは明らかに焦りの色を見せ、攻撃が全く噛み合いませんでした。更には、フェリペ・メロが球際で競り合ってアリエン・ロッベンを倒した際、あろうことが足で踏み付ける蛮行を働きます。1人欠いたこの瞬間に事実上の終戦。それにしても、この日のメロは、ロビーニョへのスルーパス、同点弾となるオウンゴール、そして一発退場。まさに独り相撲でした。如何せん、ブラジルは優勝しか認めてない国なので、帰国したら国民からたっぷりと“制裁”を受けるのか心配ですね。
一方、この試合の後に行われたもう一つの試合。アフリカ勢初の準決勝進出を目指したガーナと、過去W杯を2度優勝経験があるものの現在はプレーオフの常連国となったウルグアイとの対決。この試合も退場者を出す展開となりました。しかも、試合終盤に意外な結末を迎えました。試合そのものは、ガーナが前半ロスタイムにスレイ・ムンタリのロングシュートで先制。ウルグアイは守備の要のディエゴ・ルガーノが前半に負傷退場する苦しい展開。しかし、ウルグアイも後半にディエゴ・フォルランのFKで同点に追いつきます。この後は、南アの大観衆を味方にしたガーナが主導権を握って攻勢を仕掛けますが、南米の曲者ウルグアイも鋭いカウンターで応戦。両者とも中々追加点が入りませんでした。
しかし、延長後半のロスタイムのガーナの右FKから攻撃。ゴール前の混戦からガーナが立て続けに2本のシュートを放ちます。ドミニク・アディエのヘディングでウルグアイゴールを割ったかに見えましたが、ライン上にいたルイス・スアレスがなんと両手でブロック。決定的な得点機をハンドで掻き出す悪質な反則の為、ガーナにPKを与えただけでなく、スアレス自身も一発退場(&次の試合も自動的に出場停止)の処分。残り時間を考えても、このPKのプレーで終わりでした。しかも、キッカーは今大会3得点中、2点をPKで決めているアサモア・ギャン。なので、誰もがガーナの勝利を九分九厘確信したでしょう。
ところが、この絶好機をギャンがクロスバーに直撃して痛恨の失敗。この瞬間にタイムアップの笛。結局、延長戦でも決着が付かずにPK戦へ。ただ、日本vsパラグアイ戦のように、両チームとも膠着状態のままPK戦に縺れ込むのとは状況が全く異なり、ガーナは勝てるはずだった試合をものに出来なかったツケをたっぷりと支払う羽目になります。両チームとも2人まで成功しますが、ガーナは3人目と4人目がGKフェルナンド・ムスレラに阻止されます。ウルグアイは4人目こそ失敗しますが、5人目のセバスティアン・アブレウが落ち着いてチップキックを決めてついに決着。ウルグアイが1970年メキシコ大会以来40年ぶりの準決勝進出を果たしました。敗北の責任を一身に背負ったギャンが両手で顔を覆って泣き崩れている姿は、胸が締め付けられるものがありました。
ラグビーであれば、相手の反則によりボールをグラウンディングできなかった場合、その反則が無くてもトライに至っていた可能性が高い場合は「認定トライ」となりますが、サッカーはボールがゴールラインを完全に越えてない限りは、もちろん得点には認められません。とはいえ、極刑を受ける覚悟でハンドを犯したスアレスは、相当に勇気のいる判断をしたと思います。もし、これまで2度のPKを決めているギャンの習性をスアレスが見抜いて、リスクを承知で“神の手”を使ったのであれば、スアレスはディエゴ・マラドーナよりも凄いと思いますね(苦笑)。ちなみに、マラドーナは1990年イタリア大会のソ連戦でも、主審の見えない角度から自陣ペナルティエリア内で“神の手”を使い、相手のPK機を阻止したことがあります。
おそらく、スアレスの行為に対しては「勝利に対する凄まじい執念」なのか、それとも「勝利の為なら手段を一切選ばない」と受け止めるのか、賛否両論でしょうね。ただ、個人によって受け止め方が異なると思うので、一概に良い悪いの判断は出来ないと思います。文化というのは育った環境によって異なるのと同様に、フェアープレーの概念も個人によっても大きく異なりますし、国によっては更に異なるので、決して普遍的なものではないのかもしれません。それに、南米の場合は、かつてロハス事件というもの凄い事件もありますから、勝利に対する執念は日本人では想像も出来ないくらい凄まじいものがあります。
今回のスアレスのハンドは、生死を彷徨う状態の中、その瞬間において何が最善なのか、理屈抜きで生まれた本能のプレーなのでしょうか。英雄と国賊を分けるものは、まさに紙一重なのかもしれませんね。
〔追記〕
7月3日、国際サッカー連盟(FIFA)はオランダが53分に記録した得点を、ブラジルのオウンゴールからオランダのMFウェスレイ・スナイデルのゴールに変更したことを発表。この変更により、スナイデルの今大会通算ゴール数は4ゴールとなりました。記事の本文も訂正致しました。
・準々決勝
オランダ 2(0-1)1 ブラジル (@ポート・エリザベス/ネルソン・マンデラ・ベイ・スタジアム)
得点者:オランダ)53分&63分 ウェスレイ・スナイデル
ブラジル)10分 ロビーニョ
ウルグアイ 1(0-1)1 ガーナ (@ヨハネスブルグ/サッカー・シティ・スタジアム)
(延長0-0、0-0:PK戦4-2)
得点者:ウルグアイ)55分 ディエゴ・フォルラン
ガーナ)45分+2 スレイ・ムンタリ
国際サッカー連盟の今大会の関連ページ
日本サッカー協会の今大会の関連ページ
出場32チームの最終登録メンバー(各国23名)
〔写真はGetty imagesより〕
* * * * *
同じ退場劇だけど、どえらい違いですね
準々決勝の最初の試合であったオランダvsブラジル戦は予想外の展開でしたね。前半だけ見るとブラジルが優位に試合を運んでいたので、堅守速攻のスタイルのブラジルがこのまま逃げ切るのかと思いました。しかし、後半はブラジルの守備が崩壊して逆転されます。ビハインドを背負ってからのブラジルは明らかに焦りの色を見せ、攻撃が全く噛み合いませんでした。更には、フェリペ・メロが球際で競り合ってアリエン・ロッベンを倒した際、あろうことが足で踏み付ける蛮行を働きます。1人欠いたこの瞬間に事実上の終戦。それにしても、この日のメロは、ロビーニョへのスルーパス、
一方、この試合の後に行われたもう一つの試合。アフリカ勢初の準決勝進出を目指したガーナと、過去W杯を2度優勝経験があるものの現在はプレーオフの常連国となったウルグアイとの対決。この試合も退場者を出す展開となりました。しかも、試合終盤に意外な結末を迎えました。試合そのものは、ガーナが前半ロスタイムにスレイ・ムンタリのロングシュートで先制。ウルグアイは守備の要のディエゴ・ルガーノが前半に負傷退場する苦しい展開。しかし、ウルグアイも後半にディエゴ・フォルランのFKで同点に追いつきます。この後は、南アの大観衆を味方にしたガーナが主導権を握って攻勢を仕掛けますが、南米の曲者ウルグアイも鋭いカウンターで応戦。両者とも中々追加点が入りませんでした。
しかし、延長後半のロスタイムのガーナの右FKから攻撃。ゴール前の混戦からガーナが立て続けに2本のシュートを放ちます。ドミニク・アディエのヘディングでウルグアイゴールを割ったかに見えましたが、ライン上にいたルイス・スアレスがなんと両手でブロック。決定的な得点機をハンドで掻き出す悪質な反則の為、ガーナにPKを与えただけでなく、スアレス自身も一発退場(&次の試合も自動的に出場停止)の処分。残り時間を考えても、このPKのプレーで終わりでした。しかも、キッカーは今大会3得点中、2点をPKで決めているアサモア・ギャン。なので、誰もがガーナの勝利を九分九厘確信したでしょう。
ところが、この絶好機をギャンがクロスバーに直撃して痛恨の失敗。この瞬間にタイムアップの笛。結局、延長戦でも決着が付かずにPK戦へ。ただ、日本vsパラグアイ戦のように、両チームとも膠着状態のままPK戦に縺れ込むのとは状況が全く異なり、ガーナは勝てるはずだった試合をものに出来なかったツケをたっぷりと支払う羽目になります。両チームとも2人まで成功しますが、ガーナは3人目と4人目がGKフェルナンド・ムスレラに阻止されます。ウルグアイは4人目こそ失敗しますが、5人目のセバスティアン・アブレウが落ち着いてチップキックを決めてついに決着。ウルグアイが1970年メキシコ大会以来40年ぶりの準決勝進出を果たしました。敗北の責任を一身に背負ったギャンが両手で顔を覆って泣き崩れている姿は、胸が締め付けられるものがありました。
ラグビーであれば、相手の反則によりボールをグラウンディングできなかった場合、その反則が無くてもトライに至っていた可能性が高い場合は「認定トライ」となりますが、サッカーはボールがゴールラインを完全に越えてない限りは、もちろん得点には認められません。とはいえ、極刑を受ける覚悟でハンドを犯したスアレスは、相当に勇気のいる判断をしたと思います。もし、これまで2度のPKを決めているギャンの習性をスアレスが見抜いて、リスクを承知で“神の手”を使ったのであれば、スアレスはディエゴ・マラドーナよりも凄いと思いますね(苦笑)。ちなみに、マラドーナは1990年イタリア大会のソ連戦でも、主審の見えない角度から自陣ペナルティエリア内で“神の手”を使い、相手のPK機を阻止したことがあります。
おそらく、スアレスの行為に対しては「勝利に対する凄まじい執念」なのか、それとも「勝利の為なら手段を一切選ばない」と受け止めるのか、賛否両論でしょうね。ただ、個人によって受け止め方が異なると思うので、一概に良い悪いの判断は出来ないと思います。文化というのは育った環境によって異なるのと同様に、フェアープレーの概念も個人によっても大きく異なりますし、国によっては更に異なるので、決して普遍的なものではないのかもしれません。それに、南米の場合は、かつてロハス事件というもの凄い事件もありますから、勝利に対する執念は日本人では想像も出来ないくらい凄まじいものがあります。
今回のスアレスのハンドは、生死を彷徨う状態の中、その瞬間において何が最善なのか、理屈抜きで生まれた本能のプレーなのでしょうか。英雄と国賊を分けるものは、まさに紙一重なのかもしれませんね。
〔追記〕
7月3日、国際サッカー連盟(FIFA)はオランダが53分に記録した得点を、ブラジルのオウンゴールからオランダのMFウェスレイ・スナイデルのゴールに変更したことを発表。この変更により、スナイデルの今大会通算ゴール数は4ゴールとなりました。記事の本文も訂正致しました。
















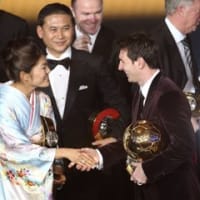


恐らくスアレスには残り時間が分かっていてのプレーだと思います。
手を出さなければ確実に決勝点ですし自分が
レッドカードで退場になっても仮にPKが決まらなければ残り時間から1人少なくても影響はない
ですからね。
これぞ勝利への執念というべきでしょう。
そういえば95年のアンブロカップでイングランドと対戦した日本が1-1で迎えたロスタイム
で柱谷が決定的なシュートを手で防ぎレッドカードで退場となり、PKも決められて負けたシーンがありました。
あの時に新聞記者は柱谷を非難したらしいですけど、個人的には当然のプレーだと思ってました。
本当に南米勢はこういう事を当たり前にやりますから、フェアープレー一本槍では日本は永遠に勝てないと思います。
ちなみにブラジルのフェリペ・メロの蛮行は
見苦しかったですね。
踏みつけただけでなくボールを手で奪おうとしてましたから・・・・・
それを毅然と退場させた西村主審のジャッジは素晴らしかったと思いますし、ゲームコントロールの重要性をまざまざと見せ付けてくれました。
ギャンが泣き崩れていたのを観た時、駒野はPKの失敗を気にすることは無いと思いましたね。
ただ、ショックを受けているはずのギャンも、PK戦で一番手で蹴ったその精神力は凄いと思いました。
おそらく、スアレスも頭では間に合わないと思ったから、咄嗟の判断で手を使ったのでしょう。
「フェアープレー」という名の不作為の罪をかぶるのか、
それとも勝利への執念の為に自ら進んで極刑を受け入れるのか、
究極の選択だったのでしょうね。
ただ、迷わず後者を選択したことに、南米の凄みを感じました。
もちろん、相手を負傷させるファールは絶対に撲滅すべきです。
しかし、「プロフェッショナルファール」に対する認識は、日本ではまだ薄いと思いますね。
数年前に、朝日新聞で井原がプロフェッショナルファールに対して擁護したら、
読者から反発されたことがありましたから。
フェアープレーを絶対的に善しとする日本の風潮では、
反則を逆手にとって戦略にする発想は生まれにくいのかもしれませんね。
実は、昨日のアルゼンチンの敗戦にもショックは受けているのですが、やっぱり、現実を受け止めつつ前進しなくちゃ!(なんのこっちゃ?笑)と思いながら、重い足を引きずりながら、ここまでやってきました。
来てみると、またまた、サッカーを巡る因縁話を詳しく知ることができ、私の受けた敗戦の傷など、なんと軽いものか、と思い知ったのです。(ロハス事件の記事も読ませていただきました。)
こういうことの是非を問う意味すら、軽く思えてしまうほど、彼らの本能的なプレーというのは、止められないのだろうし、そういった理屈で割り切れないことの積み重ねが、プレーする人間が変わっても、観客の中には受け継がれていくものなのだ、とも思いました。
とても、不思議な気持ちです。
でも、得がたい情報の数々、しかも映像つき。
そういう点で、このブログには、雑誌以上のおもしろさを感じます。
今日も、ありがとうございました。
この写真をよく見ると、スアレスの左側の4番の選手も左手を上げているので、まさに2枚ブロックですね(笑)。
ガーナがFKを蹴る直前に、ウルグアイが選手間同士で話し合っていたのか分かりませんが、
おそらくウルグアイは誰が入っても、同じ事をやっていたと思います。
むしろ、南米だと、あの場面で手を使わない方が批判されるのかもしれませんね。
こういう咄嗟の判断は、教えられて出来る事ではないと思います。
それに、南米の選手は大抵が貧困階層が多く、しかも半端ではない競争社会ですから、
勝負に対する執念は尋常ではないです。
競技環境や脈々と受け継がれた伝統の蓄積が、自然と実行させたのかもしれませんね。
逆に、日本の選手がスアレスのようなプレーをしたら、侃侃諤諤の議論が起きるような気がします。
如何せん、日本のスポーツ界は“汗と涙の甲子園”のように、
「スポーツ選手は純真でさわやかであるべきだ」という建前がありますから。
日本のスポーツは、良くも悪しくも教育の一環ですからね。
まあ、こういう考え方も決して悪くは無いのですが、やはり重要な場面で淡白なプレーになりがちですね。
以前、フェアープレーについて記事にしたことがありますので、
お時間がありましたらご覧になって下さい。
http://blog.goo.ne.jp/nekonabe48/e/e365c8b47faba3f08a8b792c9298090a