三重県と岐阜県の県境は、江戸期より有数の真宗地帯。お寺といえば、真宗(東西本願寺)のお寺と考えて略間違いはありません。ご住職から「蓮如上人の絵伝(えでん)と思われる掛け軸が4本見つかりました。確認していただけないか」という依頼が有りました。そこで、本日(6月12日)は確認作業に専念。
写真・・本堂南余間に掛けられた4本の軸。紛れも無き「蓮如絵伝」です。「蓮如絵伝」とは、蓮如上人のご一生を絵で表わしたもの。

ご覧の通り、保存状態は良好。極めて良質の「蓮如絵伝」です。初公開となります。一幅は各5段。一段に2画面。一幅で10の場面が描かれている事になります。ですから、この「蓮如絵伝」は、蓮如上人のご一生を40の場面で構成。
蓮如上人、本願寺第8代宗主にして「本願寺再興の上人」。江戸期中期以降、蓮如上人の足跡が色濃い地域である近畿・北陸・東海地方で盛んに製作されました。主として、ご蓮如上人縁のご旧跡寺院が所有する場合が多いのです。現在確認されている蓮如絵伝は、約200本余り。今日、新たに一本が加わりました。
蓮如絵伝には、白眉の場面が多い。その代表例に「腹籠りの聖教」の段がある。上記の「蓮如絵伝」では、3幅目(右から)の最下段に描かれている。蓮如上人創建の吉崎御坊が炎上した際、本光房了顕は燃え盛る御坊の建物に飛び込み、自らは火達磨となりながらも、自らの腹を掻(か)っ捌(さば)いて、腹のなかに聖教を入れ殉死した。この物語が門徒の涙を誘わない筈はないし、その信仰を頂点にまで高揚させた筈なのです。情の人である蓮如上人に相応しい話なのです。
「親鸞絵伝」と比較して「蓮如絵伝」は、ローカル色が強いという特徴があります。つまり、「親鸞絵伝」のように本山・本願寺が末寺に下付したものではなく、地方の有力寺院が蓮如上人との結びつきを絵伝のなかに描きこみ門徒教化の重要な手段としたのです。ここに史実と伝承が入り混じった「蓮如絵伝」が成立しました。今、「蓮如絵伝」がおもしろい。
写真・・本堂南余間に掛けられた4本の軸。紛れも無き「蓮如絵伝」です。「蓮如絵伝」とは、蓮如上人のご一生を絵で表わしたもの。

ご覧の通り、保存状態は良好。極めて良質の「蓮如絵伝」です。初公開となります。一幅は各5段。一段に2画面。一幅で10の場面が描かれている事になります。ですから、この「蓮如絵伝」は、蓮如上人のご一生を40の場面で構成。
蓮如上人、本願寺第8代宗主にして「本願寺再興の上人」。江戸期中期以降、蓮如上人の足跡が色濃い地域である近畿・北陸・東海地方で盛んに製作されました。主として、ご蓮如上人縁のご旧跡寺院が所有する場合が多いのです。現在確認されている蓮如絵伝は、約200本余り。今日、新たに一本が加わりました。
蓮如絵伝には、白眉の場面が多い。その代表例に「腹籠りの聖教」の段がある。上記の「蓮如絵伝」では、3幅目(右から)の最下段に描かれている。蓮如上人創建の吉崎御坊が炎上した際、本光房了顕は燃え盛る御坊の建物に飛び込み、自らは火達磨となりながらも、自らの腹を掻(か)っ捌(さば)いて、腹のなかに聖教を入れ殉死した。この物語が門徒の涙を誘わない筈はないし、その信仰を頂点にまで高揚させた筈なのです。情の人である蓮如上人に相応しい話なのです。
「親鸞絵伝」と比較して「蓮如絵伝」は、ローカル色が強いという特徴があります。つまり、「親鸞絵伝」のように本山・本願寺が末寺に下付したものではなく、地方の有力寺院が蓮如上人との結びつきを絵伝のなかに描きこみ門徒教化の重要な手段としたのです。ここに史実と伝承が入り混じった「蓮如絵伝」が成立しました。今、「蓮如絵伝」がおもしろい。












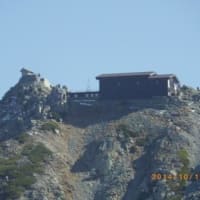







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます