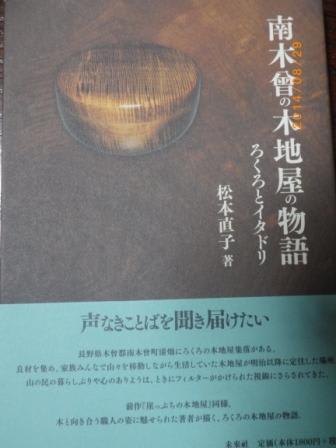撮影スタップ(10名)は大阪から。早速、撮影開始。勿論、こんな大がかりな撮影現場を直に見るのは初めて。

何を撮影しているのか。事前に用意されたお膳を撮影。

このお膳の献立が自坊取材の主たる目的なのです。

この精進料理は、三重県いなべ地方(三重県北部山間部)の伝統的なお葬式の料理です。つい最近まで、自宅葬が当たり前でした。その時には、必ず振舞われた精進料理)。この精進料理の献立のなかで、目に引くのが「赤飯と唐辛子汁」。全国的にも、いなべ地方だけに伝わってきた「赤飯と唐辛子汁」の献立と思われます。何故に、葬儀に際しての精進料理に「赤飯と唐辛子汁」が必ずついたのか???これについては、後に詳しく解説。
このお膳一式の撮影に何と30分以上の時間が費やされました。
撮影は内陣に進みます。ご本尊の宮殿(くうでん)が撮影。ここには、浄土真宗のご本尊、阿弥陀如来様がおあします。

そして、撮影は庫裡(くり)の土間に移動。ここが調理現場。皆さん、土間の広さにビックリ仰天。自坊の庫裡は、江戸後期(1830年)に建てられた典型的な浄土真宗の庫裡構造。この土間にて、ご門徒が煮炊きできる構造になっています。報恩講のお斎(とき)も全てここで調理されます。昨年(H25.4.15)に修行された二法要(親鸞聖人750回大遠忌法要・本堂修復法要)に際しても、ふる回転にて約500人分の精進料理をここで調理したのです。

写真・・おくどさんにて「赤飯」・手前の大鍋にて「唐辛子汁」が・・・
続く・・・・
このブログの訪問者が、233000人(正確には、233153人)を超えていました。いつも訪問していただき感謝申し上げます。

何を撮影しているのか。事前に用意されたお膳を撮影。

このお膳の献立が自坊取材の主たる目的なのです。

この精進料理は、三重県いなべ地方(三重県北部山間部)の伝統的なお葬式の料理です。つい最近まで、自宅葬が当たり前でした。その時には、必ず振舞われた精進料理)。この精進料理の献立のなかで、目に引くのが「赤飯と唐辛子汁」。全国的にも、いなべ地方だけに伝わってきた「赤飯と唐辛子汁」の献立と思われます。何故に、葬儀に際しての精進料理に「赤飯と唐辛子汁」が必ずついたのか???これについては、後に詳しく解説。
このお膳一式の撮影に何と30分以上の時間が費やされました。
撮影は内陣に進みます。ご本尊の宮殿(くうでん)が撮影。ここには、浄土真宗のご本尊、阿弥陀如来様がおあします。

そして、撮影は庫裡(くり)の土間に移動。ここが調理現場。皆さん、土間の広さにビックリ仰天。自坊の庫裡は、江戸後期(1830年)に建てられた典型的な浄土真宗の庫裡構造。この土間にて、ご門徒が煮炊きできる構造になっています。報恩講のお斎(とき)も全てここで調理されます。昨年(H25.4.15)に修行された二法要(親鸞聖人750回大遠忌法要・本堂修復法要)に際しても、ふる回転にて約500人分の精進料理をここで調理したのです。

写真・・おくどさんにて「赤飯」・手前の大鍋にて「唐辛子汁」が・・・
続く・・・・
このブログの訪問者が、233000人(正確には、233153人)を超えていました。いつも訪問していただき感謝申し上げます。