ことしの夏はあの戦争から64年目の夏・・・
第二次世界大戦アジア太平洋戦争の末期、1945年8月9日未明、ソ連軍は旧満州国との国境を越えて参戦(進攻)してきます。アメリカ軍との戦争で息も絶え絶えになったところに来るなんて・・・戦争なんてそういうものです。
戦力 日本軍104万人 ソ連軍157万人、モンゴル軍1.6万人
戦死者 日本軍8万人 ソ連軍8200人
戦傷者 日本軍59万人 ソ連軍2万人
参戦の情報は、とうぜん日本軍(関東軍)もわかっていたようですが、ソ満国境にいた開拓民の避難は日本軍の動きを悟られないために見送られたようです。圧倒的な機動力、火力の差で戦争にもなりません。日本軍は敗走を重ねます。
かくしてソ連軍の侵攻、虐殺、暴行、略奪・・・開拓民132万人の逃避行が始まります。なんとか日本に帰れたグループ、足止めを余儀なくされたグループ、全滅したグループといろいろです。
満蒙開拓中国残留孤児という言葉が生まれます。逃避行中に親が死んだ子、このまま飢えて死ぬより子どもだけは生きていて欲しいと子どもを託した親、いろいろです。
 ことし4月NHKで「遥かなる絆」というドラマが放映されました。城戸久枝著「あの戦争から遠く離れて」(情報センター出版局2007年刊のドラマ化です。著者のお父さんは中国残留孤児、すさまじい境遇から日本に帰国するという話ですが、その中で育ててくれた優しい義母、日本人と知っても友情を貫いてくれた友達の話しが出てきます。
ことし4月NHKで「遥かなる絆」というドラマが放映されました。城戸久枝著「あの戦争から遠く離れて」(情報センター出版局2007年刊のドラマ化です。著者のお父さんは中国残留孤児、すさまじい境遇から日本に帰国するという話ですが、その中で育ててくれた優しい義母、日本人と知っても友情を貫いてくれた友達の話しが出てきます。
井出孫六著「終わりなき旅」(岩波書店1985年初出)、山崎豊子著「大地の子」(文言春秋社1987年初出)から20年・・・大地の子、残留孤児という言葉も古いものになりました。
城戸久枝さんは大地の子の時代からもう一世代下の人、いまの中国との関係を模索し、中国残留孤児の裁判のお手伝いもしてるようです。
本の中の記述に、「大地の子」の何度目かの再放送を見ながら著者のお父さん(城戸幹さん)は
「なあ、久枝。お父ちゃんがいたころは、あんな甘いもんじゃなかったよ」といってたそうです。そっとティッシュで鼻をかみながら。
関連した次の本を読んでみました。「大地の子」「あの戦争から・・・」よりさらに甘くないお話しです。
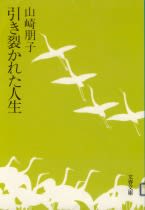 山崎朋子著「引き裂かれた人生」(文春春秋社1987年初出)
山崎朋子著「引き裂かれた人生」(文春春秋社1987年初出)
中国残留孤児訪日調査団のうちの6人の聞き取り追跡ルポです。山崎さんはそのころすでに著名な作家であり国際ペンクラブ中国作家協会を通じて現地取材が可能になったようです。養母に酷使された人、集団自決から生き残った人、ようやく帰ったが父は特養ホームにいた人、家庭的に恵まれた人、一時帰国したが自分を棄てた実の母との確執、日本の人との養子縁組で帰った人、キレイ事ではないさまざまな人生があります。
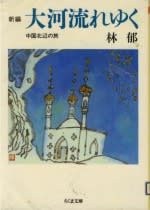 林郁著「大河流れゆく」(1988年朝日新聞社初出)
林郁著「大河流れゆく」(1988年朝日新聞社初出)
ソ中国境・大河黒竜江(アムール河)の近く、ソ連進攻により避難も叶わず置き去りにされた婦女子、集団自決、現地民の報復、深い傷跡を残し、その後に続く過酷な現実を必死に生き抜いた姿を丹念にルポしています。満蒙開拓団指導部によるソ連軍対策用の婦女提供の話し、帰国して「乙女の碑」を建てたそうです。ダブル・レイプです。著者にはほかに「満州・その幻の国ゆえに」という著書があります。
64年前の8月、ソ連軍の進攻から筆舌に尽くしがたい物語がはじまりました。
関連した本を読みましたが中途半端です。詳しくは本を読んでみてください。
60数年前の旧満州(現中国東北部)でどうしてこんなことが起きたか。旧満州って何なんだ。よく考えるべきときです。今は国の指導者は国民が選べる時代です。
第二次世界大戦アジア太平洋戦争の末期、1945年8月9日未明、ソ連軍は旧満州国との国境を越えて参戦(進攻)してきます。アメリカ軍との戦争で息も絶え絶えになったところに来るなんて・・・戦争なんてそういうものです。
戦力 日本軍104万人 ソ連軍157万人、モンゴル軍1.6万人
戦死者 日本軍8万人 ソ連軍8200人
戦傷者 日本軍59万人 ソ連軍2万人
参戦の情報は、とうぜん日本軍(関東軍)もわかっていたようですが、ソ満国境にいた開拓民の避難は日本軍の動きを悟られないために見送られたようです。圧倒的な機動力、火力の差で戦争にもなりません。日本軍は敗走を重ねます。
かくしてソ連軍の侵攻、虐殺、暴行、略奪・・・開拓民132万人の逃避行が始まります。なんとか日本に帰れたグループ、足止めを余儀なくされたグループ、全滅したグループといろいろです。
満蒙開拓中国残留孤児という言葉が生まれます。逃避行中に親が死んだ子、このまま飢えて死ぬより子どもだけは生きていて欲しいと子どもを託した親、いろいろです。
 ことし4月NHKで「遥かなる絆」というドラマが放映されました。城戸久枝著「あの戦争から遠く離れて」(情報センター出版局2007年刊のドラマ化です。著者のお父さんは中国残留孤児、すさまじい境遇から日本に帰国するという話ですが、その中で育ててくれた優しい義母、日本人と知っても友情を貫いてくれた友達の話しが出てきます。
ことし4月NHKで「遥かなる絆」というドラマが放映されました。城戸久枝著「あの戦争から遠く離れて」(情報センター出版局2007年刊のドラマ化です。著者のお父さんは中国残留孤児、すさまじい境遇から日本に帰国するという話ですが、その中で育ててくれた優しい義母、日本人と知っても友情を貫いてくれた友達の話しが出てきます。井出孫六著「終わりなき旅」(岩波書店1985年初出)、山崎豊子著「大地の子」(文言春秋社1987年初出)から20年・・・大地の子、残留孤児という言葉も古いものになりました。
城戸久枝さんは大地の子の時代からもう一世代下の人、いまの中国との関係を模索し、中国残留孤児の裁判のお手伝いもしてるようです。
本の中の記述に、「大地の子」の何度目かの再放送を見ながら著者のお父さん(城戸幹さん)は
「なあ、久枝。お父ちゃんがいたころは、あんな甘いもんじゃなかったよ」といってたそうです。そっとティッシュで鼻をかみながら。
関連した次の本を読んでみました。「大地の子」「あの戦争から・・・」よりさらに甘くないお話しです。
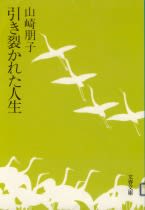 山崎朋子著「引き裂かれた人生」(文春春秋社1987年初出)
山崎朋子著「引き裂かれた人生」(文春春秋社1987年初出)中国残留孤児訪日調査団のうちの6人の聞き取り追跡ルポです。山崎さんはそのころすでに著名な作家であり国際ペンクラブ中国作家協会を通じて現地取材が可能になったようです。養母に酷使された人、集団自決から生き残った人、ようやく帰ったが父は特養ホームにいた人、家庭的に恵まれた人、一時帰国したが自分を棄てた実の母との確執、日本の人との養子縁組で帰った人、キレイ事ではないさまざまな人生があります。
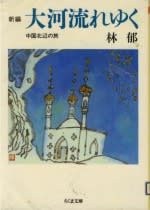 林郁著「大河流れゆく」(1988年朝日新聞社初出)
林郁著「大河流れゆく」(1988年朝日新聞社初出)ソ中国境・大河黒竜江(アムール河)の近く、ソ連進攻により避難も叶わず置き去りにされた婦女子、集団自決、現地民の報復、深い傷跡を残し、その後に続く過酷な現実を必死に生き抜いた姿を丹念にルポしています。満蒙開拓団指導部によるソ連軍対策用の婦女提供の話し、帰国して「乙女の碑」を建てたそうです。ダブル・レイプです。著者にはほかに「満州・その幻の国ゆえに」という著書があります。
64年前の8月、ソ連軍の進攻から筆舌に尽くしがたい物語がはじまりました。
関連した本を読みましたが中途半端です。詳しくは本を読んでみてください。
60数年前の旧満州(現中国東北部)でどうしてこんなことが起きたか。旧満州って何なんだ。よく考えるべきときです。今は国の指導者は国民が選べる時代です。
※コメント欄オープン。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます