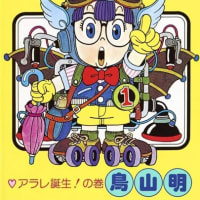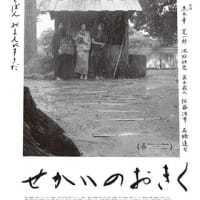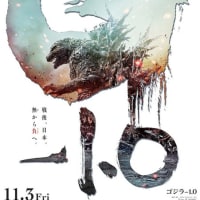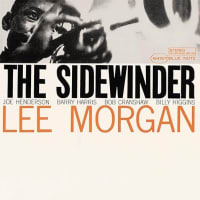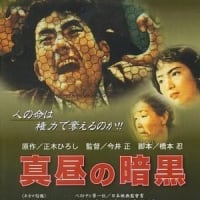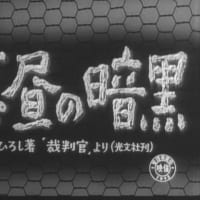さくらももこ氏が亡くなって、もう半年になる。行年55というのは、あまりに早い(※1)。
ただ、それでもやはり、さくらももこは、客観的に見て幸せな人だった。こう言っては失礼に聞こえるかもしれないが、あのような画力でプロ漫画家になれて、しかも国民的な大ヒットに恵まれて巨額の財産にも恵まれたというのは、人生時間の長短を超えた幸せなことだ(※2)。漫画家としてのみならず、エッセイストとしても、作詞家としても、ラジオパーソナリティーとしてもそれなりの成功をおさめたのだし。
さくらももこ氏が、かくも知名度の高い存在になったのは、もちろんアニメの影響が大きい。日本アニメーションはさくらももこに足を向けて寝られないが、さくらももこもまた日本アニメーションに足を向けて寝られまい。TARAKOもまた、さくらももこと日本アニメーションの双方に足を向けては寝られまい(※3)。
で、絵の巧拙の話だが。
たしかに絵柄の好き嫌いは別として、赤塚不二夫も植田まさしもいしいひさいちも西岸良平(※4)も北見けんいちも密度の薄い単純な線で(※5)、特段に絵がうまい漫画家ではない(※6)。
が、さくらももこの、とくに初期の下手さは半端ではない(※7)。最初はかなり驚いた。蛭子能収並みだ。
ただ、デビューに至る経緯を回顧した『夢の音色』(1987)にあるように、もともとは普通の少女漫画を描いていた(※8)さくらももこが、他の投稿者と差別化するために、あえてまったく絵柄を変えてエッセイ的漫画を描くようになったということらしいので、正統派の絵が描けないということでは決してないのだと思う。このことは、さくらももこの名誉のために言っておいてもいいだろう(※9)。
さて。
そんなさくらももこの代表作『ちびまる子ちゃん』が日曜夕方に始まって大ブレークした90~91年頃、私は高校生で、私のいた学校でもずいぶん流行ったものである。まる子を賞賛するあまり、『サザエさん』をなぜか異様なまでの情熱をこめてディスっていたK.I.氏。さくらさきこさん(※10)こそ理想の女性だと、これまた情熱をこめて公言していた変態的なS.M.生(※11)。・・・
みんな、みんな、『まる子』にハマっていた。『りぼん』本誌でもともと知っていた者も、そうでない者も。
ただ、絵柄自体が、原作もアニメも他の長寿作品-たとえば『亀有』-と同じくだんだん洗練されスッキリ見やすくなっていくのに反比例して、他の長寿作品-たとえば『亀有』-と同様に、内容は落ちていったように思われてならない(※12)。
もちろん、そういう物言いというのは、若い世代から見れば老人の懐古癖のイチャモンに過ぎない場合が大半だが、『亀有』と『まる子』に関しては正当に思えてしまう(※13)。レトロテイストのアルアルエッセイ漫画ではなくなったからね、少なくとも(※14)。
はまじ、たまちゃん、ブー太郎のような実在した普通のキャラより、野口さん、永沢くん、藤木くんといった創作のエキセントリックなキャラに頼るようになってからは-90年代半ば以降、アニメでいうと再開以降は-、好き嫌いは人それぞれだが、少なくともエッセイ漫画という初心からは別物になり果てたのは事実だろう(※15)。優劣評価とも好き嫌い評価とも別に事実として。
アルアル的エッセイ漫画の醍醐味という部分では、単行本初期の後ろのほうに入っていた「ほのぼの劇場」としてまとめられた初期の短編こそ、さくらももこエッセイ漫画のエッセンスだろう。実際、前出の同級生K.I.氏などは最初『まる子』目当てで単行本を買ったが、巻末の短編群のほうにハマっていたものだ。かくいう私も、K.I.氏と同様に、『まる子』本編より読み切り短編群のほうが気に入ったお仲間の一人である。
たとえば、『あこがれの鼻血』(1985)など、読みやすくて感情移入もしやすい、お手頃なアルアルエッセイという感じで、『5月のオリエンタル小僧』(1986)や『放課後の学級会』(1988)と同様に『まる子』本編に編入される形でアニメ化もされているが、これらは『まる子』シリーズ本体よりも起承転結もしっかりしており、ビギナー向けのお勧め作と言っていいだろう。
また、『みんな恥知らず』(1986)の最後の、
「子どもの心って、大人の固くなってしまった心ではわからないほど敏感で傷つきやすくて、ほんの些細なことでいちいち悩んでいるのです」
という言葉は、私にとって、はじめて読んだ高校生の頃から、大学で教育心理学を専攻していた頃まで、妙に心に深く残っていた言葉である。
『いつか遠いところで』(1988)は、さくらももこが学生時代に家庭教師をしたときのエピソードだが、有名大学の学生が掃いて捨てるほど生息している東京城南地区で学生時代を過ごした自分からしたら、失礼ながら無名の短大生にそんな何軒も家庭教師の口があるという清水の事情に、何だか驚いてしまう(※16)。
そして、『ひとりになった日』(1987)は、読んでからだいぶ経った頃に、私もほとんど同じ経験をしたので、私にとっては最も親近感のある、思い入れのある佳品である。普通に実写ドラマ化しても、きっと感情移入しやすい作品に仕上がるに相違ない。
それから、妹の姉へのコンプレックスをテーマにした『フランス人形とちび姫』(1988)は、さくらさきこファンにはバイブルとも言うべき作品で、私も印象に残っている。
受験生の夏休みを描いた『夏の色もみえない』(1987)も、何となくほんのりとしたリリカルな味わいがよい、愛すべき小品。
初潮をテーマにした『いつものかえりみち』(1988)などは、年齢的に『まる子』本編には編入しようがない読み切り短編ならではの話であるとともに、当然ながら絶対に女流漫画家にしか描けない作品である。
かなり恋愛テイストの強い高校時代の話、『陽だまりの粒』(1991)は、ある意味、正統派少女漫画に近い作品であり、作者がもともと描きたかったのは、こんな世界だったのかもしれないとも思う(※17)。
かくして、あざとくなってからの『まる子』本編に興味を失って久しい私ですら、これらの初期短編はちょっとした座右の宝であり、今もヒマがあると文庫に手がのびることがあるのだった。
合掌。
(※1)
中村勘三郎丈のとき、北の湖理事長のとき、小林麻央さんのときの書き出しと同じ・・・って、自分で自分をパロッてどうする??
(※2)
これも小林麻央氏のときと同じ物言いだな。こっちについては、自分で自分をパロッているつもりでもないんだが(苦笑)。
(※3)
正直、TARAKOに声優としての才がそれほどあるかどうかは私は懐疑的なのだが、ルパンの山田康雄やドラえもんの大山のぶ代と同様に、 地声のままで日本人の誰もが知る取り換え不能なオンリーワンの声として必要とされているのなら、まあやはり「才能がある」のだろう。たぶん(なお野原しんのすけの矢島晶子は地声そのままではない)。
それに、たとえまる子のイメージが強すぎて他の役ができなくなったとしても、長寿番組のタイトルロールにはそれと引き換えにするだけの価値があろう。
(※4)
西岸良平の絵は密度の薄い一見すると単純で簡単な絵なれど、なかなか侮れない。
一平の同級生の一人、「ズボン女」こと「松本聖子ちゃん」が、他のキャラと同様に単純な線の顔なのに、なぜか他の娘たちとはレベチの美少女だってことがちゃんとすぐわかるあたり。「やるな、おぬし!さすがはハリー細野の認めた才覚よ!」と感服したくなる。
(※5)
あとはまあ人物の絵の密度と背景の絵の密度がまるで別次元という水木しげるのような、いささか変わった人もいるが。
(※6)
ただし、一見密度の薄い、単純で簡単そうな絵だからと言って、誰でも同じように描けるかというと、さにあらず。
実際、本稿の主題であるまる子ちゃんなんて、いかにも簡単そうな絵でありながら、別の人が描くと、どうしても似ない。どこか違う。単純そうな絵ほど、意外に同じようには描けないという不思議がある。
かのスヌーピーなど、まさにその典型であろう。簡単そうに見えて、誰が描いてもああは描けない。どうしても間抜けなニセスヌーピーになってしまう。あのスヌーピーの顔の微妙な曲線は、おそらくシュルツ画伯本人にしか描けないものなのだろう。
(※7)
後期はそれなりに絵柄は整理され綺麗になった。また、自画像は、はっきり言って現実の山田花子みたいな本人よりはるかにかわいく洗練されていた。まるで小林よしのりみたいなナルシズム美化願望自画像だ(あと、高橋留美子も美化タイプとして指を屈してよさそうだが、高橋留美子の場合、美化というよりいつまでも若くてスリムな時代の姿のままの自画像と言うべきか)。
漫画家の自画像というと、水木しげるなどはただ淡々と自分の似顔絵を描いているだけだが、手塚治虫のように、ややコミカルにデフォルメして描くのが普通で、石ノ森章太郎の、あのおなじみの、顔のパーツが中央に集まったような特徴的な自画像などは、コミカルにデフォルメしたタイプの典型だろう。
いっぽう、鳥山明のガスマスクロボットの自画像は、美化でもデフォルメでもただの似顔絵でもなく、自身の実際の顔と何ら関係ないという変わったタイプのものだが、わざと個人を特定しにくくしたのだろうか(もっとも、「ペンギン村グランプリ」、「世界一つおいのだーれだ大会」のときのような、ごく普通の自画像のときもあったが)。
(※8)
世代的にはたぶん高橋亮子の作品あたりを読んだ世代だろうか。いいなあ、高橋亮子の漫画は。アニメになっていればよかったのに。忘れ去られてしまうには、あまりに惜しい。高橋亮子作品の素晴らしさについても、いつか別稿で詳述したいものである。
(※9)
たとえば、作品の知名度のわりに作者名が記憶されていないことでは吉沢やすみと双璧と言っていい、『あさりちゃん』の室山まゆみなども、ドタバタギャグの印象が強いが、ゲストの大人の女性キャラの顔などは明らかに王道少女漫画タッチである(ただ90年代以降の世間一般の少女向け漫画は、そもそも昔の萩尾望都作品みたいに露骨に「瞳に星」なんていう絵ではないが)。
なお余談ながら、室山まゆみが実は「二人で一人」型の漫画家であることは、藤子不二雄(藤子・F・不二雄、藤子不二雄A)と違ってあまり知られていないが、とくにきょうだい漫画家というユニットは世界的にも珍しいかもしれない(他ジャンルならウォシャウスキー兄弟とか来生たかお&来生えつこなんてのもいるが)。ウィキペディアによると、室山まゆみはストーリーも絵も完全な合作スタイルだそうで、原作と絵で分かれるゆでたまご(つまり『巨人の星』や『美味しんぼ』や 『釣りバカ日誌』のスタイル)やペンネームは共同でも実質的には一部を除いてそれぞれ別々に描いていた藤子不二雄とは、その点でも一線を画している。
(※10)
漫画の中でのまる子ことさくらももこは実際は三浦美紀、お姉さんのさくらさきこは実際は三浦範子というらしいが。
(※11)
たしかにお姉さんは、さくらももこの単純な絵でも、群を抜いてかわいいルックスに描かれてはいるが(2006年の実写ドラマスペシャルで見たときも、まる子より率直に言ってずっとかわいかったものね)。
でも、清水のちびまる子ちゃんランドのディスプレイや販売グッズなどについては、キャラとして 推されているのはまる子とクラスメートばかりで、おじいちゃん以外の家族は無視に近い扱いである。けだし不当なり。お姉さんは、たぶん隠れファンがかなり多いと思うのだが。
(※12)
個人的には『亀有』で一番すきな回は「北国よいとこ」(59巻所収)だ。着想もいいし、構成も実に無駄がなく、完璧である。
限られたページ内での無駄のない完璧な構成という点で、『パーマン』の「死の船」、「わたしの命は狙われている」、『ドラえもん』の「白ゆりのような女の子」、『めぞん一刻』の「一刻館の昼と夜」、『ポーの一族』の「グレンスミスの日記」らと比肩できよう。
(※13)
ドラゴンボールもそうだが、初期の冒険ファンタジーコメディ作品と中期以降の戦闘力インフレバトル作品ではあまりに別物すぎるので、これはもはや同じ比較の俎上に乗せるべきではなかろう。優劣や好き嫌いは別として(「子どもに夢を」をモットーとする故・寺田ヒロオ氏あたりなら、初期のドラゴンボール探しのあたりは絶賛しても、フリーザやセルのあたりは、漫画として認めないかもね)。
(※14)
まあ、実際の子どもの頃のエピソードだけでは、何十年ものロングラン作品としてはネタがもたないのは当然である。
(※15)
ただ、エッセイ漫画ではなくとも、やはり小学校を舞台にした日常っぽい子ども向け作品でなければ受けないということか、鳴り物入りで期待されアニメになった『コジコジ』が一敗地にまみれ、『まる子』以外にも代表作をと狙った作者にとっても、フジテレビの二匹目のドジョウを狙ったTBSにとっても悲惨な黒歴史に終わってしまったことを思うと、何とも痛ましい(そういえば、アニメ版の『三丁目の夕日』が90年代初頭にやはりTBS系列でアニメ化され、後の実写映画のようにはヒットせずに終わってしまったことがあったが、あれも同時期のフジテレビの『まる子』大ヒットに触発され、昭和の子ども時代懐古アニメという伝で二匹目のドジョウ狙いが外れたものだったのだろうか。どうもこのあたりの時期のTBSは、「貧すれば鈍する」だったようだな)。
(※16)
まあ、たしかに私がかつて勤めたことのある個別指導塾でも、女子学生講師の中には、たまに一流とは呼ばれない大学の人もいたようだが・・・でも、そういう人は、やっぱり小学生の授業しかやらせてもらえてなかったみたいね。
(※17)
作者の自画像に、既に美化癖のバイアスがだいぶ見えるところはご愛嬌。
ただ、それでもやはり、さくらももこは、客観的に見て幸せな人だった。こう言っては失礼に聞こえるかもしれないが、あのような画力でプロ漫画家になれて、しかも国民的な大ヒットに恵まれて巨額の財産にも恵まれたというのは、人生時間の長短を超えた幸せなことだ(※2)。漫画家としてのみならず、エッセイストとしても、作詞家としても、ラジオパーソナリティーとしてもそれなりの成功をおさめたのだし。
さくらももこ氏が、かくも知名度の高い存在になったのは、もちろんアニメの影響が大きい。日本アニメーションはさくらももこに足を向けて寝られないが、さくらももこもまた日本アニメーションに足を向けて寝られまい。TARAKOもまた、さくらももこと日本アニメーションの双方に足を向けては寝られまい(※3)。
で、絵の巧拙の話だが。
たしかに絵柄の好き嫌いは別として、赤塚不二夫も植田まさしもいしいひさいちも西岸良平(※4)も北見けんいちも密度の薄い単純な線で(※5)、特段に絵がうまい漫画家ではない(※6)。
が、さくらももこの、とくに初期の下手さは半端ではない(※7)。最初はかなり驚いた。蛭子能収並みだ。
ただ、デビューに至る経緯を回顧した『夢の音色』(1987)にあるように、もともとは普通の少女漫画を描いていた(※8)さくらももこが、他の投稿者と差別化するために、あえてまったく絵柄を変えてエッセイ的漫画を描くようになったということらしいので、正統派の絵が描けないということでは決してないのだと思う。このことは、さくらももこの名誉のために言っておいてもいいだろう(※9)。
さて。
そんなさくらももこの代表作『ちびまる子ちゃん』が日曜夕方に始まって大ブレークした90~91年頃、私は高校生で、私のいた学校でもずいぶん流行ったものである。まる子を賞賛するあまり、『サザエさん』をなぜか異様なまでの情熱をこめてディスっていたK.I.氏。さくらさきこさん(※10)こそ理想の女性だと、これまた情熱をこめて公言していた変態的なS.M.生(※11)。・・・
みんな、みんな、『まる子』にハマっていた。『りぼん』本誌でもともと知っていた者も、そうでない者も。
ただ、絵柄自体が、原作もアニメも他の長寿作品-たとえば『亀有』-と同じくだんだん洗練されスッキリ見やすくなっていくのに反比例して、他の長寿作品-たとえば『亀有』-と同様に、内容は落ちていったように思われてならない(※12)。
もちろん、そういう物言いというのは、若い世代から見れば老人の懐古癖のイチャモンに過ぎない場合が大半だが、『亀有』と『まる子』に関しては正当に思えてしまう(※13)。レトロテイストのアルアルエッセイ漫画ではなくなったからね、少なくとも(※14)。
はまじ、たまちゃん、ブー太郎のような実在した普通のキャラより、野口さん、永沢くん、藤木くんといった創作のエキセントリックなキャラに頼るようになってからは-90年代半ば以降、アニメでいうと再開以降は-、好き嫌いは人それぞれだが、少なくともエッセイ漫画という初心からは別物になり果てたのは事実だろう(※15)。優劣評価とも好き嫌い評価とも別に事実として。
アルアル的エッセイ漫画の醍醐味という部分では、単行本初期の後ろのほうに入っていた「ほのぼの劇場」としてまとめられた初期の短編こそ、さくらももこエッセイ漫画のエッセンスだろう。実際、前出の同級生K.I.氏などは最初『まる子』目当てで単行本を買ったが、巻末の短編群のほうにハマっていたものだ。かくいう私も、K.I.氏と同様に、『まる子』本編より読み切り短編群のほうが気に入ったお仲間の一人である。
たとえば、『あこがれの鼻血』(1985)など、読みやすくて感情移入もしやすい、お手頃なアルアルエッセイという感じで、『5月のオリエンタル小僧』(1986)や『放課後の学級会』(1988)と同様に『まる子』本編に編入される形でアニメ化もされているが、これらは『まる子』シリーズ本体よりも起承転結もしっかりしており、ビギナー向けのお勧め作と言っていいだろう。
また、『みんな恥知らず』(1986)の最後の、
「子どもの心って、大人の固くなってしまった心ではわからないほど敏感で傷つきやすくて、ほんの些細なことでいちいち悩んでいるのです」
という言葉は、私にとって、はじめて読んだ高校生の頃から、大学で教育心理学を専攻していた頃まで、妙に心に深く残っていた言葉である。
『いつか遠いところで』(1988)は、さくらももこが学生時代に家庭教師をしたときのエピソードだが、有名大学の学生が掃いて捨てるほど生息している東京城南地区で学生時代を過ごした自分からしたら、失礼ながら無名の短大生にそんな何軒も家庭教師の口があるという清水の事情に、何だか驚いてしまう(※16)。
そして、『ひとりになった日』(1987)は、読んでからだいぶ経った頃に、私もほとんど同じ経験をしたので、私にとっては最も親近感のある、思い入れのある佳品である。普通に実写ドラマ化しても、きっと感情移入しやすい作品に仕上がるに相違ない。
それから、妹の姉へのコンプレックスをテーマにした『フランス人形とちび姫』(1988)は、さくらさきこファンにはバイブルとも言うべき作品で、私も印象に残っている。
受験生の夏休みを描いた『夏の色もみえない』(1987)も、何となくほんのりとしたリリカルな味わいがよい、愛すべき小品。
初潮をテーマにした『いつものかえりみち』(1988)などは、年齢的に『まる子』本編には編入しようがない読み切り短編ならではの話であるとともに、当然ながら絶対に女流漫画家にしか描けない作品である。
かなり恋愛テイストの強い高校時代の話、『陽だまりの粒』(1991)は、ある意味、正統派少女漫画に近い作品であり、作者がもともと描きたかったのは、こんな世界だったのかもしれないとも思う(※17)。
かくして、あざとくなってからの『まる子』本編に興味を失って久しい私ですら、これらの初期短編はちょっとした座右の宝であり、今もヒマがあると文庫に手がのびることがあるのだった。
合掌。
(※1)
中村勘三郎丈のとき、北の湖理事長のとき、小林麻央さんのときの書き出しと同じ・・・って、自分で自分をパロッてどうする??
(※2)
これも小林麻央氏のときと同じ物言いだな。こっちについては、自分で自分をパロッているつもりでもないんだが(苦笑)。
(※3)
正直、TARAKOに声優としての才がそれほどあるかどうかは私は懐疑的なのだが、ルパンの山田康雄やドラえもんの大山のぶ代と同様に、 地声のままで日本人の誰もが知る取り換え不能なオンリーワンの声として必要とされているのなら、まあやはり「才能がある」のだろう。たぶん(なお野原しんのすけの矢島晶子は地声そのままではない)。
それに、たとえまる子のイメージが強すぎて他の役ができなくなったとしても、長寿番組のタイトルロールにはそれと引き換えにするだけの価値があろう。
(※4)
西岸良平の絵は密度の薄い一見すると単純で簡単な絵なれど、なかなか侮れない。
一平の同級生の一人、「ズボン女」こと「松本聖子ちゃん」が、他のキャラと同様に単純な線の顔なのに、なぜか他の娘たちとはレベチの美少女だってことがちゃんとすぐわかるあたり。「やるな、おぬし!さすがはハリー細野の認めた才覚よ!」と感服したくなる。
(※5)
あとはまあ人物の絵の密度と背景の絵の密度がまるで別次元という水木しげるのような、いささか変わった人もいるが。
(※6)
ただし、一見密度の薄い、単純で簡単そうな絵だからと言って、誰でも同じように描けるかというと、さにあらず。
実際、本稿の主題であるまる子ちゃんなんて、いかにも簡単そうな絵でありながら、別の人が描くと、どうしても似ない。どこか違う。単純そうな絵ほど、意外に同じようには描けないという不思議がある。
かのスヌーピーなど、まさにその典型であろう。簡単そうに見えて、誰が描いてもああは描けない。どうしても間抜けなニセスヌーピーになってしまう。あのスヌーピーの顔の微妙な曲線は、おそらくシュルツ画伯本人にしか描けないものなのだろう。
(※7)
後期はそれなりに絵柄は整理され綺麗になった。また、自画像は、はっきり言って現実の山田花子みたいな本人よりはるかにかわいく洗練されていた。まるで小林よしのりみたいなナルシズム美化願望自画像だ(あと、高橋留美子も美化タイプとして指を屈してよさそうだが、高橋留美子の場合、美化というよりいつまでも若くてスリムな時代の姿のままの自画像と言うべきか)。
漫画家の自画像というと、水木しげるなどはただ淡々と自分の似顔絵を描いているだけだが、手塚治虫のように、ややコミカルにデフォルメして描くのが普通で、石ノ森章太郎の、あのおなじみの、顔のパーツが中央に集まったような特徴的な自画像などは、コミカルにデフォルメしたタイプの典型だろう。
いっぽう、鳥山明のガスマスクロボットの自画像は、美化でもデフォルメでもただの似顔絵でもなく、自身の実際の顔と何ら関係ないという変わったタイプのものだが、わざと個人を特定しにくくしたのだろうか(もっとも、「ペンギン村グランプリ」、「世界一つおいのだーれだ大会」のときのような、ごく普通の自画像のときもあったが)。
(※8)
世代的にはたぶん高橋亮子の作品あたりを読んだ世代だろうか。いいなあ、高橋亮子の漫画は。アニメになっていればよかったのに。忘れ去られてしまうには、あまりに惜しい。高橋亮子作品の素晴らしさについても、いつか別稿で詳述したいものである。
(※9)
たとえば、作品の知名度のわりに作者名が記憶されていないことでは吉沢やすみと双璧と言っていい、『あさりちゃん』の室山まゆみなども、ドタバタギャグの印象が強いが、ゲストの大人の女性キャラの顔などは明らかに王道少女漫画タッチである(ただ90年代以降の世間一般の少女向け漫画は、そもそも昔の萩尾望都作品みたいに露骨に「瞳に星」なんていう絵ではないが)。
なお余談ながら、室山まゆみが実は「二人で一人」型の漫画家であることは、藤子不二雄(藤子・F・不二雄、藤子不二雄A)と違ってあまり知られていないが、とくにきょうだい漫画家というユニットは世界的にも珍しいかもしれない(他ジャンルならウォシャウスキー兄弟とか来生たかお&来生えつこなんてのもいるが)。ウィキペディアによると、室山まゆみはストーリーも絵も完全な合作スタイルだそうで、原作と絵で分かれるゆでたまご(つまり『巨人の星』や『美味しんぼ』や 『釣りバカ日誌』のスタイル)やペンネームは共同でも実質的には一部を除いてそれぞれ別々に描いていた藤子不二雄とは、その点でも一線を画している。
(※10)
漫画の中でのまる子ことさくらももこは実際は三浦美紀、お姉さんのさくらさきこは実際は三浦範子というらしいが。
(※11)
たしかにお姉さんは、さくらももこの単純な絵でも、群を抜いてかわいいルックスに描かれてはいるが(2006年の実写ドラマスペシャルで見たときも、まる子より率直に言ってずっとかわいかったものね)。
でも、清水のちびまる子ちゃんランドのディスプレイや販売グッズなどについては、キャラとして 推されているのはまる子とクラスメートばかりで、おじいちゃん以外の家族は無視に近い扱いである。けだし不当なり。お姉さんは、たぶん隠れファンがかなり多いと思うのだが。
(※12)
個人的には『亀有』で一番すきな回は「北国よいとこ」(59巻所収)だ。着想もいいし、構成も実に無駄がなく、完璧である。
限られたページ内での無駄のない完璧な構成という点で、『パーマン』の「死の船」、「わたしの命は狙われている」、『ドラえもん』の「白ゆりのような女の子」、『めぞん一刻』の「一刻館の昼と夜」、『ポーの一族』の「グレンスミスの日記」らと比肩できよう。
(※13)
ドラゴンボールもそうだが、初期の冒険ファンタジーコメディ作品と中期以降の戦闘力インフレバトル作品ではあまりに別物すぎるので、これはもはや同じ比較の俎上に乗せるべきではなかろう。優劣や好き嫌いは別として(「子どもに夢を」をモットーとする故・寺田ヒロオ氏あたりなら、初期のドラゴンボール探しのあたりは絶賛しても、フリーザやセルのあたりは、漫画として認めないかもね)。
(※14)
まあ、実際の子どもの頃のエピソードだけでは、何十年ものロングラン作品としてはネタがもたないのは当然である。
(※15)
ただ、エッセイ漫画ではなくとも、やはり小学校を舞台にした日常っぽい子ども向け作品でなければ受けないということか、鳴り物入りで期待されアニメになった『コジコジ』が一敗地にまみれ、『まる子』以外にも代表作をと狙った作者にとっても、フジテレビの二匹目のドジョウを狙ったTBSにとっても悲惨な黒歴史に終わってしまったことを思うと、何とも痛ましい(そういえば、アニメ版の『三丁目の夕日』が90年代初頭にやはりTBS系列でアニメ化され、後の実写映画のようにはヒットせずに終わってしまったことがあったが、あれも同時期のフジテレビの『まる子』大ヒットに触発され、昭和の子ども時代懐古アニメという伝で二匹目のドジョウ狙いが外れたものだったのだろうか。どうもこのあたりの時期のTBSは、「貧すれば鈍する」だったようだな)。
(※16)
まあ、たしかに私がかつて勤めたことのある個別指導塾でも、女子学生講師の中には、たまに一流とは呼ばれない大学の人もいたようだが・・・でも、そういう人は、やっぱり小学生の授業しかやらせてもらえてなかったみたいね。
(※17)
作者の自画像に、既に美化癖のバイアスがだいぶ見えるところはご愛嬌。