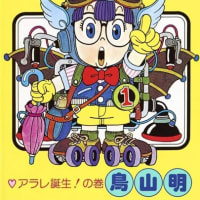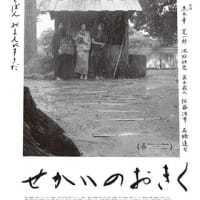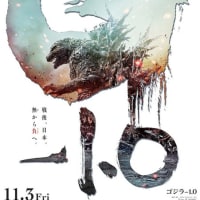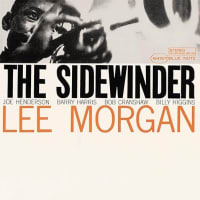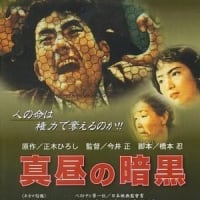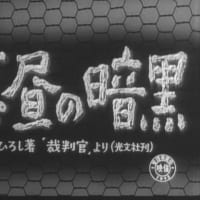『ララミー牧場』は、1959年から1963年にかけて、計4シーズン放映された米国のテレビ西部劇である(※1)。日本でもテレビ朝日系列で放映され、大人気を博したとのことである(※2)。
主人公は、両親亡き後に牧場を継いで自営しつつ、駅馬車中継所(※3)を兼業するスリム・シャーマン(※4)と、スリムの片腕として牧場を共に支える元流れ者の早撃ちガンマン、ジェス・ハーパー(※5)。この二人が全4シーズン通じての主役として、だいたい交互に一方が主役をやり、もう一方が脇にまわる(※6)。
また第1シリーズには、スリムの弟のアンディ少年(※7)と、先代以来の番頭格である家事まかない担当のジョンジー老人(※8)が、第3・第4シリーズには、ジョンジーに代わる家事まかない担当のデイジーおばさん(※9)とスリムの養子になった孤児のマイク少年がレギュラーで登場する(※10)。
なお、余談ながら、ウィキペディアやその他の文献に間違いが多いことを指摘せねばなるまい。たとえば、ウィキペディアの2018年9月現在の記述では、3シリーズの1話はマイク初登場編なのに、マイクが出ていないと書かれていたり。本来ならスリムが主役なのに、ジェスのほうが人気が出たためスリムからジェスに主役が交代した・・・というのも記憶錯誤。1シリーズの最初から二人は同格で、ほぼ交互に主役回があった。
これらの誤謬は、再放送がなかなかなく、日本はもとよりアメリカでも資料が少なかったせいかもしれない。たとえば、わが国では、社会現象を起こすほどのヒット作でありながら、70年代以降、再放送がなかった(※11)。
それが2017年頃から衛星劇場で流れるようになり、それが幾度もリピートされたおかげで、われわれ世代にとっても身近になった。また、収録話数は少ないながらも、当時の貴重な日本語吹き替え版を収めたDVDも出ている。
以下、自分の備忘メモとして書いておいた各話のあらすじや感想を掲載しておこう。
(※1)
原題は「牧場」のつかない『Laramie』で、これはワイオミング州の都市の名前。つまり舞台になる町の名前そのままである。日本の感覚でいうと『長野』とか『松本』とか『上田』とか『飯田』とかっていうドラマタイトルである。
そういえば、これは余談になるが、あの人気ロマンティックラブコメ『ノッティングヒルの恋人』(1999)も、原題はただの『Notting Hill』である。こちらは、ロンドンの高級住宅街にして同時にフリーマーケットが盛んな庶民的な街でもあるということだから、『三軒茶屋』みたいな感じのタイトルだろうか。
(※2)
『ララミー牧場』は、もともと淀川長治氏のテレビブレーク作であり、『日曜洋画劇場』(1966~2013)にレギュラーで出るようになったのは、『ララミー』が大ヒットし、テレ朝でVIP的存在になった流れからである。私はテレ朝の日曜洋画ムック『映画はブラウン館の指定席で/淀川長治と『日曜洋画』の20年』(1986)で、最初にこのドラマに興味を持った。
(※3)
長距離を走り続けると馬が疲れるので馬の交換をしつつ、乗客にもコーヒーなどを提供する、今日でいうなら給油と休憩のできるサービスエリア。ちょっと昔の言い方をすれば、ドライブイン。
(※4)
スリム・シャーマン役の俳優は、ジョン・スミスというまるでキョンの偽名のような簡単な名前である。
(※5)
ジェスのロバート・フラーは日本で大人気になり、来日時には空港にファンが殺到し大フィーバーになったという、言わば60年代のヨン様か。
(※6)
日本語吹き替え版ジェスの声は久松保夫。すなわち『スタートレック/宇宙大作戦』(1966~1969)のミスター・スポックの声の人である。劇場映画のほうでは、ヴィスコンティ映画の名優バート・ランカスターのフィックス(定番)声優として知られる。
いっぽうスリムの声は村瀬正彦。私の記憶に残るのは『ドラえもん/のび太の大魔境』(1983)に登場する王子(演ずるはアトムの清水マリ!)の愚直な従者役である。
(※7)
町の高等学校に行ったという設定で2シリーズ以降では消えるが、2シリーズに1回だけゲスト復帰の主役回がある。
日本語版の声はナタリー・ウッドの渋沢詩子だったらしいが、アンディの登場回はDVDに未収録のため、私は未聴である。残念。
(※8)
ジャズのスタンダードナンバー「スターダスト」、「ジョージア・オン・マイ・マインド」で有名な作曲家のホーギー・カーマイケルが、なぜか俳優としてレギュラー出演。日本でいうと小林亜星みたいなものか。
なお、日本語版の声は、『タイムボカン』シリーズ(1975~83)のグロッキー、ボヤッキー、トボッケーらや、『巨人の星』(1968~1971)の伴宙太、『もーれつア太郎』(1969~1970、1990)のココロのボスなどが有名な八奈見乗児(やなみじょうじ)だったそうだ。
(※9)
デイジーおばさんの役のスプリング・バイイントンという人は、『若草物語』(1933)、『我が家の楽園』(1938)といった戦前の名作で既に母親役をやっている実はキャリアの長い大女優である。が、上記の映画と『ララミー』のときとではかなり雰囲気が変わっているため、上記の映画を見ている人でも、おそらく言われなければ同じ女優だとは気づかないのではなかろうか。
(※10)
他にララミーの町のモート保安官(たぶん声は雨森雅司なのだ。それでいいのだ)と駅馬車馭者のモーズが準レギュラーとしてたびたび登場。
(※11)
たとえば、私の若い頃(80年代後半〜90年代前半)、深夜に『スパイ大作戦』(1966〜1973)や『ミステリーゾーン』(1959〜1964)が再放送されることがあっても、『ララミー』はなかった。
主人公は、両親亡き後に牧場を継いで自営しつつ、駅馬車中継所(※3)を兼業するスリム・シャーマン(※4)と、スリムの片腕として牧場を共に支える元流れ者の早撃ちガンマン、ジェス・ハーパー(※5)。この二人が全4シーズン通じての主役として、だいたい交互に一方が主役をやり、もう一方が脇にまわる(※6)。
また第1シリーズには、スリムの弟のアンディ少年(※7)と、先代以来の番頭格である家事まかない担当のジョンジー老人(※8)が、第3・第4シリーズには、ジョンジーに代わる家事まかない担当のデイジーおばさん(※9)とスリムの養子になった孤児のマイク少年がレギュラーで登場する(※10)。
なお、余談ながら、ウィキペディアやその他の文献に間違いが多いことを指摘せねばなるまい。たとえば、ウィキペディアの2018年9月現在の記述では、3シリーズの1話はマイク初登場編なのに、マイクが出ていないと書かれていたり。本来ならスリムが主役なのに、ジェスのほうが人気が出たためスリムからジェスに主役が交代した・・・というのも記憶錯誤。1シリーズの最初から二人は同格で、ほぼ交互に主役回があった。
これらの誤謬は、再放送がなかなかなく、日本はもとよりアメリカでも資料が少なかったせいかもしれない。たとえば、わが国では、社会現象を起こすほどのヒット作でありながら、70年代以降、再放送がなかった(※11)。
それが2017年頃から衛星劇場で流れるようになり、それが幾度もリピートされたおかげで、われわれ世代にとっても身近になった。また、収録話数は少ないながらも、当時の貴重な日本語吹き替え版を収めたDVDも出ている。
以下、自分の備忘メモとして書いておいた各話のあらすじや感想を掲載しておこう。
(※1)
原題は「牧場」のつかない『Laramie』で、これはワイオミング州の都市の名前。つまり舞台になる町の名前そのままである。日本の感覚でいうと『長野』とか『松本』とか『上田』とか『飯田』とかっていうドラマタイトルである。
そういえば、これは余談になるが、あの人気ロマンティックラブコメ『ノッティングヒルの恋人』(1999)も、原題はただの『Notting Hill』である。こちらは、ロンドンの高級住宅街にして同時にフリーマーケットが盛んな庶民的な街でもあるということだから、『三軒茶屋』みたいな感じのタイトルだろうか。
(※2)
『ララミー牧場』は、もともと淀川長治氏のテレビブレーク作であり、『日曜洋画劇場』(1966~2013)にレギュラーで出るようになったのは、『ララミー』が大ヒットし、テレ朝でVIP的存在になった流れからである。私はテレ朝の日曜洋画ムック『映画はブラウン館の指定席で/淀川長治と『日曜洋画』の20年』(1986)で、最初にこのドラマに興味を持った。
(※3)
長距離を走り続けると馬が疲れるので馬の交換をしつつ、乗客にもコーヒーなどを提供する、今日でいうなら給油と休憩のできるサービスエリア。ちょっと昔の言い方をすれば、ドライブイン。
(※4)
スリム・シャーマン役の俳優は、ジョン・スミスというまるでキョンの偽名のような簡単な名前である。
(※5)
ジェスのロバート・フラーは日本で大人気になり、来日時には空港にファンが殺到し大フィーバーになったという、言わば60年代のヨン様か。
(※6)
日本語吹き替え版ジェスの声は久松保夫。すなわち『スタートレック/宇宙大作戦』(1966~1969)のミスター・スポックの声の人である。劇場映画のほうでは、ヴィスコンティ映画の名優バート・ランカスターのフィックス(定番)声優として知られる。
いっぽうスリムの声は村瀬正彦。私の記憶に残るのは『ドラえもん/のび太の大魔境』(1983)に登場する王子(演ずるはアトムの清水マリ!)の愚直な従者役である。
(※7)
町の高等学校に行ったという設定で2シリーズ以降では消えるが、2シリーズに1回だけゲスト復帰の主役回がある。
日本語版の声はナタリー・ウッドの渋沢詩子だったらしいが、アンディの登場回はDVDに未収録のため、私は未聴である。残念。
(※8)
ジャズのスタンダードナンバー「スターダスト」、「ジョージア・オン・マイ・マインド」で有名な作曲家のホーギー・カーマイケルが、なぜか俳優としてレギュラー出演。日本でいうと小林亜星みたいなものか。
なお、日本語版の声は、『タイムボカン』シリーズ(1975~83)のグロッキー、ボヤッキー、トボッケーらや、『巨人の星』(1968~1971)の伴宙太、『もーれつア太郎』(1969~1970、1990)のココロのボスなどが有名な八奈見乗児(やなみじょうじ)だったそうだ。
(※9)
デイジーおばさんの役のスプリング・バイイントンという人は、『若草物語』(1933)、『我が家の楽園』(1938)といった戦前の名作で既に母親役をやっている実はキャリアの長い大女優である。が、上記の映画と『ララミー』のときとではかなり雰囲気が変わっているため、上記の映画を見ている人でも、おそらく言われなければ同じ女優だとは気づかないのではなかろうか。
(※10)
他にララミーの町のモート保安官(たぶん声は雨森雅司なのだ。それでいいのだ)と駅馬車馭者のモーズが準レギュラーとしてたびたび登場。
(※11)
たとえば、私の若い頃(80年代後半〜90年代前半)、深夜に『スパイ大作戦』(1966〜1973)や『ミステリーゾーン』(1959〜1964)が再放送されることがあっても、『ララミー』はなかった。