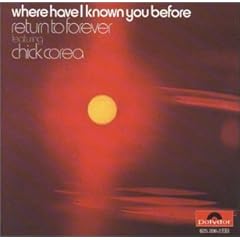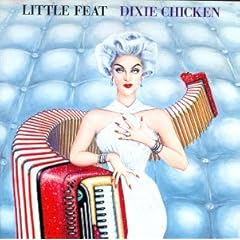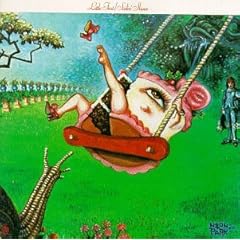短期集中連載のヘビーメタル三部作、いよいよ最終回です。
---
最初にBlue Oyster Cult(BOC)の名前を知ったのは、高一の頃。
同級生のT君がファンで、話をいろいろ聞かされていました。
でも、その時は、音は聞いていませんでした。
なにしろ、プログレに走っていて、それ以外のジャンルまで手が出せませんでしたから。
それから暫くしてFMから素晴らしい曲が流れてきました。
それがBOC「死神/(Don't Fear) The Reaper)」。
76年発売の「タロットの呪い」からの曲です。
当時、BOCのライブアルバムが発売されて、メンバー全員がギター持って演奏する、というME262が話題になりました。
それから、随分時が過ぎて、そうだ「死神」が聞きたい、と思ったのはCDの時代の初期の頃。
タワーレコードでBOCコーナーを見たけど、生憎オリジナルアルバムは置いて無くて、「死神」の入っているベスト版
( これだったか)
これだったか)
を購入。
ただ、残念なのはライブの演奏だったんです。
スタジオ版よりコーラスがちょっと粗っぽいのが残念。
オリジナルは74年発売の「Agents of Fortune / タロットの呪い」

1. This Ain't the Summer of Love
2. True Confessions
3. (Don't Fear) The Reaper
4. E.T.I. (Extra Terrestrial Intelligence)
5. Revenge of Vera Gemini
6. Sinful Love
7. Tattoo Vampire
8. Morning Final
9. Tenderloin
10. Debbie Denise
全体的にゴリゴリとしたハードロック(これがヘビーメタルなのかな?)。
この中で、やはり(Don't Fear) The Reaperは出色の出来ですね。
YouTubeの映像です
Don't Fear the Reaper live
前述のベスト版の中で「う!! これはすごい!!」と思ったのが「Hearvester of Eyes」と切れ目無く続く「Flaming Telepathy」。
いったいどのアルバムの曲だろうと、と探してみたら、冒頭のT君が進めていた「Secret Treaties/オカルト宣言」
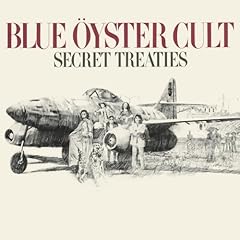
1. Career of Evil
2. Subhuman
3. Dominance and Submission
4. ME 262
5. Cagey Cretins
6. Harvester of Eyes
7. Flaming Telepaths
8. Astronomy
全体を通して聞いたのは今回が初めてですが、流れるようなアルバム構成は見事です。
先に述べた「ME 262」はLPでいうとA面の締めだったんですね。カッコいいです。
(ジャケットのジェット戦闘機がME262ですね)
他の曲もギターの流れるようなフレーズといい、ボーカルのハーモニーといい、「華」があります。
このアルバムは、何度も繰り返して聞いてしまいそうです(今も繰り返して聞いています)
「タロット」に「死神」という名曲がありましたが、このアルバムにもまけず劣らぬ名曲「Astronomy」があります。
Astronomy
[おまけ]
アマゾンでブルーオイスターカルトを調べたら、若き日のアーノルド・シュワちゃんのエクササイズCDが見つかりました。
いったいどの曲聞きながらエクササイズしたのでしょう。

----
にほんブログ村へ登録しました。
 ←この記事が気に入ったらクリックしてください
←この記事が気に入ったらクリックしてください
---
最初にBlue Oyster Cult(BOC)の名前を知ったのは、高一の頃。
同級生のT君がファンで、話をいろいろ聞かされていました。
でも、その時は、音は聞いていませんでした。
なにしろ、プログレに走っていて、それ以外のジャンルまで手が出せませんでしたから。
それから暫くしてFMから素晴らしい曲が流れてきました。
それがBOC「死神/(Don't Fear) The Reaper)」。
76年発売の「タロットの呪い」からの曲です。
当時、BOCのライブアルバムが発売されて、メンバー全員がギター持って演奏する、というME262が話題になりました。
それから、随分時が過ぎて、そうだ「死神」が聞きたい、と思ったのはCDの時代の初期の頃。
タワーレコードでBOCコーナーを見たけど、生憎オリジナルアルバムは置いて無くて、「死神」の入っているベスト版
(
 これだったか)
これだったか)を購入。
ただ、残念なのはライブの演奏だったんです。
スタジオ版よりコーラスがちょっと粗っぽいのが残念。
オリジナルは74年発売の「Agents of Fortune / タロットの呪い」

1. This Ain't the Summer of Love
2. True Confessions
3. (Don't Fear) The Reaper
4. E.T.I. (Extra Terrestrial Intelligence)
5. Revenge of Vera Gemini
6. Sinful Love
7. Tattoo Vampire
8. Morning Final
9. Tenderloin
10. Debbie Denise
全体的にゴリゴリとしたハードロック(これがヘビーメタルなのかな?)。
この中で、やはり(Don't Fear) The Reaperは出色の出来ですね。
YouTubeの映像です
Don't Fear the Reaper live
前述のベスト版の中で「う!! これはすごい!!」と思ったのが「Hearvester of Eyes」と切れ目無く続く「Flaming Telepathy」。
いったいどのアルバムの曲だろうと、と探してみたら、冒頭のT君が進めていた「Secret Treaties/オカルト宣言」
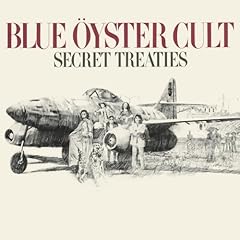
1. Career of Evil
2. Subhuman
3. Dominance and Submission
4. ME 262
5. Cagey Cretins
6. Harvester of Eyes
7. Flaming Telepaths
8. Astronomy
全体を通して聞いたのは今回が初めてですが、流れるようなアルバム構成は見事です。
先に述べた「ME 262」はLPでいうとA面の締めだったんですね。カッコいいです。
(ジャケットのジェット戦闘機がME262ですね)
他の曲もギターの流れるようなフレーズといい、ボーカルのハーモニーといい、「華」があります。
このアルバムは、何度も繰り返して聞いてしまいそうです(今も繰り返して聞いています)
「タロット」に「死神」という名曲がありましたが、このアルバムにもまけず劣らぬ名曲「Astronomy」があります。
Astronomy
[おまけ]
アマゾンでブルーオイスターカルトを調べたら、若き日のアーノルド・シュワちゃんのエクササイズCDが見つかりました。
いったいどの曲聞きながらエクササイズしたのでしょう。

----
にほんブログ村へ登録しました。