ブラックミュージックを5枚聞く企画の、第3回目はニューオリンズ特集。
ということで、豪華に2枚まとめて聞きました。
言わずもがなですが、ニューオリンズはルイジアナ州最大の都市。
古くは、18世紀フランス領ルイジアナの首府であった港町。
港町とはいえ、ミシシッピ川を140キロも遡ったところにあるそうで、そのあたりの距離感はさすがに大陸的ですね。
港町には、いろいろなものが集ってきます。
フランス領ルイジアナというだけあって、領主国フランスからの移民が、さらにフランス領になる前の領主国スペインの文化の上にフランス風の文化を上乗せし、アフリカからは大量の黒人が奴隷として連れてこられてアメリカ社会の中で故郷アフリカの魂をじわじわと浸透させ、カリブ海からヴードゥー教に代表される黒人文化が入り込む。
そういう風土から生まれたのがクレオール文化と呼ばれるアメリカ南部特有の文化だそうで、実はキッド・クレオール&ザ・ココナッツなんてのが流行っていた頃に初めてこの単語を知りました。
そういうクレオール文化の一端を担ったのが、アフリカからやって来た人たち。
軍隊から払い下げられた楽器を手に取り、毎週コンゴ・スクウェアというところに集って楽曲の披露をしていたそうで、それがニュー・オリンズ・ジャズの始まりと言われています。
そして、ここからミシシッピ川をシカゴまで遡って花開いたのが、シカゴ・ブルース。ですが、今回は、ニュー・オリンズのお話。
Southern Nights/Allen Toussaint
中島美嘉との共演でご存知の形も多い、かもしれません。
アラン・トゥーサンといえば、ニュー・オリンズ音楽を代表するようなプロデューサーであり、ミュージシャン。
ありとあらゆる、といっていいほどのミュージシャンのプロデュースを手がけています。
あの独特なピアノの音、そしてホーンセッション。
アラン・トゥーサンの作り出す音って、そんなイメージがあります。
「Southern Nights」は、1975年の作品。
LP時代のA面にあたる部分では、曲と曲の間にSEとしてサザンナイトの一部が挿入されています。
全体的な流れが「Southern Nights」に向けて集中するような作りになっているみたいです。
そして名曲「Southern Nights」。
アラン・トゥーサンていままで、ゲストプレーヤーとしてピアノ弾いてるところぐらいしか知らない、と思っていたのですが、この曲聞いたことありました。
アメリカ南部のちょっと蒸し暑いような夜の帳の向こうから、静かに流れてくるような印象的なイントロ。
ナイトパーティーの喧騒が、ふと静かになって、トゥーサンの歌声に引き込まれていくようです。
いつ、どこで聞いたのかも忘れていました。
でも、イントロを聴くなり「ああ、この曲がSouthern Nightsだったのか。」と記憶が蘇りました。
名曲には、時間の壁を軽々と飛び越えてしまう不思議な力があります。

[Southern Nights/Allen Toussaint]
1. Last Train
2. Worldwide
3. Back in Baby's Arms
4. Country John
5. Basic Lady
6. Southern Nights
7. You Will Not Lose
8. What Do You Want the Girl to Do?
9. When the Party's Over
10. Cruel Way to Go Down
Yellow Moon/The Nevil Brothers
もう一枚は、アラン・トゥーサンともかかわりのあるネビル・ブラザーズ
長兄Art Nevilleを中心とした、ファミリーバンド。
Yellow Moonは1989年に発表された7枚目のアルバム。
新聞かなにかで紹介されていて、このジャケットになにか惹かれるものがありました。
アラン・トゥーサンが比較的洗練された音作りだったのに対して、ネビル・ブラザーズは、黒人特有のグルーヴ感を押し出した力強い音作り。
ファンクというのではないけれど、なんだか大地にしっかりと根を下ろしたような安心感と、土臭さを感じます。
11曲目の「Healing Chant」なんて、うっかりと癒し系かと思って聞くと大変。
ヴードゥーの魔法にかかりそうです。
8曲目には、しっかりと「VooDoo」なんて曲もありますし。
一方6曲目の「With God on Our Side」では、アーロン・ネビルが。神に導かれ青い空をどこまでも上っていくかのような歌声を聴かせてくれます。
このアルバムはiPodに入れて毎日のように聞いていました。
意外、といっては失礼ですが、初めて聞いたにもかかわらず意外にツボにはまった一枚でした。

[Yellow Moon/The Nevil Brothers]
1. My Blood
2. Yellow Moon
3. Fire and Brimstone
4. Change Is Gonna Come
5. Sister Rosa
6. With God on Our Side
7. Wake Up
8. Voodoo
9. Ballad of Hollis Brown
10. Will the Circle Be Unbroken
11. Healing Chant
12. Wild Injuns
----
にほんブログ村へ登録しました。

ということで、豪華に2枚まとめて聞きました。
言わずもがなですが、ニューオリンズはルイジアナ州最大の都市。
古くは、18世紀フランス領ルイジアナの首府であった港町。
港町とはいえ、ミシシッピ川を140キロも遡ったところにあるそうで、そのあたりの距離感はさすがに大陸的ですね。
港町には、いろいろなものが集ってきます。
フランス領ルイジアナというだけあって、領主国フランスからの移民が、さらにフランス領になる前の領主国スペインの文化の上にフランス風の文化を上乗せし、アフリカからは大量の黒人が奴隷として連れてこられてアメリカ社会の中で故郷アフリカの魂をじわじわと浸透させ、カリブ海からヴードゥー教に代表される黒人文化が入り込む。
そういう風土から生まれたのがクレオール文化と呼ばれるアメリカ南部特有の文化だそうで、実はキッド・クレオール&ザ・ココナッツなんてのが流行っていた頃に初めてこの単語を知りました。
そういうクレオール文化の一端を担ったのが、アフリカからやって来た人たち。
軍隊から払い下げられた楽器を手に取り、毎週コンゴ・スクウェアというところに集って楽曲の披露をしていたそうで、それがニュー・オリンズ・ジャズの始まりと言われています。
そして、ここからミシシッピ川をシカゴまで遡って花開いたのが、シカゴ・ブルース。ですが、今回は、ニュー・オリンズのお話。
Southern Nights/Allen Toussaint
中島美嘉との共演でご存知の形も多い、かもしれません。
アラン・トゥーサンといえば、ニュー・オリンズ音楽を代表するようなプロデューサーであり、ミュージシャン。
ありとあらゆる、といっていいほどのミュージシャンのプロデュースを手がけています。
あの独特なピアノの音、そしてホーンセッション。
アラン・トゥーサンの作り出す音って、そんなイメージがあります。
「Southern Nights」は、1975年の作品。
LP時代のA面にあたる部分では、曲と曲の間にSEとしてサザンナイトの一部が挿入されています。
全体的な流れが「Southern Nights」に向けて集中するような作りになっているみたいです。
そして名曲「Southern Nights」。
アラン・トゥーサンていままで、ゲストプレーヤーとしてピアノ弾いてるところぐらいしか知らない、と思っていたのですが、この曲聞いたことありました。
アメリカ南部のちょっと蒸し暑いような夜の帳の向こうから、静かに流れてくるような印象的なイントロ。
ナイトパーティーの喧騒が、ふと静かになって、トゥーサンの歌声に引き込まれていくようです。
いつ、どこで聞いたのかも忘れていました。
でも、イントロを聴くなり「ああ、この曲がSouthern Nightsだったのか。」と記憶が蘇りました。
名曲には、時間の壁を軽々と飛び越えてしまう不思議な力があります。

[Southern Nights/Allen Toussaint]
1. Last Train
2. Worldwide
3. Back in Baby's Arms
4. Country John
5. Basic Lady
6. Southern Nights
7. You Will Not Lose
8. What Do You Want the Girl to Do?
9. When the Party's Over
10. Cruel Way to Go Down
Yellow Moon/The Nevil Brothers
もう一枚は、アラン・トゥーサンともかかわりのあるネビル・ブラザーズ
長兄Art Nevilleを中心とした、ファミリーバンド。
Yellow Moonは1989年に発表された7枚目のアルバム。
新聞かなにかで紹介されていて、このジャケットになにか惹かれるものがありました。
アラン・トゥーサンが比較的洗練された音作りだったのに対して、ネビル・ブラザーズは、黒人特有のグルーヴ感を押し出した力強い音作り。
ファンクというのではないけれど、なんだか大地にしっかりと根を下ろしたような安心感と、土臭さを感じます。
11曲目の「Healing Chant」なんて、うっかりと癒し系かと思って聞くと大変。
ヴードゥーの魔法にかかりそうです。
8曲目には、しっかりと「VooDoo」なんて曲もありますし。
一方6曲目の「With God on Our Side」では、アーロン・ネビルが。神に導かれ青い空をどこまでも上っていくかのような歌声を聴かせてくれます。
このアルバムはiPodに入れて毎日のように聞いていました。
意外、といっては失礼ですが、初めて聞いたにもかかわらず意外にツボにはまった一枚でした。

[Yellow Moon/The Nevil Brothers]
1. My Blood
2. Yellow Moon
3. Fire and Brimstone
4. Change Is Gonna Come
5. Sister Rosa
6. With God on Our Side
7. Wake Up
8. Voodoo
9. Ballad of Hollis Brown
10. Will the Circle Be Unbroken
11. Healing Chant
12. Wild Injuns
----
にほんブログ村へ登録しました。










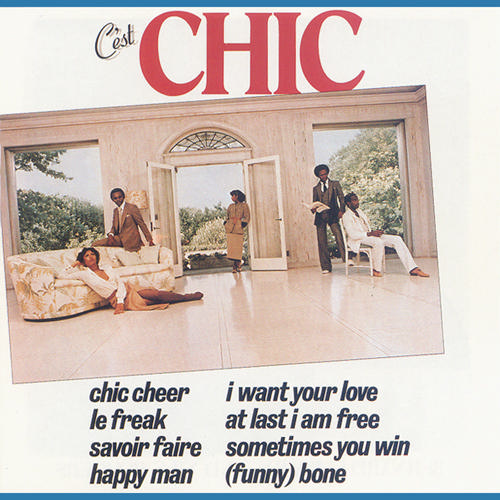









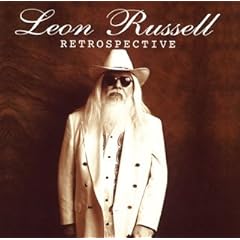
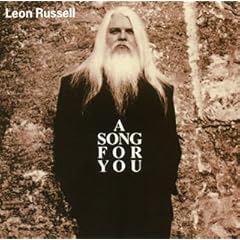

 のせいでしょぅか。。。
のせいでしょぅか。。。




