最近、落語ばっかり聴いている。もう、ようつべの動画はあらかた観た。(ちなみに「あらかた」ということは、1000を下らない数である) もちろん、落語の会にも足を運ぶ。ここ一年のカレンダーを見返してみたら、休日のほとんどが落語だった。お目当てがあるにしても、何人かの会や寄席の顔ぶれの中には、講談のほかに浪曲も入ることある。
あるとき、機会があり、玉川奈々福の独演会に行ってみた。気恥ずかしさを覚えつつ、合いの手の三味線の音に身を引き締めながら、奈々福のうなりに聴き惚れる。これが案外楽しい。期待以上の喜びがあった。
太福の会にも行った。一生懸命大汗かきながら、バカな話をまくし立てる。やばい、こっちも楽しい!さて、帰ってから思い返すと、ふたりのマクラの中でなにかと「広沢虎造」の名が出てきていた。畏れ多い高名のようなのだが、浪曲ニワカとしては馴染みがない。(この時点で相当失礼な話なのだが)
で、今度はようつべで「虎造」を聴きだすわけだ。当然、ようつべには未整理の音源がかなりあった。始めはこの濁声の良さがわからずに眉をひそめたのだったが、何席か聴いてしまうと、どっぷりとハマってしまった。次第に、BGMのように何時間でも聴きっぱなし状態に。曲師の弾く三味線が、ベベン、ッベン、ッベン、ベンベンベンベンベン~!!と煽り立て、よぅ~っ!ととびっきり調子のいい合いの手が入ると、それにあわせて虎造節がうなりを上げる。低いところからせり上げる節回しに、こっちも顎を前後左右に揺すりながら首をくゆらす。なんと浪曲とは、これほど気持ちがいいものか。遠い昔から身に沁み込んでいるソウルミュージックのようだ。
その中でひと際引き込まれたのが、やっぱり、清水の次郎長ものだった。
♪~ 春の旅、花たちばな駿河路行けば~、富士のお山は春霞ぃ~
ただ残念なことに、物語が途切れていてコンプリートされていないようなのだ。いやいや、ようつべ自体がそもそもタダなので文句は言ってはいけない。
で、密林でCDを探してみたが、どうやらようつべに上がっているタイトルしか見当たらなかった。どうも、浪曲では次郎長の一生を全部追っかけてるわけではないようだ。CDの購入は諦めたものの、代わりにこんな本を見つけた。
 |
ご存知!清水次郎長伝 |
| 広沢 虎造 | |
| ベストセラーズ |
村上豊の挿絵、縞の合羽に三度笠、旅姿の次郎長が表紙。「秋葉の火祭り」からはじまって「追分宿の仇討ち」まで、虎造『次郎長伝』を抜き書きした速記本だ。あの名前はこういう字を書くのかと、おさらいするにはちょうどいい。オマケ程度に、付録にダイジェスト版のCDが付いている。
はてさて、こうも気持ちよくハマってしまうと、一通り、次郎長の物語をなぞってみたくなった。そこで目を付けたのが小説だ。この村上元三『次郎長三国志』を読みだしたのはそんな次第。
 |
次郎長三国志(上) (角川文庫) |
| 村上 元三 | |
| 角川グループパブリッシング |
 |
次郎長三国志(下) (角川文庫) |
| 村上 元三 | |
| KADOKAWA / 角川書店 |
これが、めちゃくちゃ面白い。一話一話、ひとりずつ順に出てくる登場人物をクローズアップした筋書きで、最後に、次の話のサワリに触れて締める。まるで連続ものの最後に、「ちょうどぉ、時間となりました~」とでも言っているかのように話を切り、うまく次に引っ張るところはニクイ。
さてこの話のスジ。まず初めに、桶屋の鬼吉と関東綱五郎の二人が次郎長の子分になるところから始まる。つぎに、次郎長一家の番頭格の大政があらわれる。一家を構えた当初からのブレーンとして頭脳明晰な軍師であり、時に次郎長の名代ともなり、事があれば一騎当千の武者である大政という人物がいてこそ、のちに清水一家という海道一の大看板ができるのである。ただ浪曲と比べると、子分の顔ぶれがずいぶんと違うし、キャラも色あいが異なっていた。特に勝手が違ったのは、石松だった。石松の登場は、あんがい遅い。しかも片眼でもなければ、しゃべりがおぼつかないドモリになっていた。どうやら、石松のキャラとして世間で認知されている、片目でおっちょこちょいの無鉄砲な性格は、浪曲風に創作されたものだった。あの愛嬌たっぷりの愛されキャラは、実在した豚松という子分のキャラを混ぜたものらしい。しかも、石松の最後の描写も、浪曲ほどの悔しい死に様ではなかった。浪曲の石松と言えば「江戸っ子だってね、寿司食いねえ」の台詞で有名な金毘羅代参の帰りの三十石船でのやりとりが見せ場なのだが、これもない。だいたい、船の上で、次郎長の子分で腕っぷしが強い奴は誰だと順に聞くにしても、はじめの方で名前が出てくる小政はこの時点ではまだ次郎長の子分ではなかった。当の小政は、石松と入れ違いのタイミングで次郎長の盃を受けるのだ。その小政、愛想なしで可愛げがないが、喧嘩はめっぽう強い。剣を持てば得意の居合の技が冷徹なほどに切れがよく、惚れ惚れした。
ところどころ、話のスジは浪曲で聴いていたものとは描写が違っていて、やや面食らうところはある。宿敵、黒駒の勝蔵との闘争も浪曲ほど派手でない。だけども、まあ読んでいて面白いからどうでよかった。クライマックスはもちろん荒神山の喧嘩、大政が鬼神のごとき働きを見せるのが気持ちよい。吉良の仁吉と法印大五郎の犠牲があったものの、この喧嘩こそが、東海道に次郎長一家あり!を見せつける一戦であった。
さてさて物語は、その後の次郎長一家の活躍をどう派手に描くのか・・・と思いきや、最終章ではまるで後日談のような書き方になっていて、冷めたものだった。調子っぱずれな印象がつよく、まるで代演で出てきた辛気臭い講釈師が、最後を淡々と語って幕引きをしてしまったようだった。そう、まるで徳川の世が終焉してのご一新ののち、明治の新しい世の中で鳴りを潜めて、派手な喧嘩はできなくなった寂しさを真似るように。じゃあ次郎長は時代に取り残されて老いぼれるしかなかったのか?と言えばさにあらず、富士山裾の開墾事業に精をだす、地元の篤志家となっていた。明治という新しい世の中になり、博徒は、徳川時代に腰に差してた長脇差という牙を取り上げられたのだが、次郎長はそんな子分たちの持て余したエネルギーを、茶畑の開墾へと注ぎ込んだ。足りぬ手は、なんと囚人を使った。縄を解いて作業の自由を得た囚人たちは、逃げようともせず熱心に鍬を握って汗を流してたという。地元の評判も良かったらしい。次郎長の人柄が、そんなところにも影響しているような気がして胸が熱くなる。
明治になってからの次郎長といえば、山岡鉄舟を抜きには語れるものではない。そもそもこの物語を読むにあたり、僕の興味もそこだった。さんざん暴れまわって役人さえも手を焼いた次郎長を心服させた鉄舟との、そのエピソードを知りたかった。ところが、その描写はあんがいあっさりとしたものだった。そこは物足りない。
次郎長の養子となった天田愚庵(五郎)のいきさつも出てくる。もともとこの愚庵が、次郎長一家の顛末を『東海遊侠伝』という本にまとめたからこそ、後世にまで活躍のあれこれが伝えられたわけだった。この『次郎長三国志』も、その大筋きをなぞったものらしい。この小説の内容こそが実物の次郎長伝に近いのだな。
とはいっても、やはり観衆をぐっと聴き込ませる浪曲の面白さはこっちはこっちで別格のものではあるが。
満足度7★★★★★★★
なお、もうひとつ、次郎長一家を描いた小説に、津本陽『修羅海道ー清水次郎長伝』がある。
物語は、幼少期の描写から始まる。のち、旅の僧に「あと三年の命」と告げられて、繁昌していた米屋をたたみ、博打打の世界へと身を投げる。実父三右衛門がよく絡んでくるし、吉良の武一のもとで厄介になっているくだりもある。『次郎長三国志』では割愛されていた話だ。次郎長の連れは、熊五郎。これも出てこない名。まあそんなことはいいとしても、なんだかどうも、読んでいても面白い気分が湧いてこない。途中で読むのをやめ、あいだをすっ飛ばして、荒神山の喧嘩から読み直してはみたが、その後の明治になってからの次郎長のエピソードの数々さえも、あまり面白くはなかった。
たぶんこの作家と僕があわないのだろう。
評価なし、ということで。
 |
修羅海道―清水次郎長伝〈上〉 (角川文庫) |
| 津本 陽 | |
| 角川書店 |
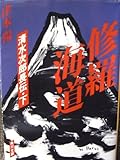 |
修羅海道―清水次郎長伝〈下〉 (角川文庫) |
| 津本 陽 | |
| 角川書店 |
ここで、いったん「次郎長伝」の成り立ちを簡単におさらしてみる。
そもそも、いまでは浪曲の演目として有名な「次郎長伝」は、もともと講談でその名を博した物語だった。元をたどれば、実際の次郎長一家の喧嘩にも参加した講釈師・松廼家太琉がその見聞をまとめたものだ。ただ残念ながら、太琉は講談として演じるまでに仕上げることができなかった。それを現在のような形に作り上げたのが、三代目神田伯山だった。
伯山は、太琉の作ったものと、愚庵が子分から聞き込んでまとめ上げたオーラルヒストリー、『東海遊侠伝』をもとに、さらに自らの聞き取りも付けたし、派手なラメの入ったきらびやかな脚色を施して、魅力たっぷりの次郎長一家を作り上げた。
その伯山、この「次郎長伝」が大当たりして、八丁荒らしと呼ばれるほどの人気を博した。ある時、楽屋に「石松の息子」を名乗る男がやってきて、俺の親父でさんざん稼いでおいて許さねえから金をだせ、と凄んだことがあったらしい。
なにが息子なことか、もとより石松の造詣はほぼ架空のものであるうえに、そもそも石松は妻帯していない。間の抜けた強請り野郎がいたものだ。ところが、そんな男に財布ごとくれてやって帰した伯山。いぶかしんだ弟子に理由を聞かれ、「俺の講談が人を一人産んだんだ、うれしいじゃないか」と笑ったという。そんな逸話が残るほど、「次郎長伝」はウケたのだ。
これを浪曲でやろうとしたのが、再三名前をだしている浪曲師広沢虎造(二代目)だったのだ。しかし、明治になって興った浪曲という新しい芸能を、当時の講談師は見下していたようで、「次郎長伝」を口演する虎造を伯山は快く思っていなかったらしいが。さて「次郎長伝」に目を付けた虎造、自分らしい手を加えようと、石松には、講談にはない笑いの要素を入れた。「寿司食いねえ」「江戸っ子だってねえ」や「馬鹿は死ななきゃ治らない」の名文句は、ここで生まれた。実在の人物とはまるで違ってはいても、粗暴で無鉄砲でありながら愛嬌ものの石松がここで登場してきたからこそ、次郎長ものの人気はさらに不動となったのであろう。だいたい、実在かどうかなんて、世間は頓着していなかったと思うのだ。大衆意識とすれば、真田十勇士にしたって、鞍馬天狗にしたって、過去の人物にきれいな装飾をして、望まれるヒーローでありさえすればよかったのだろうから。
石松を挙げたので大政について。
教養があり、度胸もあり、腕っぷしも強い。なんといっても、元尾張藩士で槍の名手。侍が嫌になって博徒の世界に身を投げた。しかし、実際は違うらしい。どうも現在の常滑あたりの回船問屋の長男だったらしい。武士の身分を捨てたと言った方が、覚悟を背負っているように見えるのだろう。『次郎長三国志』では、名古屋に残してきた別れた妻が、大政を慕って清水までやってきたりしたが、大政くらいの大物ならば、そのくらいのロマンスがなくちゃ分が悪いというものだ。
小政には、講談と落語に「小政の生い立ち」という演目がある。落語では、喬太郎がたまにかけるネタだ。次郎長一行が金毘羅詣りの帰り道に立ち寄った浜松の道端で、まだ年端の行かない子供時代の小政に出会う。生意気でませたガキで、次郎長本人と知るや子分にしてくれるように頼む。ついでながら石松のことは見くびって軽くからかう。当然、作り話。子分として新参の小政でありながら、その心意気は幼き頃よりの筋金入り、とでも作り上げたい作者の意図が見える。幼少のころから次郎長のもとにいた小政は、まさに子飼いの子分だ。しかし、人付き合いの下手な小政の性格もあって、どうも他の連中とは仲が良いわけではなかったらしい。明治になってからは、次郎長のもとから独立していたようだ。善人になっていく次郎長が、我慢できなかったのだろうか。
ここまでくると、作り物ではなく、もっと実態を知りたくなってきた。やはり、『次郎長三国志』の中の次郎長と子分たちを、わずかながら信じ切れていない気持ちがある。好きとか嫌いとかじゃなくて、実態はどうだったのか?という疑問。ほんとうに普段から質素に木綿の着物しか着なかったのか、あれだけの立ち回りを潜り抜けるほど強かったのか、なぜ人が変わったかのように地域振興に心血を注いだのか、等々。
そこでまずこの本。高橋敏『清水次郎長 ―幕末維新と博徒の世界』
聞き取り話や、ましてや創作とは無縁の、しっかりと時代背景や地域経済の観点から次郎長の生きざまを照らし出している。
 |
清水次郎長――幕末維新と博徒の世界 (岩波新書) |
| 高橋 敏 | |
| 岩波書店 |
次郎長の地元清水の港は、江戸時代、駿府の外港として栄えた港町だった。ここには、甲州信州から江戸に届けられる年貢米が、富士川を下って運ばれてきた。また反対に、「甲州行塩」が川を上っていった。そのほか様々な物資の中継港として清水港は発展していった。運搬を担うのは主に人足で、気も強い荒くれもの、それを束ねる方も当然柔ではない。そう、その束ねた人物こそが次郎長だったという。世間とは一線を置いた渡世人の住人かと思いきや、そうでもなかったようだ。
なお、江戸末期文久元年(1861)の清水港の職業構成を示す数字が紹介されている。総戸数697戸。うち港湾流通関連は360戸、じつに全体の52%をしめていた。ちなみにそのほかは、漁師157戸、魚渡世100戸、その他生活関連(大工や鍛冶屋やら)80戸であった。360戸の港湾関連のうち、荷揚げ人足は200戸もあったようだ。つまり、清水港で暮らす人々の半分以上は港で働き、そのまた半分以上は荷揚げ荷下ろしに従事する労働者というわけだ。次郎長は、その商人側であり、労働者を束ねる側であった。たとえば江戸の町でいえば、祭りごとから揉めごことまで諸事一切を任せられた火消し人足の親方と同じなのだろう。
ここで気付く。そうか、次郎長と仇敵・甲州黒駒の勝蔵は、富士川舟運の利権を巡って対立していたのだ。だいたい海側と山側の隣同士が仲がいいわけがない。現在だって、静岡と山梨双方が言い張る、富士山の正面がどっちかの論争も、もともとお互いに対する悪感情が根っこにあるんじゃないか、とさえ思えてきた。
ときに。訳あって人殺しまでする次郎長たちのこと、ほとぼりが冷めるまでしばらく清水を離れることがしばしばあった。清水を去るにしても、東は探索の厳しい江戸に近くなるので、自然と足は西へ向かう。そんな次郎長は、よく寺津(現在の愛知県西尾市)の間之助のところに腰を落ち着かせたのだが、これにもわけがある。寺津のあった三河の国は、尾張徳川家が支配したお隣の尾張の国とちがい、細切れ状態に分割されていた。ここがミソだ。三河一国に7~11藩が並立していて、おまけに頻繁に領主が替わる。たとえば、吉田藩(7万石)10回、西尾藩(6万石)9回、刈谷藩(2万3千石)9回。どうみても多すぎる。これでは地元を把握する前にまた次の知行地へと鞍替えとなり、また次の殿様も把握する前に、、、の繰り返しとなる。くわえて、他藩の飛び地、幕府直轄領、60余の旗本知行地が入れ組み状態でからみ合う。
ただ、こうした幕府の政策は当然であった。有事の際、西に陣取る外様大名の行軍の妨げにせんが為であったことが明白なのだ。(残念ながら幕末のとき、その期待は水泡となるが) ひっきょう、ここにやってくる大名は譜代が多くなるのだが、たいていが幕府の要職についているため、領内支配はおろそかになる。そうやって放置された弊害は、次第に警察力の弱体化に帰結することとなる。つまり、取り締まりが緩いことをいいことに、博徒が悠々と幅を利かす土地柄というわけなのだ。またここは伊那街道の終着地なので、陸路、海路の拠点として、各地の物産の流通拠点となっていた。ここから東は江戸、西は上方・瀬戸内へと物資が行き来する。そう、寺津も清水の港と同じ経済構造なのだ。なるほど、次郎長の勢力背景や活動地域の訳が読めてきた。
また、黒駒の勝蔵の人となりの記述も興味深い。
勝蔵は、旧知の檜峯神社の神主・武藤外記の感化もあって尊王攘夷の思想を持っていたという。おまけに、親分である竹居の安五郎(どもやす)が牢死したこともあり、反幕の意識が強かった。対して、幕末には役人と一緒に勝蔵を捕まえようとしていた次郎長。討幕派の勝蔵と佐幕派の次郎長という対比。たいてい力の弱い支配者は、手配書の廻ったお尋ね者を逮捕するにあたり、土地の有力者に十手を預けるのだが、これが博徒が博徒を追いかける図式となるのだから皮肉なもの。ただ、明治まで逃げ延びて公卿の家臣として身を隠した勝蔵だったのに、のちにかつての罪状で捕縛され刑死する末路をたどるのは因果応報であろう。
この本のなかで、高橋氏は釘を刺している。愚庵の『東海任侠伝』がいかに任侠の美談にして語ろうが、事実は、血で血を洗う凄惨で残酷な道程となった次郎長立身の足跡なのだ、と。そうなのだ。次郎長の活躍がいくら威勢がよくたって、ヤクザ同士の抗争であることには、かわりはない。
さて。
ずいぶんと自分の中で次郎長像と言うものが出来上がってきた。もう少し、違う視点で次郎長を評価したものはないか、と欲が出る。いいものが見つかった。黒鉄ヒロシ『清水の次郎長』(上下巻)だ。
 |
清水の次郎長〈上〉 (PHP文庫) |
| 黒鉄 ヒロシ | |
| PHP研究所 |
 |
清水の次郎長〈下〉 (PHP文庫) |
| 黒鉄 ヒロシ | |
| PHP研究所 |
黒鉄は、彼の地元で礼賛ずくしの英雄坂本龍馬でさえ、容赦なく断罪する人だ。彼の眼にはどのように映っているのだろう?と興味津々。(以下、再度同じことがらに触れることもありますのでご容赦)
幼少期の次郎長の、底意地の性悪なことありゃしない。
読み知った話であっても、漫画付きで紹介されると、その意地の悪い目付きが、凶悪性を持った手の付けられないヤクザものとしか見れない。黒鉄は言う。<次郎長にはヒトとしての「ナニカ」が欠落している>と。つまらないジョークをちょいちょい入れてくるのには閉口するが、次郎長の性根を鋭く暴く。あたかも化けの皮をむしるような意地悪さで。
明治になって博徒取締の法により投獄された次郎長。次郎長の養子天田愚庵(山本五郎)の書いた次郎長自伝『東海遊侠伝』は、次郎長の減刑運動の一環だという。石松の脚色はすでに理解していたが、そもそも当の『東海遊侠伝』には、石松の記述はわずかしかないらしい。講談として面白くしようと神田伯山が石松を片目と創作し、浪曲の広沢虎造が性格を無鉄砲でちょっと短慮にし、小説で村上元三がドモリにした。たしかに黒鉄ヒロシが言うように、そんな危なっかしい奴を、次郎長が自分の代参で遠く四国の金毘羅さんまで遣わすのか?って思うのは当然なのだ。むしろ、喧嘩が強いのはそのままとしても、道中での同業者への仁義や挨拶を含めて判断力を要する大役を任せられるくらいの人物であったはずだと思う。
大政の前身にも諸説あり、小政の死に方にも諸説ある。むしろボヤけているのが当然なのかもしれない。「商売往来」に載っていない彼らアウトローなのだから、口伝てで伝わるうちにどうとでも変わる。そこがオーラルヒストリーの弱点でもある。
また宿縁の敵役、黒駒の勝蔵についても、黒鉄は疑う。<『東海遊侠伝』に書かれた程に、勝蔵は凶悪な性格であったろうか。仮にも親分と呼ばれる男である。相応な器量がなければ、その立場にはなれないと思うのだが。>講談「荒神山の血煙」の場面で出てくる吉良の仁吉も、神戸の長吉も、穴太徳も、どうやら性格や行動に手を加えられていた。ただ、読み物として考えれば、この辺はそれでいいと思う。ようは、いかに次郎長をカッコよく引き立てられるか、が肝なのだから。
明治元年(1868)に清水港で起きた咸臨丸事件にからんだ疑惑も書いている。次郎長は「死ねば仏だ。仏に官軍も賊軍もあるものか」と、海に投げ捨てられたままだった旧幕軍乗組員の屍体を収拾した。まさに次郎長の侠気あふれるエピソードであり、それがのちの鉄舟との知遇のきっかけであるというのが定説だ。しかし、二人はおそらくその前年にすでに会っている。しかも、それはただ会っただけじゃない。将軍慶喜の側近であった鉄舟は、江戸入り前の官軍の大将として駿府に滞在していた西郷と面会しよう試みていた。そんな、近づくことさえもできずに難渋していた鉄舟を、警護しながら駿府まで送り届けたのは次郎長なのだ。実際、これは地元の古老の話として残っている。となれば、咸臨丸事件の時点では二人は旧知であったわけで、むしろ、駿河湾に放置されたままだった屍体の収拾は、次郎長の侠気を煽った鉄舟の指示だったのではないか、と疑っている。黒鉄は、次郎長もうまくそれを利用した節があるとまで言う。のちに収拾した7人の埋葬地を掘り起こしたところ、人数以上の人骨が出てきたらしいのだ。それは、石松の仇敵・吉兵衛たちを討ち果たした後に、彼らの死骸を埋めた場所ではないか?、「死体は死体の下に隠せ」というミステリーがあったよね、と謎解きをしている。黒鉄はこの漫画で、義侠心あふれる「強きを挫き弱気を扶く」任侠世界のヒーローの正体を、容赦なく暴いてしまった、という印象だ。
晩年の、地域の産業を盛り立てようとする事業者、英語の普及に勤めた理解者、近所の子供たちに対する好好爺等々、まるで心を入れ替えたかのような善人としての評価がのこる次郎長。裏腹に、武士階級の支配力が著しく弱まった幕末に、身分制度の綻びからはみ出したアウトローたちを纏め上げ、利権がらみで闇社会を支配、武装化し、勢力争いを繰り返しながらネットワークを広げ、その過程で多くの喧嘩や出入りで何人もの命を奪ってきたのもまぎれもなく次郎長である。
明治の新しい時代に生き残った次郎長に、地べたから這い出てきた亡霊が言う。<トーナメント戦というやつは、必ず頂点ができる、それがオメエだったというだけの話だよォ>と。のちに鉄舟と知遇を得ていたことも大きかったろうが、黒駒勝蔵のように斬首にされてもおかしくなかった立場だったのだ。
さっきの亡霊が続ける。<テメエの身の廻りを見渡してみやがれ、同類の死臭がぷんぷんと匂っていやがるだろうが>
なにを真っ正直な堅気の顔していやがるんだ、お前だってさんざん人を殺してきただろうに、と言わんばかりに。晩年の善人の顔は、そんな亡霊たちを追い払う言い訳なのだとすれば、精力的であったのも頷ける気がしてきた。
次郎長は、雨の中の農作業がたたって高熱を発し、40余日も寝込んだ末に畳の上で死んだ。享年74歳。博徒の大親分としては幸せな場所での大往生だった。喧嘩で命を落とすともなく、大政や小政よりも長生きした。死に接して不満などなかっただろうなあ。利と、義と、情の絶妙なバランス感覚を持ち合わせた次郎長は、アウトローとしては珍しく、成功者として死んでいった。
最後に、ついでながら。
次郎長ものの読み物は、現在、それを下敷きに大きく形をゆがめて、動物の世界に姿を変えたものがある。それが、現代落語の新作を作らせたら随一、三遊亭白鳥「任侠 流れの豚次伝(全十話)」の連続ものだ。でてくるのは豚の豚次、鶏のチャボ子、牛の牛太郎、象のマサオ、パンダのパン太郎、虎の虎夫、、、たまに人間。潰れかけの動物園の立て直しに豚次が奔走する、第三話「任侠流山動物園」はつとに有名で、柳家喬太郎、春風亭一之輔、柳家三三ほか、多くの噺の名手が高座でかけている。
 |
池袋演芸場十日間連続 創作落語「任侠 流れの豚次伝 全十話」 |
| 三遊亭白鳥 | |
| 三遊亭白鳥 |
第一話 豚次誕生秩父でブー!
第二話 上野掛け取り動物園
第三話 流山の決闘(任侠流山動物園)
第四話 雨のベルサイユ
第五話 天王寺代官切り
第六話 男旅牛太郎
第七話 悲恋かみなり山
第八話 チャボ子絶唱
第九話 人生鳴門劇場
第十話 金毘羅ワンニャン獣の花
全十話で五千円。生で聴くには及ばないものの、10日通うと思えば安いもの。しっかりオチも用意されてます。
もちろん浪曲でも、玉川大福が演る。客が呆れて帰らないかを気にしながらの一席は、違う可笑しみもあいまって抱腹。
こちらも是非機会があれば。
 |
DVD>新世紀浪曲大全玉川太福 () |
| 玉川太福,玉川みね子 | |
| クエスト |
ブログからでも購入できるようですよ。→http://tamagawadaifuku.sakura.ne.jp/?p=1329 「国本武治物語」も必聴です!
※以上、敬称略ご容赦ください。
また、ニワカゆえに言葉や言い回しが間違っているかもしれませんが、粗忽者よとご笑納ください。










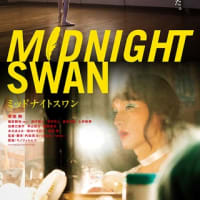

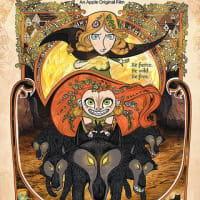





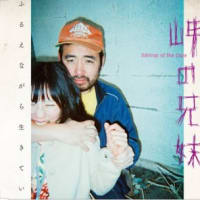
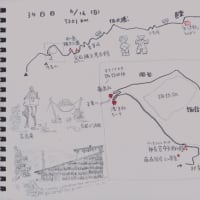
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます