村上龍さんの「最後の家族」を読みました。
2001年に書かれた本で、テレビドラマ化されたこともあるそうですが
残念ながらその記憶はありません。
~この小説は、救う・救われるという人間関係を疑うところから出発している。
誰かを救うことで自分も救われる、というような常識がこの社会に蔓延しているが、
その弊害は大きい。そういった考え方は自立を阻害する場合がある~
帯に書かれた著者の言葉に惹かれて、古本屋さんで購入しました。
あらすじはこうです。
大学デビュー(こんな言葉が出現したのは一体いつなのでしょうか・・)に失敗し
自宅に引きこもった秀樹。
会社をリストラされそうな父親の秀吉。
長男の引きこもりに悩みながらも、家族会やカウンセリングに通う専業主婦の昭子。
大学受験を前に自分の道を模索する知美。
一見平凡に見える四人家族ですが、それぞれに悩み迷って生きています。
ある日隣家の主婦が夫の暴力に合う場面を偶然秀樹が目撃し、
その主婦をDV被害から救い出そうと奔走することを軸に物語は進みます。
秀樹は主婦を救おうと様々に手段を考え、また実行もするのですが
結局は救い出すことは叶いません。
最後に秀樹が法的手段を講じるために訪れた法律事務所で、彼は女性弁護士から
こう言われます。
「DVは救うとか救われる、といったことでは解決しないんです。
他人の指示ではなく、自分は家を出るのだという自覚が必要なのです。
また、主婦を救いたいというのはDVの第一歩なんです。
救いたいという思いは、案外簡単に暴力につながります。
彼女は可愛そうな人だ。だからぼくは救わなければならない。ぼくがいなければ彼女は生きていけない。
そういう風に思うのは、他人を支配したいという欲求があるからなんです。
そういう欲求が、ぼくがいなければ生きていけないくせに、あの態度はなんだ、と言う風に変わるのは
時間の問題なんですよ。
他人を救いたいという欲求と、支配したいと言う欲求は、実は同じです。
そうしてそういう欲求を持つ人は、その人自身も深く傷ついている場合が多いんです。」
そして、弁護士から誰かに救われたことがあるでしょう、と尋ねられた秀樹は
母親に救われたと答えます。
弁護士は、母親が自立したことが結局は秀樹を救ったことを指摘し
秀樹は一人で生きていけるようになること、を自覚し新たな道を歩みだすのです。
私の息子も大学デビューに失敗しました。
今では明るくその当時の自分を振り返って、彼なりの分析でその原因を話してくれたりしますが
ここに至るまでの道のりは暗く長く厳しいものでした。
パチンコ三昧になり何度も道を踏み外し、そのたびに私は東奔西走し
お金も随分使いました。
私の行動は、この物語で秀樹がDV被害者の主婦を救い出そうと必死になる姿と
全く同じです。
本人に何の自覚もないのに、私だけが救い出そうとあれこれ考え行動し
彼の回りをグルグルと騒ぎ続けていました。
私の息子を救いたいというのは、本の中の弁護士が言うとおり
支配したいという欲求だったと今ならわかります。
私の行動もまた、暴力だったのです。
そして支配したい私もまた、深く傷ついていました。
それでも秀樹が救いたいという無駄な行動の中で弁護士にたどり着いたように
私もまた、息子を救いたいとアンテナを張る中で今のカウンセラーにたどり着きました。
それは、本の中の母・昭子とダブります。
昭子が家族会やカウンセリングによって自分の生き方を考えるようになったように
私もまた、カウンセラーと出会うことによって自分の中に蓋をして隠していた感情をみつめ
考えるようになりました。
自分をみつめる中で、家族の関係も徐々に明るくクリアで暖かいものに
自然と変わってきたように感じています。
最近では、息子との関係もずっと風通しのよいものになりました。
お互いの気持ちを隠すことなく主張できるようになり、
その結果今までのような、言わないけれどわかってよね、と言った陰険な雰囲気は
全くなくなりました。
干渉しない、というニュアンスともまた、違うと感じます。
相手を大切に思うと、自然と相手を信用できる、という感覚でしょうか。
私の場合、いつまでも子どもを未熟な存在、自分よりも劣っている存在(酷い言い方ですが)
と何処かで思っていたのかもしれません。
私が親からそう思われていたように。
未熟でダメなヤツだから教えてやらなければならない、
といつも上から話しをしていたのでしょう。
今の息子はいわゆるニートです。
世間の常識からみれば、甘えた立場ですし何を考えてんだっ!と言いたくなるでしょう。
でも、私も最近わかるようになりました。
決して息子も、今の状態でいいとは思っていません。苦しく思っているし、焦ってもいます。
自分に果たして何ができるのか、不安で押しつぶされそうになっています。
本人がわかっているのですから、私からそれ以上言うことは何もありません。
私が代わりに生きる訳でもなく、お願いして生きてもらっているのでもありません。
彼が彼なりに納得して、生き方の答えを自分で見つければいい、
そう考えていますし、きっといつかそうなるでしょう。
いろんな風に人は生きていけるし、生きる実感をもてればそれでOKだと。
本の中の四人家族は結局、バラバラになって生きていきます。
秀吉はリストラされ、ローンが支払えなくなった家を売却し故郷へ一人帰ります。
そこで新しい人生を探すのです。
昭子は家族会での仕事をすることになり、以前から付き合っていた年下のボーイフレンド
(この点は羨ましくもあり、また現実はこうはいかない・・・と思いました)との新しい関係が始まります。
知美は大学ではなくイタリアへ旅立ち、そこで自分の道を探し始めます。
秀樹は弁護士を訪ねたことをきっかけに司法試験を目指すスクールに通うことになりました。
バラバラになることは一見崩壊のようにみえますが
全く違いますね。
一人で生きられるようになること、それが家族にとっても大切なことなんでしょう。
どの家族にもあてはまる話しだとは思いません。
でも私にとっては、とてもすんなりと実感をもって納得できた小説でした。
2001年に書かれた本で、テレビドラマ化されたこともあるそうですが
残念ながらその記憶はありません。
~この小説は、救う・救われるという人間関係を疑うところから出発している。
誰かを救うことで自分も救われる、というような常識がこの社会に蔓延しているが、
その弊害は大きい。そういった考え方は自立を阻害する場合がある~
帯に書かれた著者の言葉に惹かれて、古本屋さんで購入しました。
あらすじはこうです。
大学デビュー(こんな言葉が出現したのは一体いつなのでしょうか・・)に失敗し
自宅に引きこもった秀樹。
会社をリストラされそうな父親の秀吉。
長男の引きこもりに悩みながらも、家族会やカウンセリングに通う専業主婦の昭子。
大学受験を前に自分の道を模索する知美。
一見平凡に見える四人家族ですが、それぞれに悩み迷って生きています。
ある日隣家の主婦が夫の暴力に合う場面を偶然秀樹が目撃し、
その主婦をDV被害から救い出そうと奔走することを軸に物語は進みます。
秀樹は主婦を救おうと様々に手段を考え、また実行もするのですが
結局は救い出すことは叶いません。
最後に秀樹が法的手段を講じるために訪れた法律事務所で、彼は女性弁護士から
こう言われます。
「DVは救うとか救われる、といったことでは解決しないんです。
他人の指示ではなく、自分は家を出るのだという自覚が必要なのです。
また、主婦を救いたいというのはDVの第一歩なんです。
救いたいという思いは、案外簡単に暴力につながります。
彼女は可愛そうな人だ。だからぼくは救わなければならない。ぼくがいなければ彼女は生きていけない。
そういう風に思うのは、他人を支配したいという欲求があるからなんです。
そういう欲求が、ぼくがいなければ生きていけないくせに、あの態度はなんだ、と言う風に変わるのは
時間の問題なんですよ。
他人を救いたいという欲求と、支配したいと言う欲求は、実は同じです。
そうしてそういう欲求を持つ人は、その人自身も深く傷ついている場合が多いんです。」
そして、弁護士から誰かに救われたことがあるでしょう、と尋ねられた秀樹は
母親に救われたと答えます。
弁護士は、母親が自立したことが結局は秀樹を救ったことを指摘し
秀樹は一人で生きていけるようになること、を自覚し新たな道を歩みだすのです。
私の息子も大学デビューに失敗しました。
今では明るくその当時の自分を振り返って、彼なりの分析でその原因を話してくれたりしますが
ここに至るまでの道のりは暗く長く厳しいものでした。
パチンコ三昧になり何度も道を踏み外し、そのたびに私は東奔西走し
お金も随分使いました。
私の行動は、この物語で秀樹がDV被害者の主婦を救い出そうと必死になる姿と
全く同じです。
本人に何の自覚もないのに、私だけが救い出そうとあれこれ考え行動し
彼の回りをグルグルと騒ぎ続けていました。
私の息子を救いたいというのは、本の中の弁護士が言うとおり
支配したいという欲求だったと今ならわかります。
私の行動もまた、暴力だったのです。
そして支配したい私もまた、深く傷ついていました。
それでも秀樹が救いたいという無駄な行動の中で弁護士にたどり着いたように
私もまた、息子を救いたいとアンテナを張る中で今のカウンセラーにたどり着きました。
それは、本の中の母・昭子とダブります。
昭子が家族会やカウンセリングによって自分の生き方を考えるようになったように
私もまた、カウンセラーと出会うことによって自分の中に蓋をして隠していた感情をみつめ
考えるようになりました。
自分をみつめる中で、家族の関係も徐々に明るくクリアで暖かいものに
自然と変わってきたように感じています。
最近では、息子との関係もずっと風通しのよいものになりました。
お互いの気持ちを隠すことなく主張できるようになり、
その結果今までのような、言わないけれどわかってよね、と言った陰険な雰囲気は
全くなくなりました。
干渉しない、というニュアンスともまた、違うと感じます。
相手を大切に思うと、自然と相手を信用できる、という感覚でしょうか。
私の場合、いつまでも子どもを未熟な存在、自分よりも劣っている存在(酷い言い方ですが)
と何処かで思っていたのかもしれません。
私が親からそう思われていたように。
未熟でダメなヤツだから教えてやらなければならない、
といつも上から話しをしていたのでしょう。
今の息子はいわゆるニートです。
世間の常識からみれば、甘えた立場ですし何を考えてんだっ!と言いたくなるでしょう。
でも、私も最近わかるようになりました。
決して息子も、今の状態でいいとは思っていません。苦しく思っているし、焦ってもいます。
自分に果たして何ができるのか、不安で押しつぶされそうになっています。
本人がわかっているのですから、私からそれ以上言うことは何もありません。
私が代わりに生きる訳でもなく、お願いして生きてもらっているのでもありません。
彼が彼なりに納得して、生き方の答えを自分で見つければいい、
そう考えていますし、きっといつかそうなるでしょう。
いろんな風に人は生きていけるし、生きる実感をもてればそれでOKだと。
本の中の四人家族は結局、バラバラになって生きていきます。
秀吉はリストラされ、ローンが支払えなくなった家を売却し故郷へ一人帰ります。
そこで新しい人生を探すのです。
昭子は家族会での仕事をすることになり、以前から付き合っていた年下のボーイフレンド
(この点は羨ましくもあり、また現実はこうはいかない・・・と思いました)との新しい関係が始まります。
知美は大学ではなくイタリアへ旅立ち、そこで自分の道を探し始めます。
秀樹は弁護士を訪ねたことをきっかけに司法試験を目指すスクールに通うことになりました。
バラバラになることは一見崩壊のようにみえますが
全く違いますね。
一人で生きられるようになること、それが家族にとっても大切なことなんでしょう。
どの家族にもあてはまる話しだとは思いません。
でも私にとっては、とてもすんなりと実感をもって納得できた小説でした。













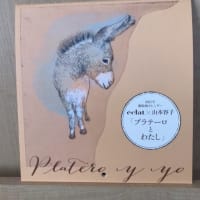
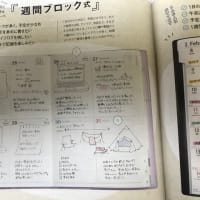










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます