渡りを六分、景気を四分に据え申し候。 千利休~『石州三百ヵ条』

今回は、庭造り、露地の飛び石についての利休の名言です。
茶庭である露地の飛び石は、茶室へと至る庭の通路として設置され、千利休の安土桃山時代頃に成立した、比較的新しいものです。
その名の通り、平らな石を飛び飛びに並べ、その上を客人が伝い歩いたため、古くは「伝い石」とも呼ばれました。これらの石の並べ方、配置について利休は「渡り(歩きやすさ)を六分、景気(美観)を四分」に按配して据えよ、と示したものです。
まずはこの句の出典から、原文と現代語訳をご紹介しましょう。
【原文】
「飛石ハ利休ハ渡りを六ふん、景氣を四ふんに居申候由、織部ハわたりを四ふん、景氣を六ふんにすへ申候、先、飛石ハ渡りのためなれば、わたりを第一とす、然共、まつすくに同じやうにつゝけてハかたく候、それゆへひつミを取也、しかれとも無用の所にて、わさとひつませ候ハ作物にてあししき也、何そ木にても下草にても、いき當りをよけ候ためにひつませ、又ハ石のとめ合により不足成るところにすへ石を置、それより居へつゝくるやう渡りを第一にするなり、尤よき石ハ嫌ふなり、あしき石にて見立よく居なすへし、今時、物すきとてあそここゝと石をひつませ、渡りの心なきハ嫌ふ也」
(『石州三百ヶ条』(『茶道古典全集』第二巻 千宗室編纂 淡交社)
【現代語訳】
飛び石を利休は、渡りを六分、景気を四分として設置、配列したという。弟子の織部は渡りを四分、景気を六分として並べたのだ。
そもそも飛び石は、渡って歩くためのものなので、渡りを第一とする。しかし石をまっすぐ同じように続けたのでは、固くみえる。それゆえ歪みをつけるのである。かといっても、無用の場所でわざとらしく歪ませるのは作り物でよくない。たとえば樹木や下草が障りとなる場合、これをよけるために歪ませ、または石と石とのつなぎに間が開いてしまった時、その足りない所へ据え石を置くとよい。その石より次の石へと続くように、渡りを第一とするのだ。さてまた、見映えのよい石は嫌う。見劣りする石を収まりのよきように見立てて据えよ。今どきの数寄者と称する人が、あちらこちらと石を歪ませ、渡りの心がないのは考えものだ。
(水野聡訳 2023年5月 能文社)
利休のいう、「渡りを六分、景気を四分」は、ぼくたち日本人の美的価値基準が、全き対称ではなく、いずれかの極へ少しずれ、傾く非対称性を象徴しています。
これは伝統的日本文化・芸術の諸相で広く観察される現象です。
なぜ日本人は非対称とわずかなずれを美しいと感じるのか。日本文化のいくつかの分野でサンプルケースをたどっていきましょう。
■利休は美が四分、織部は美が六分
まずは、利休作と伝えられる露地の飛び石と織部作の露地を見てみましょう。

利休のいう「渡りを六分、景気を四分」はいい換れば、機能が六割、美が四割とも考えることができます。すべて実用品であり、“用の美”たる茶道具の美的価値を四分とした利休に対し、弟子の織部が六分としたのは興味深いことです。利休形の代表たる樂茶碗と歪んだ織部焼茶碗を見比べた時、師と弟子のバランス感覚の違いがよく表れているのではないでしょうか。

■日本文化は不足の美
さて、「六分、四分」は機能と美のバランスですが、美そのもののバランスについても、東洋、とりわけ日本では、「五分、五分」すなわち完全なる均衡を理想の美とはしていません。
日本古来の絵、水墨画・山水画では絵の構図として「一角様式」が伝統的に踏襲されています。
これらの作品では、山や川などメインモチーフはいずれかの一隅に偏って描かれ、他は大きな余白として残され、何も描かれないのです。
この「一角」技法は、南宋の画家、馬遠より起こり、禅画を中心として日本でも広く普及していきました。

鈴木大拙は「一角」について、仏教思想(華厳経)の「一即多、多即一」とひもづけて、以下のように論じます。
「日本人の芸術的才能のいちじるしい特色の一つとして、南宋大画家の一人馬遠に源を発した「一角」様式を挙げることができる。この「一角」様式は、心理的にみれば、日本の画家が『減筆体』といって、絹本や紙本にできるだけ少ない描線や筆触で物の形を表すという伝統と結びつている。(中略) 非均衡性・非相称性・「一角」性・貧乏性・単純性・さび・わび・孤絶性・その他、日本の美術および文化の最も著しい特性となる同種の観念は、みなすべて「多即一、一即多」という禅の真理を中心から認識するところに発する。」
(『禅と日本文化』鈴木大拙 岩波新書 1940.9.30)
美術技法として見れば、「一角」の余白部分は、鑑賞者の想像力に働きかけ、創造力を呼び起こすもの、とされます。峻厳たる岩山の何も描かれない余白に、あるいは月を見、あるいは帰雁の連なりを見、時には古寺の晩鐘の音までをも聞くのです。
余白は不完全であり、不足ですが、そこに新たなる価値、生命が生み出される。ぼくたち日本人は、このようにして美を感じ、命を与えてきました。
■五分五分は神の座、人は三分一である
利休の飛び石の「六分、四分」は非均衡、非対称により、茶庭に美と生命を与えようとするものでした。
ひとたび茶道具へと目を転じた時、この非対称性は『南方録』の〈カネワリ〉と呼ばれる茶道具配置法に顕著に表れてきます。
〈カネワリ〉は台子に茶道具を飾り付けるための厳密な配置分法です。
台子の天板の上に五本の線を均等に割り付け、原則としてその線上に各道具を置いていきます。
この五つの線を〈陽カネ〉と呼び、中央の〈第一のカネ〉から、右、左へと〈五番目のカネ〉まで、茶道具の位(価値)に応じて配していく技法です。
面白いのは、この線(位置)の上に置く道具はすべて、真上に置かず少し右か左へとずらして置くというもの。ずらし方には〈三分一〉と〈峰ずり〉と呼ばれる二種類があります。一つ物と呼ばれる、飾りの主役級たる大名物茶道具は中央のカネにただ一つ〈峰ずり〉で置く。その他の道具は、他のカネにすべて〈三分一〉で置くこととされています。

■翁、すなわち神のみが中央の道を行く
「能にして能にあらず」とされる、能の秘曲〈翁〉。能の各流儀、各家では〈翁〉を演じる上で、様々な口伝・秘伝が伝えられてきました。
シテ方某家に伝わる習い(相伝)では、翁が登場する時、シテは橋掛かりの中央を通って本舞台に入る、とされています。そして、その他すべての曲では、シテは橋掛かりの中央線が右肩あたりにくるように、やや左寄りに橋掛かりを運ぶ決まりになっているという。
いうなれば、通路の真ん中は神のみに許される通り道。人間は神の道を憚って、やや脇に寄って通らねばなりません。開演前の鏡の間では、〈翁飾り〉をし、演者は塩で身を清め、舞台は火打石で清められる。
〈翁〉は古代の神が降臨する、神聖なる儀式として今も特別に重んじられています。
もしも神の座を冒す者あらば、いかなる神罰が下ることやら。
日本人が無意識に真中を避ける文化的背景には、超自然的な存在への畏敬があるのかもしれません。しかし怖れ、憚るとはいっても深山、辺境に神を遠ざけることはせず、ごく身近に祭り、共に祝い、共に寿福を享受するために生活の諸所に〈神の庭〉を設けていたのではないでしょうか。
オフィシャルホームページ【言の葉庵】
千年の日本語を読む【言の葉庵】能文社 (nobunsha.jp)

今回は、庭造り、露地の飛び石についての利休の名言です。
茶庭である露地の飛び石は、茶室へと至る庭の通路として設置され、千利休の安土桃山時代頃に成立した、比較的新しいものです。
その名の通り、平らな石を飛び飛びに並べ、その上を客人が伝い歩いたため、古くは「伝い石」とも呼ばれました。これらの石の並べ方、配置について利休は「渡り(歩きやすさ)を六分、景気(美観)を四分」に按配して据えよ、と示したものです。
まずはこの句の出典から、原文と現代語訳をご紹介しましょう。
【原文】
「飛石ハ利休ハ渡りを六ふん、景氣を四ふんに居申候由、織部ハわたりを四ふん、景氣を六ふんにすへ申候、先、飛石ハ渡りのためなれば、わたりを第一とす、然共、まつすくに同じやうにつゝけてハかたく候、それゆへひつミを取也、しかれとも無用の所にて、わさとひつませ候ハ作物にてあししき也、何そ木にても下草にても、いき當りをよけ候ためにひつませ、又ハ石のとめ合により不足成るところにすへ石を置、それより居へつゝくるやう渡りを第一にするなり、尤よき石ハ嫌ふなり、あしき石にて見立よく居なすへし、今時、物すきとてあそここゝと石をひつませ、渡りの心なきハ嫌ふ也」
(『石州三百ヶ条』(『茶道古典全集』第二巻 千宗室編纂 淡交社)
【現代語訳】
飛び石を利休は、渡りを六分、景気を四分として設置、配列したという。弟子の織部は渡りを四分、景気を六分として並べたのだ。
そもそも飛び石は、渡って歩くためのものなので、渡りを第一とする。しかし石をまっすぐ同じように続けたのでは、固くみえる。それゆえ歪みをつけるのである。かといっても、無用の場所でわざとらしく歪ませるのは作り物でよくない。たとえば樹木や下草が障りとなる場合、これをよけるために歪ませ、または石と石とのつなぎに間が開いてしまった時、その足りない所へ据え石を置くとよい。その石より次の石へと続くように、渡りを第一とするのだ。さてまた、見映えのよい石は嫌う。見劣りする石を収まりのよきように見立てて据えよ。今どきの数寄者と称する人が、あちらこちらと石を歪ませ、渡りの心がないのは考えものだ。
(水野聡訳 2023年5月 能文社)
利休のいう、「渡りを六分、景気を四分」は、ぼくたち日本人の美的価値基準が、全き対称ではなく、いずれかの極へ少しずれ、傾く非対称性を象徴しています。
これは伝統的日本文化・芸術の諸相で広く観察される現象です。
なぜ日本人は非対称とわずかなずれを美しいと感じるのか。日本文化のいくつかの分野でサンプルケースをたどっていきましょう。
■利休は美が四分、織部は美が六分
まずは、利休作と伝えられる露地の飛び石と織部作の露地を見てみましょう。

利休のいう「渡りを六分、景気を四分」はいい換れば、機能が六割、美が四割とも考えることができます。すべて実用品であり、“用の美”たる茶道具の美的価値を四分とした利休に対し、弟子の織部が六分としたのは興味深いことです。利休形の代表たる樂茶碗と歪んだ織部焼茶碗を見比べた時、師と弟子のバランス感覚の違いがよく表れているのではないでしょうか。

■日本文化は不足の美
さて、「六分、四分」は機能と美のバランスですが、美そのもののバランスについても、東洋、とりわけ日本では、「五分、五分」すなわち完全なる均衡を理想の美とはしていません。
日本古来の絵、水墨画・山水画では絵の構図として「一角様式」が伝統的に踏襲されています。
これらの作品では、山や川などメインモチーフはいずれかの一隅に偏って描かれ、他は大きな余白として残され、何も描かれないのです。
この「一角」技法は、南宋の画家、馬遠より起こり、禅画を中心として日本でも広く普及していきました。

鈴木大拙は「一角」について、仏教思想(華厳経)の「一即多、多即一」とひもづけて、以下のように論じます。
「日本人の芸術的才能のいちじるしい特色の一つとして、南宋大画家の一人馬遠に源を発した「一角」様式を挙げることができる。この「一角」様式は、心理的にみれば、日本の画家が『減筆体』といって、絹本や紙本にできるだけ少ない描線や筆触で物の形を表すという伝統と結びつている。(中略) 非均衡性・非相称性・「一角」性・貧乏性・単純性・さび・わび・孤絶性・その他、日本の美術および文化の最も著しい特性となる同種の観念は、みなすべて「多即一、一即多」という禅の真理を中心から認識するところに発する。」
(『禅と日本文化』鈴木大拙 岩波新書 1940.9.30)
美術技法として見れば、「一角」の余白部分は、鑑賞者の想像力に働きかけ、創造力を呼び起こすもの、とされます。峻厳たる岩山の何も描かれない余白に、あるいは月を見、あるいは帰雁の連なりを見、時には古寺の晩鐘の音までをも聞くのです。
余白は不完全であり、不足ですが、そこに新たなる価値、生命が生み出される。ぼくたち日本人は、このようにして美を感じ、命を与えてきました。
■五分五分は神の座、人は三分一である
利休の飛び石の「六分、四分」は非均衡、非対称により、茶庭に美と生命を与えようとするものでした。
ひとたび茶道具へと目を転じた時、この非対称性は『南方録』の〈カネワリ〉と呼ばれる茶道具配置法に顕著に表れてきます。
〈カネワリ〉は台子に茶道具を飾り付けるための厳密な配置分法です。
台子の天板の上に五本の線を均等に割り付け、原則としてその線上に各道具を置いていきます。
この五つの線を〈陽カネ〉と呼び、中央の〈第一のカネ〉から、右、左へと〈五番目のカネ〉まで、茶道具の位(価値)に応じて配していく技法です。
面白いのは、この線(位置)の上に置く道具はすべて、真上に置かず少し右か左へとずらして置くというもの。ずらし方には〈三分一〉と〈峰ずり〉と呼ばれる二種類があります。一つ物と呼ばれる、飾りの主役級たる大名物茶道具は中央のカネにただ一つ〈峰ずり〉で置く。その他の道具は、他のカネにすべて〈三分一〉で置くこととされています。

■翁、すなわち神のみが中央の道を行く
「能にして能にあらず」とされる、能の秘曲〈翁〉。能の各流儀、各家では〈翁〉を演じる上で、様々な口伝・秘伝が伝えられてきました。
シテ方某家に伝わる習い(相伝)では、翁が登場する時、シテは橋掛かりの中央を通って本舞台に入る、とされています。そして、その他すべての曲では、シテは橋掛かりの中央線が右肩あたりにくるように、やや左寄りに橋掛かりを運ぶ決まりになっているという。
いうなれば、通路の真ん中は神のみに許される通り道。人間は神の道を憚って、やや脇に寄って通らねばなりません。開演前の鏡の間では、〈翁飾り〉をし、演者は塩で身を清め、舞台は火打石で清められる。
〈翁〉は古代の神が降臨する、神聖なる儀式として今も特別に重んじられています。
もしも神の座を冒す者あらば、いかなる神罰が下ることやら。
日本人が無意識に真中を避ける文化的背景には、超自然的な存在への畏敬があるのかもしれません。しかし怖れ、憚るとはいっても深山、辺境に神を遠ざけることはせず、ごく身近に祭り、共に祝い、共に寿福を享受するために生活の諸所に〈神の庭〉を設けていたのではないでしょうか。
オフィシャルホームページ【言の葉庵】
千年の日本語を読む【言の葉庵】能文社 (nobunsha.jp)


















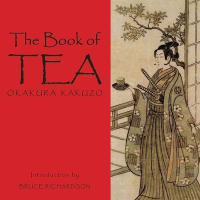








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます