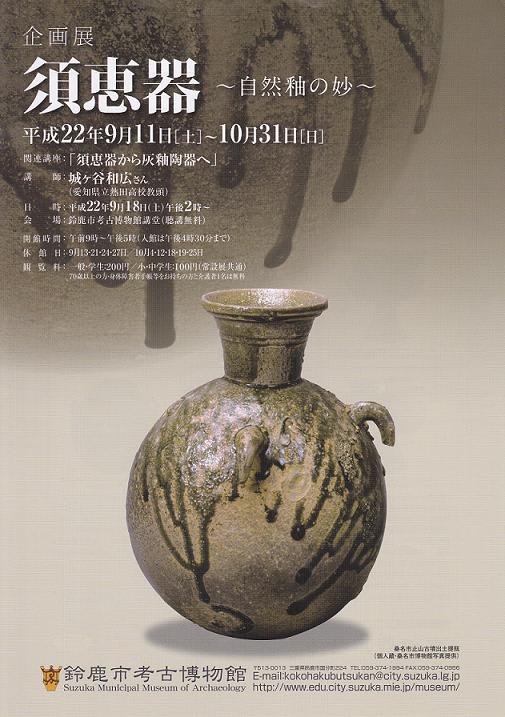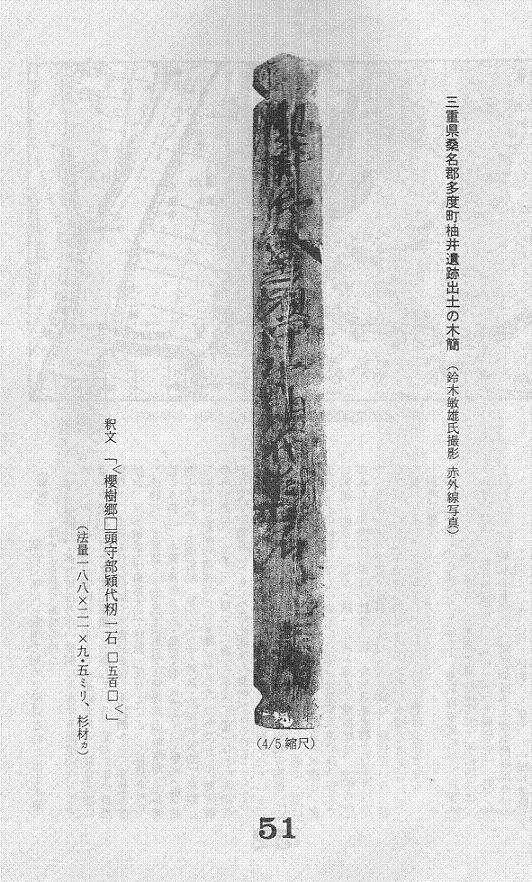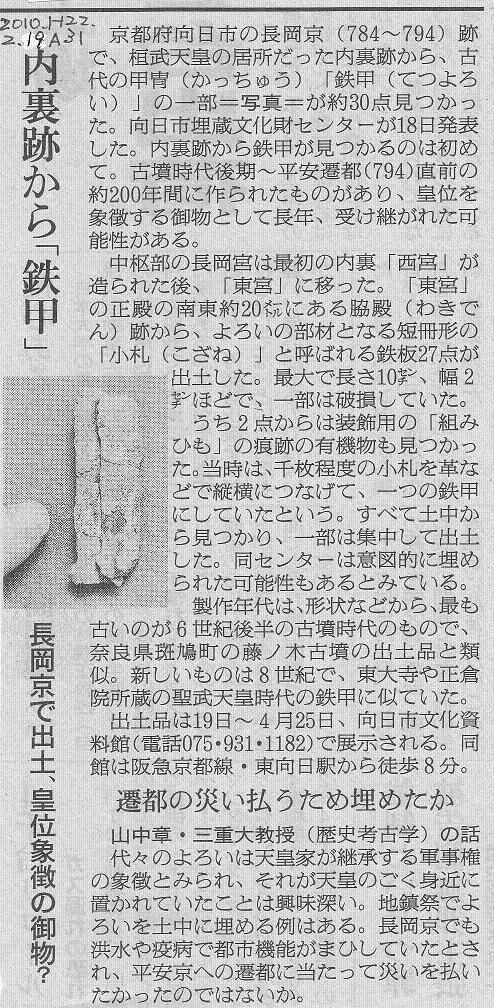中日新聞 2010年9月18日 より引用
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
奈良・巻向遺跡 祭り用 果肉残るものも
邪馬台国の有力候補地、奈良県桜井
市巻向遺跡で、女王卑弥呼の宮殿の可
能性がある大型建物跡(三世紀前半~
同中ご)から、二千個以上のモモの種
が見つかった。桜井市教育委員会が十
七日発表した。モモは当時、不老長寿
の神聖な果実と信じられ、市教委は「大
規模な祭りで、大型建物エリアが特殊
な場所だったことを示している」とみ
ている。モモの種には果肉が残るもの
もあった。ほかに東海系のミニチュア
土器や絵画土器などの土器片、黒漆塗
りの弓、剣型などの木製品、竹かごが
壊された状態で見つかった。(中略)
市教委の橋本輝彦文化財係長は「これ
ほど大量のモモの種の出土は初めてで
は。集落内のモモをかき集め、遺跡全
体にかかわるような大事な祭りだった
可能性がある」と話す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼卑弥呼がモモを供えて祭りを行った
のだろうか。それにしてもかなりの数
の種が腐食もせずに残っていたもので
す。東海系のミニュチュア土器も発掘
されたとあり、東海からの献上物でし
ょうか。中央の権力者として力を発揮
していたのではと想像します。このあ
たりは赤塚次郎著「幻の王国・狗奴国
を旅する」のP162を参照してください。
 こめぞう
こめぞう