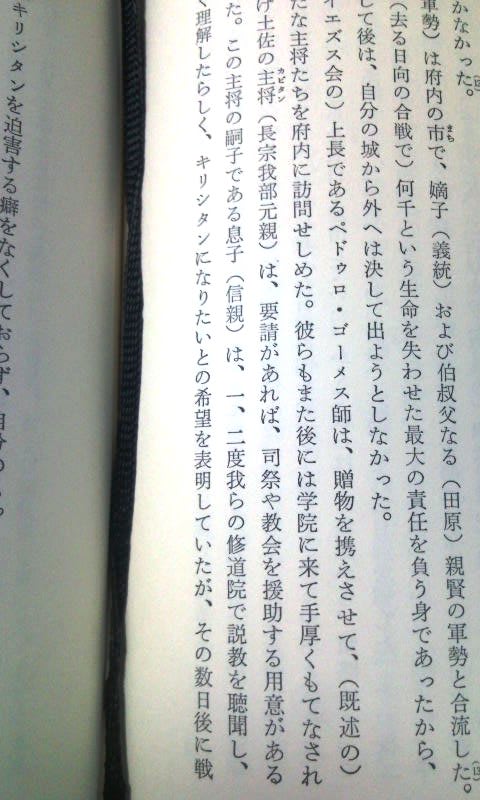(この文章は手直しを繰り返して、歴史小説 『鳥無き島の蝙蝠』~長宗我部元親伝~の原稿にします)
「空海が受け取った仏教の原質」はよく知られていない。インドで生まれた仏教は、当初、偶像崇拝を否定していたが、ギリシャ文明と出会い初めて仏像を生み出した。つまり、日本に伝わった仏教はシルクロードの西側で欧州の壁に跳ね返され、弾圧を逃れて東に辿りついた仏教である。
逃れの里日本に辿りついた仏教が、古代ユダヤ・キリスト教と習合していた(故に異端として弾圧を受けた)という可能性は否定できない。
初期仏教美術(ガンダーラ美術)には、ギリシャ方面の彫刻技術が取り入れられた痕跡が色濃く残っており、仏教伝来の軌跡を辿るうえで非常に重要なキーになります。
「シッダルタの誕生」

<shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"></shapetype><stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas></formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock><shape id="図_x0020_1" o:button="t" href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/SiddhartaBirth.jpg" alt="ファイル:SiddhartaBirth.jpg" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1025" style="WIDTH: 456pt; HEIGHT: 333pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square"></shape><imagedata o:title="SiddhartaBirth" src="file:///C:DOCUME~1kochi53LOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image001.jpg"></imagedata>
ガンダーラ美術は、ギリシャ、シリア、ペルシャ、インドの様々な美術様式を取り入れた仏教美術として有名。開始時期はパルティア治世の紀元前50年-紀元75年とされ1世紀~5世紀にその隆盛を極めたが、匈奴が侵入して繁栄も終わりを告げた。
大乗仏教は、この頃生まれた。「兜跋(とばつ)毘沙門天像」という頭に鳳凰のついた冠をかぶった像が存在し、毘沙門天の起源がギリシア神話のヘルメス(ローマのメルクリウス)であるという説がある。
岡山の上原遺跡で見つかったトサカをもった人面土器が関連あるかも知れない。
こうしてみると、我々日本人が飛鳥時代後半に受け入れた仏教は、西域文化と習合した後の有仏像仏教であり、百済に伝わってから東洋的進化を遂げたものであったことが解る。日本は、仏教導入に伴い漢字と仏典だけを手に入れたと勘違いしているが、真実は遥かギリシャに繋がる西域の文化をも取り込んだ(習合していた)と言えるのである。
本地垂迹(ほんじすいじゃく)は、アジア圏の東西における宗教と学問が合一した結果ですから、これらを解きほぐして行けばいろいろなことが解ります。
空海は、三教指帰を著して、複数の宗教(学問体系)の中から仏教(インドを起源とする外国の学問)を選択し、中国に受け取りに行きました。日本の既存の宗教では解決できない問題を「習合」によって解決することが目的です。
空海が恵果に学んだ仏教は、既に偶像崇拝を認容していたから、西方に伝授された仏教が、イラン高原地方で進化した後、ソグド人などの隊商・騎馬民族の手によって東洋に伝わったと考えるべきだろう。
その昔、シッダルタが生まれた頃、イラン高原には、ソグド人という男女平等な契約に基づく結婚を認めた交易を得意とする騎馬民族が繁栄していました。彼らの都市はソグディアナと呼ばれ、中心地はサマルカンドです。空海が生まれ変わりと讃えられた「不空三蔵」の母はサマルカンドの女性です。
その昔、宗教は、生活規範であり、哲学・心理学・科学・化学・物理・数学・天文学・気象学などの学問の総体系であり、それらを神仏の力と融合させるものでした。
織田家が福井の剣神社で祭っているスサノオは牛頭天皇と習合しています。スサノオ・牛頭天王の神紋は木瓜紋で、津島神社を崇敬していた織田家は木瓜を家紋とした。津島信仰
この「織田木瓜」は鳥の巣を図案化したもので、ぬくぬくとした家庭をイメージしています。また、木瓜→胡瓜ですから「西域から伝わったもの」を意味しています。
牛頭天皇は明治期の神仏分離令まで祇園社(八坂神社)の祭神で、古代インドのコーサラ国にあったという祇園精舎の守護神です。スサノオには奇稲田姫クシナダヒメが、牛頭天皇には頗梨采女ハリサイジョという妻がいます。織田家は男女の和合を祭っているとも言えます(昔の日本人がハヒフヘホをファフィフフェフォと発音していたことからすれば、ハリサイジョはファリサイ派のことか?)。
私は、これら全てが、「男女和合」を賛美する「理趣教」に繋がると考えています。「理趣教」が古代インドの性愛書「カーマ・スートラ」を仏教に取り込んだものと考えれば整合する。双方とも好奇の目で見られがちだが情欲を目的としたものではない。人倫の教えである。
日本の知識人は、空海以前から積極的に海外に知識を求め、様々な学問・宗教との「習合」を繰り返しています。
男女の自由平等・恋愛を賛美する思想が西域仏教に織り込まれ、日本の多神教と習合したことが解ります。女性を排斥し、女犯を禁じた仏教においては極めて異端です。
この理趣教を空海は後生大事に守り、弾圧を恐れて最澄には渡さなかったのです。
理趣教は、詳しくは「大楽金剛不空真実三摩耶経」といいます。私には『大変楽しい、ダイヤモンドのように大切なもので、空虚ではない真実(或いは、不空が見出した真実)が織り込まれたもので、ブッダの妻・麻耶を讃える経』と読めます。
そもそも麻耶(母)が産まなければシッダルタも仏教もこの世に無いのですから、仏教の女性排斥論は、空海には修正しなければならない宿題だったのでしょう。
私は、四国88か所が四国のへそに位置する高知県長岡郡本山町を中心とする結界であり、そこには空海が最澄に渡すのを拒んだ「理趣教(立川教)」を根本教義に据えた学問が栄えていたと考えています。空海は、自身が生きる時代には修正できないと考え、四国88か所をもって結界を張り巡らし、その中心地である本山町に密かに秘めた・・・ 証拠を集め、この推論の精度を徐々に高めて行きたいと思います。
いずれにせよ、空海は、私たち現代人が大切にし、人間の生活には当たり前と考えている「男女和合」「夫と妻が共に暮らす」ことを容認する経典を、遥か1200年前に輸入し、ダイヤモンドに例えていたのです。
次回は「密教がミトラ経(太陽信仰)」を表していることなど・・・ パンニャハラミツッタ~