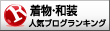僕は匂いの強い食べ物が好きです。
にんにく、ネギ、韮。これからの季節は夏に向けてエスニックに「パクチー」
家人には大変に評判が悪いのですが、ヤミつきの匂いです。
種を植えるとまず双葉が出て、そのあと本葉になるのですが、双葉は匂いがないですが本葉になるとあの独特の匂いがします。

今年の夏はバサバサとかけてみようかと。
にんにく、ネギ、韮。これからの季節は夏に向けてエスニックに「パクチー」
家人には大変に評判が悪いのですが、ヤミつきの匂いです。
種を植えるとまず双葉が出て、そのあと本葉になるのですが、双葉は匂いがないですが本葉になるとあの独特の匂いがします。

今年の夏はバサバサとかけてみようかと。