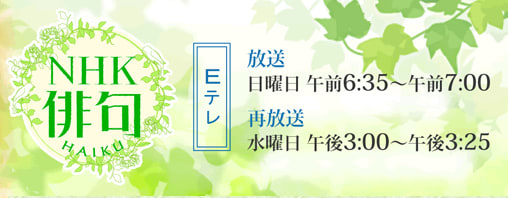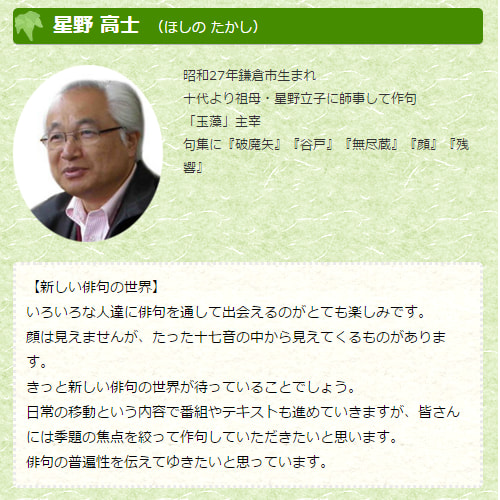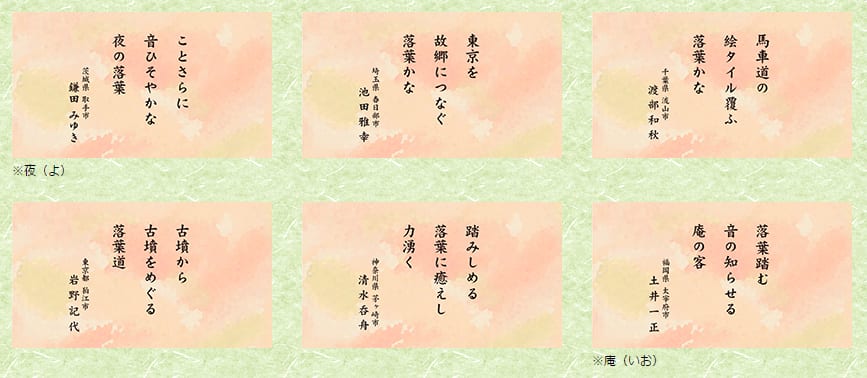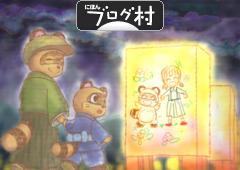(勝山句会 於 坂本公民館 平成27年9月21日(月)19:30~)

 今日はもう12月3日です。ブログ作りが進まなくて申し訳ありません。
今日はもう12月3日です。ブログ作りが進まなくて申し訳ありません。

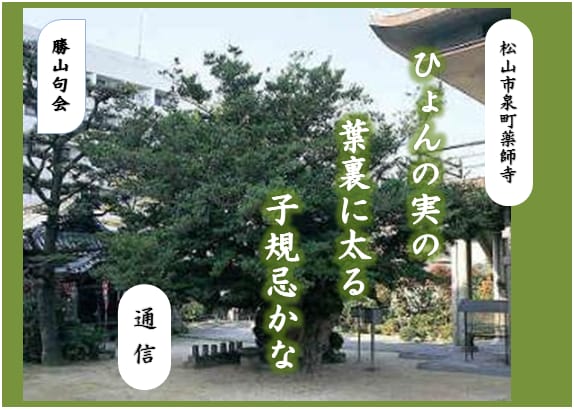
 季語紹介
季語紹介  子規忌 読み方:シキキ(shikiki)正岡子規の忌日。季節:秋。分類:宗教。月日:9月19日。 【weblio 季語・季題辞典より】
子規忌 読み方:シキキ(shikiki)正岡子規の忌日。季節:秋。分類:宗教。月日:9月19日。 【weblio 季語・季題辞典より】
 写真:松山市ホームページより引用
写真:松山市ホームページより引用 
 竹内コメント
竹内コメント 境内に子規の句碑「我見しより久しきひょんの茂哉」があります。
境内に子規の句碑「我見しより久しきひょんの茂哉」があります。

 ひょんの茂(ひょんの木)とは「いすの木」のこと。
ひょんの茂(ひょんの木)とは「いすの木」のこと。
蚊母樹 読み方:イスノキ(isunoki) マンサク科の常緑高木。庭木、建築材となる。季節:秋。分類:植物。 【weblio 季語・季題辞典より】

 泉町薬師寺のいすの木(松山市指定天然記念物)については、松山市ホームページ→観光イベント→松山の歴史文化→指定文化財→市指定文化財→記念物「いすの木(泉町 薬師寺)」に詳細があり、「いすの木は、さして珍しい木ではないが、これほど大きいのは珍しい。…云々」…これは一度見に行かねば。
泉町薬師寺のいすの木(松山市指定天然記念物)については、松山市ホームページ→観光イベント→松山の歴史文化→指定文化財→市指定文化財→記念物「いすの木(泉町 薬師寺)」に詳細があり、「いすの木は、さして珍しい木ではないが、これほど大きいのは珍しい。…云々」…これは一度見に行かねば。  (県立中央病院の東側にあります。)
(県立中央病院の東側にあります。)

 ひょんの実【瓢の実】について
ひょんの実【瓢の実】について
「葉や枝にイチジク状の虫えい(虫こぶ)ができて、長さ4~5cmにもなり、その中の幼虫が成虫になって出たあとの穴に、風があたるとヒョウヒョウと鳴る。その音色から、別名ヒョンノキともいう。子供はこれを笛がわりに吹いて遊ぶこともあった。」
【松山市ホームページ「いすの木」解説より】

 写真:「公益財団法人京都市都市緑化協会みどりの相談所だよりQ&A」より引用
写真:「公益財団法人京都市都市緑化協会みどりの相談所だよりQ&A」より引用 
 毎年恒例、坂本公民館の地域めぐり事業で窪野町の正八幡神社を訪れた際に、地元の方に「これがひょんの実だよ。子どものころは笛にして遊んだもんだ。」と教えてもらいました。木の実だと思い込んでました。虫こぶだったんですね…。珍しくて、ずーっと持っていました。
毎年恒例、坂本公民館の地域めぐり事業で窪野町の正八幡神社を訪れた際に、地元の方に「これがひょんの実だよ。子どものころは笛にして遊んだもんだ。」と教えてもらいました。木の実だと思い込んでました。虫こぶだったんですね…。珍しくて、ずーっと持っていました。

 竹内 評
竹内 評  人生とは海のようなものと言った先人がいる。潮が引くと汚れた海底が覗き、満ちると隠れて一見平和な景色となる。今の世は引き潮だと。 (9月号 鶴巻頭 鶴抄三の句)
人生とは海のようなものと言った先人がいる。潮が引くと汚れた海底が覗き、満ちると隠れて一見平和な景色となる。今の世は引き潮だと。 (9月号 鶴巻頭 鶴抄三の句)
 季語紹介
季語紹介  初潮 読み方:ハツシオ(hatsushio) 陰暦8月15日満月の大潮の満潮。季節:秋。分類:地理。 【weblio 季語・季題辞典より】
初潮 読み方:ハツシオ(hatsushio) 陰暦8月15日満月の大潮の満潮。季節:秋。分類:地理。 【weblio 季語・季題辞典より】
 写真:無料写真素材「写真AC」より引用
写真:無料写真素材「写真AC」より引用 

 竹内 評
竹内 評  「老体は耐ふる外無き残暑かな」ならば、材料が良いので「鶴抄」句。 (9月号 鶴巻頭 鴇抄三の句)
「老体は耐ふる外無き残暑かな」ならば、材料が良いので「鶴抄」句。 (9月号 鶴巻頭 鴇抄三の句)
 季語紹介
季語紹介  残暑 読み方:ザンショ(zansho) 立秋以後の暑さ。季節:秋。分類:時候。 【weblio 季語・季題辞典より】
残暑 読み方:ザンショ(zansho) 立秋以後の暑さ。季節:秋。分類:時候。 【weblio 季語・季題辞典より】
 写真:久谷の里山(写真のページ)様から引用
写真:久谷の里山(写真のページ)様から引用 
 「鶴抄」とは
「鶴抄」とは  竹内さん編集の句集「つるき」には、「鶴巻頭」というコーナーがあります。「鶴抄一」「鶴抄二」「鶴抄三」「鴇抄一」「鴇抄二」「鴇抄三」「白鷺一」「白鷺二」「白鷺三」が、以前の「特選」「入選」「佳作」に対応しています。
竹内さん編集の句集「つるき」には、「鶴巻頭」というコーナーがあります。「鶴抄一」「鶴抄二」「鶴抄三」「鴇抄一」「鴇抄二」「鴇抄三」「白鷺一」「白鷺二」「白鷺三」が、以前の「特選」「入選」「佳作」に対応しています。

 竹内 評
竹内 評  惜しい一句。「終えの一服」が「終へて一服」ならば「鴇抄」句。 (9月号 鶴巻頭 白鷺抄三の句)
惜しい一句。「終えの一服」が「終へて一服」ならば「鴇抄」句。 (9月号 鶴巻頭 白鷺抄三の句)
 季語紹介
季語紹介  残暑 読み方:ザンショ(zansho) 立秋以後の暑さ。季節:秋。分類:時候。 【weblio 季語・季題辞典より】
残暑 読み方:ザンショ(zansho) 立秋以後の暑さ。季節:秋。分類:時候。 【weblio 季語・季題辞典より】
 写真:久谷の里山(写真のページ)様から引用
写真:久谷の里山(写真のページ)様から引用 
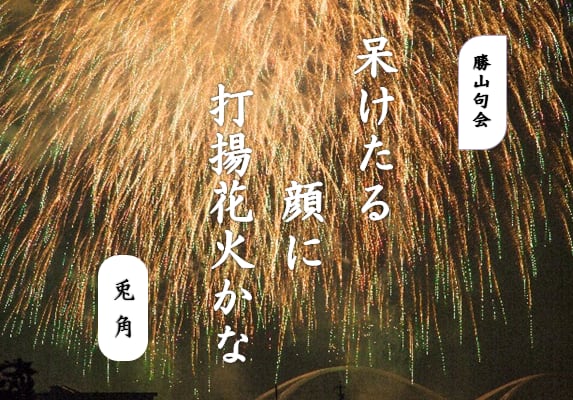
 竹内 評
竹内 評  真下から花火を見上げる人の大半は不思議と口を開けている。(調査済み) (通信つるき句会平成27年8月号 地籟一 四点句)
真下から花火を見上げる人の大半は不思議と口を開けている。(調査済み) (通信つるき句会平成27年8月号 地籟一 四点句)
 季語紹介
季語紹介  花火 読み方:ハナビ(hanabi) 火薬に他の薬料を配合して、球のなかにつめ、木筒などに入れて、火を点じて空中に打ちあげるもの。季節:夏、秋。分類:人事。 【weblio 季語・季題辞典より】
花火 読み方:ハナビ(hanabi) 火薬に他の薬料を配合して、球のなかにつめ、木筒などに入れて、火を点じて空中に打ちあげるもの。季節:夏、秋。分類:人事。 【weblio 季語・季題辞典より】
 写真:無料写真素材「写真AC」より引用
写真:無料写真素材「写真AC」より引用 

 竹内 評
竹内 評  この句は肩の張ったところが無い。このような句の良さが判る選者が増えるといいですね。 (9月号 鶴巻頭 鶴抄二の句)
この句は肩の張ったところが無い。このような句の良さが判る選者が増えるといいですね。 (9月号 鶴巻頭 鶴抄二の句)
 季語紹介
季語紹介  台風(颱風) 読み方:タイフウ(taifuu) おもに秋に発生する熱帯性低気圧に伴う暴風雨。季節:秋。分類:天文。 【weblio 季語・季題辞典より】
台風(颱風) 読み方:タイフウ(taifuu) おもに秋に発生する熱帯性低気圧に伴う暴風雨。季節:秋。分類:天文。 【weblio 季語・季題辞典より】
 写真:無料写真素材「写真AC」より引用
写真:無料写真素材「写真AC」より引用 
 そして最後に…
そして最後に… 


 蓮行さんに教えてもらって、初めて見た
蓮行さんに教えてもらって、初めて見た 「NHK俳句」。
「NHK俳句」。
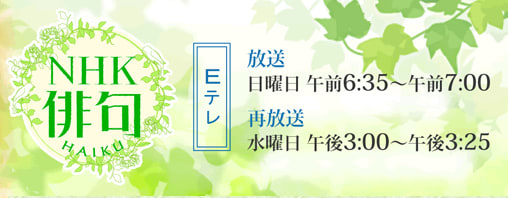
 以下、NHK俳句のホームページより引用
以下、NHK俳句のホームページより引用 
当日の司会者は岸本葉子さん。

選者は、星野高士さん。
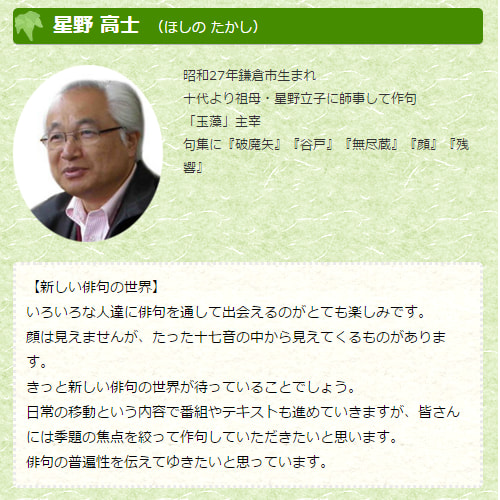
ゲストは桂右團治さん(女性落語家として初の真打ち)でした。
星野選者、当日の生コメントより抜粋。7番(蓮行さんの句)
「これは、あの、別に難しいことは言ってませんね。なんとなく日常の感じなんですね。でも日課っていうのはみんなそれぞれあるじゃないですか。『朝起きてどうしよう…でも、落ち葉がちょっと積もっている。この落ち葉のことも日課に加えよう。』この落ち葉に対する想い、それが出てるんじゃないでしょうかね。」
入選作品発表後の司会者コメントより
「『落ち葉掃く~』すごく素直ですね。落ち葉の季節に続くなという感じがしました。」
そして、入選作品。

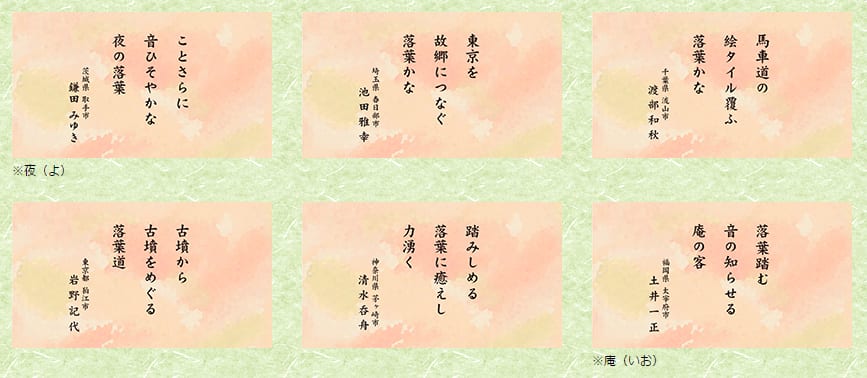

 毎週、何千通(?)もの投句があるそうです。その中から選ばれた9句。
毎週、何千通(?)もの投句があるそうです。その中から選ばれた9句。
そして、9句の中から一席、二席、三席が選ばれます。
蓮行さん、これからも投句がんばってください。
 ブログ担当より
ブログ担当より  勝山句会の資料「つるき」はすでに10月号を預かっています。
勝山句会の資料「つるき」はすでに10月号を預かっています。
10月19日(月)19:30~ 《課題季語》鶺鴒・背黒鶺鴒・石たたき・庭たたき・黄鶺鴒 ・・・句会開催済み。
11月16日(月)19:30~ 《課題》冬眠 ・・・句会開催済み。
(「次回予告」の存在が危ない… )
)
12月の勝山句会は、たぶん、21日(月)(予定)でしょう。
「つるき」11月号、12月号を預かる前に、なんとかして10月号の句を紹介したいです。 がんばります。
がんばります。

 荏原地区の常夜燈の総ざらえです。
荏原地区の常夜燈の総ざらえです。

 では、常夜燈が一番多くある東方町からいきまーす。
では、常夜燈が一番多くある東方町からいきまーす。

 )
)
 )
)






 以上が東方町の9基の常夜燈でした。
以上が東方町の9基の常夜燈でした。




 さあ、クルッとUターンして、川西のほうへ向かいます。(御坂川の西という意味だと思う。
さあ、クルッとUターンして、川西のほうへ向かいます。(御坂川の西という意味だと思う。 )
)





 今回は常夜燈担当さんの写真を大きめに入れてみました。
今回は常夜燈担当さんの写真を大きめに入れてみました。


 まとめに、詳細マップを入れておきます。
まとめに、詳細マップを入れておきます。 
 )
)




 あー、やっと、荏原地区の20基の常夜燈のまとめができました。
あー、やっと、荏原地区の20基の常夜燈のまとめができました。 (笑))
(笑))












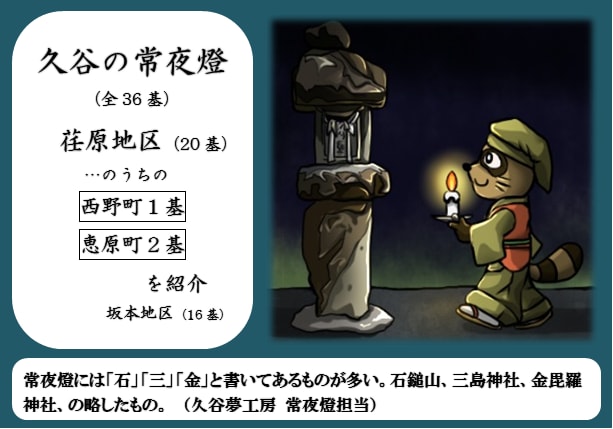

 (…笑
(…笑
 )
)

 家の周りにお堀があるところへ来るので、そこを左折。
家の周りにお堀があるところへ来るので、そこを左折。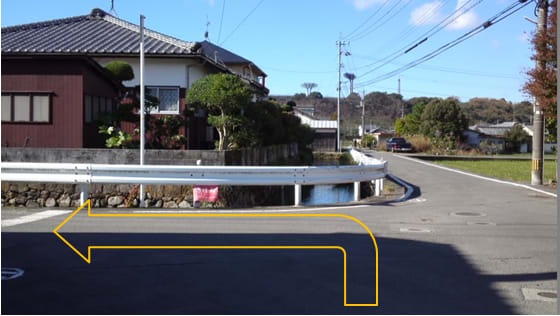







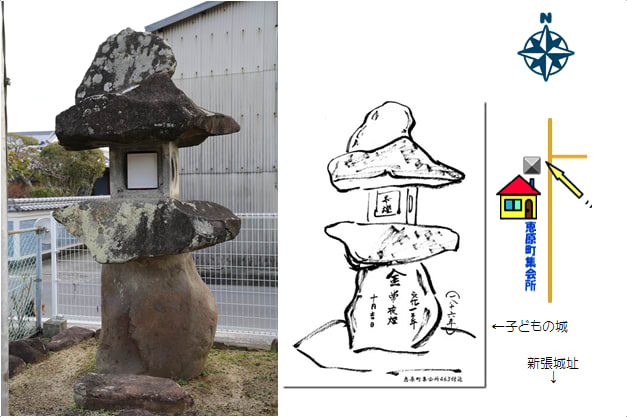









 西野町集会所、恵原町集会所、新張城址について少々手直しさせていただきました。
西野町集会所、恵原町集会所、新張城址について少々手直しさせていただきました。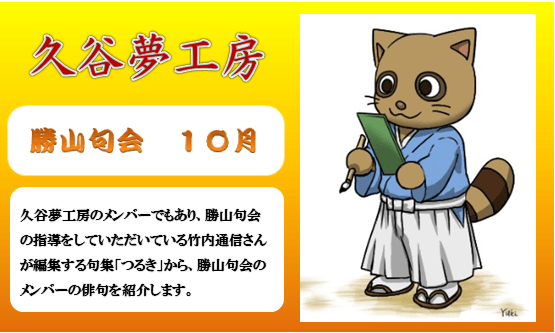
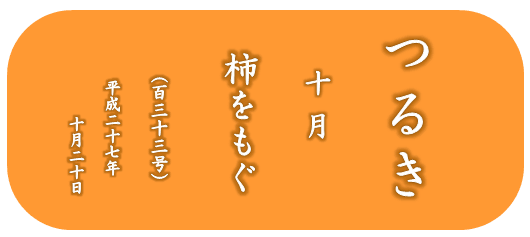


 竹内通信さんがなぜ「久谷村」と書いたのか・・・。
竹内通信さんがなぜ「久谷村」と書いたのか・・・。
 窪野町と久谷町と浄瑠璃町で「坂本村(1890年~)」。
窪野町と久谷町と浄瑠璃町で「坂本村(1890年~)」。

 竹内コメント
竹内コメント  季語紹介
季語紹介 
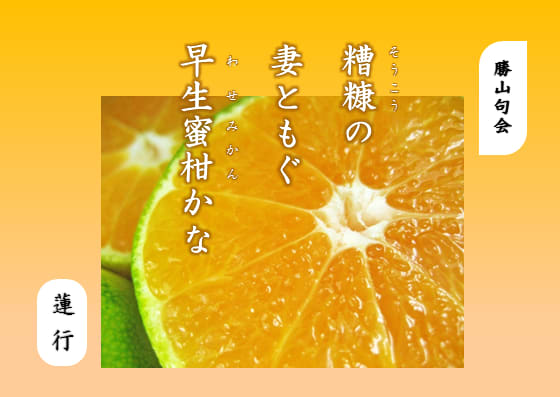
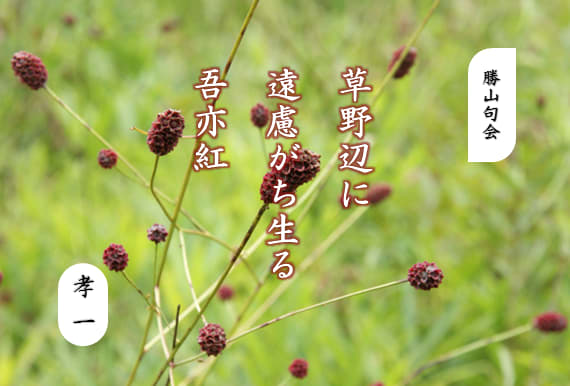


 あまり意味のない「次回予定」
あまり意味のない「次回予定」 (ブログ担当より)
(ブログ担当より)

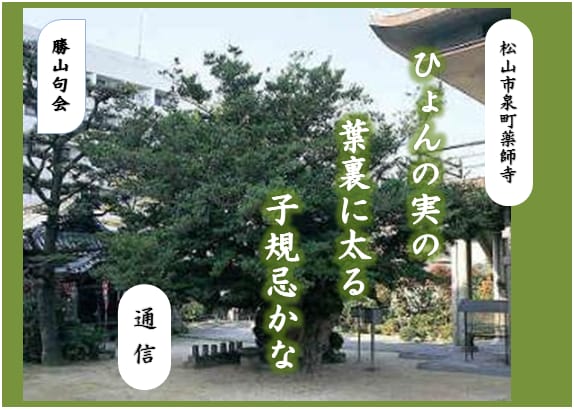




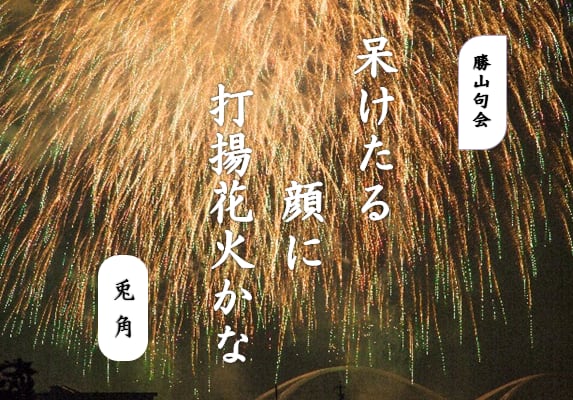



 蓮行さんに教えてもらって、初めて見た
蓮行さんに教えてもらって、初めて見た