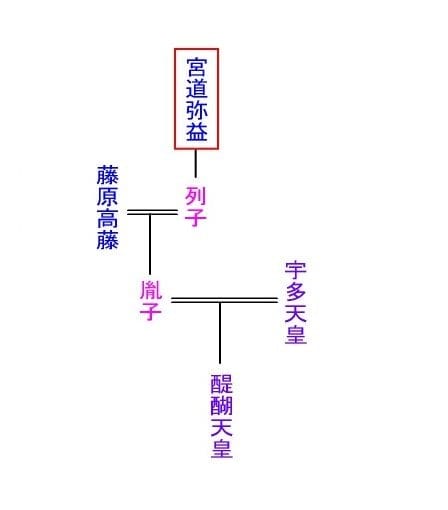※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2009年)
ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。
『源氏物語』における光源氏と明石の君のモデル!?
藤原高藤と宮道列子のロマンスの地
藤原定方 (ふじわらのさだかた)
873年(貞観15年)~932年(承平2年)
平安時代中期の官人。歌人。管弦の名手。
邸宅が三条坊門小路の北面にあったため、三条右大臣と呼ばれる。
歌集『三条右大臣集』を遺す。
父は、藤原高藤。
母は、宮道列子。(宮道弥益の娘)
姉または妹である胤子(たねこ・いんし)は宇多天皇の女御で醍醐天皇の生母となる。
定方は子宝に恵まれ、5人の男子と13人の女子が確認されている。
娘のひとり・能子を醍醐天皇の後宮に入内させる。(能子は醍醐天皇崩御後、天皇の同母弟・敦慶親王と交際を経て、藤原実頼の妻となる。)
政治家としてよりも文化人としての功績を遺す。
宇多上皇や醍醐天皇主催の歌合で活躍し、醍醐朝の宮廷歌壇活動に寄与した。
従兄弟で娘婿でもある藤原兼輔、紀貫之や凡河内躬恒とも歌人同士として交流があった。
山科に勧修寺を建立したことから、子孫は「勧修寺流」と呼ばれる。
祖父の宮道弥益と両親、兄弟たちとともに勧修寺の南にある宮道神社に祀られている。
紫式部とその夫・藤原宣孝はともに藤原定方の曾孫にあたる。
また、紫式部が仕えた一条天皇中宮彰子は定方の玄孫である。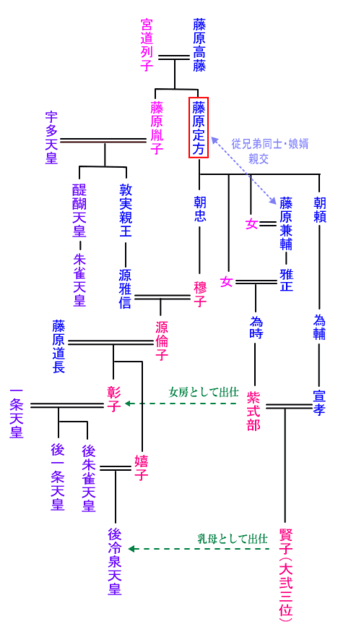
三条右大臣の名で歌人として知られる藤原定方。
『百人一首』には以下の歌が撰ばれています。
名にしおはば 逢坂山の さねかづら
人に知られで くるよしもがな
三条右大臣
三条右大臣の歌碑は、宮道神社や逢坂関記念公園<滋賀県大津市>、嵯峨野に建立されています。
定方の子孫にも、『百人一首』に撰ばれた歌人が多いので系図にしてみました。
系図と歌をご覧くださいませ。
 定方の五男・藤原朝忠
定方の五男・藤原朝忠
あふことの たえてしなくは なかなかに
人をも身をも 恨みざらまし
中納言朝忠 定方の曾孫世代:紫式部・藤原公任・藤原実方
定方の曾孫世代:紫式部・藤原公任・藤原実方
めぐりあひて 見しやそれとも 分かぬまに
雲がくれにし 夜半の月かな
紫式部
滝の音は 絶えて久しく なりぬれど
名こそ流れて なほ聞こえけれ
大納言公任
かくとだに えやはいぶきの さしも草
さしも知らじな もゆる思ひを
藤原実方朝臣 定方の玄孫世代 :藤原賢子(大弐三位)・藤原定頼・藤原道雅
定方の玄孫世代 :藤原賢子(大弐三位)・藤原定頼・藤原道雅
ありま山 ゐなの笹原 風吹けば
いでそよ人を 忘れやはする
大弐三位
朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに
あらはれわたる 瀬々の網代木
権中納言定頼
今はただ 思ひ絶えなむ とばかりを
人づてならで 言ふよしもがな
左京大夫道雅
【参考】
「平安時代史事典CD-ROM版」 監修:角田文衞/編:(財)古代学協会・古代学研究所/ 発行:角川学芸出版
「今昔物語集 本朝部(中)」編:池上洵一/発行:岩波書店
「カラー 小倉百人一首」 編著:島津忠夫・櫟原聰/発行:京都書店