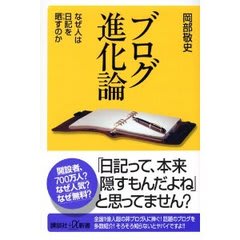なんだかスッキリしない本だった。
「暴走老人!」というタイトルと本の内容があまり一致していない。
タイトルにだまされたような気分だ。(おそらく出版社の仕業)
あとがきを見たら、
「テーマは『暴走する老人たち』ですが、私は老人批判を展開したかったわけではありません。暴走の現実を追いかけていくことで、現在進行している人と人とのかかわり方の根底的な変化を見たかったのです」と書いてあった。
なんだよー。老人批判じゃないのかよー。「暴走老人!」というタイトルだけで、既に(老人を)批判してると思うけどー。
ぼくは、「暴走老人!」たちの批判を読みたかったのだ。近頃の老人たちはどうなってんだー、ちょっと、いや、かなりおかしいんじゃないかー、という話を読みたかったのに、いつの間にか現代社会の批判? みたいになっちゃってる。なんだよ、この本、つまんねーな、という結果になる。
読んでいるうちに飽きてきます。
簡単に言うと、現代は社会の変化のスピードが速すぎて、それに適応できない老人たちがあちこちで「暴走」的な行動を起こしている、というもので、暴走の原因は、現代社会にあるのではないかという問題提起です。なるほどね。そうかもしれません。しかしですね、適応できていないのは、老人たちだけではありませんよ。中高年だって似たようなものです。「暴走中高年!(または暴走老人予備軍)」もたくさんいるわけです。
昔から、頑固じじいや意地悪ばあさんと呼ばれる人たちはたくさんいたはず。そういった昔の老人たちと現在の老人たちとの間に違いはあるのか、あるとすれば何なのか、そういう視点がもっと欲しかった。一番大きな違いは、時代ですけど。
著者は芥川賞作家ですが、老人をテーマにするのであれば、もっと老人と接してみて、よく観察し、研究・考察してもらいたいですぬ。
タイトルにだまされてはいけません。要注意。
「暴走老人!」というタイトルと本の内容があまり一致していない。
タイトルにだまされたような気分だ。(おそらく出版社の仕業)
あとがきを見たら、
「テーマは『暴走する老人たち』ですが、私は老人批判を展開したかったわけではありません。暴走の現実を追いかけていくことで、現在進行している人と人とのかかわり方の根底的な変化を見たかったのです」と書いてあった。
なんだよー。老人批判じゃないのかよー。「暴走老人!」というタイトルだけで、既に(老人を)批判してると思うけどー。
ぼくは、「暴走老人!」たちの批判を読みたかったのだ。近頃の老人たちはどうなってんだー、ちょっと、いや、かなりおかしいんじゃないかー、という話を読みたかったのに、いつの間にか現代社会の批判? みたいになっちゃってる。なんだよ、この本、つまんねーな、という結果になる。
読んでいるうちに飽きてきます。
簡単に言うと、現代は社会の変化のスピードが速すぎて、それに適応できない老人たちがあちこちで「暴走」的な行動を起こしている、というもので、暴走の原因は、現代社会にあるのではないかという問題提起です。なるほどね。そうかもしれません。しかしですね、適応できていないのは、老人たちだけではありませんよ。中高年だって似たようなものです。「暴走中高年!(または暴走老人予備軍)」もたくさんいるわけです。
昔から、頑固じじいや意地悪ばあさんと呼ばれる人たちはたくさんいたはず。そういった昔の老人たちと現在の老人たちとの間に違いはあるのか、あるとすれば何なのか、そういう視点がもっと欲しかった。一番大きな違いは、時代ですけど。
著者は芥川賞作家ですが、老人をテーマにするのであれば、もっと老人と接してみて、よく観察し、研究・考察してもらいたいですぬ。
タイトルにだまされてはいけません。要注意。