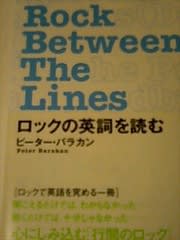新潮文庫「走れメロス」の中の短編で、女生徒の独り言のような形で文章が続いていきます。これを書いたときの太宰は30歳。30歳の男が、女学生の口調で文章を書いているという光景を想像すると…… ちょっとコワイですか。でも、ぼくは彼の気持ちが少しわかるというか、似たような経験があります。
昨年、学校の課題でロアルド・ダールの「アンブレラ・マン」という短編を訳しました。その主人公(語り手)が12歳の女の子で、その女の子の口調で文章を作っていく。これが意外に快感。「オ、オレって、けっこうかわいい」とか思いながら(笑)、自分が女の子になったような錯覚に陥るのです。
「人間失格」くらいしか読んだことのない人におススメです。太宰のイメージが少し変わるでしょう。
太宰治 女生徒
昨年、学校の課題でロアルド・ダールの「アンブレラ・マン」という短編を訳しました。その主人公(語り手)が12歳の女の子で、その女の子の口調で文章を作っていく。これが意外に快感。「オ、オレって、けっこうかわいい」とか思いながら(笑)、自分が女の子になったような錯覚に陥るのです。
「人間失格」くらいしか読んだことのない人におススメです。太宰のイメージが少し変わるでしょう。
太宰治 女生徒