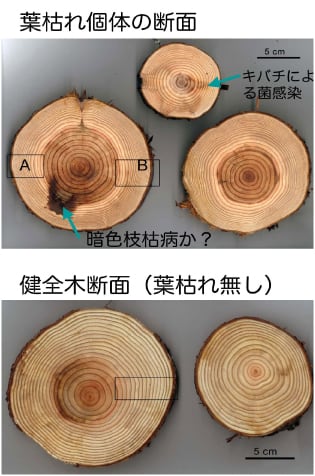昨日 びわ湖の東側の森林の持続ある流通を
どうして行こうかなーという集まりに行った。
そこで 山の仕事をされている永源寺の方と話をした。
炭焼もされているそうだが 岩魚も育てておられるらしい。
岩魚は 清流にしか住めない。
永源寺は かなり上流で川に生活排水が流れているわけではない。
かなり前から 天然の岩魚は獲れなくなっているのは知っていた。
炭を入れから岩魚が育つようになったという事だ。
そんな上流の川の水質が悪いという事は
森林から流れてくる水が ヤバイという事である。
それも かなり前から・・・。
今まで 結びついていなかったことに 愕然とした。
水は 水。 森林は 森林じゃなかったのよねぇ。
12月1日に ブックマークにある「炭は地球を救う」の
炭作さんの奥矢作で「だいず先生…」の名古屋大の
高野先生が進行役をされてシンポジウムがある。
永源寺の方にも以前資料を送ってあった。
昨日 お会いして
「シンポジウムの事 教えてもらってうれしかった」と
言って頂いた。もちろん 参加される。
この方も 炭窯の近くの木が元気な事を実際に知って
いる人だ。
もう一人 霊山の山で仕事をされている方も
最近 山の樹に元気がない事に気がつかれとの事なので
炭を森林に還して 元気にしたいという話をしたら
ぜひにと言われて 一緒に行く事になった。
永源寺から 多賀 彦根に続く鈴鹿山脈で仲間が
少しづつ増えつつある。
シンポジウムの詳しいことは 炭作さんのブログを
ご覧下さい。
どうして行こうかなーという集まりに行った。
そこで 山の仕事をされている永源寺の方と話をした。
炭焼もされているそうだが 岩魚も育てておられるらしい。
岩魚は 清流にしか住めない。
永源寺は かなり上流で川に生活排水が流れているわけではない。
かなり前から 天然の岩魚は獲れなくなっているのは知っていた。
炭を入れから岩魚が育つようになったという事だ。
そんな上流の川の水質が悪いという事は
森林から流れてくる水が ヤバイという事である。
それも かなり前から・・・。
今まで 結びついていなかったことに 愕然とした。
水は 水。 森林は 森林じゃなかったのよねぇ。
12月1日に ブックマークにある「炭は地球を救う」の
炭作さんの奥矢作で「だいず先生…」の名古屋大の
高野先生が進行役をされてシンポジウムがある。
永源寺の方にも以前資料を送ってあった。
昨日 お会いして
「シンポジウムの事 教えてもらってうれしかった」と
言って頂いた。もちろん 参加される。
この方も 炭窯の近くの木が元気な事を実際に知って
いる人だ。
もう一人 霊山の山で仕事をされている方も
最近 山の樹に元気がない事に気がつかれとの事なので
炭を森林に還して 元気にしたいという話をしたら
ぜひにと言われて 一緒に行く事になった。
永源寺から 多賀 彦根に続く鈴鹿山脈で仲間が
少しづつ増えつつある。
シンポジウムの詳しいことは 炭作さんのブログを
ご覧下さい。