法律不遡及の原則
法律不遡及の原則を、今頃習っている。
法律不遡及の原則とは、ある法律の、効力が生じる前に行われた行為については、その法律の効力は及ばないという原則である。通常、人はある行為を行うとき、その時点で有効である法律の効果が生じることを予期しているが、これを担保するのがこの原則である。さもなければ、人々の予期は否定され、社会生活を営む人々の合理性が損なわれ、その時点で合法であった行為について法的紛争が生じる、恐れがある。
しかしながら、あらゆる法律においてこの原則が及ぶのではない。
例えば、ある時点から金利の限度額を制限する法律が施行された場合、この法律の解釈として、金利の限度額を超えるような契約を行ってはいけないと解する場合と、金利の限度額をこえるような状態を許してはいけないと解する場合に、法律不遡及の効果が変わってくる。前者の場合には、この法律に照らして、過去において金利の限度額をこえる契約を結んだ場合には、その金利は現在においても有効であるが、後者の場合にあっては、この法律の定める限度額まで、金利を縮減する必要がある(この場合、法律不遡及の原則は守られている)。
また、法律不遡及の原則は立法の原則ではないため、法的に確定するためには、法律の条文に書きこむことが賢明であり、書きこんでない時には、具体的・個別的に解釈する必要が生じる。
また、戦後の民法大改正のときには、「家」を中心に個人の尊厳や男女の本質的平等を犠牲にした古い価値観を刷新しするため、一般的に遡及効が認められたことがあった。とはいえ、既成事実を重視して、この改正前にすでに戸主が死亡するなどして長男に家督相続をした場合などにおいては、改正後においても遡及効は認められないとされた。
以上
法律不遡及の原則を、今頃習っている。
法律不遡及の原則とは、ある法律の、効力が生じる前に行われた行為については、その法律の効力は及ばないという原則である。通常、人はある行為を行うとき、その時点で有効である法律の効果が生じることを予期しているが、これを担保するのがこの原則である。さもなければ、人々の予期は否定され、社会生活を営む人々の合理性が損なわれ、その時点で合法であった行為について法的紛争が生じる、恐れがある。
しかしながら、あらゆる法律においてこの原則が及ぶのではない。
例えば、ある時点から金利の限度額を制限する法律が施行された場合、この法律の解釈として、金利の限度額を超えるような契約を行ってはいけないと解する場合と、金利の限度額をこえるような状態を許してはいけないと解する場合に、法律不遡及の効果が変わってくる。前者の場合には、この法律に照らして、過去において金利の限度額をこえる契約を結んだ場合には、その金利は現在においても有効であるが、後者の場合にあっては、この法律の定める限度額まで、金利を縮減する必要がある(この場合、法律不遡及の原則は守られている)。
また、法律不遡及の原則は立法の原則ではないため、法的に確定するためには、法律の条文に書きこむことが賢明であり、書きこんでない時には、具体的・個別的に解釈する必要が生じる。
また、戦後の民法大改正のときには、「家」を中心に個人の尊厳や男女の本質的平等を犠牲にした古い価値観を刷新しするため、一般的に遡及効が認められたことがあった。とはいえ、既成事実を重視して、この改正前にすでに戸主が死亡するなどして長男に家督相続をした場合などにおいては、改正後においても遡及効は認められないとされた。
以上










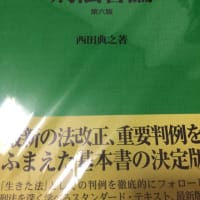
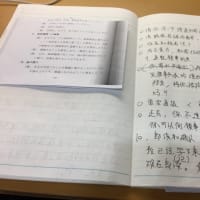
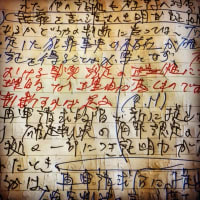

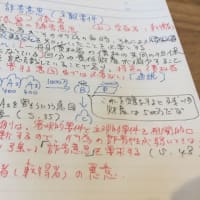
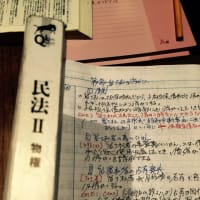
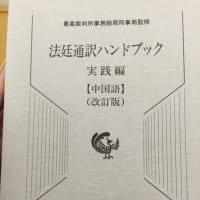
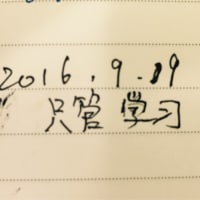

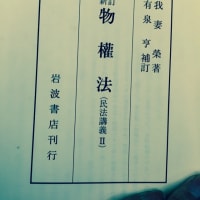
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます