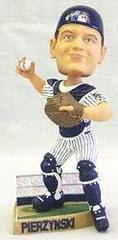
(リードも肩も一流ではないが、優れた「野球頭脳」を持つA.J.ピアジンスキー)
スカパー!MLBライブのコメンタリー陣(レギュラー)には、プロ野球選手経験者はいない。プロ野球の現場で仕事をしていたのも、横浜大洋ホエールズ・横浜ベイスターズで通訳や外国人選手スカウト、国際担当理事だった牛込惟浩さんと、アトランタ五輪野球競技日本代表チーム、横浜ベイスターズ、NYメッツ、SFジャイアンツで通訳などを務めた小島克典さんだけで、あとは野球界という業界の人たちから見れば、私を含めて「シロウト」の集団である。また実況アナウンサーでも節丸裕一さんや近藤祐司さんのように、局アナの経験がない人たちもいる。
こうした顔ぶれが揃っていることもあって、スカパー!MLBライブでコメンタリーが「技術論」を口にすることをあまり快く思わない人が、野球関係者ばかりでなく、視聴者やファンの間にも存在することは認識している。あくまでも好意からではあるが、あるプロ野球OBの解説者はコメンタリー陣のひとりに「中継で技術論はしゃべらないほうがいい」と忠告したことがあったそうだ。また現在、NHK-BSのメジャー中継で解説者が全員プロ野球OBになっているのも、ある超大物OBが「野球中継にシロウトの解説はいらん」と局の幹部に言ったのがきっかけだったとも耳にしたことがある。そういえば野茂英雄がドジャースでデビューした前後から、パンチョこと伊東一雄さんをはじめ、非プロ野球OBの解説者が次々とNHK-BSから姿を消し、困惑した記憶がある。一応「同業者」なのであまり悪口めいたことはいいたくないが、正直なところ、現在のNHK-BSのメジャー中継で聞きたいと思う解説は、今季から加わった長谷川滋利氏しかいない。引退後の彼は口先だけでなく本当の意味で「ネット裏での勉強」をしていると思うし、いずれはメジャー初の日本人コーチ、そして監督にも上り詰めるのではないかという期待が持てる。
さて今日、近藤さんと担当したカブス対ホワイトソックスのインターリーグ中継で、私も「技術論」をコメントする場面があった。7回裏一死から、カブスのリードオフマンであるファン・ピエールが三塁打で出塁したあと、二番打者トッド・ウォーカーの放った打球を一塁手のポール・コネルコが捕球するやいなや本塁に送球し、突入を図ったピエールが捕手のA.J.ピアジンスキーのブロックに阻まれ憤死したプレーについてである。
このプレーの判定は微妙で、ピエールがホームに滑り込んだ瞬間には、彼の左手がプレートをタッチするのが早かったようにも思えたし、コネルコの送球を受けたピアジンスキーもいわゆる「追いタッチ」だったようにに見えた。
ところがリプレイを見ると、一塁からの送球を捕球したのとほぼ同じタイミング(実際には0コンマ数秒早かったかもしれないが)で、ピアジンスキーが自分の左足をピエールが滑り込んでくると予想される位置に移動し、微妙にホームプレートをふさいでいたのである。先日、中日ドラゴンズの福留孝介が本塁突入を図った際にも議論の的になったが、野球規則ではキャッチャーは本塁に突入してくる走者に対して、完全にホームプレートをふさぐことは禁じられているが、ピアジンスキーは合法と違法のラインギリギリのライン上で実に頭脳的なプレーを見せた。もちろん、躊躇なく本塁に転送したコネルコの好判断も賞賛されるべきだろう。
さて、私はこのプレーについて、直後に実にいい角度からのリプレイが流されてきたこともあって、かなり詳しくその内容についてコメントした。帰宅して録画を見ても、この場面での私のコメントは単純な「感想」ではなく、確かに「技術論」にまで言及していたと思う。スカパー!のコメンタリー陣に対しては、おそらくこうしたことを指して「技術論を語るな」という意見が向けられるのだろう。
しかし、私からすれば大きく二つの点で反論したいことがある。まず、プロ野球OBの解説者は全員、こうしたプレーがあったとき、きちんと「玄人の意見」を視聴者に伝えているのかということだ。ハッキリ言ってしまえば、もし地上波のプロ野球中継で今日のコネルコとピアジンスキーが見せたようなプレーがあったとしても、かなりの確率で、実況アナウンサーはゴールの絶叫を連発したあのヒトのように、ただただ「超ファインプレーです!」と叫ぶのみだろうし、解説者はコネルコやピアジンスキーのプレーを賞賛するよりも、ピエールの「暴走」を責め立てるのではないだろうか。しかし「野球解説」に必要なのは、野球規則を踏まえた上で、メジャーで一、二を争う超俊足のピエールに対し、コネルコが飛んでくる打球とそのあと自分がすべきプレーをシミュレーションしていたからこそ、あの躊躇のない本塁送球が生まれたのであり、またピアジンスキーがいかに野球規則ギリギリの線でピエールの進路をふさいで彼の本塁タッチを遅らせたかを、それこそ「プロ」の目で語ることであるはずだ。また、ピエールの本塁憤死を責めるなら、その背景にあるカブスの不振やダスティー・ベイカー監督の采配を「詳細に」解説しなけらばならない。しかし残念なことに日本の地上波プロ野球中継に携わるアナウンサーや解説者の多くは、こうした仕事の本質を忘れた実況をして、結果として視聴者の離反を招いている。
そして、コメンタリー陣のキャリア(プロ野球OBでない)という見方に対しては、私を含めてお金をもらって放送でしゃべったり物を書く仕事をしている以上、確かに「元プロ野球選手」ではないが、決して「野球のシロウト」ではないのだと反論したい。むしろ今日のコネルコとピアジンスキーが見せたようなプレーがあった場合、それを詳細に分析・解説することを忘れたり二の次にして、バカみたいに絶叫したり、ピエールの本塁憤死を責め立てるようなことばかり口にしたり書いたりしたら、私は仕事をなくすことになるだろう。ファインプレーの価値判断は見る人によっても異なる。しかし、少なくともプレーの巧拙を見分ける最低限以上の「観察眼」「鑑識眼」は持ってこの仕事をしていると私は自負しているし、他のコメンタリー陣も同様、あるいは私以上だと思う。
芝居、特に歌舞伎の世界には昔から「見巧者(みごうしゃ)」という言葉がある。「goo辞書」によれば「芝居などを見なれていて、見方のじょうずな・こと(さま)」を意味するのだが、この言葉を私に教えてくれたのはスポーツライターの玉木正之さんだ。玉木さん、あるいはコラムニスト・翻訳家の芝山幹郎さんなどは、まさにスポーツの世界における「見巧者」と呼ぶにふさわしい人だし、私もベースボールについて書いたり話をしてお金をもらっている以上、まだまだその域には及ばないとしても野球において「見巧者」であることをめざしたいと思う。
日本において、メジャーリーグ野球の最高の「見巧者」であったのは、言うまでもなく今はなきパンチョこと伊東一雄さんだ。伊東さんといえば、そのアメリカ野球に対する博識ぶりが今でも語り草になっているが、いわゆるトリビア的な知識だけでなく、少年時代から戦前の職業野球に足を運ぶなど数多くの試合を見続けたことにより、何よりもプレーの巧拙を見分けて視聴者に紹介する観察眼・鑑識眼が優れていたからこそ、日本におけるメジャーリーグの第一人者になれたのである。伊東さんはメジャー中継で選手を紹介したりプレーについてコメントする際、視聴者に分かりやすいように日本のプロ野球選手をたとえや引き合いに出すことがよくあった。日本プロ野球史上最高のショートストップである吉田義男さんの野球史における価値など、私は伊東さんに教えてもらったようなものだ。その伊東さんの師匠だったのは、これまた日本の野球評論や実況中継解説のパイオニアである中沢不二雄さんだった。
昔といわずつい十数年前までは、現在もCSの「プロ野球ニュース」でキャスターを務めている佐々木信也さんや、今季殿堂入りを果たした豊田泰光さん、あるいは元TBSアナウンサーの渡辺謙太郎さんや現在同じ中継でコンビを組んでいただいている石川顕さんなど、野球・スポーツ中継における「見巧者」が何人も存在した。しかし、いまスポーツ中継に携わるアナウンサーや解説者に、果たしてどれぐらいの「見巧者」が存在するのか?
プロ野球OBの解説者がもし「技術論はオレたちの領域」と言うのであれば、単に「自分の経験談を披露するだけ」のコメントではなく、「自分の経験も照らし合わせての」技術論を大いに聞かせてもらいたいものだ。ここでは実名を挙げないが、地上波の解説者のなかには、この人に「お前みたいなシロウトが技術論を語るな」と言われたら、大いに反論に転じるであろうと思われる人が数人いる(まあ、だいたい想像はつくでしょうが=笑)。
もちろん、事実の誤認や見当外れのコメントもあるだろう。しかし、現在の私は、そしてこれからの私も、「しゃべりっぱなし」「書きっぱなし」のままで生活ができるほどの余裕はない。ピアジンスキーに関して言えば、昨年の対インディアンス戦で高津信吾が1イニング3本塁打を浴びてセーブを失敗した試合に見られたように、リード面ではお粗末なところが少なくないし、盗塁阻止率も低い。ただ、今日見せたプレーや、昨年のア・リーグ優勝決定戦での「疑惑の振り逃げ」の際に垣間見せたように、「野球頭脳」は非常に高い選手だ。また人間的にも(つまらないトラッシュトークをして相手からパンチをお見舞いされる「お子ちゃまぶり」はまだ見受けられるが=笑)、ジャイアンツ在籍時に投手陣から総スカンを食らった当時から見れば格段に成長している。私はこういう成長する選手が好きだし、チャップリンの有名な言葉「Next One(次回作を見てくれ)」は、現在のピアジンスキーにそのままあてはまるのではないだろうか。そして、野球について物を書いたり話したりする自分の仕事においても、私は「Next One」を座右の銘にしていきたいと考えている。
追記:今日の中継の終了間際、試合を回顧するところで、近藤さんにいきなり「いかがでしたか、牛込さん」と話しかけられて一瞬硬直したあと、思わず「いや、もう少し若いんですが……」などと失礼なことを口にしてしまいました(笑)。いや、牛込さんに間違えられたのは光栄ですし(牛込さんからすれば「ふざけるな」でしょうけど=笑)、あくまでも「いつまでも若い牛込さんよりももう少し若い」と言う意味で言ったのですが(笑)。それにアメリカから持って帰るのも私は「フォアローゼズ」ぐらいですが、牛込さんはものすごく素晴らしい「薔薇」を持ち帰りましたからねえ(これでフォローになっただろうか=笑)。




















しかし、私は一視聴者時代から思っていましたが、プロ出身の解説者の方々の「技術論」は高度なあまり時に感覚的、観念的に過ぎ、一般視聴者の理解を超えています。基本的には多くの視聴者の方(私も含め)に理解してもらえるのは「戦術」「選手起用」百歩譲って「投球の組み立て」まででしょう。一部のプロ出身の方の指摘する「微妙なテイクバックの取り方」的な技術論は理解を超えています。生意気を言わせていただくと彼らの発言はそういう技術論意外は「変わった選手のところに打球が飛ぶんですよねエ」的な非科学的なものが多いように思えます(そういうマンネリ感も嫌いではありませんが)。
コメンテーターの仕事において、旬なそしてトリビアなメジャー情報をお届けすることは大事な要素ですが、やはりゲ-ムを中継しているわけですから試合展開や個別のプレーを評論せずは点睛を欠くと言わざるを得ません。素人代表のコメンテーターとしてもできる限りの勉強をして「技術論」にもドシドシ入っていきたいと思います。そしてその技術論もプロ出身者的な感覚的なものではなく、たとえばデータの裏付けがある等客観的かつロジカルなものでありたいですね。
私が辟易させられるのは、「バットを構えるときは、立小便をするときの感覚で打席に立って」と解説するあのヒトですかね。最近は「喝!」でも有名ですが(笑)。まあ言わんとすることはわからなくもないけど、軽犯罪法違反ですからねえ(笑)。あまりにも言ってることが観念的過ぎるので、一緒に中日-巨人戦の解説をしていた近藤貞雄さんに「そんな高度なことはあなたぐらいのレベルに達しないと誰にも分かりませんよ」と思い切り皮肉を言われていたことがありましたね。私は先週の試合で思わず1回使ってしまったのですが、「キレ」という言葉の使い方も考え直す必要があるでしょうね。私は少なくとも速球が「キレる」という表現には違和感を感じるのですが。まあできれば速球は「伸びる」、変化球は「曲がる」「落ちる」「ブレーキがかかる」、体は「動きがスムーズ」など、別の表現にしたほうがいいかなと考えています。
僕は一般企業に勤務してから今の仕事に転身したため、
アナウンサーとしてのキャリアは、大勢いる同期の友人より5年以上も遅れてスタートしたわけです。
最初の頃はいつも「実況するのは素人でも、実況を聴くのは玄人だぞ」と思っていましたね(笑)。
視聴者としては5年以上も経験豊富なわけで、それを放送に活かさなくては、と思っていました。
プロ野球選手の経験は全くなくても、多くの試合、多くの選手、多くのプレイを見てきた経験は、放送でどんどん活かしていくべきだと思いますよ。
“技術論”と言っても、プロ未経験者でも分かることは多々あります。表現に気をつければ許されると僕は思います。
ただ、経験者でなければ分からないか、分かっても未経験者の言葉では説得力に欠けるレベルのものについては、
ぐっと我慢することも必要なのかもしれません。
僕も野球を伝える側の一人として、大先輩方に負けないような「見巧者」を目指したいと思います。
プロ経験者に聞きたいのはそんなことじゃなくて、場面場面での当事者の心理面です。これこそ経験者の強みだと思うのですがねえ(苦笑)
話は変わりますが「メジャーリーグのバッティング技術」(JDC出版)という本はご存知でしょうか?著者である塚口洋祐氏はプロどころか高校時代は硬式野球ではなくソフトボールの経験者だそうです。
ところがこの本を、オリックスに移籍した清原が読んで参考にしたとか。
肉体的にはガタガタですが、あれだけのベテランが、まだ上手くなろうとして手に取った技術書が、元プロが上梓したものではなかった事実をしったら、「喝」の長老はどう思うでしょうね。
スカパーのMLB Liveを好きなのは、野球経験者ではない皆さんのコメンタリーに、エンタテインメント性を大きく感じるからです。
#さまざまな角度からそれぞれのプレーに光をあててコメントされるとまたその方のコメントをききたくなります。(プロ野球経験者のコメントは、往々にして、ひとつ、よくて二つ三つぐらいの角度からしか光をあてることができないので)
日本の野球中継を、スカパーでも、あまりみたくない理由は(地上波では変なタレントがでてきてぶち壊すからなおさら)、プロ野球出身者の解説があまりにエンタテインメント性に欠けていてつまらないからです。(奥さんの内助の功の話しや、「ここは気合いで」などというつまらない精神論を延々とききたくない)
#「ここは気合いで」という話しが、例えば、前の打席で死球を受け、腰がひけている打者に、「踏み込んで行く勇気を持たないと、今後、プロでは食べて行けませんから、ここは(恐がらず)気合いをいれて」という具体的な話しならわかるのですが、ただ状況説明もせず、ノーアウト満塁の場面で新人選手が代打ででてきて「○○さん、若いのだからここは気合いしかありませんよ」とアナウンサー相手に叫ぶだけだったら、解説者はいりません。
技術論:
野球経験者ではない方々が、野球経験者でしかわからない部分を知ったかぶりして「あそこはこうだから」とコメントされるのは、たしかにおいおいなのでしょうが、たくさん野球をご覧になっている野球経験者ではない方々が、玄人の野球観戦者として、その立場から技術論をコメントされるのは、ありでしょう。
#立場が違うとまた面白い見方があるはずです。
余談ですが、
私はW杯の中継を、画像は地上波のライブ中継、音声はスカパーのDATA放送(スカパーはライブ中継できないので、スタジオで複数の解説者がTVをみながら和気あいあいとお茶でも飲みながらコメントしあっている)でみています。
#地上波のアナウンサーは、普段海外のサッカーを中継をしてしない方達なので、かなりの有力国でないと勉強不足が露呈してしまうが(スペインの国王の名前もちゃんと言えなかったり、ペルニアという選手を最初から最後までヘルニアと呼んでいたりしていてがっくりしました)、スカパーのアナウンサーや解説者は普段スカパーで海外のサッカーを中継している人達なので、雑談形式のライブ番組をきいていても、横にサッカーの元選手の友人がすわっていて一緒に飲んでいるような雰囲気があるので、音声だけでも楽しいのです。
#相撲で親方達の解説をきいていてもつまらないとおもったことはあまりなかった。彼らの技術論が、精神論にかたよらず、的確だから?
今ひとつ理由がわからないのですが・・・。
やっぱり話す訓練をしていないからかな~。MLBの場合、元選手でも徹底的に話し方を鍛えられると言われていますよね。
現場でちっともお会いできない小島克典です。(あ、松原さんは先週お会いしましたね…)
ネットサーフしてたらこのページにたどりついて、フムフムそーだよその通りだよな!と読みふけりました。同時にすっかり忘れてた記憶がフラッシュバックして来たので、忘れないうちに書き残しときます。
サンフランにいた時、スランプに陥ったデビット・ベル(現フィリーズ)が「開幕の頃と今(確か6月前半)のメカニック、どこか違うところある?」と聞いてきたことがありました。日本から来て数ヶ月の、外国人のボクに、です。
ショーン・ダンストン(もう引退)に至っては、シーズン終盤のミーティングで「うち(SF)にはビデオコーチもいるんだから、彼らも活用しようよ」とフツーな顔して言い放ったのを強烈に覚えています。
なぜなら…。ボクを含めて3人いたビデオコーチは誰ひとりとして、プロでプレーした経験がなかったからです。
その時ボクは、この仕事に就けた喜びを感じました。誇りを持って仕事しようって思いました。だってプレーオフ争いしてるバリバリのメジャーリーガーが、日本で言うシロートの僕らを頼ってきたんですから。。
ショーンの言葉を聞いてから、ボクの仕事は「志事」になりました。志(こころざし)を持って取り組む仕事になりました。顔色伺いながら、オベッカ使いながら、誰かに仕(つかえる)える仕事じゃなくて。
コメンタリーみんなで、いつか日本の常識を覆しましょうね。時間はかかると思いますが、現場の選手たちも、ベテランOBたちも、いつかきっと変わりますよ。。。
「志事」っていうのはいい造語ですね。私が出版社で編集者をしていた当時痛感していたのですが、不特定多数に情報を発信するメディアに勤務していながら、その自覚がない、そして仕事に対する使命感や志が皆無としか思えない同僚や後輩を見て、情けない思いをしたことがあります。
MLBで小島さんが経験したベルやダンストンの話を読んで思い当たるのは、最近でこそそういう人はいませんが、1920年代ころまでのMLBには、選手経験がない監督が何人かいたことも影響しているのではないかと思います。たとえば1918年にレッドソックスをワールドシリーズ制覇に導いたエド・バーロウはもともと新聞記者出身で、その後マイナーリーグの経営者を経てメジャーのフロントで要職につくようになった人です。彼の監督として最大の功績といえば、ベーブ・ルースを投手から打者に転向させたことですし、その後彼はヤンキースにGMとして引き抜かれ、30年代以降の黄金時代を築き、のちに殿堂入りも果たすわけです。
昔、よくパンチョ伊東さんや八木一郎さんがよくメジャー中継の解説で話したり、記事で書いていたのですが、メジャーやアメリカの野球メディアには「野球を監督よりも知っているのはGM、さらによく知っているのはラスベガスのオッズメーカー」という言い伝えがあるそうです。オッズメーカーに関してはなんともいいようがないのですが、GMに関しては間違いなくそのとおりで、ヤンキースのキャッシュマンやレッドソックスのテオ・エプスタインのように、プロ選手としての経験がない人はもう珍しくありませんからね。取材に行くたびに痛感するのですが、確かにあちらの球界では「プロ野球選手」とともに、フロント、球場運営、メディアに「野球のプロフェッショナル」が大勢います。
もちろん、ピント外れのことを書いたりコメントした入れば、逆に選手経験のないことを逆手に取られてとんでもないことになりますから、不断の「理論武装」が必要であると考えています。私にとってバイブルになっているのは、ウォルター・オルストン(もとドジャース監督)が書いた「現代野球百科」です。30年以上前に書かれた本なので現代の野球に合わない記述もありますが、それでもベースボールというスポーツを深く理解するには必要不可欠の一冊だと思います。
あ、それから先週小島さんが「On The Field」でアピールしていた「ナ・リーグ強化キャンペーン」、あれは私も大賛成(笑)。やはり単純な地区分けの「カンファレンス」でなく、別々のポリシーを持って創設された「リーグ」である以上、インターリーグでもオールスターでもワールドシリーズでも、どちらかが一方的に勝ち続けるのはいい傾向ではありませんからね。それに私は松坂大輔をナ・リーグのチームに行かせたいので、ナショナルが弱すぎるのは困るんです(笑)。