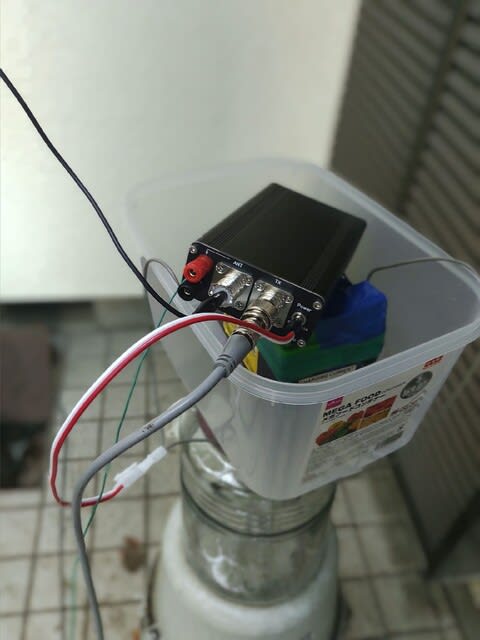
カーボンアンテナは普通垂直型の構成になるので、もう一方の端子をグランドしなければならない。実際にいわゆるアースをするわけにはいかないので、電線をその辺に転がしてカウンタポイズという構成をとるのが普通である。参考文献によれば、ラジアルは電波の放射を行うエレメントなので地面から離して長さも1/4λに合わせることになっている。これに対してカウンターポイズは地面に這わせて設置し長さも適当でよく、何本も設置して仮想グランドとして動作するということになっている。しかしながら、結局どちらの構成でもアンテナエレメントの反対につないだ電線であるわけで完全に別物というわけにもいかないだろう。カーボンアンテナの場合もカウンターポイズとして電線をつなげたが、その長さは性能に影響を与える可能性もある。そこで今回はカウンタポイズの長さの影響を調べた。SOTAの時にメインで出ている14と21MHzの性能を比較した。
実験条件:カーボンロッド:8.6mに銅線を接続(長さW)
CP=5.5m
W (m) 7.6 6.2 5 4.2
14MHz -2 -5 -2 -4
21MHz -2 -5 -1 -1
数値は常時設置してあるEFHWの受信レベルを基準にした時のカーボンのRBN相対レベル。(自宅から3.5km離れた局のデータを使用)銅線の長さによって多少の変動はあるが、すべてマイナスでEFHWアンテナに比べてあまり電波は飛んでない印象となった。次にカウンターポイズを0として実験を行った。
CP=0m
W (m) 8 7.5 6.5 4.4
14MHz +1 +1 -1 +1
21MHz +5 +4 +4 0
カウンターポイズ無しで測定したところ、いずれもEFHWを上回るレベルで予想に反してよい性能となった。
カウンターポイズをなくしたらなぜ性能がよくなったのか。それは、そこから電波が無駄に放射されていたということではないだろうか。そもそもカーボンロッドに銅線をつける方式は、
①アンテナを長くしての放射抵抗を大きくして
②カーボンロッドに流れる電流を小さくし、
③カーボン抵抗による熱損失を小さくする。
ことを狙ったものである。カーボンロッドを流れる電流が減るが、銅線のエレメントにも電流を流れるので、そこからも電波を放射される。効率よく電波を輻射するために、できれば銅線も地上から離す方が良い。地面に接しているカウンターポイズも短くした方が結果が良かったのは、カウンターポイズからも電波が輻射されていたことの証左ではないだろうか。
共振周波数の測定
アナライザーで調べてみると、8.6mポールのみの場合の並列共振周波数(1λ)は32.1MHz、1/2λで16MHz程度となる。14MHzは半波長以下、21MHzは半波長以上。
また4.4mの銅線をつなげたとき(全長13m)の並列共振周波数は25MHz、1/2λで12.5MHzとなる。14,21MHzともに半波長以上の長さとなる。
チューナーでのマッチングを行うので、エレメント長さを1/2λにぴったり合わせる必要はない。実際エレメントの長さに対する性能の変化はブロードだった。ただ、あまり長くなると放射パターンが崩れるので大体このあたりに収めておくのが望ましいのではないだろうか。インピーダンスが高くなってチューニングが困難な場合はエレメント長さを多少調整する。
まとめ
今回の実験の結果より、14,21MHzでの特性を考えると、8.6mのカーボンロッドに、6から8mの銅線エレメントを追加、マッチングが取れればカウンターポイズ無しの構成にしてEFHWと同様あるいはそれ以上の結果が得られた。できるだけ銅線エレメントも地上から高い場所に設置する。










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます