
私が中、高校生の頃、テレビで”オヤコ鷹”という連続時代劇ドラマが放送されました。
少年期の勝海舟とその父親である勝小吉が主役でした。
内容は覚えておりませんが、とても面白かった記憶があります。
この本の、”氷川清話”は勝海舟が、序盤では、その生い立ちや、幕末から明治維新までの活躍の自慢話を書いたものです。
中盤以降は、自分が接した多くの人物(50名以上)を上から目線で評価しています。
さらには、会ったこともない歴史上の人物まで評価しています。
実践的な行動力に優れていたことは確かでしょうが、自慢が鼻につきました。
ただ、江戸っ子のべらんめえ調の文章は、口語体で、楽しめました。
しかし、なんといっても面白かったのは、勝小吉の自伝である、”夢酔独言”です。
42歳になった小吉が ”男たるものは、決して俺がまねをばしないがいい。
孫やひ孫ができたらば、よくよくこの書物を見せて、身のいましめにするがいい。” という考えから著した自伝です。
6歳の時に旗本勝家の養子となり
7歳の時に他家の子供との喧嘩の罰として30日間座敷牢に入れられます。
13歳で最初の家出するも3ヶ月で帰宅。
20歳で再び家出し、帰宅後は座敷牢に2年以上入れられます。
柱に細工をして、いつでも脱走できる状態でありましたが、心機一転を計るため、あえて留まり、読書にふける毎日を過ごします。
その後、剣術や柔術の腕っぷしと、弁がたつことを活用して有名人になっていきます。
なんというか、清水の次郎長的な、頼りにされるし、世話も焼くという人物像が頭に浮かびます。
小吉と海舟に共通する才覚は経済に明るかった点です。
小吉は青年時代から刀剣の目利きとなり、売買で儲けていきます。
とにかく破天荒な少年が、そのまま大人になり、才覚を発揮していく様が正直に書かれていて、感動しました。










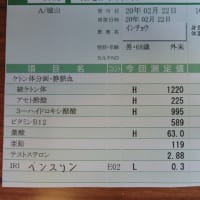
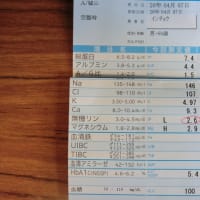
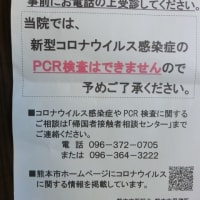

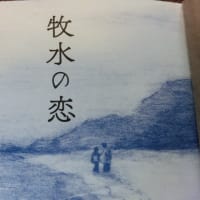
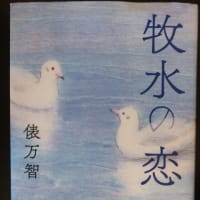
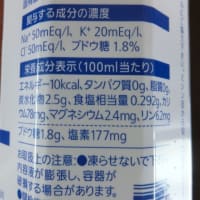


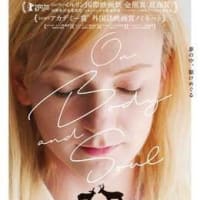
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます