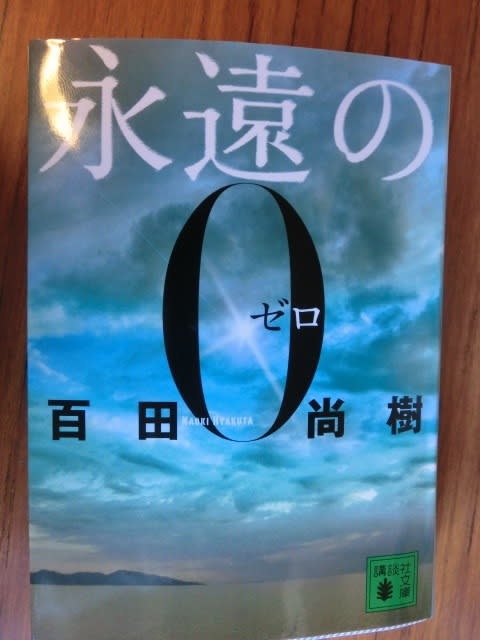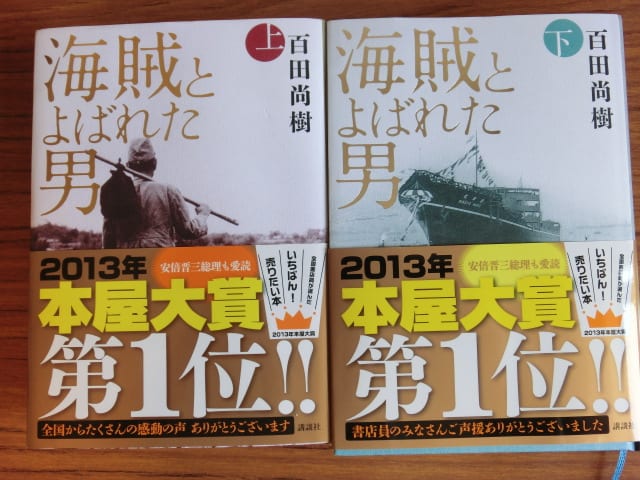この4日間は、ひたすら”1Q84”を読み続けました。
素敵な恋愛小説です。
とても情熱的でピュアな恋愛小説です。
ファンタジーの要素も強く、ハードボイルドなトーンも有るのですが、こいつは、まぎれもなく恋愛小説です。
しかし、ピュアな恋愛を夢物語と考える人にとってはファンタジー小説のカテゴリーに入るのかも知れません。
しかし、私は、この作品を恋愛小説だとみなします。
もともと、村上春樹は、”羊”シリーズなどの、ファンタジーだかなんだか訳の分からないストーリー展開が得意でした。
しかし、この作品に限って言えば、ちゃんと訳の分かる、エンタメ小説です。
個人的には、最高に楽しい作品でした。
村上春樹は隠喩の巧みさで有名ですが、この作品でも至る所にそれが認められました。
ネタバレにはならないので一部アップしてみます。
演奏が終わった後の拍手を長く聞いていると、終わりのない火星の砂嵐に耳を澄ませているみたいな気持ちになる。
二年の歳月が彼の身体から多くの物を持ち去っていた。まるで収税吏が、貧しい家から情け容赦もなく家財道具を奪っていくみたいに。
また、ドストエフスキーを思い起こすような描写もあります。
意地の悪そうな老人が、頭の悪そうな雑種犬を散歩させていた。
頭の悪そうな女が、醜い軽自動車を運転していた。
醜い電柱が、空中に意地悪く電線を張り巡らせていた。
世界とは、「悲惨であること」と「喜びが欠如していること」との間のどこかに位置を定め、それぞれの形状を帯びていく小世界の、
限りのない集積によって成り立っているのだという事実を、窓の外のその風景は示唆していた。
読み終えての満足度は100点です。
これほどの長編小説は、ジャン・クリストフや、魅せられたる魂以来ですが、没頭することが出来ました。
しかし、没頭した分、仕事も、ブログも、ゴルフの練習も、何もかもが、はかどりませんでした。