【4月12日は何の日】パンの記念日
【4月13日は何の日】水産デー
【4月14日は何の日】オレンジデー
【4月15日は何の日】いちご大福の日
【前の答え】お茶
Q1,美味しいボクを入れるポイントは4つ。
茶葉の( )
お湯の( )
お湯の( )
( )時間
→茶葉の量、お湯の温度、お湯の量、煎出時間
Q2,ボクの実は、何個の種子が一つにまとまっているでしょうか?
a,2 b,3 c,4 d,5
→b,茶畑の地図記号はここに由来します
Q3,ボクに含まれている、殺菌作用を持つ成分は?
a,カテキン b,カフェイン c,タンニン d,フラボノイド
→a,c,
【脳トレの答え】天むす
【正しく読むと?の答え】乖離 →かいり
【空欄にチャレンジの答え】〇む△い▢ →おむらいす
【今日の話】
「ばっか食べ」をしていませんか?
「ばっか食べ」とは、ご飯とおかずを交互に食べるのではなく、
一つずつ、そればっかりを食べる食べ方のことです。
近年、この「ばっか食べ」が増えてきているそうです。
和食は交響曲のようだ、なんていう言葉を聞いたことがありませんか。
複数の素材や味を組み合わせて
食材としての特徴をつくり出しているからそういうんです。
ところが残念なことに、寿司のネタを外して刺身として食べたり、
丼もののご飯を先に食べて後から具を食べるとか・・・。
ハンバーガーを、バンズと具に分けて食べることを考えれば、
ヘンなのがわかりますよね。
さて和食は、おかずの味で味付けしながら
ご飯を食べていくという独特の食べ方をします。
ご飯と主菜を一口食べたあと、ご飯と副菜を食べ、
その次にご飯と漬物を合わせて味わい、
さらにお味噌汁を飲みます。
この一連の流れは、ご飯と何かを一緒に食べているんですよね。
このような食べ方を口中調味というんです。
簡単に言えば、ご飯とおかずを口のなかで混ぜて、味を作るということなんです。
日本の食事は、昔から一汁三菜を基本にしてきました。
代表的なものが汁物に主菜、副菜、香の物でしょうか。
おかずをつまんだらご飯、味噌汁を飲んだらご飯・・・というように、
必ずご飯に戻ってくるように箸を動かします。
ご飯を食べずにおかずを食べると、しょっぱく感じます。
ご飯が基本だからこそ、主食なんです。
口の中でご飯とおかずを混ぜ合わせたとき、
唾液と混ざっておかずの塩分が薄められてちょうどいい濃度になります。
おかずとご飯はほどよく口の中で調味されて、美味しくなるんです。
目の前に、ご飯と味の濃い肉料理があるとします。
それを食べるとき、口中調味で食べていくと、少しの量のおかずでご飯を食べることができます。
そうしないとおかずの量も増えるので、多くの脂肪を摂ることになります。
口中調味は、味だけでなく、
高脂肪のものでも知らない間に脂肪分やカロリーをカットしたり、
その時の体調にあわせて調節することができるということなんです。
口中調味という食べ方は、
食べる人が自由自在に栄養バランスをコントロールできるという
優れた食べ方なのです。
また、口中調味という食べ方は、
味わいの面で高い文化性をもっています。
ぜひ、心がけてみて下さい。
Q1,一汁三菜の形式ができたといわれているのは何時代でしょうか?
a,平安 b,鎌倉 c,室町 d,江戸
Q2,一日三食食べるようになったのはいつからでしょうか?
a,平安 b,鎌倉 c,室町 d,江戸
Q3,日本で二食から三食に変わったのはどう変わったでしょうか?
a,朝食が増えた b,昼食が増えた c,夕食が増えた
【今日のひと言】「優しさ」「厳しさ」「明るさ」が、人格の三要素。
「人に優しく」「自分に厳しく」「希望や展望を失わず」。
「寛容」に「謙虚」に「前向き」に。
【今日の脳トレ】

【正しく読むと?】披瀝
【空欄にチャレンジ】〇つ〇れ△
【算数で楽しもう】
1 3 6 9 と+−×÷を使って、10をつくりましょう。
【4月13日は何の日】水産デー
【4月14日は何の日】オレンジデー
【4月15日は何の日】いちご大福の日
【前の答え】お茶
Q1,美味しいボクを入れるポイントは4つ。
茶葉の( )
お湯の( )
お湯の( )
( )時間
→茶葉の量、お湯の温度、お湯の量、煎出時間
Q2,ボクの実は、何個の種子が一つにまとまっているでしょうか?
a,2 b,3 c,4 d,5
→b,茶畑の地図記号はここに由来します
Q3,ボクに含まれている、殺菌作用を持つ成分は?
a,カテキン b,カフェイン c,タンニン d,フラボノイド
→a,c,
【脳トレの答え】天むす
【正しく読むと?の答え】乖離 →かいり
【空欄にチャレンジの答え】〇む△い▢ →おむらいす
【今日の話】
「ばっか食べ」をしていませんか?
「ばっか食べ」とは、ご飯とおかずを交互に食べるのではなく、
一つずつ、そればっかりを食べる食べ方のことです。
近年、この「ばっか食べ」が増えてきているそうです。
和食は交響曲のようだ、なんていう言葉を聞いたことがありませんか。
複数の素材や味を組み合わせて
食材としての特徴をつくり出しているからそういうんです。
ところが残念なことに、寿司のネタを外して刺身として食べたり、
丼もののご飯を先に食べて後から具を食べるとか・・・。
ハンバーガーを、バンズと具に分けて食べることを考えれば、
ヘンなのがわかりますよね。
さて和食は、おかずの味で味付けしながら
ご飯を食べていくという独特の食べ方をします。
ご飯と主菜を一口食べたあと、ご飯と副菜を食べ、
その次にご飯と漬物を合わせて味わい、
さらにお味噌汁を飲みます。
この一連の流れは、ご飯と何かを一緒に食べているんですよね。
このような食べ方を口中調味というんです。
簡単に言えば、ご飯とおかずを口のなかで混ぜて、味を作るということなんです。
日本の食事は、昔から一汁三菜を基本にしてきました。
代表的なものが汁物に主菜、副菜、香の物でしょうか。
おかずをつまんだらご飯、味噌汁を飲んだらご飯・・・というように、
必ずご飯に戻ってくるように箸を動かします。
ご飯を食べずにおかずを食べると、しょっぱく感じます。
ご飯が基本だからこそ、主食なんです。
口の中でご飯とおかずを混ぜ合わせたとき、
唾液と混ざっておかずの塩分が薄められてちょうどいい濃度になります。
おかずとご飯はほどよく口の中で調味されて、美味しくなるんです。
目の前に、ご飯と味の濃い肉料理があるとします。
それを食べるとき、口中調味で食べていくと、少しの量のおかずでご飯を食べることができます。
そうしないとおかずの量も増えるので、多くの脂肪を摂ることになります。
口中調味は、味だけでなく、
高脂肪のものでも知らない間に脂肪分やカロリーをカットしたり、
その時の体調にあわせて調節することができるということなんです。
口中調味という食べ方は、
食べる人が自由自在に栄養バランスをコントロールできるという
優れた食べ方なのです。
また、口中調味という食べ方は、
味わいの面で高い文化性をもっています。
ぜひ、心がけてみて下さい。
Q1,一汁三菜の形式ができたといわれているのは何時代でしょうか?
a,平安 b,鎌倉 c,室町 d,江戸
Q2,一日三食食べるようになったのはいつからでしょうか?
a,平安 b,鎌倉 c,室町 d,江戸
Q3,日本で二食から三食に変わったのはどう変わったでしょうか?
a,朝食が増えた b,昼食が増えた c,夕食が増えた
【今日のひと言】「優しさ」「厳しさ」「明るさ」が、人格の三要素。
「人に優しく」「自分に厳しく」「希望や展望を失わず」。
「寛容」に「謙虚」に「前向き」に。
【今日の脳トレ】

【正しく読むと?】披瀝
【空欄にチャレンジ】〇つ〇れ△
【算数で楽しもう】
1 3 6 9 と+−×÷を使って、10をつくりましょう。










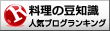



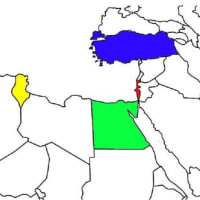

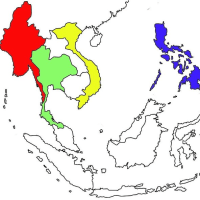





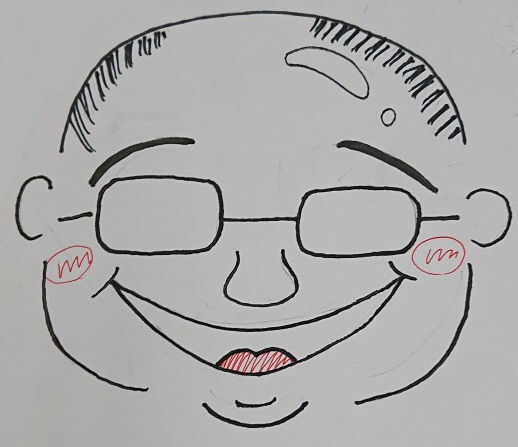
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます