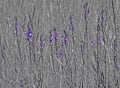夏空に、積乱雲が広がるのを見ていると、後立山連峰にかよった頃を懐かしく思い出した。もう半世紀も前、7月の今頃、岳友と会社をサボって八方尾根から鹿島槍の赤岩尾根へ縦走したとき、120㎏を担いだ“担荷さん”と20㌔のキスリングを担いだ私達が“追いつ追われつ”登った道すがら、“担荷さん”に教えてもらった八方池の美しさは、後に眺めたヨセミテのミラ―レイクやゴルナグラートのリッフェル湖より綺麗だと思っている、唐松小屋近くの草付き斜面に咲いたクロユリの群落、今も、鮮明に思い出す・・・・。
第7波のコロナ蔓延が近いと言うのに不謹慎である。・・・が今、行かなければジジイに来年は無いかも知れないのだ。山小屋も乗り物も、ひと月前から予約してある。連日の雨を覚悟で7月18日(海の日)“Julius Caesar Crosses the Rubicon.‼”のだ、と 阪急三番街からアルピコバスに乗りました。
良く揺れる夜行バスの旅はジジイには無理なのダ~。一睡も出来ないまま、八方尾根バスターミナルに着きました。泣きっ面に雨、ここで降りたのは3名のみでした。
バスターミナルで八方尾根ケーブル乗場までの距離を聞いたら“10分ほどだ、歩いたら?”と言うが、雨の中を歩くのは嫌だったからタクシーを呼びました。これが“大正解!”タクシーで登リ坂を8分余り要したから、もし歩いていたら雨の中、30分以上かかっただろう。
雨のためゴンドラ、リフトともガラ空きで、貸し切り状態でした。雨具を着ての乗り物でしたが、足元には花々が咲き乱れ、幻想的な景観を見せてくれました。今日(7月19日)が、もし天気だったら八方池をピストンするつもりでしたが、雨のため、予約したおいた八方池山荘(標高1,830㍍)に宿泊することにしました。
八方池山荘には朝早く着いたのですが、山荘は快く入れてくれました。三重県から来ているという受付嬢に何処か山の会に所属していますか?聞かれたので“JACで老醜を晒している”と答えたら、2階の個室へ案内してくれました。キャンセルが多かったのか、宿泊客は私を含め5人だけでした。お風呂もあったが、風邪をひきそうなので、やめました。
寝る前に、7月20日の八方尾根の1時間ごとの天気予報をみたら、6時~9時は曇り、10時太陽マーク、12時曇り、13時~18時太陽マークでした。

八方尾根ば、かつてはアルピニストの登竜門と云われていましたが、今ではゴンドラ、リフトを乗り継ぎ八方池山荘(標高1,830㍍)まで労せずして登れるようになり、今や私の様な高齢ハイカーやツアー登山者の対象となっています。
昨夜の八方尾根の1時間ごとの天気予報を信じて、6時朝食、7時、霧雨の中でしたが雨具を着けて飲み物、行動食を持って出発しました。因みに、八方山荘から八方池までは1時間30分の行程ですが道は、木道コースと山道コースに分かれています。登りは足元の安定している木道コースを選びました。木道が終わるあたりで、夜明けとともに八方池山荘を出発した若い女性二人が下山して来るのに出合ました。







木道が終わると山道コースと一緒になり、石神井ケルンの先にある建物(立派なトイレ)に着きました。ここには第二ケルンがあり、小広くなっていて、濃霧に見え隠れする八方尾根上部が少し見えました。ここから八方ケルン(標高2,035㍍)まで、急なゴロタ道の登りで20年ほど前に訪れた面影もない悪路になっていました。八方ケルンを過ぎたあたりで霧雨もあがり、白馬鑓ヶ岳、杓子岳、白馬岳の下の方が見えてきました。“展望案内版”から下の方を眺めると、僅かに雪田を残す八方池が見えまました。木道をくだって八方池の畔にある奥宮の祠に8時30分に着きましたが、残念ながら“八方池の美しい映り込み”は見られませんでした。目的の一つだったユキワリソウも、風が強くて思う様に撮影することが出来ません。
あきらめて、第三ケルンの立つ稜線へでると15㍍を超える強風で、立っているのがやっと、早々に八方ケルンから第二ケルンへと下りました。風もおさまったので雨具を外し、身軽になりました。
下りは、山道コース(尾根通し)を選びました。木道コースとの分岐から下を眺めると、天候が回復すると見たのか、続々とツアー登山の人達が登ってくるのが見えました。

10時過ぎ、ヤナギランが咲く八方池山荘にもどり、預けてあった荷物を回収して、下山しました。リフトの乗継点ではニッコウキスゲの大群落を散策しました。リフトの足元には、シモツケソウ、クガイソウ、クルマユリなどが咲き最高の美しさでした。“あずさ46号”を待つ、白馬駅から返り見する山々は、やはり厚い雲の中でした。(小さい写真はクリックで拡大します)