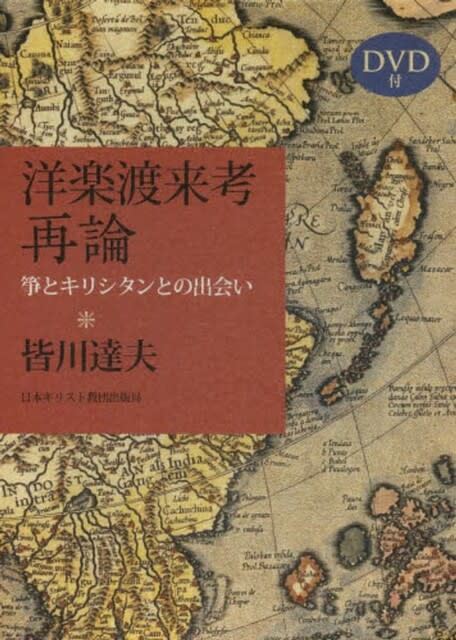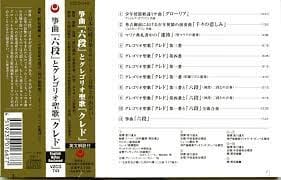会津藩祖保科正之が定めた『家訓』15箇条
その第一条は『大君の儀一心大切に忠勤に励み、他国の例をもって自ら処するべからず。若し二心を懐かば、すなわち我が子孫にあらず。面々決して従うべからず』
大君すなわち徳川将軍家にはひたすら忠勤に励み、決して背いてはならないというもの。これが幕末
他国の例にならって決めるべからず。徳川宗家に背く者は我が子孫に非ず。家臣の面々はそのような藩主には従」というもの。
その中に「婦女子の言は一切聞くべからず」の
一条を定めた。それは正之の室「聖光院お万」の所業に懲りたからだ。
「聖光院お万」は京都上賀茂神社の神官の娘で、東福門院和子の侍女
だった。東福門院和子は、徳川秀忠の五女。後水尾天皇の后として入内
していた。尚、保科正之も秀忠の子であり、和子の兄となる。
そんな関係からか、正之の室となったお万は、なにかと藩政に口出しを
するようになった。
さらに、とんでもない事件が起きる。お万の娘「媛姫」は上杉 30万石に
嫁いでいたが、側室の生んだ「松姫」が加賀100万石前田家に嫁ぐことと
なり、お万は、嫉妬して「松姫」を毒殺しようとしたのだ。
「松姫」が婚礼の挨拶に訪れた際、「媛姫」も同席して食事となった。
「松姫」の膳に毒を盛ったのだが、松姫の侍女が機転をきかせて、
「媛姫様の方が姉君ですので、どうぞお先に」と、毒の入った膳を「媛姫」
の方に回した。そのため、お万の娘「媛姫」の方が死んでしまったのだ。
この事件で、家老の成瀬が閉門幽閉となったが、「お万」はお咎めなし。
その代わり、正之は、女の業の恐ろしさに「婦女子の言は一切聞くべからず」
の家訓を遺したのだったが・・・・。
正之が亡くなり、お万の子「正経」が二代藩主となると、お万は、藩主の
生母として、ますます藩政に口出しするようになった。家老たちは正之公の
『遺訓』を盾にとって、必死に抵抗したが、お万は、甥の藤木弘隆を京都から
呼び寄せて家老に取立て、その妹を筆頭家老 保科民部正興に嫁がせて、藩政を
牛耳ろうとした。
ところが、藩主正経は病弱で、弟の正容に三代目を譲って早世してしまう。
三代目の藩主となった「正容」は側室の子だった。そうなると「お万」の
権勢は地に落ち、お万は江戸の上大崎に閑居、甥の藤木弘隆はお役御免と
なって京都に帰る途中亡くなり、保科民部は水沢村に幽閉となった。
さて、元禄3年、お万は71歳で淋しく生涯を閉じた。葬儀に藩主「正容」が
参列し、帰ろうとしたところ、「棺の中から青白い手が伸びて、正容の袴の
裾を掴み、棺に引きずり込もうとした」という怪談話まで伝えられている。
これって、まさに『鳥刺し』のラストシーンではないか。
と ここまで書いて、「投稿」をクリックしたら、突然画面が真っ白に
なって消えてしまった。一瞬からだが凍りつき、頭がクラクラしてきた。
再度 初めから書き直した次第。女の恨みはおそろしや、ゾォー。