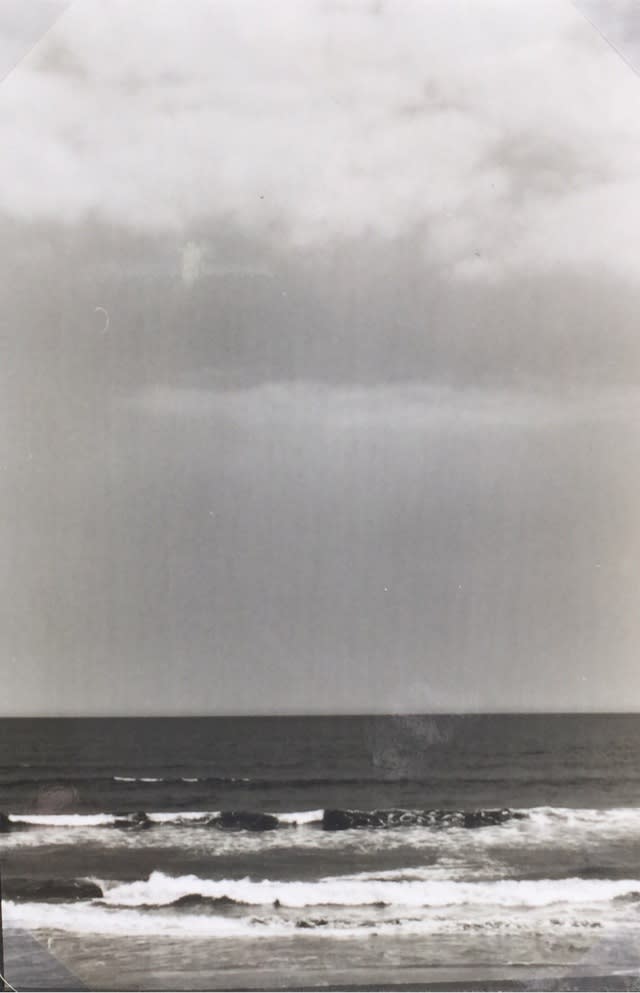六. 散り残した命
壇ノ浦/
「見る程の事は見つ。いまは自害せん」
平清盛の四男、入道相国最愛の息子と言われた知盛。清盛の死後は、兄で平家の総大将、大臣殿宗盛とともに、崩れゆく平家の主人であった。
先帝はすでに海の下の都へ旅立ち、女君たちも源氏の手にかからぬよう次々に海に入水。
一ノ谷で父を庇って討たれた息子知章に、背を向けてまで逃げてきた知盛も、乳母子の家長とともに、鎧二両をつけて入水した。
「見る程の事は見つ」と。
清盛の弟、教盛と経盛は、碇を担いでともに沈んだ。経盛の子、経正、経俊、敦盛は皆、一ノ谷で既に討ち取られた。教盛の子、通盛、業盛はすでに一ノ谷で、強弓の次男教経すら、獅子奮迅の末この同じ海底に消えた。
亡き重盛の次男資盛、四男有盛、重盛の弟行盛の子で、重盛が息子同様に育てた行盛、若人三人は、浮かぬよう共に肩を組み沈んでいった。
行盛は歌に優れ、ちょうど忠度のように、都落ちの前に、藤原定家に歌を包んで託し、のちに新撰和歌集に遺された。
総大将宗盛は遅れた。
宗盛の子、右衛門督清宗も同様だった。
船の縁に立つもののなかなか海に降りられず、時を潰しているのを、周囲の者は見かねて、通りがけにぶつかったふうにして宗盛を落とすと、清宗は自ら続いて飛び込んだ。
父子はお互いの様子を伺い、いよいよ死ねず、敵の手に落ちる。
宗盛の乳母子は果敢にも、宗盛らを引き揚げた船に乗り移り、さんざんに戦ったが首を取られた。目の前で乳母子が首を取られるのを、父子は見ているだけだった。
「海上には、赤旗や赤標が、切り捨てられ、かなぐり捨てられて、さながら竜田川のもみじ葉が、嵐に吹き散らされたかのよう、ために汀にうち寄せる白波も、うす紅に色を変え、主のない空船が、潮にひかれ風に流されどこをさすともなく、ゆられ漂いゆく姿は哀れをつくしている」
命をかける死闘といえど、ほんの一瞬のことでしかなく、夢のように流れ去る。
流れてゆくもみじ葉も、
咲いては散る沙羅双樹の花も。
平重衡/
平氏の悲劇は壇ノ浦で終わりではない。
散り残った花は、源氏の手によって散らされる。
重衡は清盛の五男で、容姿は牡丹のように美しく、父母の寵愛を受けた。なまめかしくきよらかでありながら、冗談などもいい、女房達に怖い話をしてキャーキャー言わせたり、強盗の真似をして幼い天皇を面白がらせたりなど、さまざまに心遣いのできる人物であったという。武将としても才に恵まれていたらしい。
にもかかわらず、重衡は戦で敢闘して散ることはできなかった。一ノ谷で捕虜になってしまうのである。
重衡もまた、一ノ谷の生田の森から、乳母子の後藤盛長と主従二騎で落ちていく。大将軍と見た梶原景季と庄高家は追い、矢が重衡の馬の尻に刺さった。盛長は、主人が自分の馬に乗り換えるかと思い、馬の速度を上げ、平家の赤布ももぎり取って逃げ去った。
乳母子の非情な仕打ちに、仕方なくその場で腹を切ろうとした重衡だが、追いついた高家が制止し、馬に乗せて連れ帰った。
重衡は人質となり、平家の持ち去った三種の神器との重衡の身柄との交換を迫られたが、宗盛は応じなかった。重衡も納得だった。平家の者達は生け捕りにされた重衡を恥と思い、憎んだが、鎌倉に下された重衡は、源氏の武将達には一目おかれる存在となった。
梶原景時に伴われ、鎌倉で頼朝と対面した重衡は、
「弓矢とる身の常として、敵の手にかかり命をおとすのは、恥のようであって決して恥ではありません。この上は芳恩をもって、ただすみやかに私の首をはねてください」
その後は一切物をいわない。景時はこの重衡の言葉に、「立派な大将軍だ」といって涙をながした。座につらなる人々も、みな袖を濡らした。
頼朝は重衡を狩野介宗茂に預けた。情けある狩野介は、心を尽くして重衡の世話に務めた。狩野介は千手の前を伴ってささやかな宴をひらき、重衡も琵琶をとり、見事な朗詠が一夜響いた。立聞きしていた頼朝の心にも清く響いたようであった。
重衡はかつて、清盛の頃の南都焼討の際の大将だった。奈良の寺院を焼き払うつもりはなく、暴れる僧徒を鎮めるための出兵だったが、不手際から火が伽藍に燃え移り、寺も仏像も灰塵にしてしまった。南都では重衡を憎み、鎌倉に重衡の身柄を渡すよう執拗に催促するため、重衡はとうとう引き渡されることとなった。
道中、身をやつして一人生きながらえていた妻に会うことができた。結局、木津川の河原で斬首されることとなると、大勢の見物が見はった。そこへ、元は重衡に仕えていた侍が見届けるべく現れ、重衡の望みを聞き、近くの里から仏像一体を借り、砂の上に据え、自分の狩衣の紐を外し、片端を仏の手に掛け、もう片端を重衡に握らせた。重衡は最後の念仏をし、首を差し出す。
その様は見物の心を打った。
首は、般若寺の大鳥居の前に釘付けにされた。
焼き討ちの際、ここをくぐっていったのである。
妻は骸と首を引き取りに行き、火葬してのち、生涯をかけて供養した。真夏のことゆえ、傷みの激しい亡骸を引き受けたのは気丈な心映えだと思う。
重衡には子がなく、妻も母もあれこれ苦労して祈祷なども施したが、このような運命になってみれば、
「それで宜しかったのだ。子供がありでもしたら、どんなに切なかったことであろう」と思ったようである。
壇ノ浦で宗盛が潔く海に飛び込めなかったのは、そもそも優柔不断なせいもあっただろうが、息子清宗と離れることに未練があったからだろう。
宗盛も、重衡と前後して鎌倉に下され、首を落とされた。
平宗盛/
「たとえ、蝦夷千島にても命さえあらば‥」
清宗とともに鎌倉へ送られる道中、宗盛は付き添いの義経に、命を助けてほしいと哀願する。
とうとう鎌倉で頼朝と対面したが、その態度には助けて欲しさに媚びる姿勢が痛々しく、居並ぶ武将たちは、大将軍としての覚悟のなさはおろか、一武士としての誇りすら持ち合わせぬ宗盛には、皆たいそうあきれた。
京に帰されることになり、もしや助かるのではと淡い期待をいだく父。道中で処されることを確信していた息子は、そんな父を労わりつつも、ひたすら念仏を勧めた。
最後、篠原の宿で父子は引き離され、まず父が斬られる。念仏の途中、「右衛門督もすでにか」と聞いた。死の間際にもやはり、頭の中は息子のことでいっぱいだったのだろう。
続いて、息子は、
「さて、父の御最期は、いかがでございましたか」
ときくと、聖は、
「おりっぱでございました。御安心なさりませ」
と答えた。すると右衛門督は、
「いまは憂き世におもいのこすことはない。さらば、斬れ」
と首をさしのべた。
清宗こそ最後まで、父のことを心配していたのだ。父の命よりも、父の尊厳を。きっと、幼い時分から父の欠けるところを知り、気にかけていたのかもしれない。
父知盛の盾となった知章、そしてこの清宗、ともに十六の若さにもかかわらず、それぞれのやり方で父を支えたのは、立派なことであった。
このあたりを描いた能演目には、『知章』、『碇潜』、『千手』、『通盛』、『小督』がある。
七. つまれる蕾
『平家の子孫は、男子であるかぎり、一人残らず亡き者にせよ』
六代/
「あまりかわゆくいらっしゃるので‥」
六代とは、平高清である。
平維盛の息子。六代という幼名は、平正盛から、忠盛、清盛、重盛、維盛、そしてこの高清が嫡流の六代目であることに由来する。
壇ノ浦で平家が排除された後の、幼い生残りの者達の運命を追っていく。
六代についての前に、まずは六代の父、維盛について。
父清盛よりも早くに亡くなった重盛は、権威を笠に着がちな平家一門のなかでは穏健で、法皇の信頼も厚く、源氏方によっても、若き頼朝を救い、庇護する助けとなった重盛の家系、小松方は特別視されていた。
しかし、宗盛以下の弟らとは母が異なることと、重盛自身の妻と、嫡男維盛の妻が、鹿ノ谷の陰謀で流罪となった藤原成親の縁者だったということもあり、平家のなかでは孤立しつつあった。
清盛亡き後、嫡孫の維盛ではなく、弟宗盛が権力を握ることになった。宗盛の嫡男の清宗に、昇進を先に越されるという屈辱もあった。
更に、小松家においても、資盛以下の弟とは母が異なり、維盛は長男ではあるが、女官の産んだ子であったため、十三で立嫡するまでは立場が明確でなかった。
しかし、維盛の美しさは飛び抜けており、先述の通り、青海波の舞を披露したのは十六の春、「かざしの桜にぞことならぬ」ほどで、日頃は平家を憎む者ですら、その容姿の優れたる様は賛美したという。
成年後、政治の表からは外され、大将軍として戦地に赴くことは多いものの、不運が多く、侍大将らと対立しがちで、その度に戦局は足並みが乱れ、大敗をもたらしてしまった。
富士川の戦いでは、当時まだ存命だった清盛に、なぜ骸を晒してでも戦ってこなかったかと激怒され、京に入れてもらえなかった。
また、西国へ都落ちするとき、維盛は妻子を伴うのは不憫と思い、泣く泣く京に残して行くが、別れに手間取り、やや遅れて合流したことを、宗盛や知盛は怪しんだという。維盛だけでなく、小松方は平家の集団の中では、居心地の悪い思いをしていたことだろう。
そんなことから、維盛は病がちになり、一ノ谷の前後に密かに逃亡する。妻子に会いたい思いを堪え、高野山で剃髪、熊野三山を巡礼したのち那智沖にて入水。二十七歳。
歌人・建礼門院右京大夫は、かつての維盛の青海波を瞼に浮かべて、その死を悼む。
春の花の 色によそへし おもかげの
むなしき波の したにくちぬる
驕れる人々のなかに数えられても、孤独に苦しみ、水づく生涯もあった。
さて、六代の、父維盛との別れは十歳のとき。二つ下の妹と母と、大覚寺の菖蒲谷というところに潜んでいた。頼朝は平定の後、平家の男子子孫全てを滅ぼしにかかった。しかし、肝心の嫡流六代は見つけることができず、子孫抹殺を任されていた北条時政は、鎌倉へ帰ろうとしているときに、ある女の密告で六代の居場所がつきとめられた。外から様子を伺っていると、美しい若君が子犬を追いかけて庭に飛び出してきたのを目撃する。翌日、引き渡しを求めた。十二の六代は大人びて十四、五より上にも見え、大変美しい容姿容貌。気丈に振舞おうとすれど、涙が押さえる袖からこぼれ落ちてしまう。
捕らえられ、連れていかれた六代は、すぐには斬られないでいた。子孫抹殺の命を預かっている北条時正によれば、
「あまりかわゆくいらっしゃるので、まだそのままにしてございます」
とのこと。そこへ、鎌倉殿とはかつて共に助け合った仲だという文覚上人が、助けるために弟子として保護しようかと、六代の様子を見に来た。上人はその様子、姿、人品の、この世の人とは思えぬ有様に、殺すには忍びないと感じたため、自ら鎌倉へ行き、頼朝に命乞いに行くと決心、時政には二十日の延命の猶予をもらった。
しかし、約束の二十日が過ぎても、便り一つもなかった。それでも、北条はすぐに斬る事はできず、途中で上人と会える可能性もあるからと、御輿に六代を乗せ、京を離れて東にゆっくりと進んだ。いよいよ、今日かと思ううちに、虚しく時が過ぎ、駿河国の千本松原で六代は降ろされた。足柄を越えることは、どうにも許されないと判断したためであろう。
覚悟をされた若君は、首を差しだし、声高に念仏を唱え、ふと肩にかかっていた髪を美しい手で前にかき寄せる様に、武士たちは涙を流した。
そんななかで、だれも斬る事ができず、押し付けあっているところに、馬に乗った僧があらわれ、土地の者に話を聞くと、あわや若君が斬られそうだとのこと。僧は声を張り上げ、鎌倉殿からの書状を差し出す。書状には確かに鎌倉殿の花押もあった。その場にいた者全ての涙が、喜びの涙に変わった。
文覚上人に預けられた六代は、十四で剃髪、妙覚と名乗り、修行する。頼朝は、助命を許したものの、六代が成長するにつけ、気になって仕方なく、様子を文覚にしつこく尋ねるが、文覚は意気地なしだから安心するようにと、ごまかしていた。しかし、六代が二十一の歳に鎌倉で頼朝に謁見、頼朝は一目でその聡明さ見破り、危険を感じた。
その後まもなく頼朝は亡くなり、文覚が謀反の計画で流罪になると、六代は捕らえられ処刑されてしまった。没年には二説あり1199年または1205年、享年は二十六あるいは三十一。
平家の嫡流中の嫡流でありながらも、抹殺の命令ののち、15〜20年も保護され続けた六代は、不幸中の幸いというべきなのか、人に、彼を死なせたくないと思わせ、守りたくさせる魅力に恵まれていたのだろう。「助けてほしい」などと一言も言わなくても。それは、容姿の魅力だけでなく、その人の備える清らかな心が、誰彼の心にも打ち響いたからではなかったか。
若君として、僧として、そのような素養がまさに、より良く彼を生かしていたのだろう。不思議にも、世には稀にそういう人が居るものなのだ。
六代の死によって、平家の男子の子孫は絶えた。
なお、六代の他の幼き子孫の運命を振り返ると、
宗盛の次男義宗、幼名副将は、宗盛が鎌倉へ送られる前に、ひととき父と面会したあと、河原に連れて行かれ斬首された。八歳だった。
重盛の六男、忠房は、屋島の戦いのあとに陣を抜け出した。兄の維盛と一緒だったのかもしれない。紀伊の湯浅氏に保護され、のちに湯浅宗重、藤原景清ほか平家残党と三ヶ月の篭城。ところが、頼朝より、「重盛には旧恩があり、その息子は助命する」とあり、鎌倉へ出頭。しかし頼朝が助命するなどとは嘘にすぎず、京に帰る途上で殺された。1186年1月のこと、年齢は不明。
重盛の七男、宗実も同様に、頼朝により、助命するから出頭するように要請があった。宗実は、重源の弟子に志願し、東大寺に身を潜めていたのだったが、鎌倉へ行っても助命されるはずはないと思い、然れども寺に残れば迷惑がかかると考え、奈良を発つ。しかし、それは死を覚悟の旅のこと、旅立ちから飲食を断ち、足柄を越えた関本あたりの宿で衰弱死した。1185年、十八歳。
知盛の末子、知忠は、都落ちのときにはまだ三歳。都落ちには同行せず、紀伊為教が引き取り、匿っていた。しばらくして、九条河原法性寺の一の橋のほとりの邸に隠れ住むようになった。清盛がかつて、いざという時の城郭になるように、二重の堀を備え、四方は竹で囲んだつくりになっている。ここに平家の者が潜んでいるとのうわさに、鎌倉方が攻め入った。
応戦しているうちに知忠は傷を負い、自殺。
しかし、首実検では知忠の顔を知る者はなかったため、壇ノ浦で生き残っていた母、治部卿の局が呼び出された。三つの時に別れて以来、生死も行方も不明だった我が子との、惨い形の再会。
「ただ面影にどこやら、故人の中納言を偲ばせるところがございますので、やはりこれが知忠であろうと思われます」
1196年10月、知忠は十六だった。
革命、平定、クーデターは何かをもたらすけれど、それはよいものばかりではない。そして、必ず失われるものはある。歴史はそうやって、看板を塗り替えてきた。
その渦中の者達の壮絶な生死のなかに、人としての心がつぶさに映ってみえる。
平曲として、能の修羅物として、現代にも受け継がれているのは、彼らの悲しみが、どういうわけか今を生きるわたしたちにも、心に沁みるから、
崩れていく状況のなかでも精一杯に生きる姿が、心を打つからである。
この文を書いていた間に、鳥取の地震があった。平家物語にもあるが、壇ノ浦の戦いのあった同年の1185年7月9日正午、大地震が起こり、多くの寺社の倒壊することになったのも平家の祟りなのではないかと怖れられた。
被害は近畿だけでなく、遠国にも及んでいたとのこと。土に埋まる人々のこと、また、津波も記録に窺える。南海トラフ地震であった可能性もあるらしい。
物語には、
「四大元素中の三種、水と火と風とは、常に災害をひきおこすけれども、大地にかぎって、異変をなすことはないのに、これは何とした事であろう‥」
とあるが、今の私達にしてみれば、大地は不動のものではないことは、近年は特に身につまされて承知している。
過去の時代の人々と違い、天災はいっときの大地の暴れだけでは済まない、ということにも私達は肝を冷やしている。
稼働している原子力発電、放射性廃棄物が、むき出しになってしまったら‥
その恐怖も受け入れなければならない。
いや、それは大地に、私達が終わりをもたらすことに他ならない、贖うことのできない重い罪を数万年も負う絶望である。

壇ノ浦/
「見る程の事は見つ。いまは自害せん」
平清盛の四男、入道相国最愛の息子と言われた知盛。清盛の死後は、兄で平家の総大将、大臣殿宗盛とともに、崩れゆく平家の主人であった。
先帝はすでに海の下の都へ旅立ち、女君たちも源氏の手にかからぬよう次々に海に入水。
一ノ谷で父を庇って討たれた息子知章に、背を向けてまで逃げてきた知盛も、乳母子の家長とともに、鎧二両をつけて入水した。
「見る程の事は見つ」と。
清盛の弟、教盛と経盛は、碇を担いでともに沈んだ。経盛の子、経正、経俊、敦盛は皆、一ノ谷で既に討ち取られた。教盛の子、通盛、業盛はすでに一ノ谷で、強弓の次男教経すら、獅子奮迅の末この同じ海底に消えた。
亡き重盛の次男資盛、四男有盛、重盛の弟行盛の子で、重盛が息子同様に育てた行盛、若人三人は、浮かぬよう共に肩を組み沈んでいった。
行盛は歌に優れ、ちょうど忠度のように、都落ちの前に、藤原定家に歌を包んで託し、のちに新撰和歌集に遺された。
総大将宗盛は遅れた。
宗盛の子、右衛門督清宗も同様だった。
船の縁に立つもののなかなか海に降りられず、時を潰しているのを、周囲の者は見かねて、通りがけにぶつかったふうにして宗盛を落とすと、清宗は自ら続いて飛び込んだ。
父子はお互いの様子を伺い、いよいよ死ねず、敵の手に落ちる。
宗盛の乳母子は果敢にも、宗盛らを引き揚げた船に乗り移り、さんざんに戦ったが首を取られた。目の前で乳母子が首を取られるのを、父子は見ているだけだった。
「海上には、赤旗や赤標が、切り捨てられ、かなぐり捨てられて、さながら竜田川のもみじ葉が、嵐に吹き散らされたかのよう、ために汀にうち寄せる白波も、うす紅に色を変え、主のない空船が、潮にひかれ風に流されどこをさすともなく、ゆられ漂いゆく姿は哀れをつくしている」
命をかける死闘といえど、ほんの一瞬のことでしかなく、夢のように流れ去る。
流れてゆくもみじ葉も、
咲いては散る沙羅双樹の花も。
平重衡/
平氏の悲劇は壇ノ浦で終わりではない。
散り残った花は、源氏の手によって散らされる。
重衡は清盛の五男で、容姿は牡丹のように美しく、父母の寵愛を受けた。なまめかしくきよらかでありながら、冗談などもいい、女房達に怖い話をしてキャーキャー言わせたり、強盗の真似をして幼い天皇を面白がらせたりなど、さまざまに心遣いのできる人物であったという。武将としても才に恵まれていたらしい。
にもかかわらず、重衡は戦で敢闘して散ることはできなかった。一ノ谷で捕虜になってしまうのである。
重衡もまた、一ノ谷の生田の森から、乳母子の後藤盛長と主従二騎で落ちていく。大将軍と見た梶原景季と庄高家は追い、矢が重衡の馬の尻に刺さった。盛長は、主人が自分の馬に乗り換えるかと思い、馬の速度を上げ、平家の赤布ももぎり取って逃げ去った。
乳母子の非情な仕打ちに、仕方なくその場で腹を切ろうとした重衡だが、追いついた高家が制止し、馬に乗せて連れ帰った。
重衡は人質となり、平家の持ち去った三種の神器との重衡の身柄との交換を迫られたが、宗盛は応じなかった。重衡も納得だった。平家の者達は生け捕りにされた重衡を恥と思い、憎んだが、鎌倉に下された重衡は、源氏の武将達には一目おかれる存在となった。
梶原景時に伴われ、鎌倉で頼朝と対面した重衡は、
「弓矢とる身の常として、敵の手にかかり命をおとすのは、恥のようであって決して恥ではありません。この上は芳恩をもって、ただすみやかに私の首をはねてください」
その後は一切物をいわない。景時はこの重衡の言葉に、「立派な大将軍だ」といって涙をながした。座につらなる人々も、みな袖を濡らした。
頼朝は重衡を狩野介宗茂に預けた。情けある狩野介は、心を尽くして重衡の世話に務めた。狩野介は千手の前を伴ってささやかな宴をひらき、重衡も琵琶をとり、見事な朗詠が一夜響いた。立聞きしていた頼朝の心にも清く響いたようであった。
重衡はかつて、清盛の頃の南都焼討の際の大将だった。奈良の寺院を焼き払うつもりはなく、暴れる僧徒を鎮めるための出兵だったが、不手際から火が伽藍に燃え移り、寺も仏像も灰塵にしてしまった。南都では重衡を憎み、鎌倉に重衡の身柄を渡すよう執拗に催促するため、重衡はとうとう引き渡されることとなった。
道中、身をやつして一人生きながらえていた妻に会うことができた。結局、木津川の河原で斬首されることとなると、大勢の見物が見はった。そこへ、元は重衡に仕えていた侍が見届けるべく現れ、重衡の望みを聞き、近くの里から仏像一体を借り、砂の上に据え、自分の狩衣の紐を外し、片端を仏の手に掛け、もう片端を重衡に握らせた。重衡は最後の念仏をし、首を差し出す。
その様は見物の心を打った。
首は、般若寺の大鳥居の前に釘付けにされた。
焼き討ちの際、ここをくぐっていったのである。
妻は骸と首を引き取りに行き、火葬してのち、生涯をかけて供養した。真夏のことゆえ、傷みの激しい亡骸を引き受けたのは気丈な心映えだと思う。
重衡には子がなく、妻も母もあれこれ苦労して祈祷なども施したが、このような運命になってみれば、
「それで宜しかったのだ。子供がありでもしたら、どんなに切なかったことであろう」と思ったようである。
壇ノ浦で宗盛が潔く海に飛び込めなかったのは、そもそも優柔不断なせいもあっただろうが、息子清宗と離れることに未練があったからだろう。
宗盛も、重衡と前後して鎌倉に下され、首を落とされた。
平宗盛/
「たとえ、蝦夷千島にても命さえあらば‥」
清宗とともに鎌倉へ送られる道中、宗盛は付き添いの義経に、命を助けてほしいと哀願する。
とうとう鎌倉で頼朝と対面したが、その態度には助けて欲しさに媚びる姿勢が痛々しく、居並ぶ武将たちは、大将軍としての覚悟のなさはおろか、一武士としての誇りすら持ち合わせぬ宗盛には、皆たいそうあきれた。
京に帰されることになり、もしや助かるのではと淡い期待をいだく父。道中で処されることを確信していた息子は、そんな父を労わりつつも、ひたすら念仏を勧めた。
最後、篠原の宿で父子は引き離され、まず父が斬られる。念仏の途中、「右衛門督もすでにか」と聞いた。死の間際にもやはり、頭の中は息子のことでいっぱいだったのだろう。
続いて、息子は、
「さて、父の御最期は、いかがでございましたか」
ときくと、聖は、
「おりっぱでございました。御安心なさりませ」
と答えた。すると右衛門督は、
「いまは憂き世におもいのこすことはない。さらば、斬れ」
と首をさしのべた。
清宗こそ最後まで、父のことを心配していたのだ。父の命よりも、父の尊厳を。きっと、幼い時分から父の欠けるところを知り、気にかけていたのかもしれない。
父知盛の盾となった知章、そしてこの清宗、ともに十六の若さにもかかわらず、それぞれのやり方で父を支えたのは、立派なことであった。
このあたりを描いた能演目には、『知章』、『碇潜』、『千手』、『通盛』、『小督』がある。
七. つまれる蕾
『平家の子孫は、男子であるかぎり、一人残らず亡き者にせよ』
六代/
「あまりかわゆくいらっしゃるので‥」
六代とは、平高清である。
平維盛の息子。六代という幼名は、平正盛から、忠盛、清盛、重盛、維盛、そしてこの高清が嫡流の六代目であることに由来する。
壇ノ浦で平家が排除された後の、幼い生残りの者達の運命を追っていく。
六代についての前に、まずは六代の父、維盛について。
父清盛よりも早くに亡くなった重盛は、権威を笠に着がちな平家一門のなかでは穏健で、法皇の信頼も厚く、源氏方によっても、若き頼朝を救い、庇護する助けとなった重盛の家系、小松方は特別視されていた。
しかし、宗盛以下の弟らとは母が異なることと、重盛自身の妻と、嫡男維盛の妻が、鹿ノ谷の陰謀で流罪となった藤原成親の縁者だったということもあり、平家のなかでは孤立しつつあった。
清盛亡き後、嫡孫の維盛ではなく、弟宗盛が権力を握ることになった。宗盛の嫡男の清宗に、昇進を先に越されるという屈辱もあった。
更に、小松家においても、資盛以下の弟とは母が異なり、維盛は長男ではあるが、女官の産んだ子であったため、十三で立嫡するまでは立場が明確でなかった。
しかし、維盛の美しさは飛び抜けており、先述の通り、青海波の舞を披露したのは十六の春、「かざしの桜にぞことならぬ」ほどで、日頃は平家を憎む者ですら、その容姿の優れたる様は賛美したという。
成年後、政治の表からは外され、大将軍として戦地に赴くことは多いものの、不運が多く、侍大将らと対立しがちで、その度に戦局は足並みが乱れ、大敗をもたらしてしまった。
富士川の戦いでは、当時まだ存命だった清盛に、なぜ骸を晒してでも戦ってこなかったかと激怒され、京に入れてもらえなかった。
また、西国へ都落ちするとき、維盛は妻子を伴うのは不憫と思い、泣く泣く京に残して行くが、別れに手間取り、やや遅れて合流したことを、宗盛や知盛は怪しんだという。維盛だけでなく、小松方は平家の集団の中では、居心地の悪い思いをしていたことだろう。
そんなことから、維盛は病がちになり、一ノ谷の前後に密かに逃亡する。妻子に会いたい思いを堪え、高野山で剃髪、熊野三山を巡礼したのち那智沖にて入水。二十七歳。
歌人・建礼門院右京大夫は、かつての維盛の青海波を瞼に浮かべて、その死を悼む。
春の花の 色によそへし おもかげの
むなしき波の したにくちぬる
驕れる人々のなかに数えられても、孤独に苦しみ、水づく生涯もあった。
さて、六代の、父維盛との別れは十歳のとき。二つ下の妹と母と、大覚寺の菖蒲谷というところに潜んでいた。頼朝は平定の後、平家の男子子孫全てを滅ぼしにかかった。しかし、肝心の嫡流六代は見つけることができず、子孫抹殺を任されていた北条時政は、鎌倉へ帰ろうとしているときに、ある女の密告で六代の居場所がつきとめられた。外から様子を伺っていると、美しい若君が子犬を追いかけて庭に飛び出してきたのを目撃する。翌日、引き渡しを求めた。十二の六代は大人びて十四、五より上にも見え、大変美しい容姿容貌。気丈に振舞おうとすれど、涙が押さえる袖からこぼれ落ちてしまう。
捕らえられ、連れていかれた六代は、すぐには斬られないでいた。子孫抹殺の命を預かっている北条時正によれば、
「あまりかわゆくいらっしゃるので、まだそのままにしてございます」
とのこと。そこへ、鎌倉殿とはかつて共に助け合った仲だという文覚上人が、助けるために弟子として保護しようかと、六代の様子を見に来た。上人はその様子、姿、人品の、この世の人とは思えぬ有様に、殺すには忍びないと感じたため、自ら鎌倉へ行き、頼朝に命乞いに行くと決心、時政には二十日の延命の猶予をもらった。
しかし、約束の二十日が過ぎても、便り一つもなかった。それでも、北条はすぐに斬る事はできず、途中で上人と会える可能性もあるからと、御輿に六代を乗せ、京を離れて東にゆっくりと進んだ。いよいよ、今日かと思ううちに、虚しく時が過ぎ、駿河国の千本松原で六代は降ろされた。足柄を越えることは、どうにも許されないと判断したためであろう。
覚悟をされた若君は、首を差しだし、声高に念仏を唱え、ふと肩にかかっていた髪を美しい手で前にかき寄せる様に、武士たちは涙を流した。
そんななかで、だれも斬る事ができず、押し付けあっているところに、馬に乗った僧があらわれ、土地の者に話を聞くと、あわや若君が斬られそうだとのこと。僧は声を張り上げ、鎌倉殿からの書状を差し出す。書状には確かに鎌倉殿の花押もあった。その場にいた者全ての涙が、喜びの涙に変わった。
文覚上人に預けられた六代は、十四で剃髪、妙覚と名乗り、修行する。頼朝は、助命を許したものの、六代が成長するにつけ、気になって仕方なく、様子を文覚にしつこく尋ねるが、文覚は意気地なしだから安心するようにと、ごまかしていた。しかし、六代が二十一の歳に鎌倉で頼朝に謁見、頼朝は一目でその聡明さ見破り、危険を感じた。
その後まもなく頼朝は亡くなり、文覚が謀反の計画で流罪になると、六代は捕らえられ処刑されてしまった。没年には二説あり1199年または1205年、享年は二十六あるいは三十一。
平家の嫡流中の嫡流でありながらも、抹殺の命令ののち、15〜20年も保護され続けた六代は、不幸中の幸いというべきなのか、人に、彼を死なせたくないと思わせ、守りたくさせる魅力に恵まれていたのだろう。「助けてほしい」などと一言も言わなくても。それは、容姿の魅力だけでなく、その人の備える清らかな心が、誰彼の心にも打ち響いたからではなかったか。
若君として、僧として、そのような素養がまさに、より良く彼を生かしていたのだろう。不思議にも、世には稀にそういう人が居るものなのだ。
六代の死によって、平家の男子の子孫は絶えた。
なお、六代の他の幼き子孫の運命を振り返ると、
宗盛の次男義宗、幼名副将は、宗盛が鎌倉へ送られる前に、ひととき父と面会したあと、河原に連れて行かれ斬首された。八歳だった。
重盛の六男、忠房は、屋島の戦いのあとに陣を抜け出した。兄の維盛と一緒だったのかもしれない。紀伊の湯浅氏に保護され、のちに湯浅宗重、藤原景清ほか平家残党と三ヶ月の篭城。ところが、頼朝より、「重盛には旧恩があり、その息子は助命する」とあり、鎌倉へ出頭。しかし頼朝が助命するなどとは嘘にすぎず、京に帰る途上で殺された。1186年1月のこと、年齢は不明。
重盛の七男、宗実も同様に、頼朝により、助命するから出頭するように要請があった。宗実は、重源の弟子に志願し、東大寺に身を潜めていたのだったが、鎌倉へ行っても助命されるはずはないと思い、然れども寺に残れば迷惑がかかると考え、奈良を発つ。しかし、それは死を覚悟の旅のこと、旅立ちから飲食を断ち、足柄を越えた関本あたりの宿で衰弱死した。1185年、十八歳。
知盛の末子、知忠は、都落ちのときにはまだ三歳。都落ちには同行せず、紀伊為教が引き取り、匿っていた。しばらくして、九条河原法性寺の一の橋のほとりの邸に隠れ住むようになった。清盛がかつて、いざという時の城郭になるように、二重の堀を備え、四方は竹で囲んだつくりになっている。ここに平家の者が潜んでいるとのうわさに、鎌倉方が攻め入った。
応戦しているうちに知忠は傷を負い、自殺。
しかし、首実検では知忠の顔を知る者はなかったため、壇ノ浦で生き残っていた母、治部卿の局が呼び出された。三つの時に別れて以来、生死も行方も不明だった我が子との、惨い形の再会。
「ただ面影にどこやら、故人の中納言を偲ばせるところがございますので、やはりこれが知忠であろうと思われます」
1196年10月、知忠は十六だった。
革命、平定、クーデターは何かをもたらすけれど、それはよいものばかりではない。そして、必ず失われるものはある。歴史はそうやって、看板を塗り替えてきた。
その渦中の者達の壮絶な生死のなかに、人としての心がつぶさに映ってみえる。
平曲として、能の修羅物として、現代にも受け継がれているのは、彼らの悲しみが、どういうわけか今を生きるわたしたちにも、心に沁みるから、
崩れていく状況のなかでも精一杯に生きる姿が、心を打つからである。
この文を書いていた間に、鳥取の地震があった。平家物語にもあるが、壇ノ浦の戦いのあった同年の1185年7月9日正午、大地震が起こり、多くの寺社の倒壊することになったのも平家の祟りなのではないかと怖れられた。
被害は近畿だけでなく、遠国にも及んでいたとのこと。土に埋まる人々のこと、また、津波も記録に窺える。南海トラフ地震であった可能性もあるらしい。
物語には、
「四大元素中の三種、水と火と風とは、常に災害をひきおこすけれども、大地にかぎって、異変をなすことはないのに、これは何とした事であろう‥」
とあるが、今の私達にしてみれば、大地は不動のものではないことは、近年は特に身につまされて承知している。
過去の時代の人々と違い、天災はいっときの大地の暴れだけでは済まない、ということにも私達は肝を冷やしている。
稼働している原子力発電、放射性廃棄物が、むき出しになってしまったら‥
その恐怖も受け入れなければならない。
いや、それは大地に、私達が終わりをもたらすことに他ならない、贖うことのできない重い罪を数万年も負う絶望である。