「ああ、わが息よ、わが刻々の命よ」
ローマの正義を信じ、逆境とたたかう不屈の精神
一方で生涯はいよいよ晩熟してゆく

辻邦生『背教者ユリアヌス』の世界は、とても美しい情景の広がりの上に描かれている。1600年以上昔の朝日も夕日も、今と変わらず美しかったし、それを見る人々の感情もまた変わりない。辻邦生の筆は絵画を描いているかのように、色彩を繰り広げてくれる。
例えば‥
足早に動いている白い団塊/
奇妙に黒ずんだ尖塔/
秋のはじめの朝日に金色に/
ばら色になった羽をひろげて、鷗が/
暑い、黒ずんだ夏/
ただ青い空のなかに、灰褐色の岩山が、
くっきり象嵌したように、
かたく食いこんで/
冬の雲が、紫のかげりを帯びて/
菫色を含んだ艶やかな夜/
おだやかな波は、
白いレースのような泡をかきたて/
ほの暗いまでに青い空の色/
雪の稜線は、
純潔な襟首のような曲線を描いて空を限って/
手の染まりそうに青い空/
月が皎々と眩しいほどに輝き、
柱列が青白く、
何か葬列につづく人々のように並んで/
描き出される細やかな色彩、ライン、軌跡は、油彩画よりは、繊細な透明水彩画だろうか。
登場人物描写ではその瞳の色が映し出されて、何ともその透明な輝きの中へと、自分が取り込まれ、人物と一体になるように導かれる感じがする。物語中、この描写はたびたび繰り返されることで印象に強く刻まれる。
主な人物は、こうなっている。
バシリナ:ユリアヌスの母
=透きとおった青灰色の謎めいた眼
ユリアヌス
=母親に似た灰青色の、夢見るような、おだやかな眼
コンスタンティウス:ユリアヌスの父兄を殺害した皇帝、ユリアヌスの従兄
=ぎょろりとした灰色の眼
ガルス:ユリアヌスの異母兄
=淡い眼の色の、浅黒い、どこか皮肉な感じのする青年
コンスタンティア:コンスタンティウスの妹、ガルスの妃
=燃えるような灰暗色の眼と、複雑な髪型の頭を後ろにそらすようにする癖
エウセビア:コンスタンティウスの妃、ユリアヌスの庇護者
=子供じみた、茶色の明るい眼
ヘレナ:コンスタンティウスの妹、ユリアヌスの妃
=背の高い、陰気な大きい額の下の灰暗色の眼
サルスティウス:ガリア出身でユリアヌスの優秀な片腕
=浅黒い、端正な、彫りの深い顔に、濃い青い眼
情景描写では、カメラなら少し広角、人物とそれを包む静かな自然の景色が程よいバランスで、優しい。例えば
/墓地を吹く風は、宮殿のその窓辺にも吹きつけ、仕切りの帷をゆらし、揺り籠をおおった白い薄地の布をゆらした。しかしそれは深くねむりつづける赤子の眼をさますことはなかった。彼はただ握った手を前へ少しのばし、それを顔に近づけ、小さな欠伸のようなものをしただけだった。
宮殿のなかは風の音のほか何の音もしなかった。/
/風の荒れる冬の夜には、燈火の光もなく、暗くひっそりしていた。ただ時おり幼いユリアヌスの寝室の下を、ゆっくり歩くと兵卒の長槍が、星の光にほの白く光るだけだった。その兵卒の足音は、長い冬の夜を歩きつくして、どこか夜明けのない国に入ってゆくように思われた。/
/テオノエ(エウセビアの年配の侍女)は窓のそばまでゆくと、牧草地から森のほうに眼をやった。そこには郭公の声はすでに聞こえず、いったん晴れた霧がふたたび低く切れ切れに流れはじめ、それはやがて音もたてぬ霧雨となって離宮の屋根を濡らした。そして窓に近々と枝をのばす榛の葉から、時おり、雨滴のようなものが、光って、地面にしたたりはじめた。/
/ユリアヌスは雪のなかを黙々と進む馬の背に揺られながら、本来なら皇帝軍団と決戦を交えるはずになっていたトラキアの山野を、一種の放心した表情で眺めつづけた。森も丘陵も雪のなかに白く霞み、距離感のなくなった白一色の野の拡がりに、息苦しいような沈黙がおりていた。それは急に音のしなくなった世界を見ているような感じだった。それだけに、その虚しい白い空間を夥しく満たし、ふるえ、ひらひら舞い、踊り狂い、ひたすら降りつづける雪片の大群が、異様な圧迫感となってユリアヌスの胸を押さえつけた。それは何か救いのない厖大なものがひたすらに崩れつづけている感じに似ていた。/
前回では、主にエドワード・ギボン『ローマ帝国衰亡史』を元に、ユリアヌスの生い立ちから英雄皇帝に至る生涯を追った。今回は、辻邦生『背教者ユリアヌス』の世界から、“皇帝”ユリアヌスの苦悩を読み解きたい。もちろん、この作品は小説であり、創作上の人物も登場するし、ユリアヌスの言動も作者の創造ではある。しかし、最大限、事実に則し、実在のユリアヌスの心中に深く迫る著者は、ユリアヌスの理解者であり代弁者であり、もはや時代を超え結び合った友人として、リアルな等身像を削り出している。
マルクス=アウレリウス帝のごとく、哲学的な理想をローマ帝国に再現しようとしたユリアヌス皇帝は、時代の抱える諸状況の困難に直面し、その都度、彼なりに果敢に処断してきた。しかし、哲人帝の頃とはすでに時代背景が変わっていたのである。
一つは、台頭するキリスト教徒との摩擦。先々帝コンスタンティヌス1世がキリスト教を公認(国教化ではない)したことで、聖職者が権力に結びつき、多数の教派が利権を争い、教会上層部は腐敗。皇帝の権威も、一信徒扱いとなって弱められた。それまでのローマ国教の神々は、その神殿を壊され、神像も打ち砕かれた。ギリシャ由来の神々への信仰は、ユリアヌスの理想である。寛容を叫ぶキリスト教徒が、このような破壊行為に及ぶ矛盾にユリアヌスは怒りがおさまらない。
加えてもう一つ、東方諸州との文化の違いが、ユリアヌスの統治を阻む。副帝としてガリア一帯を統治し、その誠実さと包容力で、質朴かつ堅実なガリア属州民との理想的な主従関係を築いてきたユリアヌスだったが、ヘレニズム文化地域の民衆とは、なじむことができなかった。
まず、新帝として首都コンスタンティノポリスに入城し、性急に進めたかずかずの改革が宮廷の反感を買うことになるも、皇帝の権限を尊重する慣習により反動は抑えられていた。しかし、東方征伐の拠点として冬営したアンティオキア(現シリア)は、もともと享楽的な土壌のため、質素で大真面目な異教の皇帝はあまりにもダサくて笑い者でしかなかった。露骨に中傷、反抗する民に、ユリアヌスは怒りと軽蔑で憤激しつつも、ローマの理想を信じて、ぎりぎりの寛容を維持していた。それは、ユリアヌスを敬愛していたガリア軍の兵達にも強いられた屈辱だった。
キリスト教徒にしても、シリア民にしても、その反抗的振舞いは皇帝侮辱罪や反逆罪で粛清されてもおかしくないほど度を越していた。おそらく、兄のガルス(コンスタンティウスの副帝としてアンティオキア在)ならば容赦なくそうしただろう。むしろそうする必要があったかもしれない。理想と現実の天秤を計り間違えることは、即位直後の歴代ローマ皇帝にも見られた傾向ではある。英雄としてのユリアヌスは非常に優れた知将だった。しかし、皇帝としての統治では、才能を発揮するには理想が高く、また穢れがなさすぎた感がある。
思いがけない戦死により、わずか1年半程度の統治となったが、短期間にも関わらず、彼の苦悩の深さがこの作品には描き出されている。サルスティウスが苦しむユリアヌスに寄り添うように、作者も包み込むように寄り添ってユリアヌスを描く。
この頃、ユリアヌスの生涯はすでに晩年であった。苦悩の実生活の傍ら、コンスタンティヌス帝の死、ヘレナやエウセビアの死を経て、自然に誘われるように母の死を思い、最期を迎える。
苦悩の一方で、予見される死に向かいながら、次第に一人の人間としてのささやかな救いを手にする。
物語の要所に、風が吹いている。
象徴的と見なすより、それはごく自然なもの、と私は受けとめたい。それが、風の示す意味、つまり何の象徴にもなり得ない、という象徴だからだ。逆説的で変な表現であるが‥
そこに在る、という意味しかない存在、ただし希薄な存在というのとも違う。
さておき、
以下、小説の中の、ユリアヌスの苦悩の軌跡を辿ってみる。
参考文献
『背教者ユリアヌス』辻邦生著
『ローマ帝国衰亡史』エドワード・ギボン著
『ローマ人の物語』塩野七生著
『多神教と一神教』本村凌二著
『背教者ユリアヌス』辻邦生著
『ローマ帝国衰亡史』エドワード・ギボン著
『ローマ人の物語』塩野七生著
『多神教と一神教』本村凌二著

1. 幽閉された若い皇族からアテナイの哲学生へ
ローマに求められる役割とは
ユリアヌスはかつて、ガルスとともにマケルム宮殿に幽閉されていた頃、カエサレアの教会で、周囲に促されるままに洗礼を受けている。皇帝即位時に既にキリスト教受洗者だったのは、ユリアヌスが最初だったかと思う。当時の彼は、教会の密儀的なミサの雰囲気や、質素な姿で貧民に食を施す僧の献身ぶりに、純粋に感動を覚えた。
しかし、その一方で、幼少期から彼を囲み、監視していた位の高い聖職者たちの、利権にしがみつき、醜く争うさまには不快と憤りを感じていた。
キリスト教徒への、次第にふくらむ嫌悪の感情を、ユリアヌスは時折兄のガルスにぶつけていた。ガルスも洗礼を受けていたが、ただ慣習に従ったまでで、信仰はどうでもよかったようである。ガルスは、コンスタンティヌス帝がキリスト教を公認したのは、統治を補強するための手段として利用したものだと考え、ユリアヌスにも語っている。それでもガルスは、ユリアヌスが純粋なあまりにキリスト教の欠点を声を大にして暴露し、ローマ異教信仰を賛美することの危険を、少なからず心配し、自分が副帝となって東征したのちのユリアヌスを案じて、信頼できる僧アエクス(架空)を、ユリアヌスのもとへ派遣して観察させた。尚、ガルスのこうした、ある程度ざっくりした判断や合理的な権威主義は存外、皇帝という独裁的統治者の資質にかなっていたのではないかと思えるところがある。もちろん、たびたびの残虐な粛清には非人間的な冷酷さもあり、さすがにコンスタンティウスも危機感を抱き、弟ユリアヌスも兄のこういう側面を危惧していたという。残酷さは、コンスタンティア妃の影響によるとも見られている。
さて、磊落な性格のアエクスは、ユリアヌスとの対話を通しての感想を、ガルスに報告した。
「もし副帝が心配するように、ユリアヌス殿がローマ異教を信じているとしても、その心情の公正さは、へたなキリスト教徒より、はるかに高潔だ。教会内に勢力を伸ばすことに汲々としている聖職者にくらべれば、このギリシャかぶれの青年のほうが、よりキリスト教的だと言えるかもしれぬ」
ガルスはその後、不幸にも皇帝の怒りを買い、処刑される。ユリアヌスも疑われ、抹殺されようとしていたところを、皇妃エウセビアの機転により救われ、ギリシャに留学というかたちで安全を得た。
ユリアヌスは、憧れの留学先ギリシャにおいてさえも、彼の理想である古来の信仰が廃れつつあり、キリスト教が根付き始めている現状を知り、落胆した。そんな折、恩師の妻、病的な黒い眼のヒッピア(架空)との何気ない会話に衝撃を受ける。
ヒッピアは自分の家族の周辺に起きる様々ないざこざに心が折れて、どうにもできぬと感じ、諦めと不安を感じている。
「時々不安な気持ちが起きると、教会へ行ってみたい気になりますの」
キリスト教教会には安らぎがあり、ギリシャ神殿では安らぎを感じらない、と。それを問うユリアヌスに、
「それは、キリスト教徒が、自分を棄てることを知っているからではないでしょうか。…何もかも神の前に投げだして、すべてを神の思召しのままに委託する。こう考えると、私ね、急に、いままでの不安が霧のように薄れて消えてゆくのを感じましたの。主人は、キリスト教徒は人間としての品位を持たないし、文章も粗野で、趣味も下劣だと申します。でもあのような不安におびえているとき、美しい文章や高雅な彫刻がいったい何の役に立つのでしょう?…キリスト教徒は文章を飾りません。飾る必要がないからではなないでしょうか。キリスト教徒にはただ真実だけが要るのではないでしょうか」
ヒッピアの示すこの熱狂が、ギリシャの神々を信じる人にはない、ということをユリアヌスは痛感する。
信仰はヒッピアの抱くような熱狂は必要だが、
「同時にすべてを抱擁しうる明晰な理性が支配しなければならぬ。もしキリスト教徒のように排他的な無智が熱狂を呼ぶとしたら、それは愚かしい狂気であって、リバニウス先生が解かれたような全宇宙を支配する普遍的精神と一致することはできず、またそれ故に正義を実現することはできぬ
。なせなら正義とは、ただこのロゴスの中にあるのだから」
ユリアヌスは考えをそうまとめながらも、確信を持てないままだった。宵闇のなか、露台でそんなことに思いふけっている時、町の雑踏がぼんやりと耳に響いてくる。その響きに歓喜の思いが起こる。
この歓喜は、私が地上にこうしてあることから生まれている。都市の喧騒、花、花の香りを運ぶ風、夕焼け空や星空、木立、書物、噴水、人々の声や様子‥
「この広大な世界を一つにして、そこで人々が生き、たのしみ、喋り、働き、旅をするのを保証するのがローマ帝国の役割なのだ。ローマ帝国の役割は地上に在ることの歓びを担いつづけることなのだ」
ユリアヌスはそう思い至り、幸福感に満たされたのだった。
2. ガリア副帝からローマ帝国皇帝へ
ローマはキリスト教をどう包摂すれば良いのか
この後、ギリシャ留学は短期間で打ち切られてしまい、ユリアヌスは、ガルスのときのように、皇帝の思いつきでガリア副帝に任じられた。ユリアヌスの派遣に伴ってなされたガリア方面の人事は、ユリアヌス失脚を狙う者たちばかりだった。その中で、ただ一人、エウセビアのはからいによって随行することとなった元財務官でガリア出身のサルスティウスは、ユリアヌスに深い忠誠心を抱く。既に五十年配の、体格良く、彫りの深い端正な顔立ちと、穏やかな様子、宮廷の女性たちの視線を集める見目良さ。そのサルスティウスによるユリアヌスの印象はこうである。
「エウセビア様はこの若い副帝を愛しておられるに違いない。だが、それも無理からぬことだ。人間が、このように純粋に理想を追い求めうるなどと、誰が考えたろうか。なるほど人は哲学を学ぶ。文学を修め、修辞学を研究する。だが、いずれ、そうしたものが、この世の猥雑さのなかで、ねじまげられ、希釈され、元の形も見えなくなることを知っている。どこかに、そうした現実への諦念を感じている。しかしこの若い副帝は、そうした辛い境遇のなかで知らされながらも、なお、人間本来の夢のような理想に憧れている。ガリアに向う人間のなかで、誰が、この人のように、ガリア人の幸福を真に考えているだろうか。しかしこの副帝だけは、大真面目に、ただそのことだけを考えている。自分が皇帝の虚名のために選ばれたことも、多くの売名だけの野心家たちがガリアに乗りこんだことも、知ったうえで、この人は、なお、人間が、よきことを為しうるし、為さねばならぬ、と信じている。なんという現実離れした夢想だろう。だが、人間が地上に生まれて、ただ一回きりの生をしか生きられないのなら、人間が果たせぬ夢と思い描いたこの美しい夢を、どうして描かずにすますことができるだろう。あるいは、こうして夢をみつづけた人間があるからこそ、ローマ帝国はこのように普遍の正義を保ちえたのかもしれぬ。たしかにローマはガリアに普遍の正義を行なってはおらぬ。私はローマでは蛮族出身者に過ぎぬ。だが、ここに一人のローマ人がいる。この人は普遍の正義をガリアで実現しようとねがっている。思えば、ローマの正義を支えているのは、この夢想するただ一人の人間であるかもしれぬ。なおガリアにローマの普遍の正義は実現されていない。だが、ここに一人の夢想家がいて、その不毛な土地に種となって、落ちようとしているのだ。いつ、それが豊かな麦となって、大地を覆わぬともかぎらない。私はガリア出身者だ。しかしいつガリアかローマの普遍の正義によって世界の中心にならぬともかぎらない。大切なのは、種を腐らさないことだ。種が播かれることだ。種を世代から世代へ伝えてゆくことだ。たとえ種がただちに麦をみのらさずとも、夢想のなかで種が生きつづけるかぎり、人間は、人間に失望してはならないのだ」
"人間は人間に失望してはならない"
これはユリアヌスの信条と似たところがある。
副帝ユリアヌスは、ガリア統治において、ローマの国教信仰を奨励。その一方、皇帝の偵察を恐れ、表向きはキリスト教徒として振舞う。
ガリアの司教で、ヘレナ妃に寄り添う、暗い禁欲的な眼のアブロン(架空)がその矛盾を執拗に突いてくる。
「陛下はキリスト教に単なる同情を示されているだけではないか」
アブロンのこの問いに対し、彼が宮廷に内通している可能性も考え、ユリアヌスは慎重に返答する。「人間は神の前に全て平等である」というキリスト教の考えはローマの理想と同一であり、共感する、と答える。しかし、アブロンは、帝国は支配・被支配の不平等を生み、貧富の差を生んだと反論する。ここで、ユリアヌスは秩序について論証する。
帝国において言うならば、万民平等は無秩序にならざるをえない。人々を自由にするためには、帝国の秩序が必要であり、秩序には人々の同意と自由意志による服従が必要である。その下で、人々はそれぞれの位階において幸福を得られ、自由であることができる。キリスト教徒は魂を神にあずけることで解放されるというが、これを自由というか。
別の問答もかけられる。
「陛下は古くからの信仰をどうなさろうというお積りか。キリスト教を信じながら、なぜ忌まわしい偶像神に執着しておられるか」
曰く、もし真にローマを統一する精神の原理があるとすれば、そうした雑多な合成物ではなく、統一な原理でなければならない。コンスタンティヌス帝はそれを志していたはずだ、と。
ユリアヌスはまず、キリスト教の矛盾を突く。
統一神でありながら、キリスト教の教理は四分五裂、宗教会議では血の惨事にすらなる。真実は一つと言い、教義の正統性は真実によって判定されると言うが、真理がなぜ自らの手を血で汚すか、正義がなぜ自らを不正な手段で守るか。
「私は正義とはあらゆる強制を含まぬものと思っている。正義とは自由に他ならぬ。
あなた方は人間について多くを知っている。現実がとのようなものであるか、鋭く見抜いている。それでも私は人間を自由のなかに放置する。100年経っても、500年経っても人間は自発的に正義を実現しようとしないかもしれない。しかし人間が人間を自由な存在としたこと自体が、すでに正義の観念を実現したことなのだ」
アブロンは、ユリアヌスの考えに同調することはできない、絶対神を信じる彼にとって、「人間の意志ほどあてにならぬものはない」と。
「それならば何をもって秩序と正義の尺度となさるか。
人間は神のものである正義を実現することはできない。神の絶対性に保証された秩序こそが真の秩序である。」
ユリアヌスはこう述べる。
「能うかぎりの力を尽くしてこの世の重荷をわれわれが負うのだ、われわれがそれを担って運ぶのだ、われわれが目を覚まして、自分自身を監視するのだ」
アブロンは、それは人間の傲慢以外の何ものでもない、と冷ややかに言う。
ユリアヌスは苛立ちながら、
「人間は永遠に未完成のものかも知れぬ。永遠に完成に向かって走りつづけるものかも知れぬ。だが、それは走っているのだ。そのことが肝心なのだ」
ローマは光であり、理性によって蒙昧さを照らし出すべきものである。しかし、ひょっとしたらローマは光ではなく、光であろうとする意志であり、そうした意志を放棄しない以上、ローマは光となるのかも知れぬ、ユリアヌスはそう考えた。
人間は人間の尺度によって測られるべきもの、というのはギリシャの知恵。その人間を守るのが地上の秩序。それに生気を与えるのがローマの信仰。
「神々は私たちの傍らにいるのだ。私たちは神々の寵愛のなかに生きているのだ。ああ、事がさのようであるのに、ガリラヤの狂信者は、なぜ地上の生を憎むのか?神々の恩寵は彼岸にあるのではなく、此岸にある。この息こそが神々の姿なのだ。ああ、我が息よ。我が刻々の生命よ…」
3. キリスト教に浸食されたローマの皇帝
ローマ神教に普遍的精神を求めて
このあと、ルテティアにて正帝に推挙され、コンスタンティウス帝と対立し、戟を交える直前にコンスタンティウス帝が急死したことでローマ帝国皇帝となったユリアヌス。
ローマ古来の宗教を奨励し、保護を与える一方で、キリスト教弾圧には走らず、宗教寛容令を出す。これまでのローマ皇帝は特定のキリスト教教派を支持してきたが、それを廃止し、全ての教派、全ての宗教を同等に公認するとした。
「ローマの魂はギリシア古来の神々のなかにのみ求められる。しかしローマはすべての存在にあるがままの本性における存続を許すのだ。この事実によってローマの秩序が実現されているのだ。ローマとは各自が自己を主張しつつ共存する自由に他ならぬ。私が宗教の寛容を許すのは、かかるローマの精神に基づいているからだ。諸君は諸君自らの主張に立ちつつ、ローマの秩序に服さねばならぬ理由もそこにある」
弾圧を恐れていたキリスト教徒たちはこの寛容令を喜ばなかった。彼らにとって、異教徒よりも他教派と同列にされることが屈辱だった。また、弾圧されなかったことで、殉教という栄光のステージにありつけなかったことに侮辱を感じた。ユリアヌスは当然、彼らを熱狂させ、さらなるドラマで信仰を深めさせる殉教など、断じてさせない狙いだった。さらに、これまでキリスト教が特権として得ていたもの(地位、交付金等)は剥奪、返上させられた。過去にキリスト教徒が散々の狼藉で破壊してきた異教の神殿への賠償も求められた。エルサレムへのユダヤ教神殿の再建も計画された。キリスト教が蔑んでいたユダヤ教を復興することで、キリスト教はそもそもユダヤ教から派生した一教派に過ぎないことを再認識させる狙いもあった。
「理性によらなければ正義は実現できない」と考えるユリアヌスは、「自由と寛容なくしてはローマはない」という信念で事にあたる。
ただし、信念は確信していても、現実を前に心が揺らぐ。「ローマは排他的に拡がってゆくガリラヤの連中を同化できず、最後にはローマが否認されるのでは」と。
キリスト教徒の神像破壊や神域冒瀆は一向に止まず、ローマ神教信者からの報復もエスカレートした。彼は忍耐強く、寛容と秩序維持を呼びかけ続ける。
しかし、いつまでもこの状況を続けるわけにはいかなくなった。東方ペルシアの騒乱を収めるため、ガリア軍団を主力とする東征に向かうこととなった。その間、治安を維持するためとして、キリスト教徒の身分を大幅に制限する命令を出した。そしてローマ神殿への優遇を大々的にすすめたのである。
キリスト教会への補助金交付打ち切り、キリスト教の司教や司祭の治外法権の廃止、贈られていた特権・尊称・名誉の剥奪、司祭の階級は都市の最下層との位置づけ、青少年の教育者からキリスト教徒を除外…
ユリアヌスの義憤が寛容の器から一気にあふれ出したかのようなこの制限令には、周囲から否定的な意見もあった。この時期に制限することは混乱をかえって生む可能性があると。しかしユリアヌスは既に別のステージに足をかけたらしく、キリスト教会への補助金を削った分をローマ神殿への犠牲獣の費用にそっくり回し、ユピテル神殿に毎日100頭の牛や鳥を捧げ、自らも祭儀で手を血で染めた。
懐柔と弾圧のバランスを最適化すること、キリスト教とは人間にとって何なのかを粘り強く把み、コントロールするには?
振り子のように振れつつも、ユリアヌスの抱くローマの理想は失われていない。いかに秩序を保つかが、ローマ皇帝の使命であると。
小説中で、ユリアヌスの親身な側近の会話がこの状況を確認し合っている。
側近の中でも冷静な穏健派の元老院議員テミスティウスによる。
「問題の核心はただ一つ、キリスト教をいかにしてローマの秩序に服させるべきか。つまり、熱狂的な絶対探究者たちに対して、いかにして地上の相対的な調和感覚の意味を納得させるか、ということです。おそらく人間の歴史はこの二つの生き方、考え方のあいだで揺れ動くことでしょう。一方は厳しく、他方は柔弱です。一方は渇いたような眼をし、他方は距離を置いた眼をしています。しかし人間が人間でありつづけるためには、人間を殺すような絶対を拒むほかありません。これはローマの限界ですが、同時に人間の限界でもあるのです。しかし人間の品位はただこの限界を知って、そこで踏みとどまり、その宿命を背負うところにしか生まれません。アエリア(イスラエル)の神殿再建もその一つの現れです。アリピウス、わたしはあなたの悩みはわかるが、苦悩によってしか人間は偉大にならぬのも事実です」
4. アンティオキア、ダフネ炎上
意図と結果のどちらが
正義が実現されない。
キリスト教徒への寛容も制限も、問題を積み残した状態で、解決は遠征のために中断することになったが、ユリアヌスは遠征中もこの件を考え続け、相変わらずプラトンやソクラテスを深夜に読み、帰還後に解決を図る予定だった。
ところで、ユリアヌスが台頭するキリスト教を制限する一方で、自然に廃れゆくローマ神教を露骨に再興させようとしたのはなぜなのか。
「そうだ、たとえ私が敗れようと、それは神意に他ならぬ。私は私自身である以上に、神々の心を体現した者だからだ」
神々に命運を預けるという点においては、キリスト教徒と同じに聞こえる。しかし、彼は自分にこう言い聞かせる。
「ユリアヌス、あせってはならぬ。物事はただ物事の理法に従ってしか動かぬのだ。それは物が地上に落ち、水が低地にむかって流れるのと同じだ。それに逆らうことはできないのだ。その理法に従って動いてのみ、事が成就するのだ。…信じるのだ。そしてお前の全力を尽くすのだ」
「信じる」、ここまではキリスト教の信者と同じであるが、その一方で自分の「全力を尽くす」のが彼の信仰だ。
一神教と多神教の違いを、塩野七生氏は著作の中で簡潔にこう表している。
「ギリシア・ローマに代表される多神教と、ユダヤ教を典型とする一神教の違いは、次の一事につきると思う。多神教では、人間の行いや倫理道徳を正す役割を神に求めない。一方、一神教では、それこそが神の専売特許なのである。多神教の神々は、ギリシア神話に見られるように、人間並みの欠点を持つ。道徳倫理の正し手ではないのだから、欠点をもっていてもいっこうにさしつかえない。だが、一神教の神となると、完全無欠でなければならなかった」(『ローマ人の物語』(Ⅰ 41)より)
日本人としては多神信仰は容易に了解できる。かみさまとかご先祖さまに見られていると思ったり、滝や神木に自然と手を合わせたり。
ユリアヌスはさらに哲学を修めた人ゆえに、こうした神々に普遍的精神の姿を見る。マルクス=アウレリウスの自省録はユリアヌスの鏡である。個人としての信仰以上に、ローマを体現するべき皇帝としてさらに深く、神々と結ばねばならない自負もあったようだ。ローマ皇帝として、万能感を抱いていたわけではなく、謙虚な中で真摯に、ひたすら調和を願っていた。
しかし不幸にも、彼の良心の支えでもあったこの思いを決定的に踏みにじる事件が、遠征の逗留先のアンティオキアで立て続けに起きてしまった。
ダフネはアポロンを祀った神殿と、神秘的な環境にめぐまれたローマ神教の聖地で、アンティオキアの近くにある。ユリアヌスはこの地を意気揚々として訪れたが、荒廃がひどく、大変なショックを受けた。彼がもっとも憤慨したのは、神殿の向かいにキリスト教の教会堂が建てられていて、神殿の部材を持ち出して使っている形跡もあった。さらに、教会のまわりには信者の墓まであり、聖バビュラスの墓も祀られていた。神域を墓で汚されたことを許しておけず、教会堂の取り壊し、墓の移転を命じ、神殿は新たに補修、再建させた。当然、キリスト教徒は抵抗、バビュラス様の天罰が下るだろうと背教帝を呪った。
完成した神殿で盛大な祭祀が数日にわたって催されたが、キリスト教徒が妨害し、傷害事件を引き起こした。それでも怒りをどうにかおさめたユリアヌスだったが、とうとう限界に晒された。
それは祝祭後、キリスト教徒の墓の移転が行われた日、風雨の強い夜のこと、ダフネ神殿が炎上したのである。軍が必死に鎮火に奔走したが、残念至極、神殿は見る影もなくなった。キリスト教徒らは、バビュラス様の天罰だ、と大威張りで喧伝したが、ローマ神教徒らは、これはキリスト教徒による放火だと憤った。ローマの正義を傷つけるキリスト教徒の蛮行に、業を煮やした純朴なガリア軍の将軍たちは、厳罰を命じるようユリアヌスに迫った。この状況に従来のように寛容で応じればますます見下され、次はもっと過激になるおそれもある。ローマの正義と自由が宙に浮き、ユリアヌスを大いに悩ませたが、放火をしたと自供した聖職者らが逮捕されたとの報告がきた。手を打たぬわけにはいかなかった。もっとも、冤罪かもしれないし、逆に殉教者として名を高める機に利用したのかもしれない。ユリアヌスはこれらの者を処分し、アンティオキア大教会の閉鎖を命じた。此の期に及んで背教帝の正体見たり、とキリスト教徒たちはネガティヴキャンペーンに火をつける。街の広場では、あからさまにユリアヌスをコケにする輩が増えた。これがアンティオキアの民の救いようのない品性だった。この不品行、風紀の乱れに、反逆罪や侮辱罪で粛清することも皇帝の権力を行使すれば可能だった。しかしなんと、ユリアヌスはこれにユーモアで答えたのである。『ミソポゴン(髭嫌い)』と題した触書の中で、自分の弱点を巧みな表現で誇張、これは民を唖然とさせ、悪口を言う気を失くさせたのだった。
そしてもう一つ、決定的にユリアヌスの忍耐を挫いた一件は、アンティオキアの飢饉のためにアフリカから調達した小麦を、地主や商人たちが値段を吊り上げるために買い占め、飢える民に配給しなかったことだ。民はユリアヌスの無能を恨んだが、ユリアヌスは、正義からかけ離れたこの卑劣な行為には我慢がならなかった。小説の中でユリアヌスが最も苦しい涙を流すのがこの場面である。
「見たまえ。これが人間なのだ。貪欲と吝嗇と冷酷と無慈悲…一体なぜこのような人間を見ながら、われわれは正義とか自由とか勇気とか親切とかを口にすることができたのか。…サルスティウス、われわれだけでも、この怜悧という怪物の属性から免れていようではないか。…われわれは人間であるために、最も冷酷な化け物が愚行と見なす行為をなそうではないか。われわれは地主どもから高価な小麦を買いもどすのだ。われわれは法と武力により小麦の供与を強制すべきかもしれぬ。だが、われわれはあえてこの愚直さを選ぼうではないか。
われわれの意図がこの世で実現せられずとも、人間にとって意味があるのはその意図であって、結果ではない。おそらく意図に反した結果だけが、今後ともローマの歴史を支配してゆくかもしれない。ひょっとしたら結果だけを狙った有効性の観念が人間を支配するかもしれない。しかしそのときになっても人間にとって意味があるのは、意図だけなのだ。人間にとっての真の実在はかかる善き意図による帝国なのだ」
悪意に善意で返そうとする、権力で導くのではなく、相手の気付きを待つ。この手法は、ユリアヌスが軽蔑していたイエスキリストと重なる。本来ならば通じ合えたはずなのだが、300年の隔たりの間にさまざまな人間が介在して、混沌に阻まれ、手を取り合えなくなってしまったように思う。たとえば、ユリアヌスが1世紀頃の皇帝だったら、イエスをローマの神の一人に神格化させ、崇拝したかもしれない。勝手な想像で、怒られるかもしれないが。
 コンスタンティウス2世
コンスタンティウス2世 ユリアヌス
ユリアヌス5. ペルシア討伐の途上
ローマも幻影、しかし何という‥
終章「落日の果て」だけは、途中までだがユリアヌスの回想のかたちで書かれている。メソポタミアの砂地の幕営で、ユリアヌスはそれまでの行軍の経過を頭の中で丹念にたどっている。ユリアヌスの軍は追い込まれてた。夜、外は砂を巻き上げる嵐。眠れぬまま机の上で考えに耽る中、ふとオデッセウスの昔覚えた詩句が唇に上がってくる。
葡萄の葉かげを夏の風吹き
ここは母の奥津城どころ
母バシリナ。何年も思い出したことがなかった母の墓石が、突然浮かんだ。
「母がいなければ私という存在はなかったのだ。母は、自分の赤子がローマ皇帝になることを知らなかった。しかし母が残した子供が現にここにこうして皇帝としているのだ。おそらくそれと同じようにわれわれは多くのことを知らないし、また知らないうちに多くのことを為している。
おそらく私は皇帝でいて、皇帝でないのだ。私はここにいて、同時にここにいないのだ。人生とはそういうものだ。この机のうえの燭台の火のように、ささやかな明りを厖大な闇のなかに差しだし、一瞬ゆらめいて、また消えるのだ。母が残した私をこの世に送って、母自身が死ぬとは、母が私であり、私が母でしかないことだ。人というのは、すべてそうした元永なのであろう。多くの人々がいるこのローマ帝国に現れ、やがて消えてゆく。おそらく路帝国そのものも一つの幻影であるかもしれぬ。そのなかでわたしはささやかな役割を果たしたにすぎぬ。だが、何という壮大な夢なのであろう。何という祝祭行列にも似た幻影の群なのであろう…」
ユリアヌスは、人生のある瞬間にたびたび経験した、突如差し込むような、天から何かが降りてきたような感覚にひたされることがあった。顔も知らない母を強く感じるような瞬間や、光に包まれて時間がなくなったような、身体が透明になるような感覚。その不死に似た感覚の中に、母や父がいるような気がしてひとときのめり込んでいく。
今や、その底流に在る、幻影のはかなさを受けとめ、身を委ねんとしている。
かつて、コンスタンティウス帝の急死の知らせを受けたとき、ユリアヌスをおそったのは人間の免れ得ない人間の悲しみだった。
敵であるコンスタンティウス帝の死によって、自分とガリア軍の破滅や、内戦による荒廃を回避できたことで安堵するべきところである。しかし、
「彼は自分がどこにいるのかわからない気持ちだった。ずっと以前、どこかで、いまとまったく同じ気持を味わったことがあるような気がした。そのときもたしか風の音が遠くに聞こえていた。部屋に入っても、何か新しい著述をはじめても、それはすでに前もってすべて決まっていて、ただその同じすじ道をなぞってゆくような、そんなそらぞらしい感じだった。そうだった、こうして皇帝が死ぬこと、それを風の強い日に聞くこと、それはもうずっと以前に彼にわかっていたのだった」
「すべてのことが、このような形でしか、、はっきり現れてこないのが、何か無限に悲しかった」
「誰にでもこういう瞬間がある。しかしそれは、いつでも現れるというわけじゃない。だが、こういう瞬間があって、そのとき、その本当の姿がわかるというのも事実なのだ。だが、なぜもっと別の形で、それは現れてきてくれないのか。所詮、人間は、あらゆる愛憎を失った瞬間にしか、その本当の姿を見ることはできぬのかもしれぬ。だが、そのことも悲しいことだが、しかしこうして現れたコンスタンティウスその人の姿も、何という悲しみに満ちていることだろう。それは彼がコンスタンティウスであったからではなく、もともと人間というものは、その本来の姿では、このように限りない悲しみを湛えた存在であるからかもしれぬ」
そしていよいよ、ユリアヌスは、槍に貫かれ、自分の死を迎えることになる。
6. 死に臨む
刻々に奇蹟に満たされた地上よ
「敵襲の叫びが後衛の軍団から聞こえてきたのはそのときだった。全軍団が一瞬浮き足たち、まるで激しい風に吹かれた大麦のように、一斉に恐怖にざわめいた。盾だけを持って走りだす者、槍を手にして逃げだす者、人を押しのける者、叫びだす者、ただおろおろとする者か右往左往していた。ローマの陣営は大混乱に陥っていた。将軍や将校たちの叱咤する声が聞こえた。ユリアヌスは傍の兵士の楯をとると、すぐ馬に乗った。彼は兜も胸甲もつけようとしなかった。近衛騎兵がユリアヌスの後を追った。
「たたかえ。たちどまれ。密集隊形を崩せば死ぬほかないぞ」
将軍たちの声は嗄れていた」
ユリアヌスのこの後ろ姿の、後のことはもうここには書かない。
その夜、意識混濁の中、ユリアヌスは夢を見、自分の今が人生の何時なのか、定かでなくなる。
「彼は自分がどこにいるのか、時々、わからなくなった。彼は本当はまだ自分が子供であり、首都コンスタンティノポリスの対岸の離宮で、花びらを拾って、ヴェヌスの首にかけているような気がした。母バシリナも花壇のそばに立っていて、ユリアヌスが花の環を女神像の首にかけるのを、見ているように思えた。ユリアヌスはそのバシリナが皇妃エウセビアの顔になっていたのに、まるで気がつかなかった。彼は黒づくめの服を着た婆やのアガヴェが、自分のほうに近づいてくるのを見ていた。花の香りがして、羽虫や蜜蜂の唸りが聞こえていた」
地上の美しさを実感する。
変転、興亡は彼の前を過ぎて行ったが、そこには青空が輝き、風邪が木々を鳴らし、雨が窓を打っていた。都市の雑踏、笑い、叫び、悲しみ…
「魂が地上を離れるとは、地上の全てのものが美しく、素晴らしく見えることであるに違いない。おそらく人が死ぬというのは、ただ地上を憧れるというただそのことのために、意味を持つのかもしれない。地上とは、それほどにも神々に愛された場所であるからだ」
明け方、ユリアヌスは息をひきとる。
ユリアヌスの遺骸は、皇帝旗に包まれて、首都帰還の遠い厳しい路を目指す。
「ただ風だけが、空虚な砂漠を吹き、砂丘の斜面をごうごうと音をたてていた。砂はまるで生物のように動いて、兵隊たちの踏んでいった足跡の乱れを、濃くなる闇のなかで、消しつづけていた」
「激しい風が東から西へ砂を巻き上げて吹き、終日、空の奥で風の音が鳴りつづけた」
ユリアヌスの母バシリナの、"あの夢"には続きがある。血まみれの小部屋。陣痛のさなかに再びその夢を見たとき、今回こそは恐怖をおさえて、小部屋の奥に影のように立っている男の姿を見届けようとする。それが自分の義務と信じて。
「…彼女は小部屋のなかにいるはずなのに、まわりでは木々が夜風にざわめいていた。
その巨大な男は一歩バシリナのほうに近づき、死体を、手にもった剣で示すような動作をした」
コンスタンティヌスにちがいないと思いこんでいた。夫の兄で、強権を持つ大帝コンスタンティヌスには血塗られた過去がある。しかし違った。黄金の兜の下、若々しい、端正な鼻、静かな憂鬱な眼。バシリナはそれが焼け落ちたトロイの城を背景に立つ英雄アキレスなのだとはっきりわかった。
なぜアキレスが?輝かしい英雄の生涯と、たった一矢で尽きた脆さと短い命。我が子の未来を暗示するようで不安がかきたてられる。他に、バシリナはダフネの神殿が崩れ落ちる夢も見た。
後年ユリアヌスのもとにも、似た姿の人影が現れる。黄金の兜と甲冑。ユリアヌスはそれをローマの守護神と考えた。ユリアヌスが皇帝になる少し前や死を迎える少し前などに現れ、運命を示唆した。これは、ユリアヌス自身の著述にも記されている。
 コンスタンティヌス大帝
コンスタンティヌス大帝"背教者"という呼び名には、無宗教者か、戒律をわざと破るならず者かと勘違いされる懸念があるが、ユリアヌスの場合は、ローマを守る、つまり民を守るためにのぞましい信仰は、キリスト教のような、現世より来世を重んじる宗教ではなく、現世を生きる人々を側近く見守り支えて、地上の美しさを謳歌するのに誘うような存在である神々だと考えていた。すべてを神の思し召しに委ねるのではなく、勝利を神に祈願するとしても、成功すれば神の恩恵、失敗ならば、残念ながら加護が得られなかったと考え、本筋では自分の能力に頼り、最大限の努力をするのが、ギリシャ由来の多神教信仰である。かの守護神が最後に現れ、死が示唆されたとき、ユリアヌスは冷静な覚悟と向き合う。
「自分としては力を尽くしてきて、これ以上のことはできるとは思えない。たとえどのようになろうと、最善を尽くしたことを慰めとして、なるようにならせるほかに、どんな手だてがあるだろう」
この決意の翌日、楯を取って駆け出すユリアヌスの後ろ姿が、彼の最後の"最善"となった。
信仰心は心の支えになるものである。ただし、人として最善を尽くす能力を与えられているにもかかわらず、それを放棄し、神に全てを一任する類いの信仰には、どう向き合うべきなのだろうか。向き合うも何もなく、律法を守り、恭しく下を向き、崇めひれ伏すことが求められるのだろうか。
現代においても、宗教が必要となる局面は、社会により個人により様々だといえる。大切なのは、それが強要されるものであってはならないということ。多様性を認め合う余地を持つこと。一神教では後者を許さないことが多い。その点に切り込んでいったユリアヌスを尊敬する。本当の寛容とはどんなものかを、ローマの寛容で示そうとした。しかし、そのローマの理想は当時既に劣化しており、意図が実を結ばないままに命運が尽きてしまった。
何かに身を任せていることで安住する体質を、人はかかえている。それが中世の暗黒や、ナチスの台頭を培養した素因で、自身の毒で身を焼かれる結果となる。怠惰と勤勉。
全てを焼き尽くした世界大戦から100年と経たぬ今、どうなっているだろうか。
所詮、人のすることは浅薄なのだから神に全てゆだねるがよい、ではどの神が平和構築に尽くしてくれるのか、いつなのか、あとどのくらい犠牲を出して待てばよいのか。
そして、独裁者は人間であって神ではない。ユリアヌスも皇帝という独裁者ではあった。われわれは独裁者の行いを注視していなければならないが、寛容を全く持ち合わせない独裁者の場合、目を上げることすらわれわれにはできなくさせられるだろう。
平和、自由を望むなら、怠惰なおまかせコースでは無理だ。望むだけでは得られない。神がほんとうに約束してくれない限り、不断の努力を続けるしかない。ユリアヌスの後ろ姿を心に映して。
「人間は苦悩によってしか偉大になれない」
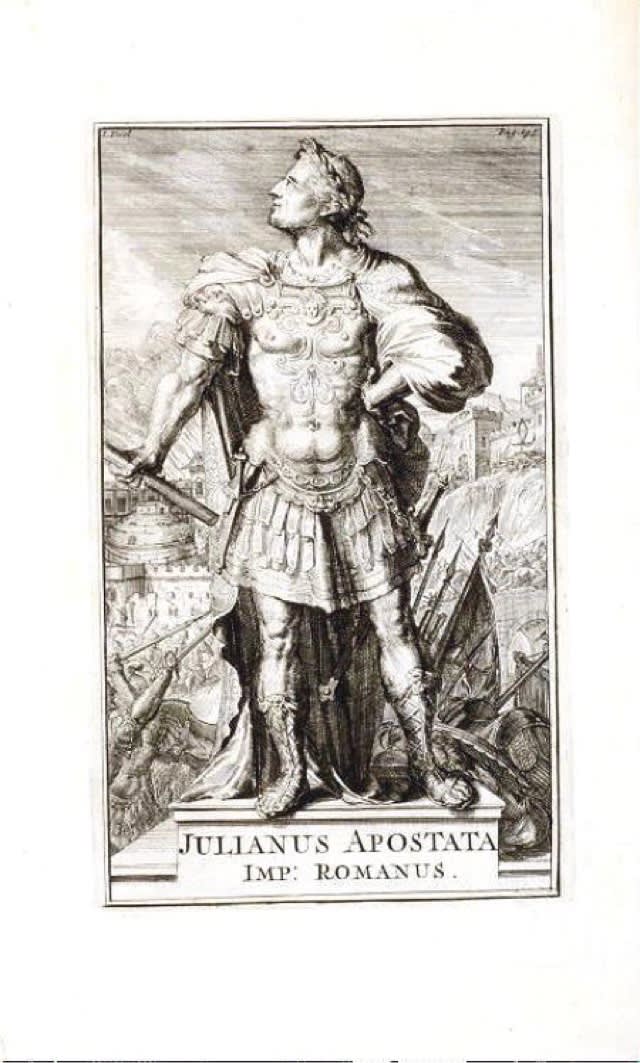
後記
ブログ開設から999日となるこの日、なかなかまとめられなかった『ユリアヌス』を書き終えられ、大きなため息、です。遠い遠い昔に生きたこの皇帝の生涯が、私のさまざまな疑問に答えを導いてくれた気がしました。辻邦生氏とユリアヌス皇帝に感謝します。









