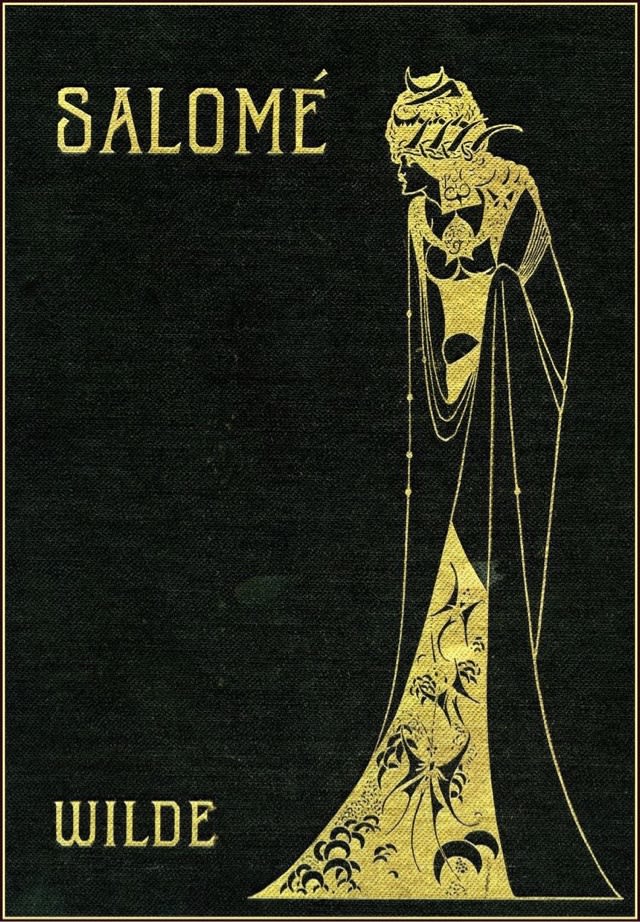三. 父子兄弟
話は戻り、木曾義仲が水島の戦いに敗れた頃。
音に聞こゆる剛の者、平家方の妹尾兼康は倉光次郎成澄に生け捕りにされ、斬られるところを木曾殿が、あたら男を失うべきではない、と成澄の弟・三郎成氏に預けた。気立ての良い妹尾は倉光にもねんごろにもてなされたものの、いつか必ず平家方に帰ろうと密かに時を待っていた。
かりそめに木曾殿に忠誠を誓い、故郷は良馬の飼育によいから案内したいと持ちかけた。
倉光や郎党を引き連れ、宿で酒に酔わせ、残らず刺し殺した。
周囲に声をかけ、手勢を集め、城郭をこしらえ、木曾の軍勢を待つ。
「にっくき妹尾め、斬って捨べきであったのに、ゆだんしてはかられたのは残念」
と義仲は、後悔した。
「きゃつの面魂はただ者とは思われませんでした。それゆえそれがしが、千たびも斬ろうとあれほど申せしに」
今井四郎(兼平)がそう言うと、義仲は、
「何ほどのことやあらん。追いかけて、討て」
と言った。
今井が三千騎を率いて、妹尾と向き合った。
籠城する妹尾と攻城する今井。
妹尾は城郭を破られ、落ちていく。
たばかられた倉光三郎の兄、倉光二郎と組んでその首も落とし、落ちて行こうとするが、妹尾の嫡子小太郎宗康、二十歳は太っていて走って来れない。妹尾は見捨ててしばらく行くが、馬を止めて言った。
「日ごろは千万の敵に会っていくさをしても、四方に一片の雲もなく、晴々とした気もちでおったが、今日は小太郎を捨てて行くためか、いっこうに先が暗くて、見えぬ。たとえこんどのいくさに命ながらえてふたたび平家の味方へまいったとしても、『兼康は、六十に余る齢をして、あといくつまで生きようと思って、一人しかない子を捨てて逃げてきたのか』などと同輩どもに言われるのが残念だ」
「さればこそ御一所でいかようにもならせたまえと、申し上げたではございませぬか。お引き返しなされませ」と郎党が言うので、兼康は引き返した。案のじょう、小太郎宗康は、歩けないほど足がはれて突っ伏していた。妹尾太郎は急いで馬から飛んでおり、小太郎の手をとって、
「お汝といっしょに討ち死にしようと思って、ここまで引き返してきた」
と言うと、小太郎は涙をはらはらと流して、
「たといわたくしこそ未熟のため、ここにて自害いたすとも、わたくしのために父上の御命まで失い参らすことは、五逆の罪にも当たりましょう。ただ疾う疾うお逃げのびくだされ」
と言ったが、
「いやいや、もはや思いきめた上は」
そこに、今井を先頭に五十騎が追いかけてきた。
妹尾は矢をさんざんに射、太刀を抜いて、まず小太郎の首を打ち落とすと、敵の中に入って多くを討ち取り、ついに討ち死にした。郎党も死力を尽くして戦い、果てた。
さらされた主従三人の首級を見た木曾殿は、
「げに、惜しかった剛の者よ」
と、妹尾の死を悼んだという。
忠と孝のはざまで、人の心はどう動くのか。
妹尾の場合は子に対しての情に動いたのだから、いわゆる孝とはちがうものかもしれないが、抽象的なモラルである忠と、側近くはっきりと形をなす孝とのはざまで、孝のほうへ下りてきた妹尾は、剛の者の兜を脱ぐかたちになった。
もしも忠を選び、剛の者として生きながらえたとしても、ここで物語として伝承されて残るほどにはならなかったかもしれない。多くの聞き手の心に響くのは、子を見捨てなかった父の姿だからだ。
わが子の首を自らの手で落とす。
その凄まじい覚悟には心をえぐられる。
鬼神の仕業ではない。立派な父の業と思う。
平家物語にはこのあとの戦いでも、梶原父子、河原兄弟、熊谷父子など、親子兄弟でかばい合う場面がいくつも描かれている。
ただし、悲しいことに美談となりえないことも起きた。
一ノ谷で敗れた平家は、舟に飛び乗り、沖に逃げていく。そんななかで悲劇はいくつも起きた。
四. "十六"
平知章/
平氏の重鎮たる平知盛。清盛の三男で、当時のナンバー2だ。一ノ谷の要衝・生田の森の大将軍だったが、子息の知章と侍の監物頼賢とともになぎさの方へ落ちて行った。
そこへ、源氏方の追っ手が迫ってきた。
追っ手の者が知盛に組みつこうと馬を寄せると、息子知章は父を討たすまいとして、中に割って入り組みつき、落ちて、取って押さえて、首をとった。そこへ、源氏方の童がきて、知章の首を取る。今度は監物が、馬から折り重なって童を討ち取った。監物はその場で矢を射、太刀をふり、一人さんざんに戦い、膝を射られて座ったままで討ち死にした。
知盛はこの間に逃げ果せ、兄宗盛の船にたどり着いた。
知盛は、宗盛の前に行って、
「武蔵守(知章)に先立たれ、監物太郎を討たれて、今は、心細くなりました。そもそも、子が親を討たすまいと敵に組むのを見ながら、子の討たれるのを助けもせずに、これまでのがれてまいる父が、どこにありましょう。あわれ、他人のことなら、いかばかり歯がゆいかしれませぬのに、さぞかし卑怯みれんな父と思われるであろうと、それがはずかしゅうござります」
た、鎧の袖を顔に押しあて、さめざめと泣く。大臣殿(宗盛)はこれを慰めて、
「武蔵守が、父の命に替わられたことはまことに殊勝ではないか。腕もきき心も剛気で、よい大将軍であったがこの清宗と同年で、たしか今年は十六歳のはず」
と言いながら、御子の衛門督清宗卿のいるほうを見て涙ぐんだ。その席に列していた平家の侍たちは、情けを解する者も解さぬ者も等しく鎧の袖をぬらした。
この日、波打ち際でもう一人、命を落とした十六歳がいた。平敦盛。若いが、宗盛、知盛の従弟にあたる。
平敦盛/
意気はずませ、齢十六の息子小次郎直家とこのたびの戦に挑んだ熊谷次郎直実。
「去年の冬鎌倉を立ちしよりこのかた、命をば兵衛佐殿にたてまつり、しかばねを一ノ谷の汀にさらさんと覚悟をきめた直実、去んぬる室山、水島両度の合戦に打ち勝って、功名した覚えのものども、直実親子に、出合えや、組めや」
しかし、小次郎が肘を射られ負傷、直実は一人、渚の方へ落ちて行く平家の公達を見つけて組み、手柄を立てたいと馬を走らせていた。
そこに、沖の船に向かって浅瀬を進んでいく一騎が目に入った。
「返させたまえ、返させたまえ」
武者は引き返し、たちまち熊谷はそれを波打ち際で組み落とし、首を搔こうと兜を押し上げてみると、それは、わが子小次郎と同年配の、十六、七の美少年だった。
「そも、いかなるお人にてわたらせたもうぞ。名のらせたまえ。助けまいらせん」
と言えば、
「まず、そういう和殿はだれぞ」
と問い返した。
「物の数にてはそうらわねども、武蔵の国の住人熊谷次郎直実ともうしそうろう」
「さては、なんじのためにはよき敵ぞや。名のらずとも、首をとって人に問えかし。人も見知らん」
「さてこそ、よき公達。この人ひとり討てばとて、負けるいくさに勝つべきはずもなし、また助けたとて、勝ついくさに負けることはよもあるまじ。けさ一ノ谷にてわが子の小次郎が、薄傷を負うてさえ心を痛めるのに、この若殿の父は、子が討たれたと聞いたら、どのように嘆き悲しむか。よしよし助けまいらせん」
しかし、振り返るとうしろに近づいてくるのは源氏方のライバル、土肥、梶原の五十騎ほどだった。
「あれをごろうじそうらえ。いかにしても助け参らせんとはぞんずれど、雲霞のごとき、味方の軍兵、よもお逃し申すまじ。あわれ、同じことなら、直実が手にかけて後世の供養をつかまつらん」と言うと、
「何を申すにもおよばぬ。とく首を刎ねよ」
熊谷はあまりのいとおしさに、どこへ刀のあてようもなく、目はくらみ気は遠くなって、しばし茫然としていたが、いつまでもためらっていられる場合ではないので、泣く泣く首をかき斬った。
「さてさて、弓矢取る身ほど、なさけないものはない。武芸の家に生まれなかったら、こんなつらい思いをしないですむのに。無情にも討ちまいらせたものよ」と、袖を顔におしあててさめざめと泣いていた。やがて、首を包もうとして、鎧直垂を解いて見ると、錦の袋に入れた笛が腰にさしてあった。
「さては、この夜明けに、城の中で管弦の音がしていたのは、この人たちであったのか。東国勢何万騎のうち、軍陣に笛を持ってきている風雅者はあるまい。公達のあわれさよ」
熊谷はあとで敦盛と知り、のちに出家して終生敦盛を供養したという。
血気はやる武将、熊谷は、手に入れた獲物に思いがけずわが子を見てしまった。そして、たった一瞬で、父の情にすり替わってしまった。そうとなれば、どうやってその首に刃をあてられよう。弓矢取る身の修羅道を思い知るのである。
そして、遺品の小さな笛が更に、失われたものの尊さ、美しさ、かけがえのなさをいやというほど知らしむるのである。その笛をとる、我が手の罪の重さ。
修羅の道には、敵とのこんな出会い方もあった。
運命が裏返る瞬間。
一方で、敦盛にとっては、この最期の刹那はどんなものであったのだろう。動揺し、ためらいながらわが命を奪う者。ただ死を待つ数秒、心は何を見ようとしたか。波打ち際には波の音、そしてさまざまな修羅の声が近く遠くに聞こえていた、それだけだったろうか。
十六という能面がある。
『敦盛』のために主に用いられるもので、女性の面、小面のように妖艶で、死の世界にはまるで無縁と思えるような輝く若さとあどけなさの面である。
喪われたのが若く美しい少年であったことが、修羅道の悲劇を深めた。二度と耳にすることのできない笛の音に思いはせても、悲しい。
一ノ谷の戦いでは、十六の敦盛、知章とともに、わずか十四の師盛も命を落とした。
師盛は重盛の七男のうちの五男。維盛、清経の弟。すでに船に逃れていたところ、他に逃れてきた武者が馬から船にドスンと飛び乗ったために船が転覆、海上に放り出された師盛は、源氏方の船に搔きよせられ、斬られた。年の若さからすれば、敵のなかに、熊谷のようにためらう者はいなかったのか。不幸な最期であった。
アツモリソウ、クマガイソウという草木もある。
花弁が赤いものと白いもの。いくさのときに付ける母衣(ほろ)に似たラン科の花。
あの苦しみの出会いと死別の時は昇華して、静かに今も存在している。
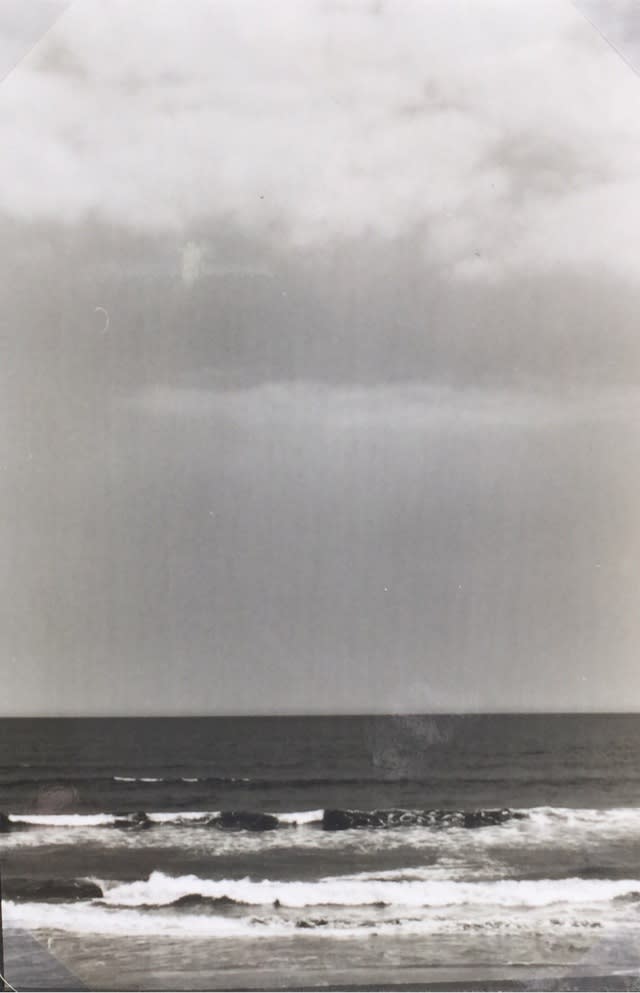
あともう一回、平家物語を書きます
話は戻り、木曾義仲が水島の戦いに敗れた頃。
音に聞こゆる剛の者、平家方の妹尾兼康は倉光次郎成澄に生け捕りにされ、斬られるところを木曾殿が、あたら男を失うべきではない、と成澄の弟・三郎成氏に預けた。気立ての良い妹尾は倉光にもねんごろにもてなされたものの、いつか必ず平家方に帰ろうと密かに時を待っていた。
かりそめに木曾殿に忠誠を誓い、故郷は良馬の飼育によいから案内したいと持ちかけた。
倉光や郎党を引き連れ、宿で酒に酔わせ、残らず刺し殺した。
周囲に声をかけ、手勢を集め、城郭をこしらえ、木曾の軍勢を待つ。
「にっくき妹尾め、斬って捨べきであったのに、ゆだんしてはかられたのは残念」
と義仲は、後悔した。
「きゃつの面魂はただ者とは思われませんでした。それゆえそれがしが、千たびも斬ろうとあれほど申せしに」
今井四郎(兼平)がそう言うと、義仲は、
「何ほどのことやあらん。追いかけて、討て」
と言った。
今井が三千騎を率いて、妹尾と向き合った。
籠城する妹尾と攻城する今井。
妹尾は城郭を破られ、落ちていく。
たばかられた倉光三郎の兄、倉光二郎と組んでその首も落とし、落ちて行こうとするが、妹尾の嫡子小太郎宗康、二十歳は太っていて走って来れない。妹尾は見捨ててしばらく行くが、馬を止めて言った。
「日ごろは千万の敵に会っていくさをしても、四方に一片の雲もなく、晴々とした気もちでおったが、今日は小太郎を捨てて行くためか、いっこうに先が暗くて、見えぬ。たとえこんどのいくさに命ながらえてふたたび平家の味方へまいったとしても、『兼康は、六十に余る齢をして、あといくつまで生きようと思って、一人しかない子を捨てて逃げてきたのか』などと同輩どもに言われるのが残念だ」
「さればこそ御一所でいかようにもならせたまえと、申し上げたではございませぬか。お引き返しなされませ」と郎党が言うので、兼康は引き返した。案のじょう、小太郎宗康は、歩けないほど足がはれて突っ伏していた。妹尾太郎は急いで馬から飛んでおり、小太郎の手をとって、
「お汝といっしょに討ち死にしようと思って、ここまで引き返してきた」
と言うと、小太郎は涙をはらはらと流して、
「たといわたくしこそ未熟のため、ここにて自害いたすとも、わたくしのために父上の御命まで失い参らすことは、五逆の罪にも当たりましょう。ただ疾う疾うお逃げのびくだされ」
と言ったが、
「いやいや、もはや思いきめた上は」
そこに、今井を先頭に五十騎が追いかけてきた。
妹尾は矢をさんざんに射、太刀を抜いて、まず小太郎の首を打ち落とすと、敵の中に入って多くを討ち取り、ついに討ち死にした。郎党も死力を尽くして戦い、果てた。
さらされた主従三人の首級を見た木曾殿は、
「げに、惜しかった剛の者よ」
と、妹尾の死を悼んだという。
忠と孝のはざまで、人の心はどう動くのか。
妹尾の場合は子に対しての情に動いたのだから、いわゆる孝とはちがうものかもしれないが、抽象的なモラルである忠と、側近くはっきりと形をなす孝とのはざまで、孝のほうへ下りてきた妹尾は、剛の者の兜を脱ぐかたちになった。
もしも忠を選び、剛の者として生きながらえたとしても、ここで物語として伝承されて残るほどにはならなかったかもしれない。多くの聞き手の心に響くのは、子を見捨てなかった父の姿だからだ。
わが子の首を自らの手で落とす。
その凄まじい覚悟には心をえぐられる。
鬼神の仕業ではない。立派な父の業と思う。
平家物語にはこのあとの戦いでも、梶原父子、河原兄弟、熊谷父子など、親子兄弟でかばい合う場面がいくつも描かれている。
ただし、悲しいことに美談となりえないことも起きた。
一ノ谷で敗れた平家は、舟に飛び乗り、沖に逃げていく。そんななかで悲劇はいくつも起きた。
四. "十六"
平知章/
平氏の重鎮たる平知盛。清盛の三男で、当時のナンバー2だ。一ノ谷の要衝・生田の森の大将軍だったが、子息の知章と侍の監物頼賢とともになぎさの方へ落ちて行った。
そこへ、源氏方の追っ手が迫ってきた。
追っ手の者が知盛に組みつこうと馬を寄せると、息子知章は父を討たすまいとして、中に割って入り組みつき、落ちて、取って押さえて、首をとった。そこへ、源氏方の童がきて、知章の首を取る。今度は監物が、馬から折り重なって童を討ち取った。監物はその場で矢を射、太刀をふり、一人さんざんに戦い、膝を射られて座ったままで討ち死にした。
知盛はこの間に逃げ果せ、兄宗盛の船にたどり着いた。
知盛は、宗盛の前に行って、
「武蔵守(知章)に先立たれ、監物太郎を討たれて、今は、心細くなりました。そもそも、子が親を討たすまいと敵に組むのを見ながら、子の討たれるのを助けもせずに、これまでのがれてまいる父が、どこにありましょう。あわれ、他人のことなら、いかばかり歯がゆいかしれませぬのに、さぞかし卑怯みれんな父と思われるであろうと、それがはずかしゅうござります」
た、鎧の袖を顔に押しあて、さめざめと泣く。大臣殿(宗盛)はこれを慰めて、
「武蔵守が、父の命に替わられたことはまことに殊勝ではないか。腕もきき心も剛気で、よい大将軍であったがこの清宗と同年で、たしか今年は十六歳のはず」
と言いながら、御子の衛門督清宗卿のいるほうを見て涙ぐんだ。その席に列していた平家の侍たちは、情けを解する者も解さぬ者も等しく鎧の袖をぬらした。
この日、波打ち際でもう一人、命を落とした十六歳がいた。平敦盛。若いが、宗盛、知盛の従弟にあたる。
平敦盛/
意気はずませ、齢十六の息子小次郎直家とこのたびの戦に挑んだ熊谷次郎直実。
「去年の冬鎌倉を立ちしよりこのかた、命をば兵衛佐殿にたてまつり、しかばねを一ノ谷の汀にさらさんと覚悟をきめた直実、去んぬる室山、水島両度の合戦に打ち勝って、功名した覚えのものども、直実親子に、出合えや、組めや」
しかし、小次郎が肘を射られ負傷、直実は一人、渚の方へ落ちて行く平家の公達を見つけて組み、手柄を立てたいと馬を走らせていた。
そこに、沖の船に向かって浅瀬を進んでいく一騎が目に入った。
「返させたまえ、返させたまえ」
武者は引き返し、たちまち熊谷はそれを波打ち際で組み落とし、首を搔こうと兜を押し上げてみると、それは、わが子小次郎と同年配の、十六、七の美少年だった。
「そも、いかなるお人にてわたらせたもうぞ。名のらせたまえ。助けまいらせん」
と言えば、
「まず、そういう和殿はだれぞ」
と問い返した。
「物の数にてはそうらわねども、武蔵の国の住人熊谷次郎直実ともうしそうろう」
「さては、なんじのためにはよき敵ぞや。名のらずとも、首をとって人に問えかし。人も見知らん」
「さてこそ、よき公達。この人ひとり討てばとて、負けるいくさに勝つべきはずもなし、また助けたとて、勝ついくさに負けることはよもあるまじ。けさ一ノ谷にてわが子の小次郎が、薄傷を負うてさえ心を痛めるのに、この若殿の父は、子が討たれたと聞いたら、どのように嘆き悲しむか。よしよし助けまいらせん」
しかし、振り返るとうしろに近づいてくるのは源氏方のライバル、土肥、梶原の五十騎ほどだった。
「あれをごろうじそうらえ。いかにしても助け参らせんとはぞんずれど、雲霞のごとき、味方の軍兵、よもお逃し申すまじ。あわれ、同じことなら、直実が手にかけて後世の供養をつかまつらん」と言うと、
「何を申すにもおよばぬ。とく首を刎ねよ」
熊谷はあまりのいとおしさに、どこへ刀のあてようもなく、目はくらみ気は遠くなって、しばし茫然としていたが、いつまでもためらっていられる場合ではないので、泣く泣く首をかき斬った。
「さてさて、弓矢取る身ほど、なさけないものはない。武芸の家に生まれなかったら、こんなつらい思いをしないですむのに。無情にも討ちまいらせたものよ」と、袖を顔におしあててさめざめと泣いていた。やがて、首を包もうとして、鎧直垂を解いて見ると、錦の袋に入れた笛が腰にさしてあった。
「さては、この夜明けに、城の中で管弦の音がしていたのは、この人たちであったのか。東国勢何万騎のうち、軍陣に笛を持ってきている風雅者はあるまい。公達のあわれさよ」
熊谷はあとで敦盛と知り、のちに出家して終生敦盛を供養したという。
血気はやる武将、熊谷は、手に入れた獲物に思いがけずわが子を見てしまった。そして、たった一瞬で、父の情にすり替わってしまった。そうとなれば、どうやってその首に刃をあてられよう。弓矢取る身の修羅道を思い知るのである。
そして、遺品の小さな笛が更に、失われたものの尊さ、美しさ、かけがえのなさをいやというほど知らしむるのである。その笛をとる、我が手の罪の重さ。
修羅の道には、敵とのこんな出会い方もあった。
運命が裏返る瞬間。
一方で、敦盛にとっては、この最期の刹那はどんなものであったのだろう。動揺し、ためらいながらわが命を奪う者。ただ死を待つ数秒、心は何を見ようとしたか。波打ち際には波の音、そしてさまざまな修羅の声が近く遠くに聞こえていた、それだけだったろうか。
十六という能面がある。
『敦盛』のために主に用いられるもので、女性の面、小面のように妖艶で、死の世界にはまるで無縁と思えるような輝く若さとあどけなさの面である。
喪われたのが若く美しい少年であったことが、修羅道の悲劇を深めた。二度と耳にすることのできない笛の音に思いはせても、悲しい。
一ノ谷の戦いでは、十六の敦盛、知章とともに、わずか十四の師盛も命を落とした。
師盛は重盛の七男のうちの五男。維盛、清経の弟。すでに船に逃れていたところ、他に逃れてきた武者が馬から船にドスンと飛び乗ったために船が転覆、海上に放り出された師盛は、源氏方の船に搔きよせられ、斬られた。年の若さからすれば、敵のなかに、熊谷のようにためらう者はいなかったのか。不幸な最期であった。
アツモリソウ、クマガイソウという草木もある。
花弁が赤いものと白いもの。いくさのときに付ける母衣(ほろ)に似たラン科の花。
あの苦しみの出会いと死別の時は昇華して、静かに今も存在している。
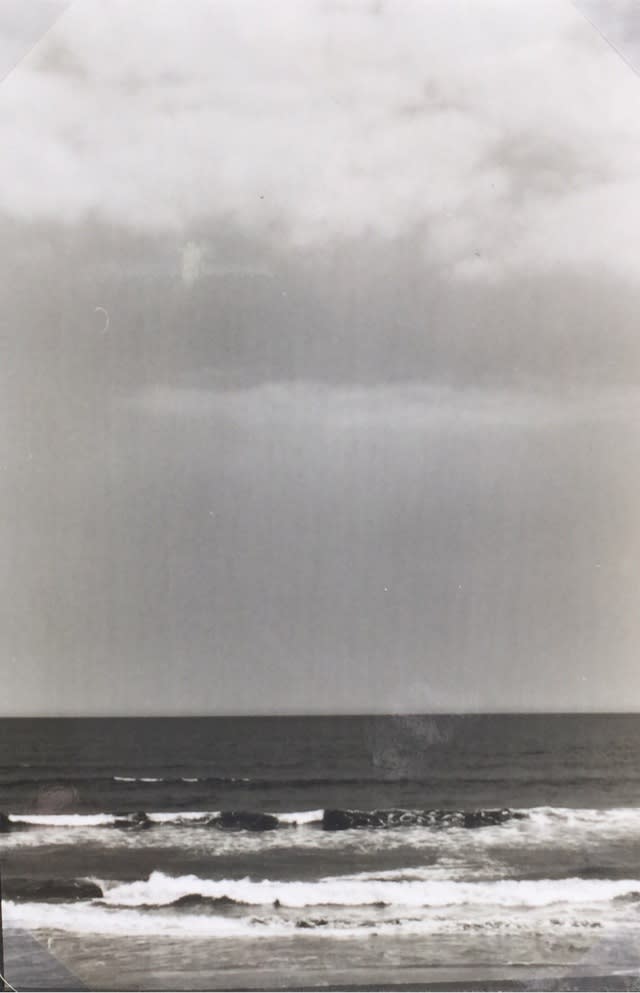
あともう一回、平家物語を書きます