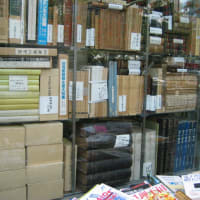絵に描いた餅は飢えを満たすことはない。しかしそれが餅の絵であるということには、いったいどのような意味があるのだろうか。概念としての「餅」が餅であるための条件はこれが飢えを満たすことができるもの、食の対象だというところにあるのではないだろうか。そうだとすれば絵に描いた餅が飢えを満たすことはできないといっておきながら、まさにその絵に描いた餅は、飢えを満たすたものに他ならない。ルネ・マグリットの作品に「これはパイプではない」と題された絵がある。たしかにそれは一枚のタブローであってタバコの煙を燻らすパイプそのものではない。わたしたちは絵の具の塗られたキャンバスを眺めているということか。しかしわたしたちは視覚与件を統合してパイプを作り上げてしまう。つまり目の前にあるものは明らかにタバコの煙を燻らす機能をもった対象なのであり、それ以外の何ものでもない。見る主体と見られる対象についてのこのような関係を考察するのがヨーロッパ的エスプリだとすれば、道元禅師の「画餅不充飢」ではこれとはまったく異なった議論が展開される。
「古仏言「画餅不充飢」」(注1)と書いていきなりその分析が始まる『正法眼蔵第二十四画餅』の巻を、むかしむかし古田紹欽先生に読んでいただいたのを思い出す。このとき「画餅」を「がへい」ではなくて「わひん」と読むが「わひょう」とも読むと教わった。当時使用したテキストは岩波の『日本思想体系12 道元(上)』だったが、たった五頁を一回当たり一時間半で三回かけて講義していただいたものだ。
最近再び読んでみた。古田先生によるコメントを書き込んだ岩波のテキストは、今でも判りにくい。理由は簡単で頭注そのものが判りずらいのと、そもそも本文そのものにも問題があるのであって、古田先生は「この「せずして」の「せず」は削って読まねばならない」とか「ここには「絵に描いた」という言葉を補って」とか、水野弥穂子の校訂したテキストをかなり批判的に読んでいらした。惜しむらくはわたしが未熟だったため、先生のコメントを充分に筆記し得なかったこと。
さて先ほどの「古仏言「画餅不充飢」」はそもそも「香嚴禅師の語を拈擧して、これを自由に評釋されたものである。『傳燈録』第十一巻、香嚴禅師の章に、「師遂に堂に帰り、集むる所の諸方の語句を遍く検するに、一言も將て酬報すべき無しと、乃ち自ら嘆じて曰く、畫餅飢に充すべからずと。是に於いて盡く之を焚く」とある。これを「古佛言く、畫餅は飢に充たず」と云はれたのである」(注2)。このことを知った上で読まないと道元禅師がなにを言いたいのかさっぱり判らない。逆にこのことを知っただけでも本文理解にはかなり助けとなるのだけれども、岩波のテキストにはその辺りの説明が一切ない(注3)。これでは「古仏言「画餅不充飢」」を「むかしの坊さんが腹が減ったとき、絵に描いた餅を見てこれは食えない、と言った」と解釈しかねない。
要するにこれは餅うんぬんの話ではなかったわけだ。一言でいうと香嚴禅師が文献からは得るものがないといってこれを焼き捨てたってことなので、道元禅師はこの場合の「画餅不充飢」を「画餅」の章で分析しているということになる。では、どのような分析がなされているのか。
(注1)『日本思想体系12 道元(上)』283頁 岩波書店 1970年5月25日第1刷
(注2)『正法眼蔵思想体系』五巻199頁 岡田宜法 法政大學出版局 昭和29年9月1日
(注3)『日本思想体系12 道元(上)』の渉典(480頁)に「古仏言「画餅不充飢」」が『傳燈録』第十一巻、香嚴章からの引用であることが示されているが、しかしこれだけでは専門家でない者には何のことだかさっぱり判らない。今日『景徳傳燈録』は活字本としては出版されていないが、京都大学図書館の開いているホームページから『景徳傳燈録』のきれいな写真版を参照することができる。しかし普通の人がこれをすらすら読めるとは到底考えられない。
「古仏言「画餅不充飢」」(注1)と書いていきなりその分析が始まる『正法眼蔵第二十四画餅』の巻を、むかしむかし古田紹欽先生に読んでいただいたのを思い出す。このとき「画餅」を「がへい」ではなくて「わひん」と読むが「わひょう」とも読むと教わった。当時使用したテキストは岩波の『日本思想体系12 道元(上)』だったが、たった五頁を一回当たり一時間半で三回かけて講義していただいたものだ。
最近再び読んでみた。古田先生によるコメントを書き込んだ岩波のテキストは、今でも判りにくい。理由は簡単で頭注そのものが判りずらいのと、そもそも本文そのものにも問題があるのであって、古田先生は「この「せずして」の「せず」は削って読まねばならない」とか「ここには「絵に描いた」という言葉を補って」とか、水野弥穂子の校訂したテキストをかなり批判的に読んでいらした。惜しむらくはわたしが未熟だったため、先生のコメントを充分に筆記し得なかったこと。
さて先ほどの「古仏言「画餅不充飢」」はそもそも「香嚴禅師の語を拈擧して、これを自由に評釋されたものである。『傳燈録』第十一巻、香嚴禅師の章に、「師遂に堂に帰り、集むる所の諸方の語句を遍く検するに、一言も將て酬報すべき無しと、乃ち自ら嘆じて曰く、畫餅飢に充すべからずと。是に於いて盡く之を焚く」とある。これを「古佛言く、畫餅は飢に充たず」と云はれたのである」(注2)。このことを知った上で読まないと道元禅師がなにを言いたいのかさっぱり判らない。逆にこのことを知っただけでも本文理解にはかなり助けとなるのだけれども、岩波のテキストにはその辺りの説明が一切ない(注3)。これでは「古仏言「画餅不充飢」」を「むかしの坊さんが腹が減ったとき、絵に描いた餅を見てこれは食えない、と言った」と解釈しかねない。
要するにこれは餅うんぬんの話ではなかったわけだ。一言でいうと香嚴禅師が文献からは得るものがないといってこれを焼き捨てたってことなので、道元禅師はこの場合の「画餅不充飢」を「画餅」の章で分析しているということになる。では、どのような分析がなされているのか。
(注1)『日本思想体系12 道元(上)』283頁 岩波書店 1970年5月25日第1刷
(注2)『正法眼蔵思想体系』五巻199頁 岡田宜法 法政大學出版局 昭和29年9月1日
(注3)『日本思想体系12 道元(上)』の渉典(480頁)に「古仏言「画餅不充飢」」が『傳燈録』第十一巻、香嚴章からの引用であることが示されているが、しかしこれだけでは専門家でない者には何のことだかさっぱり判らない。今日『景徳傳燈録』は活字本としては出版されていないが、京都大学図書館の開いているホームページから『景徳傳燈録』のきれいな写真版を参照することができる。しかし普通の人がこれをすらすら読めるとは到底考えられない。